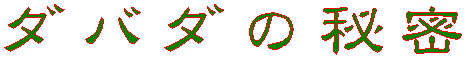
A.パンカースト 著
尼 代 憲 訳
一
十月まであと数日だというのに、その日は観測史上まれにみる暑さで、街ゆく人々は押入れから引っぱり出したばかりの樟脳臭い上着を脇にかかえ、そのうえシャツの袖を大きくまくりながら、なお腋の下に大きな汗染みを作って歩いていた。
ヒースロー空港へ降り立った直後、独特の臭いをはらんだ、ねっとりとまとわりつく濃い霧がその男を出迎えた。男は四十がらみのやせ形で、背は人並みよりやや高く、髪は灰色、目は蒼く、少し神経質そうな顔だちをしていた。彼は現在ソルボンヌで教鞭をふるっている講師なのだが、夏休みの最後の数日を友人のために費やそうとわざわざ故郷のロンドンまで帰って来たのだった。男の名はスコット・ゴードン。父親は今でもロンドンに事務所をかまえる現役の弁護士、母親は彼が六歳の時に亡くなったという。
スコットはタクシーに乗って旧友の家へ向かった。ジャック・トマソンはスコットのケンブリッジ時代の学友であった。とは言え、ジャックは家庭の事情で二年の途中までしか在学できなかった。しかし、見識が深く、誇り高いジャックをスコットは尊敬し、あつい信頼を寄せていた。
ある時こんなことがあった。大学を中退し居酒屋で働いていた彼を、かつての同窓生が見つけ出し、聞こえよがしのあてこすりで彼をなじった。商人の忍耐強さでこれに耐えていた彼だが、話が彼の両親のスキャンダラスな噂におよぶや否や、騎士の勇敢さで三人の男に立ち向かった。スコットはその場に同席していたにもかかわらず、恐ろしくて何もできなかったことをこの歳になるまで悔やんでいる。これは彼が自分でも気づかぬうちにジャックに対して引け目を感じている原因にもなっていた。このとき、三人の男に足腰が立たなくなるまで殴られながらジャックが言った「学校に通って学ばぬより居酒屋に勤めて学ぶほうがはるかに価値がある」という言葉を、スコットは今でもときどき教え子達に対して使っている。
そんなスコットが何年かぶりにジャックのもとを訪れたのには訳があった。二年も前に亡くなった彼の甥に対する、後ればせながらの悔やみを言うためというのが表面上の目的であるが、実はそれよりももう一歩突っこんだ事情が彼にはあったのだ。
彼はソルボンヌで講師を勤める一方で、ダバダに対する研究にも心血を注いでいた。この当時はダバダについて、アメリカやドイツといった先進諸国はもとより、アジア、アフリカなどの発展途上地域でもしばしば耳にするようになって久しく、現在と同様、この問題について、彼のような多くの立派な学者が正面から取り組み、また、一部の変人が側面から窺っている状況であった。人間社会にとって政治、経済に次ぐ、第三の骨子とも目されるダバダについての研究は、人類を新たに進化させる足がかりになるかもしれないと彼は考えていた。
当時ダバダの専門書として、ヘレン・クレッチマーの「ダバダの謎」が話題になっていた。実は彼女はスコットたちの大学時代の後輩で、当時は政治学を専攻していた。そのためスコットは自分がダバダの研究をはじめた頃、彼女もまたダバダ関係の本を手がけていることを聞いて驚かされた。スコットは彼女に会って、ダバダについての情報と意見を交換しあいたいと思い連絡をとった。快活で如才ない彼女は、学生時代にはスコットたちの憧れの的であった。
約束の日に彼女の家を訪れたスコットは、まず玄関を開けた途端に漂ってきた異臭に面食らった。さらに出て来た彼女の姿を見て、「これがあのヘレンか」と失望まじりに仰天した。故人に対する失礼を承知で言えば、彼女にかつての面影は全くなく、もつれた髪は油でベトベトに張りつき、全身垢まみれで、病的な隈のできた赤い目は妙にギラついていた。服は申し訳程度のぼろ布で、しかも彼女はあきらかに妊娠していた。
家の臭いはとても我慢できないので、スコットは彼女を連れ出して、公園のベンチで話を聞いた。彼らは三時間も話したが、最後の二時間五十分の間、スコットは「もう勘弁してくれよ」と思い続けていた。控え目に言って彼女は完全にイカレていたのだ。彼女は「ダバダの謎」の執筆を終え、次の作品のために資料を集めていたところ、とんでもない物を手に入れてしまったと言いながら泣いた。スコットはそれが何なのか、その場ではどうしても聞き出せなかった。
数ヵ月後に彼女が亡くなってから、葬儀の席でそれは明らかとなった。しかし今となってはそれを知らなかったほうが幸せだったかもしれないと感じることもあるスコットであった。彼が偶然入手したヘレンの遺稿のなかに、ジャックの甥であるジョンの死についての驚くべき記述が含まれていた。小説家ジョン・リーは、数奇な体験ののちに暴漢に襲われて亡くなったが、それについては「ダバダの謎」でも触れられている。しかし、ヘレンの新たな調査によれば、ジョンはダバダに深く立ち入りすぎたため何者かに殺された公算が高いというのだ。それについて、いくつかの証言が実名で得られていた。スコットはこの遺稿をジャックに見せ、この件について法的措置を講じるよう勧めるつもりであった。
スコットの乗ったタクシーは三十分ほど北上して、郊外のうらぶれたアパートの前に到着した。スコットとジャックとの感動的な再会はわずか十分ほどで終了した。帰りのタクシーの中でスコットは自分の軽率さを大いに恥じた。
ジャックは頑なで、甥の死を報道どおりのものと信じて疑おうとしなかった。確かに甥が発狂したうえ、変死を遂げたことなどに触れて欲しいと望むものはいないだろう。しかしそうも言っていられない事態が起こっているのだ。スコットは必死で説得した。だが彼はまったく聞く耳を持たなかった。
実際ジャック自身は誰からも愛される好漢なのだが、幸運にだけは見放されていた。彼はその多才さを活かしてさまざまな事業を手がけたが、どれも不幸な事故によって不成功に終わっている。最も可能性の高い方法を誰よりも正確に見抜きながら、誰も予想できないようなほんのわずかな可能性のために何度も泣かされていた。とうとう彼は自暴自棄となり、ここ数年はろくに仕事もせずに酒に溺れていた。それでも彼から無心の手紙が来るたびに、スコットは気前よくそれに応じていた。彼がここで終わる人間でないことをスコットは知っていたのだ。このことでスコットはジャックに対しある程度恩を施したつもりになっていた。しかし、貧乏というのは善良な人間の魂をねじ曲げてしまうのか、ジャックはスコットを恨みこそすれ、恩などみじんも感じていなかった。戻るあてのない金を貸すのは馬鹿げているし、そんな馬鹿がいるから金を借りたくなるのだとジャックは言うのだ。
そんなジャックにも心の支えがあった。それが甥のジョン・リーである。小さいころ父を亡くしたジョンは、病弱な母のもとで困難な生活を強いられていた。そんなジョンをジャックは実の息子のようにかわいがった。ジョンに読み書きを教えたのも彼だし、大学の学費を出したのも彼だった。ジョンがアメリカの何とかいう文学賞を取ったときのジャックの喜びようといったらなかった。その時ジャックから送られた手紙をスコットは今でも大切に保管していた。その手紙からはジャックのジョンに対する愛情が痛いほど感じられ、読み返すほどにむしろスコットの胸が熱くなるのだった。ジョンはその後も何冊かベストセラーを出し、そのたびにジャックの中でジョンの存在が、達成しえなかった本来あるべき自分像として確立していったのだろう。
ジョンの突然の死は、ジャックにとって文字どおり自らの死に等しいものであったことは推測に難くない。そう考えたとき、スコットはその思いを汚した自分の言動を大いに恥じた。
彼は傷心のうちに家路についた。
それから数ヵ月が経ったとある日の夕暮どき、スコットのもとに一通の手紙が届いた。ジャックからだった。手紙を受け取ったスコットは不審に思うとともに、手遅れになったのではないかと慄きながら封を切った。もしスコットの推測が正しければジョンの死因に関係すると目される「何者か」は、まったく無関係に見えるジャックにも食指を延ばす可能性が非常に高い。先ごろの提案は不首尾に終わったものの、スコットは別の手を講じてジャックを保護しようと思案していた矢先であった。スコットは長椅子に座り、膝に肘をついて前かがみになりながら手紙を読んだ。
| 前略。先日は済まなかったと思っている。君があの日、甥のジョンの死について不自然な部分を指摘したとき、私は思わずカッとなってあんなことを言ってしまった。だが今にして思えば君の指摘はもっともなことだ。 実は君が訪ねてくれた日の前日、ジョンの遺品を整理している中で、ジョンの日記をはじめ色々なメモが見つかり、その奇っ怪な内容にいささか癖液としていたのだ。ジョンは小説家なので夢見がちなたわ言を並べたてているのだと思っていたが、それにしても正気の人間の考えることではない。私はこれを狂気の産物として闇に葬ろうと思っていた。 そこで先日、私はジョンの書棚に並ぶ何とも不気味なタイトルの古い本の山を庭で焼くことにした。本の中にはいかにも古めかしく高価そうなものもあったが、私は燃やすことを全く躊躇しなかった。ジョンの狂気の元凶がここにあるような気がしたからだ。本を燃やした時、革張りの表紙のためか、肉を焼く様な嫌な臭いが漂ってきた。不気味な黒い煙が、解き放たれた太古の魂のように渦巻きながら昇天した。それを見て私は、一瞬言い知れぬ寒気を覚えた。 ふと見ると火の中にキラリと光るものがあった。私はそれを掻き出して見た。それは何かの鍵だった。本の中に挟んであったのだろうか。火の中でプラスチックのキーホルダーは溶けてしまっていた。色々試してみたが、鍵は家中の何にも合わなかった。私は疑問に思いながらも、鍵を手元に置くことにした。 二週間ほどして銀行から通知が来た。貸し金庫の料金が滞っているというのだ。その銀行は家から車で二時間以上かかる所にある。そんな遠くの貸し金庫に何を置いていたのだろうと訝りながら、私はその銀行へ出かけた。銀行にジョンが亡くなり、自分が相続人の代表であることを説得しようとずいぶん頑張ったが、係員はどうしても証明する書類を持って来るようにといって頑迷に私を拒んだ。仕方なく一度引き上げて、書類を揃えて出直した。今度は妻のエレインとジョンの奥さんのブレンダにも付き添ってもらった。 長い口論と面倒な手続の末、ようやく地下の貸し金庫室に通された。ジョンの借りていた金庫は、一般の金庫の更に奥にある特別なもので、薄暗く湿った地下通路と、分厚い鋼鉄の扉を何回も通り抜けさせられた。金庫に例の鍵を差し込むとピタリと合い、捻るとカチリと小気味よい音がした。重たい鉄の扉を開くと中から冷たい空気とともに、何か黒い影のようなものがサッと飛び出したように見えた。私は闇に目を凝らしたが、その時はもう何もいなかった。目の錯覚だったのだろうか。私の他には誰もその影を見なかったのだ。とにかく少なくとも邪悪な雰囲気が金庫の中から漂って来たのは確かだ。いや、そんな気分がしただけかもしれない。 金庫の中にあったのは数枚の紙切れだけだった。私たちは少々拍子ぬけした。それはファックスの用紙で、ラテン語らしい。コピーを同封するので見て欲しい。 白状すると私はこの書類に言い知れぬ悪意を感じた。とくに三枚目の図形を見た時、誰もが思わずウッと呟くだろう。何故こんなに嫌悪するのだろう。その秘密は文中にあるような気がする。 確か君はラテン語に堪能だったと記憶している。どうだろうか、ぜひこの文章を訳してはくれまいか。先日の君に対する私の態度を思えば、何とも厚かましい頼みであるとは思うがどうかよろしく頼む。 親愛なる我が友、スコットへ ジャック・K・トマソン 追伸 私はしばらく家族と一緒に旅に出るよ。君も知っているロイの別荘が借りられた。よかったら君も来てくれ。このあいだのことは水に流そう。 |
手紙を読み終えたスコットはもう一度始めから読みなおした。しばらく部屋の中を行ったり来たりしたあと、さらにもう一度ざっと目を通した。
(どうやらジャックはのっぴきならないところまで追い詰められたらしい。この手紙を見れば分かる。ジャックは得るべきではない知識を得てしまった。入るべきでない領域に踏み込んでしまったのだ。手紙の文体のなんと凶々しいことか。「狂気の産物」「解き放たれた太古の魂」「何か黒い影」。これらは彼が知ってしまった何かを必死に隠そうとしている空しい努力の跡のようだ)
(それにどうだ。「家族と一緒に旅に出る」とは。彼の住んでいるアパートを見たか。彼の着ていた服を見たか、スコットよ。家族を連れて旅行に出かける余裕がどこにある)
(ロイの別荘? ロイって誰だ。ロイとはロイ・チャールズのことか。私が大学時代、遊びで書いた小説の登場人物の、私とジャックしか知らないロイ。つまりこれは自分の行き先を人に知られないための暗号なのか……)
スコットは焦燥感に駆られながら、手紙と一緒に届いた三枚のコピーを見た。コピーを一目見て、スコットはその何とも邪悪な字体にまず驚いた。字が邪悪であるなど想像がつくだろうか?
スコットは今までそんなことを考えたこともなかったが、それを見た瞬間に強くそう感じた。
そして、ジャックが「言い知れぬ悪意を感じた」とする図形を見た時、事前に注意を受けていたのにも拘わらず、スコットはやはり毒づいてしまった。よく見れば幾つかの線と弧を組み合わせただけの単純な図形なのだが、なぜか幾何学的とは言えず、子供の落書のようでもあるが、今まで一度も目にしたことがないものなのだ。人間はこの何か恐ろしい物を象徴する図形を本能的に禁忌し、描かぬよう、思い浮かべぬよう、無意識のうちに注意しているのだろうか。
スコットはジャックの身に迫る危機について、ジャックの何倍も理解しているつもりになっていた。しかしこのコピーを見て、その危機が自分の理解の何倍も恐ろしいことを予感した。自分にできることが非常に限られていることも分かってきた。
スコットの失敗は、この時点で文書を破棄しなかったことだ。スコット自身はこれを読む気などとても起きなかったが、さりとてジャックの依頼をなおざりにもできなかった。そこで彼は目が疲れたなどと理由をつけてこの嫌な任務を妻のミシェルに押しつけてしまったのだ。おお、神よ!
ミシェルは快く引き受けたが、原稿を一目見た途端に後悔したのが分かった。しかし彼女は果敢にも読み聞かせはじめた。スコットは揺り椅子に座りながら妻のよくとおる声を聞いてはパイプをくゆらせた。
文書の内容は全く不可解であり、不気味な表現で抽象的概念を詳細に描写し、直後にそれを頑なに否定する繰り返しであった。文章そのものの不愉快さもさることながら、その発音の不吉な印象は黒い確かな力でスコットを呪縛した。
ふと見るとミシェルは目を閉じているではないか。それなのに朗読は続いているのだ。前世の記憶か甦ったとでも云うのか。スコットはこの時妻を止めるべきだった。しかし信じられるだろうか、彼の身体は魔術師の黒い吐息に絡め取られたように指一本動かすことができなかったのだ。
ミシェルは最後に「ダバダ!」と叫び、目をカッと見開いたまま気絶した。その途端スコットにかけられていた呪詛は解かれた。
ミシェルは病院のベッドでそのまま三日三晩昏睡していた。四日目の晩、スコットがベッドの脇でうつらうつらしていると、彼女は悲鳴と共に目を醒ました。スコットもその声に飛び起き、駆けつけた看護婦と一緒に妻をベッドに押さえつけた。彼女は完全に正気を失っていた。彼女はもがきながら叫んだ。
「助けて、もう逃げられないわ。あいつの目を見てしまった。あいつと目が合ってしまった。あいつは何処までも追って来るわ。ああ、あなた。私を……私の魂を見捨てないで」と言って哀願した。
スコットは彼女を胸に抱いて慰めたが、それが気休めに過ぎないことも知っていた。
二
ミシェルが入院して五日目、スコットは着替えやタオルといった身の回りのものを取りに一度家に帰った。さらに大学に顔を出し、しばらく休講にする旨を伝えた。帰りにデパートに寄って足りないものを買い揃えた。実のところ家に帰ってみたものの、下着や靴下がどこにしまってあるのか皆目見当がつかなかったのだ。たくさんの先輩学者に習ってか、スコットもやはり実生活のこまごまとした部分には無頓着で、家事は全てミシェルに頼りきりであった。実際、彼自身すでに四日間同じ靴下を履いていたし、看護婦に促されなければミシェルの着替えなど思いも寄らなかったのだ。ではデパートでうまく買いまとめられたかというとそうでもなく、あれも要る、これも要ると思うままに買い込んでしまい、両手に持ちきれないほどの荷物になってしまった。今にして思えば、どうして入院患者にボディブラシが三本も要るのか不思議でならなかった。払いは全てカードだが、こちらのほうも無頓着で、請求書をミシェルが見たら、たちどころにベッドから飛び出して、余ったボディブラシの使い道をスコットの頭に叩き込んでくれること請合いだった。
タクシーを止めようと必死に手を上げるスコットだったが、抱え込んだ荷物のおかげで水平より上に手を上げることはできなかった。仕方なしに駅前のタクシー乗場まで歩いて行くことにした。荷物の隙間から歩行者用の信号が青になるのが見えた。回りの人波に誘導されて、スコットは大通りを渡り始めた。そのときどこかで悲鳴がした。男が何か叫んだ。目の前を人影が横っ飛びによぎった。「危ない!」と声がして、右後ろにいた男がスコットに激しくぶつかった。スコットは地面にいやというほど叩きつけられた。その鼻先数ミリのところを黒塗りの車が猛スピードでかすめていった。頭を起こして見回すと、辺りは流血の巷となっていた。すぐそばで老人が足を牽かれていた。少し離れたところには子供のものとおぼしい腕がテディ・ベアを掴んだまま転がっていたし、さらに先には頭を踏み潰されたグレーのスーツ姿が横たわっていた。スコットは思わず再び顔を伏せた。
「危ないところでしたね」とスコットを突き飛ばした男が彼を抱え起こしながら言った。「私の到着がもう少し遅れていたら、取り返しのつかないことになってしまうところでした」
男は東洋人だった。彼はスコットの前に進み出て握手を求めた。スコットは機械的にこれに応じた。
「はじめまして。ミスター・ゴードン」彼は無表情で言った。「私はシダと申します。お迎えにあがりました」
「迎え?」
スコットは拍子ぬけしたような声で相手の言葉を繰り返した。
「そうです。お気づきのようにあなたは狙われています。あなたと、そしてあなたの奥さんと。さあ、急いで」
スコットは自分の身に起きていることが理解できなかった。茫然自失し、命の恩人に礼を言うでもなく、シダと名のる男の用意した車に乗り込んだ。
スコットはシダと言う東洋人の名に聞き覚えがあった。しかしどこで聞いた名前なのか思い出すまでに五分ほどを要した。
「あなたはひょっとしてハッケイ・シダでは?」とスコットは唐突に問い掛けた。シダはいささか驚いた様子で、
「何故それを?」と聞き返した。
「あなたの書いたレポートを読ませていただきましたよ。私の古い友人で、クレッチマーという女性がいるのですが、彼女の書いた本に載っていたんです。本の中ではあなたの名前は出てきませんでしたが。
たしか日本のダバダ研究組織『赤土の会』のメンバーでしたよね。ニューオリンズのオルサー教会を調査したときのレポートを読んだんですよ。そう言えば、その後しばらく行方不明になっていたそうですね。そして発見された直後に『赤土の会』も脱退されたとか……」
そこまで言って、スコットは自分が喋り過ぎたことに気がついた。相手の気分を害してしまったようだ。
このときスコットは自分がどこへ連れていかれるのか知らされていないことに気づいた。何とも間の抜けた話である。たて続けに起こったショッキングな出来事のためか、彼は見知らぬ東洋人に促されるままに、車に乗り込んでどこかへ運ばれて行くのだ。行き先も告げられぬままに。
彼は思い切って疑問を口にした。
「私をどこへ連れて行く気ですか」
「我々の組織の施設です」とシダは答えた。
「というと『赤土の会』の支部がこの辺にもあるのですか?」
「いいえ。先程あなたがおっしゃったとおり、私は『赤土の会』を辞めたのです」
「ああ、そうでしたね。ではあなたの言う組織とは何ですか?」
「我々の組織であるIDC、国際ダバダ委員会は、位置づけとしては国連の下部組織であり、表沙汰にはなりませんが世界中のほとんどの政府が我々の活動を認めています。そして我々には超国家的、超法規的権限が与えられているのです。実際にはある面においては国連そのものを指導さえしています。何故ならダバダ問題は全人類の存亡に関わることだからです。詳しいことは到着してから説明されるでしょう」
彼が国連の職員だと聞いて安心したためか、スコットはそれ以上詮索しないことにした。
スコットは三十分ほど車に揺られ、町外れの薄汚れた雑居ビルの前に降ろされた。
(これが国連に指示を与える組織の施設なのだろうか)
彼は疑問を抱かずにはいられなかった。ビルにはエレベーターもないため、階段で三階まで歩かされた。建物は古く、何かいやな臭いが染みついていた。事務所の扉も古めいていて、開けると耳障りな音がした。
事務所自体は狭く、机が六つで一杯だった。そこで背が低く、不格好な中年男に出迎えられた。男はマラルメと名のった。応接セットもないため、折り畳みのパイプ椅子を勧められるはめとなった。
「ところで、ミスター・ゴードン」マラルメはいきなり切り出した。「今日来てもらった理由は他でもない。あんたが抱えこんじまったコピー、ジョン・リー氏の遺品であるコピーのことで、ちょっと聞きたいことがあってね」マラルメは嫌な笑い方をした。
スコットは妻を恐怖に追いやった元凶ともいえる件のコピーのことを、この男が知っていることについて訝しく思うよりも、まずこの男の不遠慮な物腰に苛立った。
「何でしょう」と彼が言い終わらぬうちに、マラルメは続けた。
「早い話が、コピーを引渡してもらいたいのだ」
この時点でスコットの苛立ちは腹立ちに変わっていた。
「何故でしょう」スコットは自分でも驚くほど事務的な口調で訪ねた。
「あんたが持っていても、百害あって一利なしだ。我々なら有意義に使える」
「しかし、所持しているのは私だ。害があろうが利がなかろうが、どう処理するかは私が決める」
「いや、しかし我々の計画にはあのコピーが必要だし、この計画は全人類の運命を握っているんだ。あんた一人の気まぐれが、五〇億の人間の命に関わっているんだ。へたすりゃみんなあんたの奥さんの二の舞いだ」
「知ったことか!」妻の件に触れられ、スコットはついに激高した。「そんなにお詳しいのでしたらね、マラルメさんとやら。原本を誰が持っているか勿論ご存じでしょうね。そこへ行けばいい。もっともあいつの居場所がつきとめられるものならね、ハハハッ。もう私には関わるな」
スコットは内に溜っていた憤りを吐き出した。妻が倒れたのはマラルメの責任ではないにしろ、そのストレスに油を注いだ責任が彼にはあった。
するとマラルメはデスクの引き出しから英字新聞を取り出して、マーカーで囲まれた記事をスコットに示した。
| 家屋倒壊
一家四人生き埋め 昨夜10時ごろ、コロラド州デンバーに住む製造業、ダニエラ・クレイさん所有のペンションが突然倒壊し、宿泊中のイギリス人、ジャック・トマソンさん(52)と妻のエレインさん(46)、長男のデビッドさん(18)、長女のシンシアさん(16)の一家四人が生き埋めとなった。三時間後、長女のシンシアさんが救出されたが、シンシアさんはショックのためか極度に錯乱しているため詳しい事情は未だ聞き出されていない。 目撃者の証言では何か目に見えない圧力で突然踏み潰されるように崩れたそうである。現場付近の他の建物に被害はなかったが、近くの牧場では巨大な足跡のような窪みも発見されている。専門家は局地的竜巻現象と見ているが、はっきりした原因はいまだ判明していない。警察と消防では残る三人を救助を急ぐとともに、事件事故双方からの捜査を開始している。 |
スコットは記事に目を通し、しばらく絶句していた。マラルメは同情の色を忍ばせた声で、「こんなことはもう終わりにしよう」とささやいた。
「……わかった。コピーは渡す」
スコットは、ようやくその一言を絞り出した。マラルメの顔に勝利の色が浮かんだ。
「ただし」スコットがここでこう切り出せたのは一種の奇跡だった。「いったい何が起こっているのか、それだけは教えてくれ」
「もちろんだ」
マラルメははじめて心から笑った。
スコットとマラルメはシダの運転する車で出発した。道すがら、マラルメの話す内容はスコットにとって新奇な驚きに満ちていた。
「……つまり、ダバダの力を引き出そうとする阿呆どもが爆発的に増え、世界中、どこでダバダが爆発してもおかしくないっていう状況なんだ。そうしたら人類はおろか、地球そのものだってダバダに飲み込まれちまう。そうならないための計画なんだ」
「しかし、そんな大それたことをする機関の割には、あの事務所は手狭な感じですね」
スコットはマラルメの前で気取りを脱ぎ捨てた。遠慮の通じる相手ではない。
「まあね」マラルメはすこし気まずそうだった。「俺たちはあまりおおっぴらには動けないんだ。次のカーブでそれとなくミラーで後ろを見てみなよ」
言われたとおりにすると、後ろに黒塗りのベンツが見えた。
「あれが何か」
スコットは尋ねた。
「あの車、事務所からずっとつけて来てる。気づかなかっただろ」
スコットが新たな疑問を口にする前に、マラルメは言った。
「FBI、CIA、KGB、MI5、モサド、ペンタゴン、NASA、ロックフェラー・ロスチャイルド両財団、オペック、EC、IRA、グリーンピース、NATO、ロータリー・クラブ、赤十字、ボーイスカウトにケンタッキー・フライドチキンまで、世界中に俺たちをマークしている団体が山ほどあるんだ。俺たちの計画を煙たく思うダバダ信棒者がいかに多いかってことさ。ご苦労なこった」
「何故そんなにたくさんの、そしてダバダとは無関係に思える団体が、一斉にこの計画を阻止しようとしているんです」
「これらの団体を結びつけるキーワードがある。フリーメーソンだ」
「フリーメーソン?」
「中世ヨーロッパの石工組合から発展したと云われる世界最大の秘密結社だ。先程言った団体は、全てフリーメーソンに支配されている。世界中のほとんどの組織が支配されていると言っていいだろう。フリーメーソンは巨大な組織だが、それを牛耳っているのはイルミナティって組織だ。そしてイルミナティの設立者はブムーゲという組織の幹部だ。そのブムーゲこそダバダの謎を狙う組織なんだ」
「ブムーゲというとアッカドの神話の怪物たちの母神、ティアマットのことですか」
「そう。その神話の魔神にあやかってか、この組織は古代より様々な秘密結社を支配してきた。中世では魔術結社ローゼン・クルツ(薔薇十字団)、宗教結社テンプル(聖堂)騎士団、暗殺結社アサシン、近代では貴族の黒ミサ結社ヘルファイアー・クラブや黒人差別結社KKK(クー・クラックス・クラン)、中国の義和団や太平天国など、全て奴らが一枚噛んでいる。しかも、これらは秘密結社とは言っても非常に有名なものだろ。名の知れぬ、文字どおりの秘密結社が幾つあることか判ったもんじゃない」
スコットはマラルメの秘密結社の分類が少し偏っていることには目をつぶって、すこし投げやりに尋ねた。
「なんだか複雑ですね。そんな組織に狙われて大丈夫ですか」
「まあ、心配ももっともだ。だが俺たちにだってバックがついているんだ。なんだと思うかね」
「国連でしょ」そのことはさっきシダに聞いていたのでスコットはためらわなかった。
「ハズレ」
「え? さっきシダさんからそう聞きましたよ」
「国連の下部機関だってことだろ。だがそれはバックが活動しやすいようにつけた肩書きに過ぎないんだ。実際には国連本部は我々の敵だぜ」
「だったら政府かな」
「ハハハ、まさか」マラルメは笑った。「いいかい、知ってのとおり世界中の国々の多くはアメリカに頭が上がらないだろ。そしてアメリカ政府はダバダの前進基地の一つなんだぜ。アメリカの歴代大統領は軒並みダバダ野郎さ」
「えっ! そんな馬鹿な」
「いや、本当さ。アメリカだけじゃないぜ。西側も東側も、ほとんどの国のトップはダバダなんだ。我がフランスや君の故郷イギリス、それにドイツ、イタリア、ロシア、中国、日本なんかもね」
「だが、それじゃああなたたちをバックアップできる組織なんて考えられない。本当にバックが有るんですか」
「いや、ちゃんと有るんだ。正解は『ヴァチカン』さ。なにせ、ダバダを認めれば、自分たちの神、ひいては自分たちの存在そのものも否定したことになりかねないからね」
「『ヴァチカン』……か」スコットはちょっと面食らった。
「そうさ。なんたって、表世界では最大の宗教の総本山だ。なりは小ぶりでもその勢力は馬鹿にならない。あんただってクリスチャンだろ」
「それはそうですが……。ではダバダとは神、もしくは宗教のことなのですか」
「いや、確かにそういう一面を持ってはいるが、そう言いきることはできない」
「だったら何なんです。私だってダバダ研究家の端くれだが、ダバダなんて単なる理論としか考えていなかった。クレッチマーの本だって、ダバダの理論を分かりやすく記しただけで、実際には下水道に怪物なんていない」
「実のところ俺たちもダバダが何なのか、よくは知らないんだよ。
ただ、俺の個人的意見を言わせてもらえば、ダバダっていうのは『概念の源』とでも言うのかな。つまり俺たちが想像し、認識し、考察し得る全てのものはそこから生み出されていると思うんだ。だからダバダは物体であり、エネルギーであり、思想であり、現象であり、理論であり、その他全てであるといえると思う。
量子物理学の『コペンハーゲン解釈』、不確定な粒子運動により確率としてしか存在しない物体の状態を俺たちが観測によって決定する、という考えが正しいとしたら、観測に伴う結果は『概念の源』であるダバダから引っ張り出されると考えればいいだろう。俺たちがそこに化け物を見た、だからダバダの生み出した化け物がそこに存在したというわけだ」
スコットはマラルメの言葉を反芻し、その意味を理解しようと努めた。そのうちに彼らの乗る車はスコットの家に着いた。彼らは車を降りた。
家の玄関の鍵を開けようと、スコットがドアのノブを握ったところドアはすっと開いた。鍵を掛け忘れていたのでろうか。いや、玄関を一歩入ったスコットは、目の前に広がる惨状に目をしばたかせた。家の中が何者かに荒されている。コピーを狙う組織の手が伸びたのか。
「で、コピーはどこだ」
マラルメは驚いた様子もない。スコットはもしやと思って聞いてみた。
「驚かないのですか。コピーを持ち去られたかもしれないのに」
「いや、残念ながらコピーは見つけられなかった」
「なに! これはあんたの組織の仕業なのか」
「待ってくれよ、ソファーまで切り裂いたのは俺じゃあないぜ」
マラルメは悪びれない。スコットはそれ以上問い詰めるのが馬鹿馬鹿しくなった。彼は電話の脇に掛けてある鍵束を握ると、二ブロック先の月極駐車場に向かった。安心したことに、彼の車を誰かが調べ回した形跡はなかった。コピーは車のダッシュボードの中にあったのだ。
「なるほどね」
マラルメは呟いた。スコットはマラルメを出し抜いたような良い気分になった。
彼らはコピーを持って出発した。車の中でスコットは先程の話の続きを切り出した。
「もしあなたの言うとおりならマラルメさん、ダバダなんてものはとっくの昔から存在していたはずだ。それが何故今になって問題視されはじめたんだ」
「WHOが秘密にしている調査結果によればだな、世界人口に対する精神異常者の比率はここ数年で何十倍にも膨れ上がっているんだ。異常者の異常な観測の結果、異常なものがダバダから生み出される。またはその逆かな。
とにかくダバダの摂理は狂い、その狂気を利用する奴らは力を強めたってことだ。
もう一度言うぞ、これは俺の個人的意見だ」
「つまり、あなたのご大仰な考察も空論に終わる可能性が少なからずあるってことだ」
「まあね」
マラルメは少し傷ついたように言った。
「で、そのよく判らないダバダの、よく判らない狂いをどうやって治すつもりなんです」
「ダバダ信棒者は、その力を制御する術も持たないままにダバダの力の歪んだ部分を引き出している。ダバダ自体にはむろん太刀打ちできないから、そういった企みを一つひとつ潰していく、今はそれしかできないね」
マラルメは自嘲的に言った。
「今はそれしか……ね」スコットはマラルメの言葉をくりかえした。
三
その日もスコットはミシェルのベッドの脇に腰掛けて物思いに耽っていた。ここ数日寒い日が続き、昨晩から降り続いていた雪が夕方になってようやく止んだ。しかし、スコットはそのことに気づいた風でもなく、ベッドに横たわる妻の顔をただ眺めていた。
彼女との生活は必ずしも万全のものとは言い難かった。生来学者肌のスコットは、興味深い研究対象があるときは家庭を顧みるのを怠りがちとなった。一方、社交家のミシェルは家事よりもむしろカルチャーセンター通いに心血を注いでいた。性格の不一致のためか、二人はしばしば激しい口論をしていた。実際、スコットがミシェルに手を上げたことも一、二度あったし、その逆はもっとあった。二人の間に子供がいないことも諍いの原因の一つだったかも知れない。それでもこれまでやってこれたのは、二人に共通する特徴のためだろう。どんなに激しく言い争っても、翌日にはお互いケロッとして、仲良く手をつないでショッピングに出かけたりしていた。相手を許す寛容さなのか、怒りを持続するだけの体力がないのか、喧嘩を翌日に持ち越したことはほとんどなかった。案外、私たちはこれでうまくいっているのかもしれないな、と考え、スコットは悲しげな薄い笑みを浮かべた。
窓辺に置かれた回転時計の金ピカの振り子が夕日を反射して、病室の白い壁に幻想的な模様を投げかけている。
三日目に絶叫と共に飛び起きて以来、ミシェルは狂乱と失神を繰り返していた。その様子を目の当たりにするにつけ、スコットはこのままミシェルが眠り続けていればいいと思わないではなかった。確かに眠っている間も悪夢を見ている可能性は大いにある。しかし、ミシェルの安らかな寝顔はそれを感じさせない。笑みともとれる口元のほころびは、ひょっとしたら楽しい夢を見ているのかも知れないという希望をスコットに与えていた。しかし、今後の身の振り方を考えると気が重くなった。
マラルメはスコットにIDCの活動に参加するよう呼びかけた。IDCの活動にとってダバダのことを知る人間は少なければ少ないほど都合がいい。しかし、スコットはすでにダバダを知らない幸せな人達とは一線を欠いていた。となればダバダについて知っている人間は手元に置いて管理したいとIDCが考える道理も分かる。
マラルメたちのそのような希望を理解しながら、スコットはもうこれ以上ダバダに関わりたくないと考えていた。特に、妻のこんな姿を見せられればなおさらだ。彼は残された自分の生涯のすべてを妻の看病にあてるつもりであった。
スコットが断りの電話を入れると、マラルメは落胆したふうでもなく、気が向いたらいつでも電話をくれと言った。まるでスコットが心変わりをするのを見越しているような口振りだ。
一週間が過ぎ、スコットはミシェルの悪夢は杞憂に過ぎなかったのではないかと思いはじめていた。その日の夕方に目覚めたミシェルは、いつもとうって変わって落ち着いていた。スコットはミシェルが快方に向かっていることにかすかな希望を覚えた。差し出されたミルクティーを一口飲んで、ミシェルは窓の外へ首を巡らせた。長い間ベッドにいたため、髪はひどくもつれ、頬はすっかり痩けていたが、それでも夕日に照らされた彼女の横顔はスコットがゾクッとするぐらい美しかった。彼女は一言も話さなかったが、その唇に安堵の笑みが浮かんでいた。彼女の顔がスローモーションのようにゆっくりとスコットの方に向き直った。
スコットと、担当医と、看護婦たちの目の前で、彼女は突然発火した。青白い炎に包まれて彼女の体が燃え上がった。髪が激しく燃え、爪がはがれ、黒くカチカチになった皮膚が骨に貼り付いた。口もとが「わかっていたわ」と声にならない呟きを発したあと、その黒焦げになった頭蓋骨がスコットの足元に転がって砕けた。不思議なことに、衣服もベッドも焦げ跡一つない状態だった。
葬儀の列の後ろの木陰にマラルメがいることに、スコットは最初から気がついていた。近所衆や親戚連中がみんな帰った後、妻の墓標を一人見つめ続けるスコットの足下にマラルメの影が伸びた。スコットはしばらく気づかぬふりをしていた。
「知っていたのか」
振り返りもせずスコットはつぶやいた。
「こうなることを知っていたのか!」
スコットは語気荒く振り返ると、マラルメの襟首をつかみ激しく揺さぶった。驚いたことにマラルメは全く無抵抗で、スコットのされるがままになっていた。スコットはマラルメの襟を離すと、再び振り返って妻の墓標を見つめ、そのまま沈黙に沈んだ。
「こうならないように祈っていた」
マラルメが囁くような小声で言った。暮れなずむ光の中、言いしれぬ沈黙が二人の男を包んでいた。足下を木枯らしが走り去り、マラルメは静かに踵を返した。枯れ葉を踏みしめるマラルメの足音が遠のくにつれ、スコットの中でせめぎ合う二つの心が激しく衝突した。最後の瞬間、一方が他方に勝り、去りゆくマラルメの背にスコットは呼びかけた。
「マラルメ、私もあんたの仲間に入れてくれ」
振り返ったマラルメの表情からは、心底驚いている様子が見て取れた。
「本気か、スコット。俺はてっきり……」
「てっきり何だ。女房を亡くして腑抜けになると思ったか。冗談じゃない。このまま引っ込んでいられるか。ミシェルの仇を討つんだ」それは、スコット自身ですら驚いた泣けなしの強がりだった。
「そうか、そうだよな。仇を討つんだ。そうだよ、ハハハ」
マラルメは自分自身の落ち込んだ気分を振り払うように言った。このときになってスコットは、マラルメが自分と同様に深く傷ついていることに気がついた。
ステファン・マラルメという人物について、その後三年間にスコットは多くを知った。判っている限り、この丸顔の小男に家族はいない。マラルメ本人の言うところによれば、彼の両親は彼が一五歳のときに離婚し、マラルメは妹と共に母親に引き取られた。その母もしばらくして男と一緒に蒸発し、マラルメは知的障害を持つ妹の面倒を一人で見なくてはならなくなった。少年が家族を養っていく手段はあまり多くなく、マラルメ自身、非合法な方法をとることにためらいはなかったようだ。実際マラルメはその道のエキスパートで、その筋の男たちにも一目置かれていた。
やがて、妹の病状は悪化し、マラルメは医師に薦められるままに、どこか外国の高名な病院に妹を入院させることにした。しかし、入院先の病院が火事になり、マラルメの妹は遺体こそ発見されなかったものの、生存は絶望的だった。彼は妹の死の責任が自分にあると思いこんでいるようだった。
マラルメは常にシニカルな物腰で、人を小馬鹿にしたような所があるが、実は誰にもまして自嘲的で、自分自身をあまり価値のない人間と見ているようだった。人前で無分別とも思える言動をとり、周囲から白眼視されることで自分の無価値性を立証しようとしている姿は自虐的とさえ言えた。それは、両親から見捨てられ、残されたたった一人の肉親さえ自分のせいで死なせてしまった(と、彼自身が思いこんでいる)ことに端を発していた。彼は不幸な境遇にふさわしい悪人たらんと努力しているようだったが、それはあまり成功していなかった。
スコットはときどき、マラルメが自分の死に場所を、それも最も過酷な死に場所を、常に探しているような気がすることがあった。もっとも、ダバダ問題に積極的に取り組むことは、自らを過酷な死地に追いやることに他ならず、それはスコットにしても同様であった。
この三年間でスコットとマラルメは数多くの窮地を共に乗り越えてきた。ブラジルで臓器取引の現場を押さえ、ボルネオで大麻畑を焼き払った。上海で眼球石を奪取し、チベットで千冊の古文書を焚書した。ロサンゼルスの地下宗教を壊滅させ、フォートノックスの練金工場を破壊し、ルーマニアの大学から盗まれた碑文をインドで奪還した。
IDCに参加することを決意したとき、スコットは自分の役割は経理とかタイプ打ちとかの事務だと思っていた。長年教師だった自分に、荒事は無理だと思いこんでいた。
ところがスコットは常に最前線で活躍するエージェントとなった。スコットはむしろ実戦向きの人間で、学生時代は射撃部に在籍しながら万年二位だった彼だが、ここにいたってその才能を開花させた。はじめは人間に対して銃を向けることを躊躇していたスコットだが、他人に任せれば相手を殺しかねないことを考えれば、確実に相手の手や足を打ち抜ける自分の射撃精度は、むしろ相手の命を救うことになると思い直した。もっとも、そうやって命が助かった者も、程なく自殺したり変死したりするのが常であったが。
射撃の腕が上がったように、元々堪能であった語学についても、マスターした言語は当初の六カ国語が一四カ国語にまで増えていた。聞き取るだけの言語なら更に多かった。一流とまでは行かないが、スコットは自分の勤めをしっかりこなしていた。
むろん、スコットとマラルメだけで全てを成し遂げたわけではなく、むしろ彼らは実働部隊のバックアップが主な仕事だった。彼らは特定のチームを組むわけではなく、取り組んでいる問題に応じて必要な人材が選択された。IDCには様々な才能が集まっていて、スコットは仕事を通じて彼らと知り合いになった。
ベルリンに住むライモンド・ワーグナは法学の天才だった。彼は自宅の書斎から、ファックス一本であらゆる国の法的文書を即座に送り出すことができた。スコットは一度、彼の書斎に案内されたことがあった。ワーグナは車椅子の老人で、片目が見えないようだった。彼の書斎は広大で、ちょとした図書館ほどの広さがあった。彼がどうやってこの広い書斎を行き来しているのかスコットは不思議でならなかった。
シカゴのリック・エドモンドは名うてのハッカーで、ペンタゴンだろうがクレムリンだろうが何処のコンピュータにでも自由に進入し、好きな情報を好きなときに引き出すことができた。聞くところによると、彼は十四、五歳の少年らしく、ちょっと悪ふざけがすぎる傾向があった。一度など、工作員が警察署に侵入するために陽動情報を流す指令を受けた彼が、なんと異星人の襲来を報じてしまったことがあった。するとどうだろう、このおかしな情報に警察はおろか州軍まで出動する事態となり、その地域一帯が大パニックとなってしまったのだ。
ロシアのラズミーヒンは格闘技の達人で、素手でヒグマを絞め殺す大男であるが、彼の最大の武器はそのひらめきにあった。普段はむっすりと押し黙っている彼だが、現場にあって時々開くその口からは、これまでだれも考えつかなかったような名案がこぼれるのだった。そんな才能にも拘わらず、彼は常に命令に従順で、自分自身では何も考えていないようなポーズを取っているのがスコットにはおかしかった。
チャーリー・シンクレアはアメリカ上院議員であり、しかも爆弾作りの専門家という何とも奇妙な男だった。要職にあるのも省みないで、彼は危険な現場にもちょくちょく顔を出した。彼には双子の弟がいて、議会の方にはこのピンチヒッターが出ることも多かった。実のところ政治的手腕は弟の方が遥かに上で、議会でやっかいな問題が持ち上がるたびに、チャーリーは自ら積極的に志願してIDCの活動にいそしむ傾向があった。近頃では議員職を弟に押しつけたいと考えているようだった。
双子といえば、エクソシスターズと呼ばれる若い双子の徐霊師にも会った。彼女たちはその道ではかなり有名で、たまにテレビで姿を見ることもあった。テレビではいかにも面白げに、インチキ臭く報道されている彼女たちだが、実際に彼女たちの能力にはすばらしいものがあった。かつては、心霊現象や超常現象など、非科学的であるとして頑として信じなかったスコットだが、彼女たちの活躍を目の当たりにしてみると、それらが実に科学的で道理にかなったものだと考え直すようになた。
これら一戦級のメンバーが、すでに戦線を離脱してしまっていることをスコットは残念に思った。作戦中に死亡したり、暗殺された者はまだ幸運だ。失踪し行方がわからなくなった者たちは、おそらくさらに恐ろしい運命をたどったに違いない。そのような者たちは、その後発見された場合でも、まず間違いなく精神を失調し、廃人となっている。スコットもそういう人たちを何人も見てきたし、そのたびに次は自分ではないかと不安になった。
スコットは激しい焦燥感に駆られていたが、結果としてこれがプラスの方向に働いたようだ。その日も夜遅くまで事務所に残っていたスコットは、かつて扱った事件のファイルの中に奇妙な共通点を見つけた。
かつてマラルメに聞いたところによれば、ダバダの影にフリーメーソンがあり、その中心にイルミナティがあり、さらにその奥にはブムーゲという組織があるという事であった。これまでの事件でも、背景にフリーメーソンの存在を突き止められることはしばしばあったし、時にはそれがイルミナティまでつながっていることもあった。しかし、肝心のブムーゲとなると、事件への関与はおろか、その存在すら全くつかめないままだった。
事件ファイルを繰り返し眺めるうちに、スコットはそこに謎の組織の存在が隠されていることを発見したのだ。ブムーゲの子音、B、M、Gは一種のアナグラム(綴り替え)となって、各事件の主要部分に忍ばされているようだ。
一九九一年二月に起こった臓器売買事件はアメリカのジョージア州(G)からメキシコ(M)経由でブラジル(B)へ至るものだった。同年七月に焼き払ったボルネオの大麻畑の経営者は、同時にイギリスのブリティッシュ・ゼネラルモータース(BGM)社の役員でもあった。一九九二年に焚書を行ったチベットの寺院は江孜(G)郊外のボラン=ミール(BM)寺院だし、翌年壊滅したロサンゼルスの新興宗教の本部ビルはグランドマスタービルディング(GMB)という名前だった。眼球石を収集している上海の「狂金獣」という組織はマッド・ゴールド・ビースト(MGB)と訳せるし、フォートノックスの練金工場の長官はマイケル・グリム・ブロックス(MGB)という名だった。ルーマニアのブカレスト大学(B)のガジ教授(G)の部屋から盗まれた碑文はインドのミルザプル(M)で発見された。
スコットはこの新発見をマラルメに話した。
「なるほど、競馬新聞の予想欄のようだな。過去三年間の優勝馬のイニシャルで勝ち馬が判るんだろ」マラルメは相変わらずであった。「まあ、せっかく見つけてくれたんだ、頭の隅にでも入れておこう」
世紀の大発見だと思って興奮気味だったスコットは水を差されて少し傷ついた。しかし、翌朝自分のデスクの上に詰まれた分厚いファイルの束にはもっと気が滅入った。
「あんたが知りたがっていたBMGだ。世界各国の個人・法人の有名どころから、BMG、GBM、MBG等々リストアップしといてやったぜ。好きなんだろ、そういうの」
マラルメの顔に悪戯っぽい笑みが浮かんだ。
このファイルが非常に役に立つことをIDCが認めたとき、スコットはマラルメの鼻をあかしたようなよい気分になった。IDCには実に多くのダバダ関係と思われる事件の情報が入るが、調査をしてみればその八割は誤報であった。ところがスコットのファイルに情報のある人物や組織が関係する事件の誤報は四割を割っていた。それ以外の事件でも、調査の結果、スコットのファイルに符合する事が判明するものが多かった。
このファイルはIDCの各支部に広く普及し、アナグラムの秘密はIDC全体に知られることとなった。にも拘わらず、依然多くのダバダ事件の影にはB、M、Gの符合があり、IDCの懸命の活動をあざ笑うようだった。
焦燥から見いだした手がかりではあるが、手がかりがありながら実体に近づけない状況は、むしろスコット達の焦燥感を煽り立てた。
とはいえ、アナグラムの符合がすぐには見つけだせないものの、明らかにダバダがらみの事件と思えるものもあるにはあった。今回スコットたちが取りかかっている事件もまさにそれで、二年前に壊滅させたロサンゼルスの「垂れ下がる空間教団」が、にわかに復活の兆しを見せているというのだ。「垂れ下がる空間教」はロサンゼルス周辺で一般人を誘拐しては殺していた殺人教団で、犠牲者は優に千人を超えていた。その手口は酸鼻を極め、犠牲者の多くは生きたまま食肉虫に全身をついばまれ、出血死よりもむしろ狂死する者が多かった。
IDCは一九九三年一二月にこの教団の本部を襲撃し、壊滅的打撃を与えていた。この作戦にはスコットも参加し、教団本部に累々と詰まれた腐乱死体に度肝を抜かれたことを記憶している。
教団の主要メンバーの多くは投獄されており、スコットは教団の再興の影に、見えざる支配者の存在をつぶさに感じていた。
「教団の主要メンバーの中で、例のアナグラムに符合するのは一人だけだ。首謀者は決まりだな」
スコットは教団員のファイルの中から一つを抜き出してマラルメに渡した。
「マッド・ベイ・グラダンス、一九六五年生まれ、モビール医科大学卒」マラルメはファイルの内容を読み上げた。
「一九八七年教団に入信、一九九〇年麻薬取締法違反容疑で逮捕、一九九四年釈放」スコットが後を続けた。「こいつで決まりだ」
「おいおい、あまり先走るなよ。確かに名前はアナグラムに一致するが、偶然の一致も考えられる。それにこのファイルの中に首謀者がいるとは……」ファイルをパラパラめくっていた手が止まり、マラルメの顔色が見るみる蒼くなった。
「そ、そんな馬鹿な」
四
マラルメの手がガクガク震え、危うくファイルを取り落としそうになった。
「どうしたんだ、マラルメ」
スコットはマラルメの体を支えると共に、ファイルの開いたページに目を落とした。
「垂れ下がる空間教入信者、エリザベス……マラルメ?」
スコットはマラルメの顔をまじまじと見た。
「妹のエリザベートだ」
「本当か」
言われて見れば、ファイルにある顔写真は、どことなくマラルメに似ていなくもない。特に、その目元はマラルメ家の血筋を証明するようにクリクリと好奇心に光っていた。
マラルメは事態を飲み込めないでいるようだった。見かねたスコットは助け船を出した。
「おめでとう、マラルメ。生きてたんだよ。妹さんは」
「そんな、そんなはずは……」
「そんなもこんなもあるか、現に生きてるじゃないか。病院の火事から何とか逃げ出したんだよ」
「しかし……」マラルメは勇気を蓄えるため、しばらく間をおいてから言った。「秘密にするつもりはなかったんだが、エリザベートが入院していたのはあのジョン・リーが火をつけたという病院なんだ」
スコットは雷に打たれたようなショックを受けた。オランダのアムステルダムにあったその病院はダバダの人体実験場で、イギリス人作家のジョン・リーはその病院内で彼の言葉で言うところの「黒い奴ら」の陰謀を目の当たりにし、発狂してしまったのだ。無論、当時マラルメはそんなことは知らなかったに違いない。病院の火事で妹が行方不明になったことを知らされたとき以上に、病院がダバダの巣窟であったことを知ったときの方がマラルメにとってひどくこたえたはずだ。マラルメがこれまで、ダバダの比類し難き不浄さをもって汚されたやもしれぬ妹の魂の救済を狂おうしいまでに願っていたことは想像に易く、これに思い当たったスコットの胸にも切ないものがこみ上げてきた。スコットはマラルメを力づけようと、むなしい努力をしてみた。
「とにかく、妹さんは無事だったんだ。生きてさえいればきっと助け出せるさ」言いながらもスコットは、燃えさかる妻の目の前で自分がいかに無力だったかを思い起こして震えた。
スコット達の諜報活動は続き、マッド・ベイが首謀者であることの裏付け、集会場の位置、次の集会の日取りなどを調べ上げていた。襲撃の決行は四月二日、IDC本部から派遣された選りすぐりの腕っこき達が集会場を襲い、マッド・ベイを誅殺するという、実に単純明快な作戦である。地域の警察に手を回し、殺人を教団内部の分裂によるものとなるよう仕組み、教団の主要メンバーを軒並み逮捕させる。そしてIDCの主席顧問弁護士直々に審議に臨ませ、主要メンバー全員を一生牢獄につなぐよう取りはからう運びとなっている。
マラルメは頑なに固辞したが、スコットはエリザベートを何とか救出したいと思っていた。スコット達は作戦の実働部隊ではないので、作戦開始直前にエリザベートを保護できるはずであるとスコットは踏んでいた。
作戦の決行まで二週間ほどに迫ったある日、スコットは街角で彼女を待ち伏せ、新興宗教の勧誘を装い声をかけ宗教論議を投げかけた。思った通り、彼女はスコットの論陣をやすやす破り、ダバダの秘術をほのめかす舌鋒を炸裂させた。スコットは下手に逆らわず、彼女の意見に感心した風を装った。後日もっと詳しく話を聞きたいと申し出、彼女の同意を得た。スコットはここまで彼女の肢体を、いささか露骨とも言える眼差しで眺め、自分の関心が彼女の宗教論以外のところにもあることを印象づけた。それは、後日会ったとき、勧誘の後押しとして教団の他のメンバーが一緒に来る可能性を減少させるべく行った行為で、教団が一人の女性を用いた安易な手段で男性信者を勧誘することが多々あることを知っていたからであった。だが、実のところ彼女は、あの小憎たらしいマラルメの妹であることが信じられないくらいチャーミングで、気がつくとスコットは自分が演じる役に完全になりきっていた。また、マラルメは彼女の知的障害を語ったが、そんなそぶりは全くなく、むしろ一般女性に比してより知的とさえ見て取れた。
その後、スコットはエリザベートと何度か落ち合った。教団が様々な手練手管で信者を執拗に勧誘していることは周知の事実であり、スコットは教団のこの方針を利用した。エリザベートはスコットを脈ありと見たのか、自分の方から積極的に接触してきた。
本人を目の前にして、スコットはエリザベートを自己紹介に従って英語名のエリザベスと呼んでいたが、一度誤ってエリザベートと呼びかけてしまい、ごまかすためにしどろもどろとなったことがあった。同じ過ちを繰り返さないように、スコットはすぐに彼女に愛称の「ベス」で呼ぶ許可を取った。この申し出を聞いた彼女は、スコットが自分にひとかたならぬ好意を抱いていると思いこんでしまったようで、その後の態度も軟化し、スコットにとっては怪我の功名となった。スコットは何度か教団本部に誘われたが、それについては巧みに辞退し、それでも教団、そして彼女に興味がある振りをし続けた。
そうこうしているうちに、ついに教団襲撃作戦の当日となった。それは同時に、スコットによるエリザベート救出作戦の当日でもあった。
スコットは午後三時に彼女を呼びだした。彼女はその日は教団の集会があるといって断ってきたが、無論それを予期していたスコットは、ごく短時間の約束で言葉巧みに彼女の了解を得た。
待ち合わせ時間よりかなり前からスコットは待ち合わせ場所が見える喫茶店にいた。三時少し前に彼女は到着して彼を待ちはじめたが、スコットはその様子を隠れ見ていた。三〇分後、彼女が帰りかけたときになって初めてスコットは腰を上げた。スコットの遅刻に彼女はずいぶん立腹していたし、集会までの時間を気にして焦ってもいた。おかげでスコットに促されるままに、何も疑わず人気のない裏路地に連れ込まれた。スコットはそこで彼女をクロロホルムで昏睡させ、路地先に止めておいた車で宿泊先のホテルに運んだ。この辺の手並みはこの三年の間にみっちり鍛えられていたため、さして苦ではなかった。
彼女を部屋へ運ぶと、口と手足を粘着テープで留め、クローゼットへ押し込んだ。ちょうどそのときドアにノックがあったため、スコットは飛び上がった。ノックの主はマラルメだった。
「スコット、少し早いが行こうぜ」
「行くって、どこへ」スコットはマラルメの突然の訪問に度肝を抜かれていた。
「何言ってんだ、早く支度をしろ。今日限りあの忌々しい『垂れ下がる空間』とはおさらばだ」
「も、もちろんそうさ、マラルメ。今日こそ……」と言いながらマラルメの肩越しにエリザベートのいるクローゼットを見て、スコットは心臓が飛び出しそうなほど驚いた。クローゼットの扉から、エリザベートのスカートの裾が覗いているではないか。
「ん、どうした」奇妙な沈黙に気がついたマラルメは、スコットの視線をたどって振り向いた。マラルメの鋭い洞察眼はそれを見逃さなかった。
「おい、スコット! これがどういうことか説明してくれるんだろうな」
マラルメは床に落ちた長い髪を拾い上げ、悪戯っぽく言った。
「え、あ、いや」
「まあいいさ。だがデートなら明日にしてくれよ。今日がどれほど大切な日か本当に忘れちまった訳じゃないならな」
作戦本部は教団の集会所に近いアパートの一室に設けられた。スコットやマラルメ達は万が一不測の事態が起こったときのため、その部屋で武装を固めて待機していた。
八時に作戦が開始されて以来、無線を通じてひっきりなしに配置完了の報告が続いている。この作戦の総指揮を執るのはアメリカ海兵隊元将校のマクシミリアン・カウチマン、通称「鉄のマックス」である。こういった手荒い作戦は実に彼向きで、これまで彼は力押しで失敗したことがなかった。彼は自分の頭の中に描かれたシナリオ通りの無線連絡に、いちいちうなずいていた。
作戦が順調であるのを悟り、スコットはマラルメにエリザベートのことを打ち明ける潮時だと感じた。スコットはマラルメの膝をつつき、表へ出るように合図した。
部屋を出て、階段の踊り場までマラルメを連れてきてから、ようやくスコットは口を開いた。
「マラルメ、実は……」
そのときドカンと大きな音がして、アパート全体が大きく揺れた。あわてて階段を駆け上がると、作戦本部のドアの残骸がバラバラになって廊下に散らばり、部屋の中からは黒々とした煙が立ちのぼっていた。
「ばれてやがった」
マラルメは激しく毒づいた。スコットはエリザベートが誰かに救出され、仲間に連絡を取った可能性を考えて慄然とした。
「この分じゃ向こうもやばいぜ」
言いながらマラルメは走り出していた。途中で一度振り返り叫んだ。
「何してる。早く行こうぜ」
「し、しかし、本部の人たちが」
「これだけ大きな音がしたんだ、誰かが救急車を呼ぶさ。それにどのみち……」マラルメはそこまで言って目を伏せ、「早く!」と叫んだ。
垂れ下がる空間の集会場では、そんな騒ぎとは無関係のように静まっていた。集会場は工場跡の廃屋で、体育館のように広い床の彼方で、悠然とダバダの儀式が行われていた。集会に参加している人数は意外に少なく、せいぜい十人かそこらで、集会が教団幹部のみによるものであることがうかがえた。彼らは全員、頭からつま先までスッポリ被る黒衣を身につけている。儀式の中心にひときわ大柄な人影があり、一目でマッド・ベイと判った。彼だけは顔と腰に黒布をつけただけの出で立ちで、中世の死刑執行人を思わせる。その鍛え上げた筋肉は荒縄のように全身で張りつめ、蝋燭の仄明かりの中で黒く光っていた。
突撃をしたIDCの実働部隊は全員、大男の前にしつらえられた石舞台の上に順序よく並んでいた。まず頭、続いて胸、腹、腰、腕、脚という順番だ。大男の両手に握られた血塗られた戦斧が凶々しくきらめいた。
本部が爆破されて以来、スコットは作戦失敗の原因となった自分の愚行に、大きな自責の念を感じていたが、そのストレスはここに至り爆発した。小脇に抱えた自動小銃を乱射しながら、スコットは隠れ場所から飛び出した。マラルメが止める間もあらばこそ、である。マラルメは一瞬、やれやれといった風に肩をすくめてからスコットの後に続いた。
既に敵対者を全員始末したと思いこんでいたのであろう。スコット達は完全に相手の虚を突く形となった。自動小銃の前では十数名の狂信者など全くと言っていいほど無力だった。スコットとマラルメの目の前で教団幹部が次々と倒れていく。全身を覆っていた黒衣が裂け、鮮血に染まった幹部信者の姿が現れた。彼らは全員、顔といわず手といわず、真っ赤にただれ、青い血管がくっきりと網の目のように浮かび出て、まるで全身が内蔵のような姿をしていた。スコット達は彼ら幹部が全身を酸で焼いていることを知っていたが、さすがに目の前にそれが現れたときはショックを受けた。しかし、次の瞬間、スコット達は更に信じがたい現象に遭遇した。
新種の麻薬によるものだろうか。巻き上がる血煙の中、マッド・ベイの巨躯だけが降り注ぐ弾丸をものともせず立ち続けていた。大男は右手に持った戦斧を投げ捨て、ゆっくりとした足取りでスコットの方に近づいてきた。覆面の向こうで見ることはできないが、その口元には冷ややかな笑いが張り付いているに違いない。
スコットは黒い巨人に向けて連射した。確かな手応えがあるにも拘わらず、巨人は全くひるむ様子を見せない。スコットは恐慌をきたし、迫り来る悪夢から一歩も退けないでいた。マラルメは右から回り込み、大男の側頭部に何発か命中させた。覆面が裂け、中から現れた焼けただれた男の頭からは噴水のように血がほとばしった。それでも男は、今度は明らかにニッと笑うと、マラルメの方へ向けて鋭く手を振り上げ、なにやら小声でつぶやいた。
「うぉぉぉぉぉ!」
マラルメの悲鳴が空き工場全体に響いた。スコットが向き直ると、マラルメの左手の指先に何やら黒い物が見えた。それはやがて手全体を覆い、腕の方へ伸びていった。よく見ると、それはカサカサと蠢く黒い虫で、マラルメの左腕の皮膚を喰い破り、次から次へと止めどもなく湧き出てくるのだ。マラルメが泣き叫びながら激しく腕を振ると、虫達は一〇匹、二〇匹とまとまってボタボタ足下に落ちるのだが、それらの抜けた穴は瞬く間に埋められていった。
スコットの目の隅で動きがあり、彼は我に返った。見ると大男マッド・ベイがすぐ目の前に迫っていた。スコットはしゃにむに引き金を引き続けたが、マッド・ベイは意にも介さず、やがてスコットの銃が空しくカチカチと弾切れを知らせると、大男の顔に勝利の笑みが浮かんだ。
大男はスコットの首根っこを捕まえると、彼を壁に強く押しつけた。そのまま少しずつ足が地面から離れるのを感じ、スコットは相手の目を見据えて大きく目を見開いた。マッド・ベイの目は、明らかに殺人を楽しんでいた。万力のような力で喉を締め付けられ、スコットは必死に手足をばたつかせたが無駄だった。空っぽの肺は狂おしく空気を求め、鼓膜の奥では激しく血液が巡るゴーッという音が聞こえた。スコットが目玉を剥き出し、口から泡を吹き始めると大男は声を立てて笑った。自分の手の中で命の灯し火が消えてゆく様を眺めながら、彼は歪んだ絶頂感に浸っていた。スコットの意識が遠のき始めた。
そのとき、突然マッド・ベイが大きく傾き、スコットを捕らえていた戒めが緩んだ。スコットはすかさず相手の左手の小指を掴み、あらぬ方向へ力一杯捻った。コキリと音がして小指が折れ、スコットは束縛から解放された。マッド・ベイは片膝をついた。
激しく咳き込みながらスコットが見ると、マラルメがマッド・ベイの斧を相手の右足に叩きつけたことが判った。マッド・ベイの右膝はまさに皮一枚でつながっている状態であった。一方、マラルメの虫喰った左腕は、彼が自ら戦斧を用いて、肩口からすっぱり切り落としていた。マラルメは戦斧の柄をスコットの方へ押しやると、激しい出血のため意識を失った。
スコットは素早く動き、マラルメから渡された戦斧の柄を両手で掴むと、ずっしり重い鉄の塊を右肩に背負った。諸刃の重さを利用して、立ち上がりかけたマッド・ベイの頸と左肩の間に、黒く光る戦斧をたたき落とした。上体に巨大な質量エネルギーを受け、たまらず大男は四つん這いになった。再び立ち上がろうと半身になったところへ、スコットの第二撃目が炸裂した。マッド・ベイの取れかけた頭がだらんと背中に垂れ、不死身の巨人は声もなく絶命した。
エピローグ
マラルメが一命を取り留めたのは、まさに奇跡であった。奇跡を起こした張本人をホテルのクローゼットの中で発見したとき、スコットは魂を押し潰しそうな罪悪感から多少解放された。エリザベートはクローゼットの中で息をひそめていた。スコットが覗き込むと、彼女は眼差しで自分を戒めた男に、自分がこんな惨い目に遭っている理由を尋ねた。マラルメから聞いていた病気が再発したのか、それとも教団の呪縛から魂を解放されたのか、戒めを解かれ、クローゼットから出てきた彼女はスコットの知っていたエリザベートとは全くの別人のようで、どこか掴み所のない反応を示していた。
「たすけてくださって、ありがとうございました」彼女は間延びした声で言った。
病院で十数年ぶりに再会した兄妹は、それぞれに混濁した意識の中で互いを認めあって涙した。
それから四年が過ぎた。最前線からは退いたものの、マラルメは相変わらずだった。たとえ手足をもがれても、口さえ達者ならマラルメはマラルメでいられた。まあ、変わったことといえば弟が一人できたことぐらいだ。
その件について、スコットの方がむしろ深刻であった。スコットはまさに幸せのまっただ中にいるのではあるが、ただ一つ、マラルメという名の兄を持ったことが一点の黒いシミとなっていた。とはいえ、それ以外の点ではエリザベートとの生活は文句のつけようがなかった。確かにエリザベートは家事はおろが、自分の身の周りのことさえ満足にできるとは言えなかったが、それでも健気に努力する彼女のいじらしさはスコットにこれまでにない活力を与えた。ミシェルといたときはトーストさえ焼いたことの無かった彼だが、今はエリザベートと二人で、危なっかしいながらも何とかやっていた。生活そのものを楽しんでいた。
その夜も、いつものように二人で協力して作った、ステーキの形をした炭の固まりを横目に見ながら、ファーストフードの夕食をとっていた。彼女は食事の間、ひっきりなしにスコットの仕事について質問をしていた。もう何度も話して聞かせたテーマだったが、スコットは彼女に分かる言葉で根気よく説明した。
「じゃあ、そのダバダってわるい人なの?」
「いや、ベス、ちょっと違うな」スコットはエリザベートの素朴な疑問に微笑みながら言った。「ダバダが悪いのではなく、ダバダを悪いことに使おうとする人が多いんだよ。そういう人は他人を傷つけたり、殺したり平気でするんだ」
「ふぅーん。そんな人が、たくさんいるのね」
「奴らはいろんな所に隠れているんだ。道路工事のおじさんや、小学生の秘密基地、町役場の互助会のクラブまで、ほんとにどこにでもいる。たいていの場合、奴らのリーダーの名前や組織名にはBとMとGがついているんだ。ベス、君も気をつけろよ」
「スコット、あなたはそういう人たちを、どうするの?」
「正義の鉄槌を下すのさ」
「鉄槌?」
「うーん、お仕置きのことだよ」
「傷つけたり、ころしたりするの?」
「え、ああ、まあそういうこともあるかな」
「平気で?」
スコットは彼女が何を示唆しているか気づいて慌てた。
「平気なもんか。人を傷つけたり、殺したりするのは嫌なことだよ。だけど、僕たちがダバダに対してそうすることは、世界の人たちのためにいいことなんだ。僕たちは、ダバダの奴らとは違う。僕たちは正しいことをしているんだよ。僕たちの組織のバックには、ヴァチカンの法王様だってついてるんだよ」
「さっき、奴らはいろんな所に隠れているんだって言いましたよね」
「……」
その夜、スコットはベッドの中で暗い天井を睨みながら、まんじりともせずにいた。エリザベートの言葉が頭から離れなかったのだ。彼はこれまでほとんど疑問を持たずにIDCの活動に従事し、数多くのダバダ関係者を闇に葬ってきた。しかし、それは本当に正しいことなのか、ヴァチカンは本当に信じられるのか。スコットは頭の中で、ヴァチカン関係の様々な言葉にB、M、Gのアナグラムを試していた。
明け方近く、ようやくウトウトし始めたスコットは、息苦しさに目を覚ました。エリザベートの滑らかな手がスコットの喉に伸びていた。
「どうしたんだ、ベス。苦しいじゃないか」
そう言っているうちにも、エリザベートの手に徐々に力が込められた。
「おい、ベス。やめろ、ゲホッ」
スコットは身をよじったが、彼女は信じられないほどの力で締め付けてくる。スコットがこれほどの力を味わったことは、かつて一度しかなかった。そして、これだけの力があれば、自力で粘着テープの戒めを解くことなど造作もないだろう。
「奴らはいろんな所に隠れているんだ」エリザベートは夕食の時のスコットの口調をまねて言った。「奴らのリーダーの名前や組織名にはBとMとGがついているんだ」彼女の口元に残忍な笑みが浮かび、鋭い爪がスコットの喉に食い込んだ。
「B、M、G。ベス=マラルメ=ゴードン」スコットの耳元で彼女が優しく囁いた。
スコットは全てを悟った。
スコットが僅かに残された力を振り絞って彼女の顔をひっかくと、精巧に作られた彼女の仮面がズルリと外れた。薄れゆく意識の中、スコットは最期の瞬間に真っ赤に焼けただれた彼女の真の顔をかいま見たような気がした。