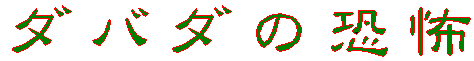
揚 明 朱 著
平 壌 万 里 訳
はじめに
愚痴を言うつもりはないのですが、ここ数年来ダバダ関係の本というと小難しい理屈ばかり。長ったらしい数式や、聞いたこともない学者の名を連綿と綴った本など一体誰が読むのでしょう。勿論、ダバダについて専門的に学んでいる学者先生達には有意義な本でしょう。しかし、ダバダの問題はそんな一握りの人間のものでしょうか。
このような状態が続けば、一般の人たちの心はダバダから離れてしまいます。ダバダに対して無関心な若者達が増加することは、私たちがこれまで築き上げてきた人類社会にとって大きな遺失となることは間違いありません。ダバダは私たちの生活に密着しているべきだと私は考えます。
このような信念を持って、私は本書の編纂を思い立ちました。私は自ら六年の歳月をかけて世界各国を歩き回り、ダバダに関係するような事件を拾い集めてきました。その中には、「私の町でも同じような事件があった」というものから、「え?
こんなものまでダバダなの」というものまで、実に色々な種類の話しがあります。全てが本当の出来事だとは言いません。中には身の回りで起こった不思議な出来事を単純にダバダと結びつけることで、自分たちの理解力に渡りをつけただけのものもあるでしょう。でも、どんなに現実離れした話しの中にも一握の真実が隠されているはずです。
民間のダバダ伝承のほとんどは素朴で、滑稽なものも多く、時々ちょっぴりホロリとさせる味のあるものばかりです。それは、私たちが忘れかけていた、心の深淵に潜む過去の自分にそっと触れる優しい手のようでもあります。
さあ、私とともにダバダの世界を楽しんで下さい。
*本書は「月刊ダバダ」1989年8月号から93年11月号に掲載された記事の中から主要なものを抜粋し、再編しました。
目次
邪能の石
妖星
暴動
発掘
川辺の石
異形放送
寄生
深海
血の日曜日
神殿
ビデオ
捜査
宇宙
魔術結社
儀式
雪原の遺跡
ダバタの拳
女子修道院
地下街
マネキン
遡行
臓器バンク
縊りの樹
邪能の石
一九六六年三月、ニューヨークに住むメアリ・カーネリアンは、ここ一年あまり連絡のない兄夫婦の住むワイゴミング州の山村に向かった。それまで毎月のように手紙をやりとりしていた両家族だが、兄嫁のマーガレットが臨月を迎えたことを知らせる手紙を最後に途絶えていた。
メアリが初めて訪れたその村は、どんよりと薄暗く、何やら妙な霧が立ちこめていた。道行く人は皆やつれた老人ばかりで、町そのものが病んだ感じがした。
メアリが訪ねていくと、迎え出た兄のユージーンはマーガレットと胎児が産褥のため亡くなったことを知らせた。久しぶりに会った兄は、どことなく疲れた感じで、ひっきりなしに奇妙な咳をしていた。妻と子を同時に亡くした男は、希望すら持てずに日々鬱々と暮らしていた。メアリが父母の待つニューヨークへ帰ろうと提案しても、兄は曖昧な返事しかしなかった。
兄がお茶を入れに席を外したとき、メアリはマントルピースの上に奇妙な銀色の小箱があるのに気がついた。それを見たとき、メアリは生前マーガレットに大きなサファイアの指輪を見せてもらった時のことを思い出した。鉛色の飾り気のない小箱をそっと手に取ると、それは何か生暖かく、脈動する感触がした。そっと蓋を開けてみると、中には琥珀でできた卵が入っていた。琥珀の卵の中には奇妙にねじ曲がった鶏の雛の死骸が入っていた。見つめるうちに、雛の死骸は皺だらけの瞼の奥の、裂け目のような片目を開き、彼女を見つめたような気がした。
途端に彼女の全身に言い難き悪寒が駆けめぐり、黒煙のごとき腕で臓腑を掻き回されたような不快感を抱いた。
その晩、彼女は赤ん坊の泣き声に目を覚ました。彼女はベッドを抜け出し、鳴き声のする方へ向かった。裏庭に壊れかけた納屋があった。泣き声はそこから聞こえる。納屋の戸を開けると、その奥に鉄格子のはまったもう一つのドアがあった。そっと覗いてみると、そこにはミイラ化しかけた女の死体が転がっていた。死体はボロ布と化した服をまとい、その胎は大きく裂けていた。左手にはマーガレットのサファイアの指輪をしていた。死体の傍らに、泣き声の主である赤ん坊が這っていた。しかし、その頭は琥珀の中の雛の死骸のそれであった。赤ん坊の鶏頭の嘴から「ダ……バダァ」と、か細い声が漏れた。
戸口で音がした。振り返るとそこに兄が立っていた。メアリはそっと眼を伏せて兄の傍らを通り過ぎ、自室のベッドに潜り込んだ。
翌朝も兄は無言で、気まずい雰囲気の中、メアリは挨拶もそこそこに家路についた。
それ以来、数ヶ月間月経の無かったメアリは、産婦人科医に予期せぬ妊娠を知らされた。そのような事に至る覚えはまるで無く、医師の診断に疑問を感じたメアリは、証拠のレントゲン写真を見せてもらった。レントゲンの黒い背景に浮かぶ白い影は、メアリの胎内に宿る何かを映し出していた。その、奇妙に変異した鶏のような頭蓋の影を見た途端、メアリは意識を失った。
妖星
グレゴールの旧い友人、ベルンハルト・レームは天文学者と言うよりはむしろ占星術師で、荒唐無稽な論文を乱発して学会を追われていた。
一九八二年六月、グレゴールの元に彼から久しぶりに手紙が来た。手紙には北の空、小熊座の脇に赤い星を発見したとあった。手紙に記された位置に赤い星など観測できなかったグレゴールは、遠方にいる何人かの友人に連絡を取り、星が見えるか確認した。しかし誰一人星を見た者は無く、グレゴールはベルンハルトの正気を疑った。
グレゴールが否定の手紙を出したのにも拘わらず、ベルンハルトはその後も毎日のように星の観測記録を送ってきた。ベルンハルトの妄想の記録によれば、彼の見つけた星は日々巨大化し、今では北極星に勝るとも劣らぬ輝きを見せている。様々な文献を当たったが、このような星の事を記した物は一つもないとのことだった。想像の産物を記した本などあるはずがない、とグレゴールは病気の友人に叱責の手紙をしたためた。ところが、星の手がかりを先に見つけたのは意外にもグレゴールの方だった。
グレゴールが問い合わせた遠方の友人の一人にパウルと言う人物がいた。彼のオカルト好きの大叔父が先頃亡くなり、パウルに大量の蔵書が遺された。その中の一つに「黒の星辰」という古文書があり、そこには北の空の赤い星、「闇に潜むダバダ座」の記述がある。それにはダバダ座を見つけた旅人の、おそろしく悲惨な最期が語られた挿話が付してあった。一見、他愛のない民間伝承のようではあるが、小熊座の脇の赤い星という奇妙な一致はグレゴールを不安にさせた。
このことを知らせたグレゴールの手紙を無視して、ベルンハルトは星の観測記録を送り続けた。最新の手紙で彼は、赤い星は月ほどの大きさに膨れ上がり、しかも星に奇妙な影がよぎるのを何度か見た、と知らせている。
グレゴールはもはやじっとしていられなかった。そんな事はないと思いながらも、心の何処かであの挿話の現実味を恐怖していた彼は、意を決してベルンハルトのもとへ訪れることにした。
ベルンハルトの住むケツァブルクの村まで、車でたっぷり七時間はかかった。グレゴールがベルンハルトの家に到着したときには既にとっぷりと日が暮れ、村の家々の窓には侘びしげな明かりが灯りだしていた。しかし、当のベルンハルトの家には明かりなど点いておらず、ノックしても返事がなかった。グレゴールは通りがかった村人に、ベルンハルトが森の方へ行ったと教えられた。
鬱蒼と茂る森の中でグレゴールはベルンハルトを三時間以上捜していた。すると突然森が開け、目の前に真っ黒い丘がそそり立った。グレゴールは丘の頂上にベルンハルトがいるのを発見した。声をかけようとした矢先、ベルンハルトの頭のすぐ上の空間に、紅蓮の裂け目が口を開けているのに気がついた。裂け目の奥では不気味に輝く白い牙が、粘つく唾液をした垂らせている。次の瞬間、空間に裂けた口吻はベルンハルトの頭を喰いちぎった。
暴動
一九九二年、ロサンゼルス市はピリピリと緊張したムードが張りつめていた。当時、黒人容疑者に対する白人警官達の暴行シーンを録画したホームビデオの映像は全米の茶の間を沸かせた。まあ、茶の間のあるアメリカ家庭はごく限られているのだが。とにかく、その評決が今日下されるのだ。
後年、その評決を巡って大変な暴動が起こったことは広く知られている。しかし、実際には暴動はその少し前から起きていた。
ロングフェスタ地区で暴動が起こったという知らせを受けて、アメリカDBDテレビのロケスタッフはロケバスを駆って町へ飛び出した。ディレクターのクリント、リポーターのオリビア、カメラマンのギルバート、ADのマイクの四人は、ロングフェスタへ向かう高速道路の高架から、下の街のひどい有様を目撃した。
ロングフェスタの街路には不潔でみすぼらしく、見るからに不健康でおぞましい様相の浮浪者じみた一団が何千人と溢れていたのだ。ロス中の下町を探しても、これほどの逸材は五人と揃えられないだろうと言う正真正銘の浮浪者達で街はごった返し、辺り一面に独特のすえたような臭いが立ちこめていた。
やがて一人の浮浪者がロケバスのいる高架上まで上がってきた。リポーターのオリビアは泣けなしの勇気を奮ってこの男にマイクを向けた。
「あなたは何処から来たのですか」
と彼女が聞くと、男はカサカサとした小声で答えた。
「フニャフニャと赤くふやけた男に連れられ、真っ暗な穴の奥で石を掘らされていた」
その時、ADのマイクは、この男が知り合いのヘンリーであることに気がついた。ヘンリーは数年前、新興宗教「垂れ下がる空間教」に入信し、それっきり行方不明となっていたのだ。この教団はダバダを神と崇めているという噂も高く、信者が行方不明になったという話しが後を絶たなかった。
マイクが声をかけるとヘンリーは一瞬驚き、返事をしようと口を開けた。するとその時、ヘンリーの口の中に黒い何かが溢れ、ヘンリーは息を詰まらせた。よく見るとそれは二センチ位の真っ黒いヒルのような軟体生物で、ヘンリーの口から次から次へと湧いて出てきた。更にヒルはヘンリーの全身の皮膚を喰い破り、その傷口からも蠢く姿を見せた。ヒル達はまるでビデオの早送りのように劇的に増殖し、ロケスタッフの見守る前で骨も残さずヘンリーを喰い尽くした。そして流れ出るように水はけから姿を消した。
下の町並みでは、全ての浮浪者達が同じような悲劇に見舞われ、街から浮浪者達の姿は消えた。しかし、この現象を目の当たりにした住民達は収拾のつかないパニックに陥り、街の混乱は収まるどころかいっそう激しくなっていた。
パニックに陥った住民の姿はその日の夜にも全世界のテレビに映し出された。しかし、その直前に起こった浮浪者達の出現と消失についての記録は、何か巨大な力によって全く削除されてしまった。
発掘
一九八四年、資産家であるサイモン・デイビス氏が亡くなり、その遺産は氏の唯一の肉親である、甥のトレミーに相続されることとなった。ところが、当のトレミーは何やら古代の遺跡に取り憑かれ、叔父の葬儀にも顔を出さず、今もってメキシコの奥地で発掘作業に没頭していた。そこで、最低限必要な手続きをとるように彼を促すため、サイモン氏の顧問弁護士であるネイサン・ヘイルズが現地に赴くこととなった。
人里離れた発掘現場を訪れたネイサンは、久しぶりに対面したトレミーの変容ぶりにしばし絶句した。トレミーは大学のバックアップを得て、当初この辺りで大がかりな発掘をしていたが、何年経っても全く成果がなく、ついに大学は資金援助を打ち切ってしまった。去りゆく同僚達を後目に、トレミーは一人黙々と発掘を続けていた。その姿は山賤さながらにみすぼらしく、痩せ細った泥だらけの手足も、ボロ布のような衣服も、巨万の富を相続した人間におよそ似つかわしくなかった。しかし、容貌の変異もさることながら、その血走った両眼に宿る狂気の兆しはネイサンの背筋に冷たいものを走らせた。
トレミーは遺産のことなどそっちのけで、自分の掘り当てようとしている遺跡の話に夢中だった。右手に持った古びた古文書を振り回しては、しきりに古代文明の驚異を熱っぽく語って聞かせたが、これはネイサンにとって久しぶりの手強い仕事となっていた。トレミーは、いよいよ明日こそ発見できるはずだと言ったが、一体いつから見た明日になるやら知れたものではない。とりあえずネイサンは今日はここに泊まり、明朝にでももう一度話をしてみようと諦めた。
ネイサンが起きたとき、既にトレミーのベッドは空っぽだった。ご苦労なことに、トレミーは日が昇るのを待って現場に出かけたようだ。テーブルの上には昨日トレミーが振り回していた本があるのが目に止まった。
「封印都市ダバッダ」
これを見たネイサンは戦慄を禁じ得なかった。この本について彼は、生前のサイモン氏から聞き及んでいた。サイモン氏は自宅の書斎から紛失したこの恐るべき本を、見つけ出したらただちに焼き払い、それを読んだ者も処分するように、日頃冷静なサイモン氏に似つかわしくない、狂おしい口振りで語っていた。その声にただならぬものを感じていたネイサンは発掘現場に急いだ。
ネイサンが現場に着くと、トレミーは目前の切り出された断層に浮かび出た太古の都市の門扉の前で狂喜していた。都市の門には人間の作とも思えぬ奇妙な歪みが生じ、見ていると眼がチカチカした。異様な黒い石でできた巨大な両開きの門扉には、ネイサンがこれまでに想像だにしたことのないグロテスクな怪物たちが無数に薄浮彫にされていた。
ネイサンが止める間もなく、トレミーは門扉の間にピックを打ち立てた。一瞬大地が鳴動し、門扉がゆっくりと開く。かび臭い異臭が立ちこめ、門の中から粘液まみれの緑色の触手が無数にのたうち出て、巨大な「それ」が現れた。
川辺の石
李寥嚥少年が学校の帰り道、炉寧川の河岸にその奇石を見つけたのは一八九一年の秋口だった。緑色の石に赤い斑の浮いた、綺麗と言うよりはむしろ不気味なものだったが、李少年はその石が妙に気になり、手に取ってみた。石はなにやら脈打つようでもあり、得体の知れぬ息吹が感じられた。少年は石を持ち帰り、自室の小箱にそっと忍ばせておいた。
生まれつき足が不自由で、気が弱い李少年にとって、学校はあまり楽しい所ではなかった。同級生のほとんどが、彼のことを遠巻きにしながら嘲笑しているように思えてならなかった。時には善人面で声をかけてくる優等生君もいるが、そんな安っぽい同情はまっぴらだった。学校で友人のできない李少年にとって、この石は唯一の友人と言えた。少年は自室で石に話しかけることが日課となった。時には脈打つ石が少年の言葉に反応するように思えることもあった。少年が石に名前を付けようと思い立ったとき、少年の脳裏に遥か彼方から「ダバダ」と囁きかける声があった。そこで、少年は石を「ダバダ」と名付けた。石は小箱の中で少しずつ成長しているようで、少年は少し大きめの箱を見繕う時期だと思った。
ちょうどその頃、少年の村ではちょっとした事件が起きていた。近所の鶏小屋が野犬に襲われる事件が続発していたのだ。どうした訳か、近年この辺には妙に野犬がたむろする兆しがあり、李少年も何度か追いかけられ、怖い思いをした経験があった。
大人達の夜警にも拘わらず、家畜の被害は増大し、ときには豚が襲われることもあった。李少年は野犬が恐ろしく、家に閉じこもりがちになった。少年は石に向かって、怖い野犬がいなくなればいいのに、と語りかけた。
翌朝、村の広場で野犬の死骸が山積みになっているのが発見された。少年は驚愕の面もちで石を見た。
ところが、野犬が退治されたというのに家畜の被害はなくならなかった。それどころか、昨日に至ってはついに人間の赤ん坊が喰い殺された。揺りかごに寝かしつけられた赤ん坊から母親がちょっと目を離したわずかな隙に、何者かが赤ん坊の頭を喰いちぎってしまった。室内には足跡もなく、いったい何者の犯行なのかと村人達は眉根を寄せた。
その後数ヶ月間に八件にも及ぶ殺人事件が起こった。悲鳴に驚いて窓の外を見た村人の一人は、隣人が何かに連れさらわれるのを目撃した。それはヒグマほどの巨大な怪物で、絶叫する隣家の男を軽々と引きずって森に消えたそうだ。
李少年はこの話に身震いした。本当に恐ろしい世の中になったものである。とはいえ、世間ではそんな怪物が騒がれているようだが、李少年にとっては身近ないじめっ子の方が問題であった。今日も弁当の中に毛虫を入れた奴がいた。
「まったく、そんな奴はいなくなってしまえばいいんだよね、ダバダ」
と少年が呼びかけると、脈動する奇石はヒグマほどにも大きくなったその身を震わせて答えた。
異形放送
イギリスはマンチェスター近郊のロブエートの町にその事件が起こり始めたのは一九九二年八月だった。午後八時五九分、その地域一帯の全家庭のテレビに突然異形のものが映し出された。画像は不鮮明ではっきりとは見て取れないが、何
やらこげ茶色と赤の斑の生物のようで、魚じみたようでもあり、ヌメヌメとのたくり回る原形質の不気味さの中に、似つかわしくない知性のきらめきがあった。
それはカサカサと聞き取りづらい話し声とも鳴き声ともつかぬ音を発した。
「ジュッジュ、ビキヤ、ル、ダバダダダ、キュキュッ、ダバダッ」
放送はキッカリ一分間続いた。
翌日の病院は大混雑だった。子供や老人など、抵抗力が弱い者がまず犠牲になった。関節の痛み、偏頭痛、黄疸などが主な症状で、原因は判らなかった。その日の夜も八時五九分から、昨夜同様の放送があった。異形の者はチャンネルと無関係どころか、電源が切れていても映し出され、出荷中の荷箱の中や、廃品処理場に打ち捨てられたテレビでさえ、その不気味な映像を映し出す始末である。
放送は何日も続き、病院はパンク寸前であった。症状は次第に重くなり、四肢の骨が奇妙な方向に捻れ、頭蓋骨が軟化し、皮膚は樹皮のように変質し、曲げた関節が裂けて透明な粘液が流れ、ついに死亡者まで出る始末であった。
ロブエートの町役場では対策本部を設けた。各地の名医を呼び集め、これまでに類を見ないロブエート病と名付けられた奇病の大量発生に侃々諤々の議論が続いたが、唯一一致した見解は、ロブエート病があの異形の放送に関係があるのではないかという事だけだった。理論的な説明はできないが、ロブエート病が発生した時期と異形の放送が始まった時期が一致していることと、テレビの無い家庭ではロブエート病が発生していないことが統一見解の理由であった。
対策本部では応急処置として各家庭のテレビを全て回収する事となった。これについては、特に若い層からの強い反発があったが、町当局側は強硬にこれを行使した。そのおかげか、ロブエート病の発生数は激減した。
しかし、中には当局の対策に楯突く輩もいるものだ。
スチーブン・ギャロットはそんな反骨精神旺盛な若者の一人であった。彼が三日も連続して無断欠勤している理由について、会社内ではちょっとした噂になっていた。スチーブンの会社の同僚であり、つき合いだして二年目の、ちょっとギクシャクし始めた恋人でもあるステフ・デュモーリエが心配するのも無理からぬ事である。
町外れのスチーブンの家のドアを合い鍵で開けたステフは、彼の部屋の散らかりっぷりに辟易した。しかしスチーブンの姿は何処にもない。捜し回るステフの耳に地下室の方から物音が聞こえた。まっ暗い地下室へ続く階段を壁づたいに降りたステフは、スチーブンの名を呼びながら手探りで電灯のスイッチを入れた。瞬きながら灯った蛍光灯の薄明かりに浮かび上がる、小型テレビの前に座ったスチーブンだった「それ」は、テレビでお馴染みの「あれ」だった。
寄生
メンデルソン教授が大学の図書館に隠された書棚があることを発見したのは一九四六年のことであった。封印されたたくさんの本の中で、教授が特に関心を示したのは、その序文に不老不死の術法と記されている「永遠のソフ=メダタイの秘法」というタイトルの本であった。
メンデルソン教授には八年前に結婚した二四歳年下の妻がいた。当初はそれほど感じなかったが、六〇歳に手が届く年齢となっていささか男の威厳を保ち難い状況となってきていた。その焦りが禁断の魔道書に付け入る隙を与えてしまったのだろう。
教授は講義もそこそこに大学から退出し、帰宅早々自室に籠もり、震える手で黄ばんだページをめくった。最初のページにあるソフ=メダタイなる人物の肖像画、両目が異常につり上がり、口元が嘲るように歪んだその顔から察するに、一六世紀最高の魔術師を自称するこの若い男はたいそう鼻持ちならず、人を不愉快にさせる術に長けた人物であったに違いないと思われる。この本自体が件の魔術師自らの手によるもので、文章のそこかしこに傲慢さと虚栄が感じられ、教授は読み進めるうちに無性に腹が立った。とはいえ、そこにもし不老不死の秘密があるのならと、教授は藁にもすがる思いで読み続けた。
一通り読み終え、今度は秘術を施す儀式を執り行う段となった。本に記された材料の多くは、日常的に家庭で使われる物であったが、中には非常に入手困難な物もあった。教授は毎日、学校から戻るとすぐに自室に籠もって儀式の準備を夜更けまで続けた。
ついに儀式の準備が整い、星々の位置も程良く、いよいよ不老不死を手に入れる時が来た。教授は魔道書に従って魔法陣を描き、古の印を切り、特別に調合した香を焚き、呪文を読み上げた。
「ノニキュモクヒ、ダバダ。ホアホアジゥュ、ダバダ!」
香炉から放たれた煙が螺旋を描いて教授の周囲に立ち上った。教授は何が起きるかしばらく待ったが、特にこれといって変化の兆しはなく、立腹のあまりこのインチキ本を足下に叩きつけた。
しかし儀式は目に見えない成功を収めていた。このところ研究ばかりで自分を省みない夫に嫌気がさしていた妻だったが、その日以来急に親切にされ、かつてのような情熱を傾けてもらえることに今は満足していた。だが、幸せは長くは続かなかった。年齢の差に対する負い目がなくなったためだろうか、教授は次第に横柄な振る舞いが多くなり、妻を傷つけるようなことを平気で言い、時には人前で悪しざまに妻を罵ったりした。やがて妻に対してだけでなく、同僚や生徒、助教授たちに対しても不愉快で鼻持ちならない態度をとるようになった。
ここ数日毎朝そうであるように、その朝も教授が洗顔をしてると顔の皮膚が大量にこそげ落ちた。教授は鏡の向こうに写し出された、両目の異常につり上がった自分の姿に向けて、復活を祝い口元を歪ませた。
深海
一九八五年一一月一九日、日本海沖二〇〇キロの所に深海調査団の巨大な母船があり、その眼下八〇〇〇メートルの所には、日本の誇る深海調査艇「しじま」があった。「しじま」は全長八メートル、完全な遠隔操作ができるが、二人まで乗り込むこともでき、計算上の最大深度は一三〇〇〇メートルとされている。
「しじま」は現在、六〇〇年前に沈んだ朝鮮の商船を調査中であった。いくつかの文献によれば、この商船には莫大な財宝が詰まれているという事であった。中には商船を蛇婆堕教団が買い取っていたとする文献もあり、学術的な意味でもその価値は計り知れないものであった。三ヶ月に及ぶ集中的調査により、ようやく一昨日にその正確な位置がつかめた。
母船のモニターに、「しじま」の強力な特殊ハロゲンライトに浮かび上がる大昔の商船の映像が送られてきた。学者と呼ばれる山師達がモニターに映る不鮮明な画像を食い入るように見ていた。商船は深海に沈んだため、海藻や貝類の付着はなく、比較的美しい状態であった。そして驚くべき事に、船体は凄まじいほどの水圧に耐え、ほぼ原形をとどめていた。昨日の調査で判明していたこの件については学者達が様々な見解を提示した。しかし、ようやく導かれた結論は「もっとよく調べないと分からない」というものであった。そこで今日は、島村教授と相模技師が初めて「しじま」に乗り込んでいた。遠隔操作だけでは埒が開かないと考えた教授が自ら志願してのことであった。
しばらくすると、モニターの隅にまた例の影が映った。ここ数日、この辺りの海底を調査していると必ずと言っていいほどこの影が映るのだ。人影のように見えるが、無論こんな深海に住む人などいない。モニターの故障も考えられたが、はっきりした原因は掴めないでいた。相模が影の方に素早くライトを向けたが、モニターには何も映し出されなかった。
ところが、教授は何かを発見したような調子で潜水艇を転回させるよう指示し、相模の方も興奮した様子でこれに従った。母船の乗組員が何を見つけたのか尋ねると、教授も相模も「あれが見えないのか」と言い返すだけで、それ以上説明し
ようとしない。「しじま」は見えない影を追いかけて暫し海底をさまよった。
そのとき、ゴゴゴ……と地響きがあり、母船が大きく傾いた。海底地震だろうか。「しじま」からの映像も大きく揺れていた。教授が「あれを見ろ」と言うと、モニターの右側に映っていた異常なほど細長くそそり立つ岩の列が隆起し、「しじま」を包み込む形で倒れてきた。それは、あたかも巨大な蛸の足のようであった。いや、見れば見るほどに、ウネウネと絡み合う様子と言い、一面に張り付いた吸盤状の突起と言い、蛸でないにしても、全長数百メートルにも及ぶ巨大な海棲生物の一部であるように見えるのだった。映像はそこで途切れ、音声も教授と相模の絶叫を最後に届かなくなった。
翌朝、近くの海上に「しじま」を発見した調査団は、「しじま」が外見上全く損傷のないことにまず驚き、続いて船内に残された二体のミイラに驚いた。
血の日曜日
一九〇五年一月二二日、ロシアの首都ペテルスブルクでデモ行進する労働者達に向けて軍隊が発砲した。世に言う「血の日曜日事件」である。デモ隊の中心はゲオロギー・ガポン率いるペテルスブルク工場労働者組合であった。しかし、二千人の組合員の内、生き残ったのは山岳地帯に逃げ込んだ僅か数人だけだった。
イワン・パステルナークは這々の体で山に逃げ込んだ中の一人である。とは言え、いずれ山狩りが行われみんな捕らえられるだろう。仲間からはぐれたイワン自身もそのことは覚悟していた。それにしても憎むべきはパヴェルである。
ガポンは無知な労働者達に人間として誇りを持って生きることの意義を説いていた。彼の目指す理念は、難しく言えば、本当に難しすぎてイワンには解らなかった。でもガポンはそんな者達のために、自らの理念を古代フェニキアの「正当な対価」を司る神の名を取って「ダバダ」と教えた。理論の理解できない労働者達にも、信仰は理解できた。労働者は「ダバダ」を合い言葉に団結した。
しかし、幹部の一人であるパヴェルが、「ダバダ」は邪神の名だと指摘した。パヴェルの祖母が蒼い顔をしてそう言ったそうだ。年寄りの戯言を真に受けるなんて馬鹿げている。それでも幹部パヴェルは組織の中の不平分子として徐々に力を付けていった。そして今日、ついに軍隊と内通し、身内のデモ隊に対して発砲させたに違いない。
イワンは前方の林の向こうに人家の明かりを見つけた。狩猟小屋か何かだろう。イワンは夜露をしのげる幸運に感謝しながら小屋に近づいた。小屋の中には人影はなかったが、ランプも灯り、先ほどまで誰かがいた形跡があった。
小屋の隅の床に地下室への入口の蓋があった。ここに隠れれば捜索隊をやり過ごせるかも知れない。イワンはそっと蓋を開け、真っ黒い口を開けた地下室へ降りていった。地下は意外と広く、手探りで壁づたいに進むうち、天然の洞窟に続
いていることが分かった。洞窟の回廊を進むと前方に仄明かりがあった。
天然の大広間には、一面に石筍を思わせる奇妙な人型が並んでいた。三〇センチほどの人型はザッと二千体程もあり、そのほとんどから奇妙な白い煙が立ち上っていた。煙の行き着く天井付近には黒いクラゲのような異様な物体が蠢いていた。胴体下部から無数に生えた、粘液を滴らせる長い触手の先にはパクパクと開閉する孔があり、そこから煙を吸い取っていた。作り物なのだろうか。
「これがダバダだよ。えーと、たしかイワン君だったね」後ろからの声に振り向くと、ガポンがいた。「君たちの魂は皆ダバダに捧げる。本当はもっとスマートにやりたかったが、結果は変わらんだろ」右手の銃が不吉な光を放っている。
「そ、それでは、先生が我々を軍隊に売ったのですか」
質問の答えは銃声だった。イワンは信じられないといった表情でガポンを見つめた。ガポンは足下で死にゆく若者をせせら笑った。
次第にかすれてゆく視界の先で、広間の片隅に置かれた人型から新たに一筋の煙が立ち上った。
神殿
一八一一年、中央アフリカはウバンギシャリの奥地に踏み入ったフランスの探検隊は、ジャングルの奥に巨大な建造物を発見した。それは、エジプトやインカに引けを取らない巨石で築かれた建物で、規模ではそれらを遥かに凌ぐ物だった。
それは王宮、王墓、神殿のいずれか、おそらく神殿であろうと、探検隊に同行していたティエール教授は推測した。それにしても、人間が使用するには不適当なほど巨大で、黒っぽい石が複雑怪奇に組み合わさり、捻れ生じた柱の上で、歪んだ天井石が不安定なほど微妙な角度で設置されていた。
探検隊にとって困ったことに、この建物を見つけた途端、現地人の案内人達は凶相もあらわに「ダバーダ、ダバーダ」と叫びながら全員逃げ去ってしまっていた。まあ、いずれにしても、この辺りまで来ると現地人といえども知っている道など無く、眼前に迫った世紀の大発見に比べればそれすらも些事に思えた。
隊長のアラン・ド・ボーダン卿は興奮に目を血走らせて一向に前進を指示した。ティエール教授の見解によれば、この建築物は神殿で、少なく見ても二六〇〇年以上前の物であるという。神殿の周囲には、さまざまなポーズの人物のレリーフがあり、当時の生活様式が現代に非常に近いものであることが伺われた。
探検隊は神殿の奥に入っていった。松明で照らし出された壁面にもいっぱいにレリーフが施されている。今度は当時の文明の片田舎の風景だろうか。服装といいポーズといい、先ほどに比べやや垢抜けない感じがした。そして、その意味が次第に分かりかけてきた。長い回廊を先に進むに連れ、レリーフに描かれた人物は猿に似た人物になり、やがて完全に猿になっていた。ティエール教授はこの一連のレリーフが、当時の人間のユーモアか、または当地の変身神話に基づく物であると仮説を立てた。そのうちにもレリーフは猿から次第に四本足の獣に変わり、ネズミに変わっていった。すると突然、レリーフに巨大な竜を象った物が加わり、奇妙奇天烈な神話の怪物が跋扈する風景に変わっていた。一行はレリーフに魅せられて、神殿の奥へ奥へと進んでいった。
レリーフに見とれ、一行から遅れてしまったフェリ助教授は信じがたい光景に遭遇した。前を行く隊員達の剥き出しの手足にはしだいに硬い毛が生え、様相は猿のようになり、やがて身が縮んで四つ足の獣となっていった。それはあたかもレリーフの再現であり、当時の彼らには知る由もなかった進化の逆転であった。彼らは夢中で先を目指し、自分たちの身に起こった変異に気がついていなかった。あるいは、それに気づくほどの知性など、とうに失っていたのか。フェリ助教授は悲鳴を上げて神殿を後にした。
残された隊員達はカサカサと地を這う虫となり、目に見えないほどの微生物となって進んでいったのかもしれない。彼らが進む先、太古より一度たりとも光の射し込むことのなかった奈落の深淵に、あらゆる生物の源となるべき何かがいるのだ。それは、その不定形の体を蠢かし、伸縮する不浄の腕を廻して、間もなく来訪する予定の、自らの遠い子孫たちを待ちかまえていた。
ビデオ
リクロニッチ博士はダバダについて広く世間の認知を得ようと画策する経済物理学者であった。しかし、一九九一年のこの時点でも、ダバダのことは禁忌の的とされており、彼の言葉に耳を傾けようとする者は少なかった。
彼の意見に同意する数少ない人物の一人にビル・マードックというテレビ関係者がいた。彼はリクロニッチ博士監修のもとで全一二回のテレビシリーズ、「現代ダバダの実態」を制作した。しかし、懸命の努力にも拘わらず、このシリーズにはスポンサーが付かず、番組は放送されぬままお蔵入りとなった。ビルはこのことを残念に思い、シリーズを六本のビデオとして販売する手はずを整えた。
第三巻まで出た時点では、ビデオの評判は思った通り今一つでたいした話題にはならなかった。しかし、四巻が出た頃、ある雑誌が妙な視点からこのビデオを取り上げた。ビデオの各巻の最後の最後、クレジットが出終わり、映像が途絶えてしばらくした後、ビデオは再び映像を映し出すのだ。それはリクロニッチ博士が、誰ともつかぬ程バラバラにされた人間の死体の前でナイフを振るっているシーンを写した三〇秒ほどの映像であった。一巻から順を追って時間を遡っているので、四巻目に至ってついに犠牲者が男であることが分かった。
何故このような映像が挿入されたのかビルにも解らなかったし、リクロニッチ博士自身も身に覚えのないことであった。ところが、しばらくして警察が博士のもとへ訪れ、殺人の容疑で連行していってしまった。
ビルは途方に暮れながらも、予定通り五巻を発売した。これについては、死体の映像が入らないよう、ビルが直々に入念なチェックをした。にもかかわらず、五巻にもやはり殺人現場が映っていた。今では死体は首がないだけで、残りはほぼ完全な形となっていた。このままなら最終巻で死体の正体が分かるだろう。ここに至ったとき、ビルは死体の正体をむしろ知りたいと考えていた。
数日後、博士は証拠不十分のまま釈放されたが、留置所から出てきた博士の精神的衰弱は狂おしいまでのものがあった。犯人に仕立てようとする取調官の執拗な努力が実ったのだろうか、博士は、あるいは自分が殺人を犯したかもしれないと考えていたようだった。FBIの特殊取調官を称する、不気味な黒服の男が何人も取調室に出入りしていたという噂もまことしやかに囁かれていた。おかげで博士の精神はボロ雑巾のようになってしまい、ここ数日というもの、突然大声で泣き出したり、部屋の隅で乾いた笑いを立てたりしていた。
六巻はビルと博士、そして警察の関係者が徹底的に検査をするという条件で発売した。しかし、ビルにはチェックしても無駄だと分かっていた。博士とビルは会社の会議室で、先ほど近所の店で購入したばかりの「現代ダバダの実態・第六巻」を見ることにした。一二〇分の番組部分を早送りし、クレジットを素通りして問題の部分にさしかかった。するとどうだろう。ビルの前のビデオ画面には、まるで鏡を見るように、ブラウン管の前に座った自分と博士の姿が映っているのだ。博士の手に握られた震えるナイフは何を意味するのだろう。
捜査
平成六年八月、年齢も性別もバラバラの八人を続けざまに殺害した連続殺人犯、染野省也を取り調べていた刑事達は、その奇怪な陳述に度肝を抜かれていた。
学生時代の染野はいたってまじめな性格で、成績も中の上と云ったところ。明るく快活な彼は友人も多く、クラブではサッカーの選手に選ばれていた。冗談が好きでクラスの人気者でもあり、女子生徒の密かな憧れの的にもなっていたようだ。
そんな彼が友人達と連れだって渋谷の地下街を歩いていると、少し薄汚れた男が隅の方に座っているのが目に付いた。男の前には黒い布が敷いてあり、その上にはタイトルのない黄ばんだ本が一冊だけあった。染野が男に近づくと、男は目深にかぶった帽子の縁越しに、胡乱な目で染野を見た。染野が男に「この本は売り物か」と尋ねると、男は「最後の一冊だ。千円にまけとくよ」とかすれ声で言った。黄ばんだみっともない本が千円というのはちょっと高いような気もしたが、周りの友人達がそれを期待しているのを肌で感じた染野は虎の子の千円を支払った。その場でページをちょっと開いた染野はすぐに後悔した。本の中は手書きの細かい文字がびっしりで、これを読むのは骨が折れそうだった。やっぱり買うのをやめようと染野が顔を上げたとき、本売りの男は忽然と姿を消していた。
染野がその本を読もうと決心するまで、実に六ヶ月がかかった。彼が自室を掃除していたら、本棚の奥から偶然その本が出てきたのだ。掃除をサボりたい気持ちも手伝って、最初の数ページをパラパラと読んでみた。しかし、そこに記された驚愕の事実に、染野はいつしか時の経つのも忘れ、読書に没頭してしまった。この本を読んだことが彼の人生の一つの転機となったことは間違いない。
染野は世界が歪んだダバダの力により、分子レベルで崩壊する刻限が迫っているのを知った。それを引き延ばすために誰を殺すべきかも知った。彼は殺すべき人間を見つけると、可能な限り迅速かつ巧妙に殺した。最も効果的で、最も露見しにくい殺人方法が不思議とひらめくのだ。その実行にあたって躊躇などしかった。六歳の子供から四九歳の会社員まで、殺すべきだと思った者を次々と殺した。それは確かに殺人ではあるが、必要な殺人だと染野は考えていた。自分は逮捕されてしまったので殺人を続けられないと、残念がってサメザメと泣きさえした。
警察は染野を凶行に走らせた本を染野の部屋で発見、押収した。そして、ダバダ研究家にこの本の分析を依頼した。ところが、どのダバダ研究家もこの本の中をちらりと覗いただけで、たちどころに恐怖に取り憑かれ、早くその本を破棄するようにと警告した。何でもその本は、日本ダバダ界創生期の怪人、田口寛重の直筆によるもので、興味の先に立つ研究家の間でも「外典ダバダ伝」と呼ばれて恐れられている書物だという。
専門家が頼れないのなら自分たちで分析するしかないと考えた警察は、一人の警部にこの本の解読を任せた。翌日、この警部は拳銃を持ったまま失踪し、今もその行方はようとして知れないでいる。
宇宙
一九九五年七月に打ち上げられた、アメリカのスペースシャトル、エンデバー号に一人のダバダ狂信者が潜り込むという事件が起こった。
ロバート・ハウントの名はダバダ研究家の間ではかなり有名で、穏健派と言われるグループ内でも、この狂人を何とか合法的に処刑したいと考える者が多いほどの悪辣ぶりであった。ただ残念なことに、NASAの内部でこのことを知る人間がいなかったため、ロバートは偽の経歴を使ってまんまと訓練生に紛れ込んでいたのだ。テレビに映し出された乗組員の名簿を見て仰天したダバダ研究家も多いはずだ。
NASAはもともと情報の一部を隠蔽する体質があるが、この回の飛行に対しては最高機密に近い扱いとなった。しかし、秘密とは必ず漏れるもので、ロバートの名に危険を感じた様々な調査機関が血眼になって情報をかき集めたかいあって、その時の管制室のボイスレコードが流出した。
シャトル発射から六時間ほどしたとき、ロバートはおもむろに何かの古文書を取り出し、忌まわしきダバダの呪文を口に上らせ始めた。搭乗員も管制室も、彼が何をしているのか気づかなかった。やがて、シャトルの右上の方向に空間の歪みが生じ、大きく裂けた暗黒の虚空から何かが現れた。搭乗員達は口々に絶叫し、祈り、呪った。彼らの言葉からそれを推測すると、シャトルの一〇倍はあろうかという昆虫の複眼のようで、七色に輝く巨大なシャボン玉のようで、ブヨブヨと息づく小惑星大のバフンウニのようで、邪悪な意思を昂然と放ち続ける毒キノコのお化けのようで、何が何だか分からないがとにかく「ウギャー」という物だったようである。
この物体はNASAをはじめ、世界各国の軍事・気象・航空レーダーに映り、南米チリでは肉眼でも目撃されている。また、霊感の強い者の多くはその瞬間、得も言われぬ寒気と圧迫感に苛まれたという。
その後、シャトルに何が起こったかは明らかではない。シャトルは予定通りに帰還し、搭乗員達にも身体的・精神的変調は認められなかったという。
ところが、この現象の結果は意外なところから明るみに出た。事件から半年後、ニューヨークのとある警察署に二人組の男が血相を変えて飛び込んできた。彼らの話によると、彼らはその日、強盗目的で男を一人殺害した。被害者となった中年男は妙に無表情で、強盗に驚くでも抵抗するでもなかった。しかし素直に従う風でもなかったため、苛ついていた彼らの一人が発砲した。頭部に弾丸を喰らった男の銃創から、黒くて細長い軟体生物が這い出てきたかと思うと、男の体は見る見る泥のようになって溶けてしまったそうだ。
二人組の強盗は覚醒剤を使用していたためただちに逮捕されたし、この事件も幻覚のためだと簡単に片づけられた。念のため現場へ派遣された警官はそこで泥まみれの衣服を発見した。ポケットにあった身分証から持ち主がNASAの職員で、先頃ロバートと共にエンデバーに乗った搭乗員の一人である事が判った。
魔術結社
イギリスには一九九三年現在でも三百を越える魔術結社がある。魔術結社といっても、そのほとんどは穏健なもので、ちょっぴり子供じみた大人の社交場といったところであった。無論本人達は大まじめである。
エリオット・バーバーも六人の仲間達と一緒に「月の視線」なる魔法結社を作った。魔術結社は暗号名を持つことが多く、月の視線は「M∴V∴」で表された。
結社は作ったものの、当初はこれといってすべき事もなく、他の魔術結社の見よう見まねで黒ミサじみた集会や、魔術理論についての討議などしていた。活動を本格的なものとしたいM∴V∴は、幽霊屋敷として名高い郊外のうらぶれた空き家を共同購入し、そこを結社の本拠地とした。そこにはかつてベスタニアという名の魔女が住んでいたというもっぱらの噂で、結社にとってこれ以上条件の揃った家はなかった。魔女が焚刑に処された噂が更に箔をつけた。
結社のメンバーの一人、アンソニー・ステクスはこの家の埃まみれの屋根裏部屋で「エーケルマーの福音書」なる本を見つけだした。魔女の家にあった本ならば魔道書に違いないと興奮気味に語るアンソニーは、イタリア語の得意なメンバーのエズラにこの本の翻訳を依頼した。
しばらくして、この二人が小屋の中で死んでいるのが発見された。遺体は外傷が無いにもかかわらず全身の骨が抜き取られていたため、怪奇事件として新聞に取り上げられ、一方で警察の捜査は難航した。エズラの手には例の福音書が握られていて、その本は葬儀の席で遺族からエリオットに託された。
アンソニー達の怪死と福音書の間に深い関係があるのは明らかだった。エリオットは福音書をひもとく前に、用心深く魔女ベスタニアについて調べ始めた。魔女は知りうる限り、一六六四年には既にそこに居た。そして、焚刑される一八一一年まで、実に一五〇年近くもそこに居続けたのだ。魔女を焼いた灰の中から一羽のカラスが飛び立ったという記録もある。
エリオットは続いて福音書の解読にかかった。途中のページにエズラのしおりが挟まっていた。「生命の秘法」と題されたページである。エリオットの脳裏に閃くものがあった。
翌週末、エリオットは封鎖されたM∴V∴の本部に他のメンバーを集めた。また、大学の級友にも片っ端から声をかけた。実に四二人の男女が、エリオットの言葉に従って、物々しい武器を携えて集まった。
エリオットは福音書に書かれた呪文を詠唱し始めた。推測が誤っていれば大恥をかくことになるが、むしろ彼はそれを望んでいた。騒ぎを聞きつけ地元の警官もやってきた。ちょうどその時、小屋の地下からドスンという音が響いた。小屋には知られざる地下室があったのだ。巧みに隠された部屋の隅の秘密の扉が開き、縺れ髪を振り乱して彼女が姿を見せた。
その後に起こった阿鼻叫喚の様子について敢えて語ろうとする者はいない。エリオットを含む一四人が死に、一〇人以上が今も精神病院にいる。
儀式
一九七〇の春から夏にかけて、スペインのウエスカという町の住民は、大挙して町外れの森に住み着いたジプシーのような一団にほとほと困り果てていた。流浪民達は夜中に不気味な儀式を行うため、夜になると決まって周囲の山々に単調なドラムの音が響いた。地域住民は森の奥から響く奇怪な叫びに仰天して、真夜中に飛び起きることもしばしばだった。
地元の警察が流浪民のリーダーに注意をしたが、それでも夜になると不気味なドラムが響くのだった。ある朝、森から流れ出る川の河岸で嬰児の死体が発見されたため、ついに警官隊が儀式を奇襲することとなった。奇襲隊には地域の有志も多数参加し、手に手に武器を持った三〇人からの男達が、ドラムの鳴り渡る暗い森の中に足を踏み入れた。流浪民達を威嚇して追い払うのが奇襲の目的だが、奇襲隊の中にはそれ以上の成果を望む者も多かった。
霧の立ちこめる森の中で足音を潜めながら進む男達の前に、巨大な篝火の明かりが見えた。森を切り開いて築かれた広場の中には百人近い流浪民達がひしめき合っていた。彼らは奇襲隊に背を向けて座り、篝火の前で踊る半狂乱の女にひれ伏していた。篝火の後ろにそびえる見たこともない神像に気づいたとき、奇襲隊の誰もが言葉を失った。
巨木を粘土で固めて作った物だろうか、三〇、いや四〇メートルはあるだろうその巨神像は、流浪民達の前にあぐらをかいて座っていた。篝火に照らし出されるその姿は狂的で、大きく張り出した太鼓腹と肉の弛んだ頬は見るからに不健康そうであり、不釣り合いに細長い腕は体側にだらしなく垂れていた。頭上の闇に融けかかったその表情は、苦悶に歪んでいるようでありながら何となく淫らで、言い知れない不快感を感じさせた。
ドラムが響き、火の粉が舞い、儀式は最高潮に達した。流浪民の中から一人の娘が選ばれた。先ほどから半狂乱で踊っていた薄汚い女呪い師が懐から細長い儀式用のナイフを取り出し、娘の着衣を切り裂いた。ここまでは興味深く見ていた奇襲隊の男達だが、その先の光景を正視できた者は少なかった。呪い師がナイフの先で娘の腹を軽く撫でると、娘の腹はそれに沿ってパックリと割け、中から大量の血とともに臓腑がこぼれ落ちた。呪い師が娘の腸を長々と引っぱり出し、右往左往しては「ダバダ、ダバダ」と叫んでいる。驚いたことに腹を割かれた娘は痛がるどころか恍惚の笑みを浮かべ、響き続けるドラムのリズムに合わせるように腰をくねらせ、自らも「ダバダ、ダバダ」と叫んでいる。
奇襲隊の全員が異常な興奮状態となり、絶叫とともに狂ったように発砲し始めた。目に入った物を片っ端から撃った。周囲に火が放たれ、巨神像は取り壊された。像の中からは粘土に塗り固められたたくさんの死体が出てきた。しかし、もはやそれを気にする者もいなかった。
火事は三日三晩燃え続け、辺り一面焼け野原となった。その焼け跡の土地には、それ以来草一本生えなくなったという。
雪原の遺跡
一九一二年一一月、南極の雪原でロバート・スコットら五人の遺体が発見された。アムンゼン隊に遅れることわずか一ヶ月にして南極点の初到着を逃したうえ、帰還途中で遭難した悲運の英雄の物語は偉人伝として今も語り継がれている。しかし、彼らの遭難の陰に隠された不可解な出来事を知る者は少ない。
スコットは初到着の先を越されたことについて激しい憤りを感じていた。このまま帰っては自分を支援してくれたスポンサー達に申し訳ないとも思っていた。その焦りが付け入る隙を与えたのだろうか、彼らの目前に大きな洞穴が口を開けているのを発見するや、それ用の装備も持たぬままに洞穴の奥を探索し始めた。
洞穴は深く、床も壁面も滑らかで、明らかに人の手によるものであった。このような極地に人間の文明の痕跡を発見できたことは、極点初到着に勝るとも劣らぬ快挙であり、それを思うとスコット達の胸は躍った。
それは数キロにも及ぶ行程であったに違いないが、起伏もなく、時々崩れかけた箇所はあったものの、通行に不便なほどでもなかったため、わずか数時間で踏破してしまった。そして、洞穴の先に広がっていた異観にスコット達は我が目を疑った。四方の壁面が見えないほどの巨大な広間には、古代の町並みがそのまま残されていたのだ。南極の地下都市! 前代未聞の大発見に、スコット達の心臓は張り裂けんばかりに高鳴った。
遺跡は非常に美しく、今すぐにも人が住めそうな状態だった。建築様式的には見たこともない物ではあるが、おそらく南米のインカ、マヤ文明に通じるものがあるだろう。それにしても、ここの住人はどうしたというのか。おそらく気候の急変か何かでこの都市に住めなくなり、ホーン岬から南米に渡ったのだろう。
薄暗い地下遺跡の調査はその後何日も続いた。調査中、何人かが不思議な影を目撃した。それに、よく耳を澄ますと、何処からか耳鳴りのように「ダバダ、ダバダ」という音が聞こえるではないか。今でもここに住む原住民が居るのだろうか。探検隊の興奮はいや増すばかりであった。
都市発見から四日目、隊員の一人が行方不明になった。ここにきて冷静に考えてみると、食料も底をつきかけているし、あまり帰りが遅れたら遭難したと思われて、母船が帰ってしてしまう可能性もあった。しかし行方不明の隊員は探さなくてはならず、探検隊は少し困った状態になってきた。
ここまでの話しは隊員の日記によるものであり、それが真実かどうか確証は持てない。日記はここで途切れ、その後探検隊に何が起こったかは想像もつかない。しかし、遺体を発見した捜索隊の報告は、いくつかの手がかりを与えている。
遺体のそばには確かに大きな洞穴が口を開けていたようである。また、遺体は五体とも仰向けで、きれいに並べられたように倒れていたし、極寒の地だというのにひどく腐敗していたそうだ。各遺体に致命的な外傷があったとも漏れ聞く。
いずれにしろ、それ以降の懸命の捜索にも拘わらず、この不思議な洞穴を再び発見した者は未だいない。
ダバタの拳
それはいつの時代のことなのか定かではない。遥か太古の記録なのか、それとも遠い未来の予見なのかも判らない。ただ一つだけ確かなことは、それが暴力の支配する荒んだ時代であるという事だけだ。
ロド親父はその町で細々と酒場を営む気のいい男で、いまどき珍しく人間らしい心を持ち続けるごく少ない人種の一人だった。だが、こんな時代ではそう言う生き方を続けることは困難であった。
この町に最近やってきた荒くれ者、自ら「ジャッジ(審判)」と名乗る大男がロドの酒場にやってきた。ジャッジはレザーのズボンを履いただけで、上半身は裸だった。金髪のモヒカン頭、顔には派手なペインティングをした、見るからにイカれたこの男は、ムキムキの胸の筋肉をこれ見よがしに振るわせて、ロド親父の前ですごんで見せた。
「オレが飲んだ酒に代金を課したのは親父、おまえの勝手な都合だろ。そんな自分勝手な理屈が通っちゃ社会ってもんが成り立たねえ、そうだろ。オレは寛大な男だ。もう一度だけチャンスをやろう。オレの酒には金なんて必要ないよな」
そう怒鳴ったジャッジの頭に何かが当たった。鶏の骨だ。骨が飛んできた方向を見ると、酒場の隅の日影で見慣れない男がフライドチキンをムシャついている。ジャッジは憤然と男に詰め寄った。
「オレの頭にこんなものを投げつけたのはおまえか、ええ」
男はジャッジを無視してチキンを食べ続け、骨をもう一本ジャッジに投げた。
「こ、この野郎!」ジャッジは巨大な拳を男の脳天に叩き込んだ……かに見えたその瞬間、男は片手をひょいと上げ、指先一つでジャッジの拳を受け止めた。男はユラリと立ち上がり、ロドとジャッジの間に割って入る位置に立った。
男が深く息を吸った瞬間、ロドは男の背中が大きく膨らむのを見た。男の上体の筋肉が著しく膨張し、着ていた革ジャンが張り裂け、その下から鋼の筋肉が露になった。謎の男に向かってジャッジが突進してきた。
「アタ!」男がジャッジの胸に軽く触れたように見えた。「アタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ、アタァ!」目にも止まらぬスピードで、男の指先がジャッジの体を何度も何度もつついた。
「な、何でい、脅かしやがって。痛くも痒くもないじゃねえか」
ジャッジが勝ち誇ったように言うと、男は答えるように、
「おまえはもう、死んでいる」と言って身を翻した。男の剥き出しの胸には北斗七星を象るような七つの傷があった。
「な、何だとぅ!」と言う間にも、ジャッジの体は奇妙に歪み、捻れ、膨らんで、最期に「ダバダ!」と叫んだ刹那、酒場の床に血と肉と骨を撒き散らした。
驚愕するロドの鼻先にチキンの代金を置いて、男はゆっくりとした足取りで立ち去った。胸に七つの傷のある男の噂はたちまち広がったが、その後、男を見かけた者はいなかった。
女子修道院
高い白壁で外界と隔絶されたパンテモン修道院は、三百年も昔からパリ郊外のその場所にあった。
シモーヌ・ロランがこの修道院の門をくぐったのは二年前、一九六四年の冬、シモーヌが一四才の時であった。両親を事故でなくした彼女は、親戚中をたらい回しにされたあげく、この古びた修道院に押し込まれる羽目となった。しかし、シスター達は身よりのない彼女を暖かく迎え、無償の愛を示してくれた。
院長のシスター・ジャンヌは時々山のように古書を買い込み、自室で夜遅くまで読書に耽る趣味があった。その日も彼女は町から古書の山を抱えて戻ってきた。シモーヌとすれ違ったとき、彼女は一冊の本を落とした。シモーヌはジャンヌを呼び止め、落ちた本を拾った。ジャンヌは引ったくるように本を受け取ると、それを他の本の後ろに隠し、礼もそこそこに、そそくさと立ち去った。しかしシモーヌは見た。その本こそが「ダバダの書」だったのだ。
その晩、シスター・ジャンヌの部屋から恐ろしい悲鳴が聞こえた。シモーヌが駆けつけたとき、既に何人かの修道女達が院長の部屋のドアを激しくノックしていた。顔を覗かせた院長は悪夢にうなされただけだと落ち着いた声で言った。
その翌日、シスター・マルグリートが誰にも告げずに修道院を去った。更に三日から一週間ごとに、修道女達が次々と修道院を去っていった。修道女の数が半数にまでなると、さすがに不信感を抱かぬ者はいなかった。
ある晩、シモーヌは、隣室のノックの音に目覚めた。隣室のシスター・ルルーのもとに誰かが訪ねてきたようだ。しばらく話し合った後、ルルーは来訪者と連れ立って出かけた様子だった。窓の外に目をやると、ルルーがジャンヌ院長に連れられて中庭を横切っていくのが見えた。二人が礼拝堂に入っていくのを見届けると、衝動的にシモーヌは部屋を抜け出し、自分も礼拝堂へ向かった。彼女が礼拝堂へ近づくと、中から短い悲鳴が聞こえた。急いで小窓から中を覗いたシモーヌは、そこでこの世のものとは思えない光景を目の当たりにした。
ジャンヌ院長の足下に倒れたルルーの頭部からは、たっぷり洗面器一杯分ほどの血が流れ続けていた。その周りを先頃修道院を去っていったシスター達がとり囲んでいる。ジャンヌは右手に持った血塗れのキリスト像を投げ捨てると、既に動かないルルーの体を仰向けにし、その喉にかぶりつき、柔らかな肉を噛みちぎっては飲み下した。それを合図に他のシスター達もルルーに群がった。
シスター・ナタリーは節くれ立った皺だらけの両手で首筋をまさぐり、プリプリした頸動脈を引きずり出すと、チュウチュウと音を立てて鮮血をすすった。シスター・ブリジットは右目に接吻すると、眼球をジュルリと吸い出した。それを奥歯で噛みしめると、卵の白味のような粘液が口角から勢いよく飛び出した。シモーヌは小さく悲鳴を上げ、自室に駆け戻った。
彼女の顔からは血の気が引き、ベッドで頭から毛布を被って震えていた。やがて廊下をひたひたと歩く足音が近づいてきた。そしてドアにノックがあった。
地下街
東京の山手線には、田端という駅がある。この駅の近くに三ヶ月前に越してきた大学生の三好七也は、この「たばた」という地名の響きに底知れぬ不快感を感じていた。それは三好が昨年読んだ「ダバダの謎」という本の影響かもしれない。
ある晩帰りが遅くなった三好は、いつものように駅の北口の地下街を通ってアパートに急いだ。地下街は人通りも少なく、どことなく不気味な感じがした。しばらく地下道を行くと、商店と商店の間に黒い大きな鉄の扉がある。三好はこの前を通るたびに、扉の向こうが気になってならなかった。
少し酒気を帯びていたせいもあるだろうか、三好は何の気なしに扉のノブをひねってみた。鍵はかかっていない。そっと開くと光が漏れてきた。扉の向こうを覗き見た三好はハッと息をのんだ。扉の向こうも地下街になっている。しかも三好がいつも通っている地下街より広くて新しく、人通りも多くて賑やかで、しかも三好のアパートの方向へ延びていた。いつの間に造ったのだろう。三好は身近な大発見に胸を躍らせながら扉の向こうに足を踏み入れた。
夜の地下道の常として、行き交う人々は何かよそよそしく、他人と目を合わせないようにしながら急ぎ足で歩いていた。
新しい地下道はかなり長く続いていた。いや、かなりなどという程度のものではない。もう十分以上歩いているが、出口はおろか標示板もない。人影も疎らとなり、ついに歩いている人はいなくなった。このころになると酔いも醒めてきて、三好は異邦に迷い込んだような焦燥感に駆られていた。
路肩にはホームレスがちらほら、段ボールの布団の隙間からこちらを伺っている。はみ出した手足の皮膚は何か不快な湿疹に覆われ、皮が剥け変色し、痘痕になって血がにじんでいる。禿頭の男の右目は虚ろで、かつて眼球があった瞼の向こうはポッカリと黒い穴が開いているだけだった。縞のシャツを着た男は左手の手首から先が無く、完全に治りきっていない切断面にはピンクの膜が張っている。道ばたで嘔吐している老女の吐瀉物の中から黒い何かが這い出ていった。子犬ほどもある大ネズミが口にくわえて行ったのは赤子の腕か。
何処からか女の子の鳴き声が聞こえる。赤いワンピースの少女が道ばたで屈んで泣いている。この気味の悪い地下道に迷い込んでしまったのだろう。三好は少女に声をかけた。振り向いた少女の顔は皮膚が剥がれ、顔面の筋肉も露に、唇も瞼も無く、眼も歯も剥き出しで、顔面には青い血管がドクドクと脈打ち、一面に三ミリほどの白い小さな蛆虫がギッシリとたかり、サワサワとそよぎながら肉を啄んでいる。三好は悲鳴を上げて、もと来た道を逃げ出した。振り向くと道ばたにいた怪異の者達がおもむろに起きあがり、自分を追いかけて来るではないか。三好はひたすら走った。耳元に感じる嫌な臭いの吐息を無視して走った。三好はそこからどうやって逃げたのかよく覚えていない。気がつくと自室で頭から布団をかぶってガタガタと震えていた。それ以来三好は昼間でもその黒い鉄の扉に近づこうとは思わなかった。
マネキン
珍しいことでもないが、一九九二年の六月、インドはバーガルプル付近のガンジス川の河岸に女性の水死体が発見された。発見者は大慌てだったが、駆けつけた警官は始めそれが遺体だとは思わなかった。遺体は大量の粘液に包まれ、表面はプラスチックのように硬直し、長い間水に浸かっていたのに腐敗の様子もなかった。水死体を見慣れた警官は廃棄されたマネキンだと思ったのだ。
ところが、これを回収する際、人形だと思って手荒に扱ったのだろう、投げ出した拍子に左手の小指がポキリと折れてしまった。すると折れた箇所から紛れもない血液がどくどくと流れ出し、これが人体であることが判明した。
検死官はこんな症状に立ち会ったのは無論はじめてであった。解剖にあたってはメスの刃が立たず、骨を切るための小型のノコギリを用いた。腹部を切開したところ、中に息づく臓器は正常に機能していたため、検死官はそれを遺体と早とちりした自分を罵った。硬質化した皮膚では縫合もできず、為す術もないままに程なく彼女は本当に死んでしまった。
遺体の身元の判別は困難だったが、半月ほどして指紋や顔写真からようやく身元が明らかとなった。遺体は川の五〇〇キロも上流に住んでいる主婦で、カリという名の女性の物だった。近所での彼女の評判はまずまずだったが、夫は半年前に蒸発してしまい、今は一人暮らしをしていた。
捜査を進めるうちに目撃証言が得られた。とは言っても、目撃者を称する男は近所でも有名な変人で、アル中のうえ虚言癖がある札付きの浮浪者であった。男が言うにはカリが川辺を歩いていると、水中から何か得体の知れない怪物が現れて彼女をさらっていったという。警察は当初この証言を取り合わなかったが、彼女がさらわれたときに落としたという宝石を男が提出したため捜査は急転した。
宝石は黒っぽい水晶のようで、内部の渦巻く黒斑が角度によってモヤモヤと煙って見えた。警察は宝石を狙った殺人という考えを早々に捨てた。死体をあのように加工する術をこの男が持っているわけがなかったからだ。
男の証言を聞いていくうちに、カリをさらったその怪物の姿が、ダバダ伝承に言う「底の住人」と酷似している事が判明した。地元のダバダ研究家が「底の住人」の想像図を見せると、男は間違いないと断言した。さらに研究家によって男が拾った宝石が「渦煙石」と呼ばれるもので、古代インダス文明においてダバダの力を引き出す媒体として使われていたことも判明した。蒸発したブラジル人の夫、パウロ・ミューレルが高名なダバダ研究家である事も分かり、家の地下から魔道書で溢れた秘密の書棚が発見された。しかし、引き出しの中で見つかった「不可視郷の央へ向かう」と書かれたメモの意味については見当もつかなかった。
カリの死体は引き取り手が無く、火葬にしても燃えなかったため、献体に出された。ところが程なくしてこの遺体が盗まれてしまった。安置室や部屋の前の廊下は粘液まみれとなっており、この際三人の警備員が死亡した。警備員の遺体は三体ともカリ同様に硬質化していた。
遡行
ニコル博士は一種の天才ではあろうが、モラルの欠如についてはその才能を持ってしても補い難いものがあった。彼はいわゆる変人であり、人を好まず、ただひたすらに研究に没頭するタイプの学者だった。
博士の死体が発見されたのは一九四三年のことで、発見者は週一度だけ訪ねてくる家政婦であった。死体はベッドに横たえられ、ともすれば眠っているようにも見受けられたが、呼吸もなく、心音も瞳孔反応もないため、駆けつけた医師によって死亡が確認された。死因ははっきりしないが、心不全か何かだろうと結論づけられた。しかし、立ち合った警官や検死官たちも、内心では死体の頭部に被せられた、豆電球がピカピカ光る、見たこともない不可解な装置に原因があるかも知れないことは薄々感じていた。
博士の死後、遺品を整理していた親戚衆が、テーブルの下に張り付けられた博士の日記を発見した。その内容には驚愕すべきものがあった。
博士は精神を過去に投射する装置の発明に成功したようで、日記の内容はその実験記録であった。はじめは五年とか一〇年前程度であったが、やがて何百年も遡って歴史的瞬間を目の当たりにしていた。博士は過去と現在を行き来しながら日記に記録していた。日記の中で、歴史の通説に大きな誤謬があることが何件か指摘されていた。博士の実験は更にエスカレートし、何億年も時代を遡って恐竜なども観察している。そして、博士はそこで驚くべき生物に遭遇した。
その生物は赤黒いゲル状の流体生物で、多細胞のアミーバ的形状をしていた。大きさは平均して五リットル分ほどだが、中には小さな池ほどもある巨大な個体も存在する。そして、それらの生物には高い知性が備わっているのだ。
博士はこの生物の観察を続けた。彼らには視覚や聴覚というものが無いようだが、何か人智を越えた感覚があり、人間には見ることのできない博士の霊体を関知できた。彼らは遺伝子工学の分野にずば抜け、様々な有機装置によって空を飛んだり、自体を他の場所に転送したりできた。
ある時、未だ兆しすら存在せぬ人体を模しているような肉塊が運び込まれ、ゲル生物の一体が肉塊に入り込んだ。すると、その肉塊は、もとよりその姿の生物であったかのように動きだしたのだ。博士はその新生物こそ人類の祖先ではないかと仮説を立てていた。
別の日、博士はある洞窟の奥に彼らの不可解な集団を発見した。彼らが一堂に会し、洞窟の奥の何かを祀っている。感覚を澄ますと洞窟の奥には黒い土をこねた偶像があった。それは、人類の祖先と仮定された新生物に酷似していたが、むしろ新生物の肉体の方がこの偶像を模していることは明らかだった。ゲル生物達は細く張り出させた肉体の一部を細かく振動させて甲高い音を立てた。それは、「ダバダ、ダバダ」と鳴っているように聞こえた。
博士の日記はここでとぎれている。その後、博士の精神は過去へ向かったまま、二度と帰ることはなかった。
臓器バンク
サウジの石油長者ヤルシ・アルダワドは裸一貫からの叩き上げで、ガッツと根性で財を築き上げた古いタイプのエグゼグティブだった。このような男の多くがそうであるように、彼も極端に死を恐れ、不老長寿を夢見ていた。しかし、若い頃の無理がたたってか、あるいは近年の不摂生の報いか、このごろどうも調子が思わしくない。それとも自分でそう思いこんでいるだけなのだろうか。
そんなアルダワドのもとに妙なダイレクトメールが届いたのは一九七五年の夏のことであった。それは「あなたに永遠の若さを」と派手な見出しの付いた広告で、法外な会費を払う特別会員の身に万一のことがあった際、だだちに新鮮な臓器を提供するシステムであった。差出人はブラジルの医療法人ダバダ臓器サービスという聞いたこともない会社だったが、アルダワドはこの広告に飛びついた。
やってきた営業マンは、ポマードで黒髪をペッタリ寝かせた斜視の嫌な感じの男で、口元には切り紙細工のような笑いが張り付いていた。説明の合間に入る、寒気のするような含み笑いは別として、臓器サービスの内容は大変満足のいくものであった。だだ、ゴールド会員とプラチナ会員の違いについて、営業マンははっきりとしたことを言わなかった。アルダワドは大変金持ちであったが、無駄な金は全く使わない主義だったので、カードの色が違うだけで会費が三倍も高いプラチナ会員にはならず、敢えてゴールド会員になることにした。まあ、アルダワド自身ゴールドという言葉に弱いのも理由の一つではあったが。
それから二〇年ほど、アルダワドはたいした病気にもかからず、齢は七〇に達しようとしていた。
ところが、ある日、彼は入浴中に倒れてしまった。主治医が駆けつけたが、大至急設備の整った病院で手術する必要があった。自家用のリムジンにベッドごと乗せられたアルダワドは、最寄りの大学病院に運び込まれた。
執刀医が病状の説明を受けているとき、手術室に黒服の男が大挙して押し寄せてきた。誰何する医師の声に、嫌らしい笑いを浮かべた中年男が答えた。彼らは臓器サービスの者で、アルダワド氏との契約で氏の身に有事が生じた際の医療スタッフであると証書を見せながら手短に説明した。そうしている間にも黒服の男達によってアルダワドは運び出されていった。
数日後、アルダワドは別の病院のベッドの上で目を覚ました。ベッドの脇にはあの嫌らしい笑いの営業マンがいた。そっと首を巡らせると、窓ガラスに自分の姿が映った。剃り上げられた頭には大きくて醜い傷があった。
「こんな老人ではプラチナ会員になった甲斐がないな」とアルダワドは嘆息した。
「しかたありませんね」営業マンはにやけながら言った。「脳疾患を患うのはたいてい年寄りなんです。その体でも大切に使えばもう一〇年や二〇年は持ちますよ。しかも、新しいあなたは大変な金持ちなんです」
営業マンが鞄から取りだしたノートにはアルダワドの履歴や癖などが細かく書いてあった。新しいアルダワドはノートの記述を丹念に読み始めた。
縊りの樹
ノルウェーの孤島の村、モーレイには一本の古びたモミの巨木がある。シグール・バイリセはモーレイの役所に勤める臨時職員で、このモミの木の手入れを主な仕事としていた。このモミはいささか手が掛かる特徴を有しているのだ。
一九七七年一〇月二二日、バイリセは八日ぶりにモミの手入れの仕事に就いた。これほど間隔が開くのは珍しいな。バイリセは木を見上げてそう考えた。木の幹には一人の女性が下がっていた。
このモミはこの辺では「縊りのモミ」と呼ばれる有名な樹で、平均して月に七、八人、多いときには二〇人以上の人がここで首を吊る。何故この木に自殺志願者が集まってくるのかは判らないし、バイリセはそんなことを考えたこともなかった。しかし年間に一〇〇人以上がここで首を吊るのは事実で、バイリセの仕事はそれら自殺者の死体を処理することである。正直言って余り気乗りのしない仕事だが、食いっぱぐれることはないだろう。
ある日、ベルゲンから一人の学者がバイリセのもとへやってきた。彼、ロアー・エッゲンは縊りのモミに強く興味を惹かれたらしく、バイリセに色々な質問を投げかけてきた。珍しく自分の仕事が脚光を浴びたことに気を良くしたバイリセは、知っている限りのことを洗いざらい話した。
モミの下に埋められた魔女の伝説はこの地方では広く知られているが、バイリセがこの話をするとエッゲンは目を輝かせた。言い伝えによるとモミの下に埋められているのは一四世紀にイギリスから渡来した女性で、地域の風習に馴染めず、村人達からひどく迫害されたらしい。復讐を誓った彼女はダバダの秘術の研究に没頭し、何人もの村人を手にかけ、ついに村人達に捕らえられて生き埋めにされたようだ。魔女は埋められる際に人類全体を激しく呪ったという。
エッゲンは街の図書館に籠もって何十冊もの本を繙いて様々な角度から伝説を検証した。二週間ほどしてエッゲンはどこかへ一時去り、一月後に戻ってきた。戻ってくるなりエッゲンは、興奮しながら役所に飛び込んできた。あのモミの下を是非掘り起こして調査したいというのだ。エッゲンは何処からか持ってきた黒い革表紙の本を振り回しては熱のこもった口調でほうぼうを説いて回った。かなりの金も撒いたのであろう、木を倒し、根本を掘り起こして調査する運びとなった。
バイリセはエッゲンに魔女の伝説を話したことを悔いていた。無論、バイリセが言わなくてもエッゲンはいずれその伝説を嗅ぎつけただろう。しかし、そんなことは分かっていても、バイリセの気は晴れなかった。バイリセは愚かさの代償として職を失い、明日から路頭に迷うのだ。
その夜、バイリセはロープを片手に縊りのモミにやってきた。四二年間見慣れたモミだが、これで見納めだ。そう思いながらモミを見上げると、そこには先客がいた。何故この木でエッゲンが首を吊ったのかは判らないし、バイリセはそんなことを考えもしなかった。