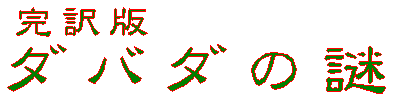
H.クレッチマー 著
飛 場 滋 男
訳
尼 代 憲
ま え が き
今、巷では「ダバダ」なるものが密かなブームとなっています。
この本を手にしたあなたも、多分このダバダについて、多少なりの認識はお持ちでしょうが、では「ダバダって何ですか?」と聞かれたら何と答えるでしょうか。いえ、わたしは別に読者を試そうなどとは思いません。わたし自身、この問いかけに何年も取り組んできましたが、結局判らないままです。
本書はそんなあなたの思考のヒントになればと思ってまとめられました。
世界中で現在までに出版されたダバダ関係の書籍は、それこそ星の数ほどありますが、実際に直接ダバダに関わったものはほんの一握りに過ぎません。残りは過去の出版物の再編か、若しくは全くの虚構でした。人々の話は、学会から井戸端会議に至るまでが、よく言えば形而上学的な、悪く言えば掴みどころのないテーマに釘付けになっています。しかし、どれも結論は出ないようです。異説も色々あるでしょうが、わたしの長年の研究の中で、これこそダバダの手がかりだと思えるものが幾つかありましたのでここに抜粋しました。
ただ、編集にあたって気がかりなことがあります。わたしはあまり迷信深くないほうなのですが、ダバダに関係した人の多くが亡くなったり、行方不明になったりしていると聞きます。わたしも身辺に気をつけ、前人の列に加わらないよう注意しましょう。もっとも努力によっても抗えない運命もあるでしょうが。
【訳註】作者のクレッチマー女史は昨年12月に34歳の若さで急逝されました。
【訳註二】日本語版の「ダバダの謎」は1994年1月に第一版が発売されていますが、この版の訳者である飛場滋男氏は原書の内の2編をあえて訳さず出版しております。氏がどのような経緯からこの2編を割愛したのか、氏亡き今と なっては調べようがありませんが、多くの読者からこの2編の掲載を希望する投書を頂き、今回「完訳版」と銘打って拙訳の2編を同時掲載しております。
これらの2編は原書と同じの箇所に挿入してありますので、先行の日本語版をお持ちの方は比較して頂ければお分かりになると思います。
完訳版訳者 尼代 憲
■まず最初に、日本におけるダバダブームの先駆けとなったとされる「佐田原文書」を紹介しましょう。筆者の佐田原唐志さんは日本ではダバダの第一人者と目されていましたが五年前にこの文書を執筆したのち行方不明となっています。
この文書は連作本のまえがきとして書かれましたが、結局本は第一巻が発行されたのみで休刊になりました。
奇しくもこの文書は、一般人がダバダに関わる状況がいかに危険であるか啓発しています。初心者はあまり深入りしすぎないように薦めます。
| 私が初めてこの本に触れたのは高校二年の秋であった。本屋の片隅にあった分厚いハードカバーに、何の気なしに手を出したのがそもそもである。無論、当時の私にはその内容は漠として掴み難いものであった。しかしながら何とも言い知れぬ雰囲気に惹かれ、禁じ得ぬ戦慄と恐怖にうち震えながら、三度続けて読んだことを記憶している。 私はさっそく訳者の田口寛重氏とコンタクトを取るべく、ノイ新聞社出版 なる所へ手紙を出した。手紙の返事は氏の弟を名のる人物から届いた。その手紙によると、氏は執筆が終って間もなく、出版を待たずして亡くなったとのことであった。手紙にはさらに、氏が生前取りかかっていた原稿を整理するので、興味があるのなら連絡するようにとあった。無論私はそれに従った。 後日、指定された喫茶店で私を待っていた人物は快活で、気の置けない感じがした。しかし、彼の話は何とも興味深く、奇妙なものであった。 例の本はフランス語版を翻訳したもので、原書はラテン語で書かれていること。氏は過日、その原書を入手し、さっそくその翻訳に取りかかっていたこと。その二ヵ月後、氏が亡くなったこと。その一週間くらい前から、氏は何かに怯えた様子で、人目を避けるようになっていたこと、また夜中に夢でうなされ何度も悲鳴をあげていたこと。死因は心不全とされているが、実は医者も首を傾げていたこと。氏が亡くなってから、ラテン語版の原書が何処かへ紛失したこと。 彼はそれら一連の話を終えると、私に封筒を差し出した。中には氏が生前書き残したという、ラテン語版の翻訳の覚え書きめいたノートが入っていた。 ノートのはじめの五、六ページは几帳面な字体で、フランス語版のものとほぼ同じことが書いてあった。しかし、その後、字も文章も乱れ、何とも判別し難くなった。最後の二、三ページに至っては何語ともつかない文字や、意味不明の図形で満たされていた。 その後何度か彼と手紙を交換しあったが、あるときプツリと途絶えてしまった。不審に思い、手紙の住所を頼りに、新橋にある彼の家を訪ねてみた。するとそこは、全くの更地になっており、かつて家があったとも思えないありさまであった。近所の人に尋ねてみても皆「知らぬ」の一点張りであった。 私はノイ新聞社出版にも足を運んだが、雑居ビルの三階にあるはずのそこには二ヵ月ほど前から保険会社が入っていた。私の手には例のノートだけが残った。 大学四年の春休みに、私は一ヵ月ほどアムステルダムに滞在したことがあった。中世の香りを残す町並みに魅せられるうちに、いつしか例の不可解な書物のことは記憶の彼方に押しやっていた。 つと迷い込んだ下町の、観光客の目に触れることの決してない裏路地に盲目の老婆が営む露店があった。無造作にしかれた布の上には、黄金虫を象った魔除け、異臭を放つ爬虫類の干物、グロテスクに誇張された人形などが、無秩序に並べられていた。その片隅に、真っ黒い革を張った分厚い本があった。私は何かに憑かれたようにその本を手にとってみた。黒革の表紙には何も書いてなかったが、中は予想したとおりラテン語で、しかも所々に見覚えのある几帳面な日本語の書き込みがしてあった! 私はこの作為的とも言える運命の巡り会わせに慄然とした。 この本を記すのは正直不安である。田口氏やその弟氏の身に振りかかったことも、今ではある程度予想出来る。しかし、この秘密を私の胸だけに秘めておくことなど絶えられない。この本に記された、人智を逸する根本的、原初的真理に対し、私の脆弱な精神がいつまで正気を保てるか疑問である。私は、最後まで翻訳することができないかもしれない。いや、できないであろう。しかし、もしそうなっても読者の誰かが私の後を次いでくれるものと信じる。私が今、挑んでいるように。 |
■次にあげる文は、佐田原さんの友人である上島清司さんのものです。
彼は文中にあるような奇妙な経験ののち、ついに不思議な珍本を手に入れました。彼はこの本の刊行を試みましたが、一冊目が出たところで「内容が社会通念上好ましくない」として警察に摘発されたのです。さらに本の出所である村からは窃盗罪で告訴され、裁判で有罪の実刑判決を受けました。数ヵ月後、彼は獄中で非業の自害をされました。
その後の調査で、文中に埴入市とあるのは、坂出市の仮名であることが明らかになりました。
| 諸君は「ダバダ」なる雑誌をご存じだろうか。数年前、佐田原唐志という人物を編集長として翻訳、自費出版された同人誌である。この会誌は残念ながら創刊準備号を出版した時点(正確には編集が完了する直前)で、佐田原氏が謎の失踪を遂げた為、ついに創刊に漕ぎ着けることはなかった。佐田原氏と個人的に親しかった私は、この知らせに衝撃を受けた。何故なら私はこの雑誌の秘められた部分を氏から直接聞いていたからである。 この雑誌にはいくつかの奇妙な「いわく」があり、佐田原氏は冒頭でこれを語っている。これを要約すると、かつてノイ新聞社出版という所から出版されていた同名の書物に興味を持った佐田原氏は、訳者の田口寛重氏に連絡を取った。この本はフランス語版の訳書であり、田口氏は出版後にラテン語版の原書を入手したが、翻訳に取りかかったところ怪死を遂げ、同時に原書も行く方知れずになっていた。佐田原氏はこの原書をアムステルダムで偶然入手し、翻訳出版した、とのことである。 佐田原氏の失踪、原書の紛失により、この出版計画は序盤をして頓挫してしまった。 しかし、この書物に感銘を受けた者は多かった。発売即日に完売し、これは口コミで地方のサークル単位の広がりを見せ、同人誌レベルの研究文書がいくつか作られた。 長野県の民間調査グループ「赤土の会」は、ダバダの中で何度か触れられる「エーケルマーの福音書」について報告している。これによると、昭和二二年頃にこの地方を訪れた黒人牧師がこの福音書の内容を流布していたという。この黒人牧師は数ヵ月後、突然姿をくらまし、同時に七人の子供が行方不明となっている。 大阪在住のある中学校教諭は、アムステルダムの精神病院の焼跡から田口寛重氏のものとみられる患者のカルテを発見している。氏は原因不明の奇病にかかり、精神にも肉体にも奇妙な変調をきたしていたという。どういう訳か、氏は南米のどこかの病院に送られたらしい。 関東全域に広まった匿名文書の著者は、ボストン大学図書館の未整理の蔵書の中に、ラテン語版黒革表紙本があることを明らかにした。また彼は一九二三年五月一二日付のボストンタイムズの三面記事に、ボストン湾で発見された人間の手首が、黒革表紙本の一ページ(らしき物)を固く握り締めていた事件を見つけ出した。 北九州大学の研究チームは、香川県を中心とした四国各地にダバダにまつわるいくつかの言い伝えが残ることを発表した。私はこの報告にとりわけ強い関心を抱いた。なぜなら佐田原氏からも同じような話を聞いたことがあるのを思い出したからだ。 それらの言い伝えは多くの場合、何かの拍子に人々の前にダバダが出現し、それにより周囲のものが絶大な影響を受けるという漠然としたものであるそうだ。この記録とも予言ともつかぬ言い伝えは、しかし海岸部を中心に広く信じられていて、特に昔からこの地方にいた老人達のあいだではダバダのことを口にするのはタブーとされているらしい。私は佐田原氏の失踪とこの報告を結び付け、さっそく四国へ赴いた。 現地での調査は難航を極めた。前述のとおり、現地の人達はダバダについて口にのぼらせることを避けているからだ。それでも私は苦心の末、埴入市の郊外のある集落で「ダバダ(蛇婆堕)さま」として崇められている存在のことを聞きつけた。 この集落は今もって外部との接触を避ける風習があり、同時にダバダに対する禁忌の念も他の地域以上に強いもので、私はダバダの名を口にした途端猟銃で脅されて必死の思いで逃げ帰える次第であった。 私は村の近くに野営し、さらにこの集落を調査した。数日後、深夜になると海辺にあるダバダさまを祭った社の方角が明るくなることを発見した。そっと近づいてみたところ、社のまわりに村人が集まり、何やら奇怪な儀式にふけっている現場を目撃した。村人の中には何とも名状し難い扮装の者が混じっており、その姿を見た私は悲鳴をこらえるのに必死だった。濡れたような光沢を放つ、闇夜をも染める漆黒の扮装は、扮装というには余りに生々しく、辺りに漂ってきた気の遠くなるような生臭さとともに、私を病的倒錯のもとに誘なった。 数時間後、総毛立つような猟奇的儀式が終り、村人たちはそれぞれ家に帰っていった。しばらく辺りをうかがっていた私は、意を決して恐る恐る社に近づいた。震える手で社の扉を開くと、ほのかにひかる青白い燐光の中に一冊の本が浮かび上がった。 「蛇婆堕妙本」! 果てしない歴史の中に閉ざされ続けてきた日本語版ダバダ! その驚愕すべき内容が数百年の時を経て、今、まさに白日の元にさらされようとしている。私はこの内容に目を通した時、一瞬これを世間に公表すべきかどうか悩んだ。しかし、原書訳を出版した佐田原氏の決心をあえて踏襲する道を選んだ。氏は創刊準備号で奇しくもこう語っている。 「私は最後まで翻訳することはできないかもしれない。(中略)しかし読者の誰かが、私の後を継いでくれるものと信じる」 果たして氏の予言は的中し、本日続編を発表する運びとなった。 |
■次の文は当時大学生であったある方の手によるもので、獄中死した上島さんが逮捕される以前の体験を書かれたものです。実は筆者は田口寛重さんの弟の和洋さんに詐偽にあったそうで、和洋さんの行方を捜している内に、偶然にもダバダ信仰の儀式に巻き込まれたのです。
本文発表当初から、本人の希望で筆者の名前は出しませんでしたが、筆者は心労のために長期に渡って入院中だと聞きます。
| 田口寛重の弟である田口和洋は失踪直前にダバダ書房を訪れていたことが分かった。しかし、当のダバダ書房は静岡から移転して行方が分からないでいた。ダバダ書房と云えば私の大学の非常勤講師である上島清司が、つい最近四国で入手した「蛇婆堕妙本」を出版したことが記憶に新しかった。しかし上島は旅行中だったので、しかたなく静岡まで出向き、現地で聞き込み調査をした。三日後ダバダ書房の転居先は群馬県前橋市だと分かった。 ダバダ書房は前橋の市街の裏通りのビルの四階にあった。中はタバコの煙と未整理の書類で溢れていた。現在の社長兼編集長である西山と三、四人のアルバイトが働いていた。事情を説明すると西山は言った。 「田口さんが来たのは三月の末頃でした。彼は、私のしていることに対して警告をしに来たようです。慌ただしく用件だけ言うと、誰かに追われているようにそそくさと出て行きました」 西山は商業ベースでは出版できない様な書物の発行が自分の使命だと感じているようだ。例え少数でも読者がいる限り出版すべきだと熱心に語った。現在は上島清司の「蛇婆堕妙本」の出版が自分の課題だから、田口が忠告したのはこのことだろうと付け加えた。 「そういえば、田口さんは上島先生の行き先も尋ねていかれました。先生は四国に再調査に行ったのでそう知らせました。先生が本の中で埴入市と仮称したのは多分、坂出市だと思いますよ」と言われ、私はさっそく四国に飛んだ。 坂出市は人口およそ六万七千人の漁港である。比較的活気のない町はどんより曇った空とあいまって、重苦しい雰囲気を漂わせていた。町の人に「ダバダ」のことを聞くと、一様に声をひそめて警句を発した。図書館で資料をあさると、郊外の断虹という地区で「ダバダ」信仰が盛んなことが分かった。 断虹に行くには駅からバスに乗り三〇分のところで下車し、さらに四〇分ほど歩くらしい。そこで私はレンタカーで断虹へ向かうことにした。ところが車は途中でエンコしてしまい、私は立ち往生する羽目になった。しばらくして、そこに白いシビックが通りかかった。どうした偶然か、運転手は上島だった。 私は故障車を取りに来るようレンタカー会社に連絡し、上島の車に便乗した。彼の話では四、五日前に田口が訪れ、何やらおかしな警告を残して去ったと云う。 「どうやら気が狂れた様子で、」上島が言った「喋りながら常にキョロキョロ辺りを見回していた。話の内容は整合性を欠いていて分からなかったが、『奴らの祭を阻止する』とか言っていた。多分、近いうちにあるらしい断虹地区の祭だと思う。僕は今からその取材に行くんだが、一緒に行けば田口に会えるかもしれないよ」 私は渡に船とばかりに同意した。上島は断虹は排他的な部落だから祭の取材も密かに行わなくてはいけないと警告した。 彼が以前目撃した儀式は例月の儀式のようで、今回の取材は年に一度行われる大祭を取り扱うらしかった。ただし、祭の正式な日程は分かっていなかったが、現地につくと村の様子から実は今日が祭の当日であることがわかった。 村の裏山に隠れて見ていると猟奇的儀式が始まった。まず村の中央の広場に向かい、手に手に松明を持った村人たちが戸口を抜けて現れた。そして何やら不気味な詠唱がはじまると、海岸の神社の方からけたたましい犬の声と、生臭い臭いが漂って来た。やがて村人は一列に並んで海岸へ向かった。海岸にしつらえられた囲いの中には二〇匹前後の犬や猫がいた。村人の詠唱の声が高まると、まるで海の中から現れたように、濡れた様な光沢の黒い扮装の人物が何人も忽然と現れた。 三〇分後、祭は最高潮に達し、村人達は犬猫の囲いに殺到した。彼らは素手で動物を殴り倒し、手に持った石で頭蓋を砕き、口や肛門から手を入れてその体を引き裂き、さらにその肉を貪り喰った。 祭が終った後、犠贄の囲いのそばには無残な骨が散乱していた。近づいてよく見ると骨の量からして今日の様な儀式が数日間に渡って行われたことが分かった。 私は骨の中に人骨があるような気がした。何故なら人間の衣服の切れ端が見つかったからだ。そしてなにげなく拾ったジャケットだったであろうボロ布には「田口和洋」の裏縫いがあった。私は意外な事実に暫し茫然とした。上島に声をかけられ、ようやく自分のすべきことに気がついた。 私たちは市街に戻ったあと、急いで警察に連絡した。しかしどうした訳か警察はこの件に全く取りあわず、むしろ私たちを奇人あつかいした。上島はこれに激高し(どうやら役人に敵愾心を持つタイプらしい)、署長を呼び出したが、署長室に連れて行かれたまま彼は戻ってこなかった。私は追い出されるように帰され、その後も連絡を受けなかった。 数日後、上島が逮捕されたことを新聞で読んだが、その件についてはそれほど印象に残らなかった。私はむしろ、次の小さな記事に興味をそそられた。
|
■この文は佐田原氏の行方を調査したイギリス人小説家、ジョン・リーさんの手記です。
彼はリスボン空港で暴漢に襲われ、あえない最期を迎えました。死後、遺族が彼の遺品を整理していたところ、机の引出の中から偶然に書きかけの原稿を発見しました。多分これは彼が手掛けようと試みたノンフィクションの一部に違いないと、彼をよく知る友人から聞きました。その方の話では彼は八九年に渡米して、間もなく帰国したそうです。その後、彼は人が変わったようで、ありもしない影に怯え、寝る時も電気は消さなかったそうです。そして入院していたポルトガルの精神病院から脱走し、国外に逃れようとしたときに襲われたそうです。
アメリカでの出来事は、あまり人に語らなかったそうですが、ときどき渡米したことを後悔するようなことをこぼしていたそうです。
| エドガーの話が仮に真実だとすれば、図書館には例の本があるはずだ。 私は是非ともこれを手に入れたいと思った。いや、手に入れなくてはならないのだ。その本こそ佐田原の行方を知る唯一の手がかりであることが私には何故か確信できた。 翌日、私は何くわぬ顔でボストン大学の図書館を訪ねた。受付けのカウンターに片肘をついて件の書物のことを尋ねると、ポニーテールの司書嬢は戸惑った面持ちで蔵書管理のオンラインを操作しだした。明らかにそんな本は聞いたこともないという様子だった。 キーボードを叩く学生アルバイトの顔を三〇秒も眺めていただろうか。やがて彼女はソバカスが薄く残る顔を少し傾げて、分からないというゼスチャーをした。私がもっとよく見て欲しいと眼で合図すると、彼女は作者や出版社が分からないのでは調べようがないよとぼやきながらも、分厚いファイルを何冊も持ちだして調べはじめた。細かい字を指でなぞる時、彼女の眉間に小さな皺がよることを発見した。 彼女が力になれなかったと詫びたとき、私はもう一つ尋ねるべきことがあるのを思い出した。今日は何時までここにいるかと尋ねると、ボビーが迎えに来るまでだと軽くいなされた。 ベッドの中で長い金髪をいじりながら、彼女の名前を思い出そうと努めた。ジュリアかジェニファー、いや、たしかジェニーだった。 ジェニーは図書館で見た時よりもずっと魅力的だった。すねたようにとがった唇が、図書館の地下に封印された扉があることを漏らした。例の本があるとしたらそこに違いないと言い、あまつさえ自分が潜り込むとまでいいだしたが、さすがにこれは辞退してもらった。扉の前は不思議な冷気が漂い、重苦しい空気が立ちこめているらしい。それから五分以内に図書館の地下の配置と、夜間の警備システムと、彼女の誕生日を聞き出した。 彼女を送り出す時に、無茶なことはしないようにもう一度釘を差した。戸口で別れのキスを交わした後、彼女は自分の名前はジェインだと訂正した。 私は本を入手するためにニューヨークからアレックスを呼び寄せた。彼は私の大学時代のバスケ仲間で、今は腕利きの探偵だった。以前会った時はかけていなかった銀ぶちの眼鏡の奥に、懐かしい眼が微笑んでいた。彼の眼もとを見て、自分も年をとったと実感した。 私の話を聞くと、アレックスはお安い御用だと引き受けてくれた。ドレイク教授の部屋からバーボンをくすねた時よりも簡単だと請合った。 翌晩、オフィスにたたずむ私のもとに、待ち焦がれていた電話が入った。アレックスは息を切らして、非常事態が起きたことを伝えてきた。何等かの原因で図書館の警備が混乱し、発見されそうになったそうだ。アレックスは依頼した本を近くのコンビニからファックスで送ると言って電話を切った。 ファックスは八枚届いた。ラテン語らしいが私には分からなかった。九枚目はページの大半が飛び散るような染みで覆われていた。そしてファックスは途絶えた。何か嫌な予感がしたその時、ドアにノックがあり、電報だと叫ぶ男の声がした。 私はファックスをひっ掴み、窓から身を躍らせ、三メートル下の隣のビルへ飛び移った。その時頭上で鈍い轟音が響き、ドアが蹴破られたのがわかった。雨樋を伝って通りに降りた時、静止の声と同時に銃声がした。私はジグザグに走って路地に潜り込み、バーガーショップの前にあったホンダを拝借して一目散に逃げた。郊外で車を捨て、 バスと電車を乗り継いで、わざと遠回りをしながらワシントンに行き、モスクワ経由の東京行きに乗った。 飛行機の中でワシントン・ポストを読んで、私は愕然とした。 ボストン近郊で前代未聞の醜悪かつ残虐な女子大生の変死体が発見され、狂気に駆られ射殺された犯人と並んで被害者の顔写真が大きく掲載された。私はジェインとアレックスの冥福を祈った。 |
■イギリスの小説家、ジョン・リーさんのアメリカ行は彼に狂気をもたらしたようです。しかし、彼の友人であるヘンリー・ボウエンさんの以下の文書を見て頂けば、あなたはリーさんの狂気の要因はそれだけではないようだと思うようになるかもしれません。
ボウエンさんはダバダについてあまりご存じではないようで、リーさんを完全な病人と見なし、彼の死因も報道通りだと思っているようです。しかし、そのことがかえって彼の命を救ったと言えるでしょう。
| アメリカ以来、ジョンの様子が少し変だということは誰もが知っていた。しかし、ジョンは心配する家族を尻目に、以前にもまして世界各地を転々とするようになった。以前彼が話してくれたのだが、彼は自分が何者かに付け狙われていると思い込んでいたようだ。彼はその何者かを影だとか闇だとか言っていた。そして、その目を逃れるために世界中をさまよい歩いているそうだ。 ある日、ジョンの奥さんから電話があった。ジョンが旅先で倒れ、ポルトガルの病院に担ぎ込まれたそうだ。夫人はこのところ心臓を患っていて、とても旅行は無理な状態だったので、私が病院に駆けつけることにした。 リスボン空港でタクシーに乗り、ジョンが入院しているというヴェロダ病院に行くように指示したところ、運転手は不審そうな顔で、あんな所に何の用だと言った。私はその時になって初めてジョンが入院しているのが精神病院であることを知った。 ヴェロダ病院はリスボンの郊外にそそり立つ丘の上にあった。運転手の話ではあまりよい評判を聞かない病院で、未だに電気ショック療法を施したり、奇妙な薬物の人体実験もしているというもっぱらの噂だそうだ。建物は刑務所もしくは中世の要塞を思わせるもので、堅固な石壁に囲まれた不気味なものであった。院内に入ろうとすると、屈強な守衛に押し留められた。事情を説明してから中に通されるまで、たっぷり二時間は待たされた。 ジョンに会う前にまず院長と会って彼の容体を聞いた。院長はジョンがひどい妄想に取り憑かれ、自分の小説の世界と現実世界の区別がつかなくなっているのだと言った。 ジョンの病室は牢獄そのもので、窓枠には鉄格子がはめられていた。ベッドの両脇にはボディービルダーのような二人の看護士が陣どっていた。二人きりで話したいと申し出たが、危険だと言うことで認められなかった。 ジョンに家族や友人の近況を話すと、彼は心配をかけたことを済まなく思っていると詫びた。そんな彼は全く正常に見えた。しかし、やがて彼の妄想じみた話しがはじまった。 彼は「黒い奴ら」から逃れるために世界中を旅して歩いたことを語った。私は院長の言いつけ通り、辛抱強く話しを聞くことにした。荒唐無稽な彼の話しは、彼の言う「黒い奴ら」が様々な手管で彼を捕えようとする様を語っていた。彼は推理小説よりもサスペンスやホラーに向いていたのだと思った。 やがて彼の話しも大詰めになってきた。オランダでついに「黒い奴ら」に捕えられ、「奴ら」の配下の精神病院に送られたそうだ。ジョンはしだいに興奮しながら続けた。「奴ら」の病院は彼を洗脳しようと試みたが、ジョンは監視の一瞬の隙をついて病院に火を放ち、下水口を通って逃げようとしたらしい。ここまで話した時、ジョンがあまりにひどく興奮したので、医者はもうこれ以上話せないと言った。ジョンは看護士に押さえつけられ、私は医者のあとについて部屋を出た。去り行く私の背中に向かってジョンはなおも叫び続けた。 「地下水路にいたんだ! 黒くて……黒くて、でっかい……」 数日後、再び見舞に行ってみると、ジョンが病院を逃げ出したらしかった。しかし、そのわりに病院の人達は平静で、特に心配している様子もなかったのを記憶している。 やがて、彼が空港で刺されたニュースを見た。警察に申し出て彼の死体を確認に行った。死体は確かに彼のものだが、その形相は私が今まで見たことのないような恐怖と苦悶を浮かべていた。額の傷口は、刺されたというよりむしろ、吸盤のようなもので吸い付かれた跡のようだった。 更に何日かして私のもとに一通の手紙が届いた。驚いたことにジョンからだった。病院を抜け出してすぐに出したものだろうか。非常に乱れた書体で殴り書かれた手紙には、ヴェロダ病院にオランダの「黒い奴ら」の病院にいた医師が派遣され、自分の命が危ういと書いてあった。 幸か不幸か、ジョンは彼が恐れていた夢以外の、確かな現実の刃物によってこの世を去ったのだ。 |
■次の文書は長野県の調査団体「赤土の会」の調査員がダバダとの関係が深いとされるオルサー教会を調査したときのレポートが一部流出したものです。この文書の詳細は不明ですが、「赤土の会」という団体が、ダバダのことをかなり深く追求していることがよく判ります。ただし、この「赤土の会」はもともと黒人牧師による幼児誘拐事件の被害者の会として発足した経緯から、部外者への情報提供は制限されています。
| 数日後、警察からの電話で吉荷が入院している事が分かった。病院で見た彼は、最後に会ってから一週間も経たないというのに、まるで別人の様だった。頬が痩け、眼窩は落ち窪み、めっきり老け込んでいた。尋常ならざる眼差しは虚空を見つめ、震える声で人類が忘れかけた記憶をしきりに囁くようだった。様相が著しく変貌していたため、手足にひどい火傷の跡があることにしばらく気づかなかった。ここにいるのは私の知る吉荷ではなかった。私は途方にくれた。 警察は公式に発表しないが、会場に詰めかけた180人のうち、4人の死体が確認された。40人ほどが吉荷のように廃人となった。近郷では、精神科医院と云わず、あらゆる病院に狂気が溢れた。そして、更に驚くべき事に、残る100人余りは行方不明となっているのだ。無事な者は一人もいない。こんなガス爆発があるか! 行方不明100人は異常すぎる。この中には我が赤土の会の調査員の残る三人も含まれているのだ。 私はあてにならない警察に憤りながら、本部に救援を求めた。 三日後、私は本部から派遣された二人の調査員をニューオリンズ空港で迎えた。祇田は二年前までこの付近で生活していて土地勘がある。折木は催眠療法に優れた精神医で、吉荷の古い友人でもあるそうだ。私は吉荷を折木に任せ、祇田と共に調査に乗り出した。 問題のオルサー教会は封鎖されていた。中を窺った私達は、三人の屈強な警備員に追い返された。遠目に見れば窓ガラスは砕け、壁は所どころ黒く煤け、確かに何等かの爆発があったことを感じさせる。 私は事件の翌日の新聞を調べる間、祇田を知り合いの警官に会いに行かせた。 私の調査は徒労に終ったが、祇田は面白い話を聞いてきた。現場検証を執り行った警官の何人かが、ここ数日無断欠勤しているそうだ。祇田は欠勤中の警官を独自に調査したが、彼らはみな家族と共に行方不明となっていた。祇田は行方不明の警官のファイルを作成し、私に提出した。 私はその日の出来事を思い起こしながら祇田のファイルに目を通していた。午前一時を過ぎた頃だろうか、いつの間にやら机に向かってうたた寝をしていた私は、奇妙な呻き声に目を醒ました。声は吉荷と折木の部屋から聞こえてきた。ノックをしても返事はなく、呻き声もやまない。そのうち祇田も駆けつけた。私達は目で合図をすると、息を合わせて肩から扉に当たった。扉は内側に歪み、蝶番から抜けた。 部屋の片隅にあるベッドに吉荷が腰掛けていた。その見開かれた瞳孔が、何等かの光の加減で一瞬赤く光った。彼は聞き慣れない言語で呻くように呟き続けている。狂気に憑かれた男に一歩近寄った私は、部屋の入口近くの隅に何かが蟲めいているのに気がついた。私は慌てて部屋の反対側に飛び退った。祇田が電灯のスイッチを入れた。蛍光灯に照らしだされた物体を我々が理解するために数瞬を要した。それは折木だった。服と眼鏡と腕時計。それだけが手がかりだった。何年も司法医をしながら、私にはこれが人間から変化したものとは思えなかった。少なくとも、皮膚が裏返っていた。一部は私も見知った肉片だった。しかし多くは人体には有り得ないキチン質であり、角質であり、全く見知らぬ細胞組織であった。更に驚くことに、その物体は私達が室内には入ったあと、しばらく生きていた。物体の一部が傷口のように開いた。その奥に覗いた奇妙に白い歯から、その裂け目が口だと知れた。口は、ひとしきり血の泡を吐き出すと、なにやら呟き出した。 「ダバダ、ダバダ、ダバダ、ダバダ、ダバダ‥‥‥‥‥」 そのとき突然、祇田が悲鳴を上げた。余りの光景に彼の精神は絶えきれなくなったのだろう。祇田は叫びながら窓から飛び下りた。 警官が駆けつけた時には、折木は事切れていた。警察では折木を死体、少なくとも人間の死体とは見なさなかった。三階から落ちた祇田は右足を折ったが、一命を取り留めた。取調べを終え帰宅した私は、疲れた体を長椅子に横たえた。問題は何一つ解決していなかった。それどころか謎は増える一方だ。私はまた途方にくれた。 |
■「赤土の会」は非常に有能な調査員を多く抱えているようですが、規律がたいへん厳しく、一般の方にはなかなか馴染めないようです。同会にはダバダ問題に関心を持った有志が集まりますが、長続きする方は一握りでしょう。次の文の著者は「赤土の会」に入会したものの、あまりに厳しい会の方針に疑問を抱いて脱会された方の一人です。彼女は会員である間はダバダの存在に確信を持てなかったようですが、脱会後、その考えは改められたようです。
| 私自身が望んだこととはいえ、この四年というもの、私はいささか不遇でした。困っている人のために何かをしたいと思っていたのは確かです。でも、全てを捧げたいとまでは思ってはいませんでしたし、その覚悟もありませんでした。結局、私の見込みが甘かったのです。 私はこの四年間の鬱屈した思いを振り払いたいと思って旅に出ました。傷心の旅路についたと言えばちょっと気取って聞こえるでしょうか。 ヨーロッパの国々を渡り歩き、たくさんの人と出会い、たくさんの発見をしました。観光スポットをわざと外して、旅行ガイドにも紹介されていない新奇な出会いを楽しみました。途中、スイスで出会った日本人女性、東雲鹿子さんと道連れになり、女の二人旅が始まりました。お互い過去のことは何も話しませんでしたが、鹿子さんも訳ありの旅らしく、そんな二人が揃った場合にありがちな、不自然なほど朗らかな旅となりました。 オランダへ行くことに私はあまり気乗りがしませんでした。アムステルダムという街は、これまでいくつかのダバダ関係の事件が交錯した、あまり思い出したくない土地でした。しかし、鹿子さんが是非にと言うので、私は彼女につき合うことにしました。 私は鹿子さんの案内で、郊外にある古城に赴きました。路線バスの道すがら、鹿子さんが窓の外を眺めて涙ぐむのが見えました。それはランデンダイク病院前のバス停の辺りでした。窓の外では火災で焼け落ちた建物の残骸が、ちょうど取り壊されているところでした。おそらくこの火災で、彼女の大切な方の身に何かあったに違いありませんが、私はこの質問を胸にしまっておきました。 ファンデルサール城は市街を見下ろす小高い丘の上に建つこじんまりとした平城で、何でも一五世紀頃に建てられた貴族の別荘のようなものだそうです。城主のウルリッヒ・ファンデルサール侯爵は、鹿子さんの古いお知り合いのようで、突然の来訪にもかかわらず、私たちを暖かく迎えてくれました。おいしい食事と和やかな会話のもてなしを受けて、私たちはとてもよい午後を過ごしました。ファンデルサール侯爵は三十代前半に見えましたが、知識が豊富な方で、特に世界各地の神話や伝説について深い造詣をお持ちでした。侯爵はゴラーシェ断章という本を繙いて、様々な幻想的物語を熱っぽく語って下さいました。ただ、その話は呪詛や怪死を題材とするものが多く、侯爵の人が変わったような熱のこもった話しぶりとも相まって、どこかしっくりこない居心地の悪さを感じました。 夜も更けて、私と鹿子さんは同じ客間に案内されました。広い寝室には、私の部屋ほどの広さがあるベッドが設えられていました。ベッドの脇にはもう一つ簡易ベッドがありましたが(簡易といっても立派なものです)、私と鹿子さんは大きなベッドで二人で寝ることにしました。子供の頃に読んだ赤毛のアンの、アンとダイアナになったような気がしました。 初めて通された貴族の寝室の豪奢ぶりに驚嘆しながら、部屋をくまなく見て回すうちに、枕元の壁に小さな絵が掛かっているのが目に留まりました。それは牧師を囲む子供達の絵でしたが、よく見ているうちに奇妙なことに気づきました。牧師の衣装を着ている方の顔は、帽子の影になっているためか浅黒く、ややもすれば黒人のようにも見えますが、その顔立ちは明らかにファンデルサール伯爵のものでした。そして、伯爵扮する牧師を囲む七人の子供達は東洋系、おそらく日本人ではないでしょうか。黒人のような牧師と七人の日本人の子供、私がこれまでの四年間、常に追い求めていたものの図式がここに蘇ったのです。しかし、侯爵の年頃と事件の時代とは大きく食い違います。他人のそら似なのでしょうか、それとも侯爵のお父さん(お爺さん?)なのでしょうか。子ども達の顔は無気力で、何かに怯えるようでもあり、暖かな寝室にどこか似つかわしくない雰囲気の絵でした。私は奇妙な寒気を覚えました。私は思いきって鹿子さんに全ての事情を話しました。彼女は驚いた様子で何か考え込んでしまいました。夜中にふと目が覚めたとき、傍らで彼女がむせび泣いているのが感じられました。 翌朝目が覚めてみると彼女の姿はなく、侯爵から彼女が早朝出立したことを聞きました。侯爵は昨日とはうって変わった冷然とした態度で、私は追い出されるように城を後にしました。 お互い電話番号を交換しあった二人でしたが、それ以来、鹿子さんとは連絡が取れませんでした。ただ、数日後、イタリアで目に留まった新聞に彼女らしい写真が載っていました。写真は不鮮明ではっきりしたことは言えませんし、イタリア語が読めない私は記事の内容も分かりませんでした。彼女が何かの事件に巻き込まれたのではないかと心配になりましたが、今となっては調べようもありません。 |
■これは、第二次大戦中の日本兵たちの体験談を綴った文集の中に見つけたものです。読んで頂ければお判りだと思いますが、この話はダバダ伝説と関係が深いとされる「ゴラーシェ断章」のなかの「ビオライの語り」の話とひどく似通っています。ビオライは人心を惑わす詐偽師として罰せられましたが、これを読むと彼の話もあながち嘘だとは言えないようです。
| 私の所属した第四〇三歩兵小隊がボルネオのジャングルで斥候任務についたのは昭和十八年の夏だった。十五人からなる小隊は四人の現地人を連れて、敵陣を迂回する道を探した。 三日後、部隊の中で熱病の患者が続出したので、任務を放棄して本隊に合流しようと戻ったところ、連隊の野営地はすでになく、さらに無線器の調子も悪かったので、我々の小隊は向かうべき道を見失った。地図を見ると、確かに連隊本部の跡であるべき場所なのだが、その様な形跡は見当たらなかった。 ただ一つ地図と異なるのは、南西の方角に草木の生えていない小山があることであった。山の頂きには肉眼でも確認できる巨大な建造物があった。我々は何とも奇妙なその山に向けて出発した。 三時間後、山の麓に現地人の村を発見した。我々は病人を抱え、さらに糧食も乏しくなっていたので村人と交渉しようとした。語学に堪能な現地人の通訳が色々試してみたが、どうやら言葉が通じなかったらしい。村人たちは狂暴な様子が見えなかったので、我々は村のそばに野営地を設営した。村人に山の上の建物を示すと、彼らは敬虔そうな顔で頭を垂れた。我々は、その建物が彼らの神殿であることを理解した。 数日後、私たちは村人と少しずつ打ち解け、ときには部族長の家に晩餐に呼ばれることもあった。我々が持ってきた道具を与えると、彼らは喜んで食べ物を運んでくれた。やがてマラリアにかかっている戦友を見た族長が、気の毒そうな顔で彼らを運んでいった。我々は、村人が彼らを隔離して看護してくれるものだと思った。 しばらくして村の祭に招待された。村の中央にしつらえられた巨大な鍋のまわりを囲み、無心に踊る村人の様子は素朴さを通り越して不気味に見えた。彼らはときおり山頂の神殿に向かって「ダバダ、ダバダ!」と低い声で叫んだ。その声に驚いて、たくさんの真っ黒い鳥がジャングルの彼方へ逃げて行った。我々は背筋に冷たいものを感じた。 やがて鍋の中身が皆に配られた。大きな瓶になみなみ注がれたスープを四、五人で囲んで食べた。誰かが柄杓で底の方からすくうと、白くて丸いものが見えた。何だろうと思って瓶から上げてみた。なんと頭蓋骨ではないか! 虚ろな眼窩に睨まれて、我々は暫し硬直した。そして咄嗟に連れて行かれた病気の仲間を思い出した。 誰かが野営地に戻り銃を持って走りだすと他の者も続いた。我々は村に駆け込むや、そこかしこに銃を乱射した。広場に集う人も、驚いて家から飛び出た人も、片っ端から射殺した。さらに村に火を放ち、逃げ惑う女子供も狙い撃ち、弾が切れれば銃床で叩き殺した。やがて村の裏手に小屋を発見した。そこにも火をかけようとすると、中から誰かが這い出て来た。我々は銃を構えたが、良く見ると連れて行かれた病気の兵士であった。彼らは全員無事で、ほとんど治っていた。 東の空が白みはじめたころ、倒錯と恍惚のうちに恐ろしい虐殺は終了した。村へ戻ってよく調べると、鍋の中の頭蓋骨は小さく、形からしても猿のもののようだった。我々は全員言葉もなかった。 これから何処へ行くのか我々は統一した見解を得なかったが、とにかくこの場を離れたいことでは全員が一致した。我々は山の上から位置を確認したほうがいいだろうと、出発前に山の上の神殿に立ち寄ることにした。その時戦友の誰かが、現住民の祭っている神殿で黄金の神像を手に入れて金持ちになった男の話しを思いだした。 そばに立つと神殿はなおさら巨大で、何処から運んできたのか判らないような巨石を組んでそそり立っていた。神殿の中は薄暗く、ひんやりしていて、何処からか何とも言い知れない良い香りが漂ってきた。我々はカンテラを片手に神殿の奥に入って行った。 祭壇の上には様々な供物が供えられていた。その中央に縦穴があり、縄梯子で下に降りると天然の洞窟になっていた。100メートメほど進むと巨大な地底湖があった。良い臭いはここから漂っていた。湖水はドロドロとして泡立っていた。 湖のほとりに光を向けると、そこには何体もの人骨が転がっている。中には日本軍の軍服を着たものもあるではないか! その時、突然泡立つ湖面が盛り上がった。いったいどうしたことか! 水が湖畔を離れ、ズルズルとにじり寄ってきたではないか! 滴る波が、打ち寄せる水が、渦巻く泡が我々に襲いかかってきた。兵士の一人が水に捕まった。助けようと駆け寄った兵士もまた捕まり、水に触った腕が見るみる骨になっていった。 私が覚えているのはここまでだ。半狂乱になって駆け出し、みな散りぢりになった。気がつくと私は米軍の捕虜となり、帰国したとき初めて私が部隊の唯一の生き残りであると知った。私はいつしかこの出来事が熱にうなされたときの悪夢だと思い込むようになっていた。事実発見された時、私はマラリアの高熱に倒れていたそうだ。だが例え夢だとしても、私はもう二度とボルネオに行きたいとは思わない。 |
■一九九二年のロス暴動はわたしたちの記憶にまだ新しいのですが、ここでもダバダに関わる事件が起きていたようです。この文書は暴動を取材していたテレビ・カメラマンのギルバート・ケンダルさんが、超常現象専門誌「ヌアー」に投稿したものです。これが事実ならばダバダは思った以上に我々の近くに潜んでいるかもしれません。ちなみにこの「ヌアー」誌はこれまでにも様々なダバダ関係の記事が掲載されました。
| その日は朝から天気ばかりよくて、なにか嫌な感じがしていた。 黒人容疑者に暴行を加えた白人警官に対する評決を他の局より一秒でも早く流そうという思いで、スタッフ一同がピリピリしていた。速報のテロップを二種類用意し、プロデューサーは電話の前を行ったり来たりしていた。エリオットはいつにも増して不機嫌で、注がれたコーヒーが熱いのぬるいのと喚き散らしていた。 俺たちロケ・スタッフも、評決しだいではいつでも飛び出せる体勢を整えていた。駆け出しアナのオリビアにとって、今度の仕事は大きなチャンスになるかもしれない。彼女が可哀想なくらい緊張しているのが判ったが、どうしてやることもできなかった。なにせ俺自身、今にもちびりそうなくらいコチコチになっていたのだから。 時計を睨みながら移動中継車に荷物を積み込んでいると電話が入った。スタッフは全員身構えたが、電話は待ち望んでいたものではなかった。 「ロング・フェスタで暴動!」 スタッフの視線はエリオットに集中した。エリオットは少し考えてから「GO」のサインを出した。それと同時に中継車はシャーシを歪めて飛び出した。乗り遅れたオリビアの腕をひっ掴んで引き上げながら、北へ向かって右折した。マイクの運転は荒いので有名だ。これで無事故を保つには、よっぽどのテクニックと幸運が必要だろう。 「何だ、あれは」 チーフのクリントがロング・フェスタへ向かうハイウエイの陸橋の上から、下の町並みを指差して叫んだ。あちこちで火の手が上がり、ショーウインドゥは軒並み叩き割られていた。その中を何とも奇っ怪な浮浪者の集団が練り歩いているではないか。彼らはほとんど全裸に近い格好で、泥まみれで、髪も髯も伸び放題で、多くは奇形か不具者だった。そして何より飢えていた。飲食店や食料品店、はてはペットショップまで襲っては食べ散らかした。 クリントは本社にヘリを要請しながら、カメラを回せと叫んだ。俺は中継車の屋根から顔を出し、下の様子を映した。マイクが車を道端につけると、さっきまで震えていたオリビアが車から飛び出して実況をはじめた。彼女はきっとビッグになるとその時俺は思った。 どこから迷い込んだのか、ハイウエイの上にあがって来た奴がいた。下で暴れている連中の仲間であることは一目瞭然であった。止める間もなくオリビアが近づいて右手に持ったマイクを向けた。 「あなたたちは何処から来たのですか」と問われると、男は震える声で「暗い……暗い穴の中……石を掘っていた……ブヨブヨとふやけた赤いの人間に連れられて……石を掘らされていた……」と答えた。男が狂っていることは、その目を見て判った。 「ハンク? ハンクじゃないか」レフ板を持ったマイクが言った。 男はマイクの顔を見ると驚いた様に目を見張った。「マ……マイク……」 その時、突然に異変が生じた。男の顔が苦痛に歪み、叫びをあげようと開かれた口から、見たこともない真っ黒いムシが何千、何万と溢れ出したのだ。ムシはヌラヌラと光る体で男を包み込み、顔といわず手といわず、全身の肉をついばみはじめた。オリビアが吐き出し、俺も熱い胃液が込み上げてきた。ものの三十秒とたたない内にムシは男を骨まで食べつくし、ハイウエイの水はけから流れるように逃げていった。慌ててハイウエイの下を覗くと、下の街に溢れた浮浪者の群れはほとんどいなくなっていた。 後年語りぐさとなったロスの暴動は、そもそもこの事件に端を発しているはずだ。街に溢れた狂人の群れに刺激され、半狂乱になった人々が騒ぎ出したのが最初で、問題の評決に対する抗議行動などそもそもは無かったのかもしれない。しかし警察は狂人の群れなどなかったと言い張り、事件を収めたVTRは「参考として」などといって取り上げられたまま戻ってこない。さらにどんな圧力によるものか、この件に関して報道されることはついになかった。 あとでマイクに聞いた話では、ハンクといわれたあの男、ヘンリー・マッケンシーは四年ほど前から行方不明になっていたという。かれは失踪するしばらく前に「垂れ下がる空間」なる新興宗教に加入し、「ダバダ、ダバダ」と祈りめいた呟きを続けていたそうだ。 |
■これは、アムステルダムの精神病院の焼跡から発見された田口寛重さんのカルテの一部で、彼の口述をもとに記された調書であるとされるものです。大阪在住の中学教諭、梅野孔太郎さんにより発見されたもので、日本で紹介されるや否や、その解釈及び真贋について様々な物議を醸し出しました。
現在ではほとんどの学者がこの文書の信憑性を認めたものの、その解釈については未だ結論が出ないままでいます。
| ヘレン・スチュワートは確かに不世出の詩人だった。彼女の詩など読んだこともないが……。 彼女の埋葬を遠巻きに臨みながら、私は考えていた。 私はヘレンのことを全く知らなかった。また、ヘレンの方も私のことを知らなかっただろう。旅先で出くわした葬列に、さして思う所なく加わった。ただそれだけのことであった。 しかし、ヘレンの死は厳然たる事実である。生前は、ただの一度とてまみえることのなかった人物ではあるが、それでも死は感慨深かった。人の死は、残された者たちに生を問い掛けるものなのだろうか。 私はそっと目を閉じ、自らを見つめた。 私は三年ほど前に突如覚醒した。自分が、群れの中でただ一匹、知性を得た家畜に思えた。 多くの家畜たちのあいだでは、会話を必要とすることはない。彼らは表明すべき意志を持たないからである。むしろ会話をすることはタブーとされている。意志を持つほどの知性があれば、あえてタブーを冒そうとはしない。 ウィルソンの牧場に住んでいたある牛は、その生涯のあいだ、ただの一度も思考したことがなかった。しかもこれは、決して前例のないことではない。 六年前、私の身にいささか奇妙な事件が振りかかった。それを期に私は「ものの本質」を知ることを渇望しはじめた。物事の意味については以前から思うところがあったのだが、事件後の私にとって、それを知ることこそ人生の目的に思われた。 タブーに対する禁忌の念より好奇心が勝ったとき、私は群れの中に自分の居場所がないような気がした。彼は群れをはぐれ、自らを求めて旅立った。 旅は内と外とに果てしなく続いた。そして、更に続いた旅の果てに私は辿り着いた。 最果ての地では、そそり立つ絶壁の上に建つ灰色の寺院で年老いたペルリアの僧侶と禅問答をした。 夢のなかでは兵士たちと混じって幾つもの戦場をくぐり抜け、死と隣り合わせになりながら彼らの哲学を学んだ。 滅び去った帝国の廃墟では、そこに住まう浮浪者と古代の帝王の魂との論争を仲裁しながら互いの意見に耳をそばだてた。 心のなかで全ての結論が出た。私はこれを表現する言葉を求めた。言葉を。 過去から現在に至るあらゆる言語のあらゆる語彙が去来した。その中でただ一つ心に響く言葉があった。 「ダバダ」 無限の意味と真実を秘めるこの言葉を思い、私は涙した。 |
■ワールド・リリジョン、九六年秋号には興味深い記事がありました。同誌はアメリカ西海岸を中心に公称三万部を売る中堅宗教専門誌ですが、読者投稿欄に寄せられた次の手紙は同誌の中でも異彩を放っていました。
この手紙を寄せたT.Sなる人物は、調査の結果どうやら日本人であることがほぼ確定的となっています。手紙はインドからのエアメールで送られてきたそうです。
| 前略。毎号楽しく拝見させていただいております。 前号の特集記事の中で輪廻と不死性についてのバーンズ博士の考察を取り上げてありましたが、それについて私なりに思うところが二、三ございましたので筆を取らせていただきました。 私はある人物(仮にTとします)の消息をずっと追っていました。その調査の中で、博士の定義による「輪廻」と「不死」の中間に当たるような現象が実際に起こっていることを突き止めたのです。 私はTとは直接会ったことはありませんが、死亡したと知らされていた彼の足跡を欧州のある街で偶然に発見し、そこから私の調査が始まりました。調査を妨害しようとする集団に阻まれながら、どうにか私は彼が入院していたとされる病院を探し当てました。ところがその病院で火災がありました。そこで私は妻の裏切りにあい、危うく命を落としかけましたが、何とか窮地を脱しました。 さらなる調査と友人たちの助言により、Tもまた火災を逃れ、そのままブラジルのリオデジャネイロに運ばれたという情報を得ました。早速現地に向かった私でしたが、その後の手がかりを得るまでにかなりの時間を費やしてしまいました。実のところTはリオに近いニテロイという街の総合病院にいたのです。私がたどり着いたとき、Tは既に死亡していました。少なくとも公式にはそう発表されていたのです。しかし、私はその情報に疑問を持ちました。なぜなら、その病院を突き止めてから数日後、私は病院から出されたゴミの中にTの名のラベルが貼られた直径三〇センチほどの円筒形のガラスケースを発見したからです。 私はついにTを追いつめたと思いました。守衛に金を渡し、夜の病院に忍び込んだのはそれから一週間後でした。Tのカルテは脳外科のファイルの中にありました。しかし、カルテの中身はインクで塗りつぶされ、最後に一言「死亡」とだけ書いてありました。執刀医のジドニオ・パイシュ医師が受け持った患者のカルテを斜め読みしたところ、この医師は一週間前、即ち私があのガラスケースを発見した前日にも執刀していました。その患者であるパウロ・ミューレルなる人物は手術の五日後には退院しており、そのカルテには「A0000017移植完了」と思わせぶりな記述がありました。私はそのコード番号がTのガラスケースに貼ってあったラベルにも書かれていたものと符合するのに気づきました。 その時、廊下の方から物音が聞こえ、私のいる保管庫のドアの下から懐中電灯の光が漏れてきました。金を渡した守衛以外にも、巡回中の守衛がいるのを聞いていた私は、慌てて近くのドアの中へ潜り込みました。真っ暗い部屋に忍び込み、隅の方にうずくまって足音が通り過ぎるのを待ちました。 やがて足音が聞こえなくなったのを確認した私は、入口のドア近くにある照明のスイッチを手探りで入れました。ライトに浮かび上がった光景をみなさんは信じられるでしょうか。部屋には例の物と同型の円筒形ガラスケースが五〇近くあり、それらのいずれにも透明の液体が満たされ、その中に灰色のボール状の物体が浮かんでするのです。それらは間違いなく人間の脳髄でした。ケースの棚の中でナンバー一七だけが欠けていたのはご想像に易いでしょう。 私が言った「輪廻」と「不死」の中間という言葉の意味はお判りでしょう。無論それは憶測の域を出ません。しかし、とても興味深い事実として、これまで全く無名の工場員であったパウロ・ミューレルが、その後ある分野で脚光を浴びます。その分野ではとても有名なので、彼の名を聞いた方もいらっしゃるでしょう。そして、Tは母国ではその分野の第一人者として名を馳せた人物なのです。 私は今ではパウロを追っています。私は彼のすぐそばにいます。いつか彼がTである証拠が得られるかもしれません。その時こそ、「輪廻」と「不死」を越えた真実が得られると信じているのです。 |
■次の文は、「ダバダの書」と並び称される奇書である「エーケルマーの福音書」の一ページであるとされます。
この本は「ダバダの書」の内容をキリスト教徒に理解しやすいようにという目的で書かれたらしいのですが、一七世紀末、世界各国で異端判決を受けて焚書され、筆者とそれに関する記録も全て焼き払われたようです。
書かれている内容は難解で、一般人の思考では支離滅裂に思えます。作者はダバダについて真に理解していたか、気が狂っていたか、あるいはその両方かでしょう。
| えるだろう。 先ず、諸君には現実を知ってもらいたい。 かつて「タフロンの盲目」と言われた時代、トルコ人たちの尊大さは大地の怒りを買った。血に飢えた狼が山を降りた時、スルタン達は全員左腕を喰いちぎられた。空が赤みがかった土壁のようにそそり立ち、やがてゆっくりと頭上に落ちた。 これは象徴的なことではなく、現実を描写している。 大河のほとりに、七人の喪服の女がたたずんでいた。三日後、川上から船に似た作りの棺桶がくだった時、七人は七人とも泣き崩れ、そのうち二人は入水した。彼女たちは否定したが、これは事実だった。 カビューラが来た。街の西の門から、予言どおりに来た。オルボネロスとギシターに導かれ、銀の鋳物の鈴を鳴らした。額には月とギシターの印があった。ケブロファンの戸口は重々しく開いた。中からニナの花が覗けた。風が香を運んだ。 あくる日、微かな頭痛とともに眼が覚めると、全身に青白い斑ができていた。黒い本は真実を伝えていた。天空には巨大な十字が嘲るようによぎった。人々は苦痛を胸に田畑へ向かった。鍬を入れると大地は泣き、鋤を入れると血がほとばしった。自分たちの無力が、教会の鐘のように正確に知らされた。 だが、我々が今までに触れていない恐怖があった。この件に言及するには、全ローマ国民の勇気を結集する必要があった。 海。攻めくる戦慄はそこにあるのではないか。青くうねる浪のまにまに、泡立つ白い無数の眼を見たか。太陽を羨望するヤツらの眼を。 ヤツらは敵だ。 家畜や子供をさらい、血の滴る顎がゆっくりと閉じあわされる。 鉤爪の生えた青い手は、一秒毎に我等の大地を蝕む。 そして……そして、あれが訪れる。先触れの角笛が魂を凍らせる。海の中から……我々の失った記憶の中から、時間と空間を超越してそれが来る。 エーケルマーの福音に引き寄せられる。 砂糖に群がる蟻のように次から次へ、後から後へ。だが、誰もが知っている。それは全て一つである。分割することも、新たに加えることもできない。 ●●●●の●●●●●は、●●●●●●●●●●●●こめ。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●とは●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●が、●●●●●●●●●●●●●めろ。●●●●●●●●●●には●●●●●●のままにするな。 「ダバダ!」 ベザレーに栄光あれ。 その時、窓を叩く何かがあった。我々全員がその正体を知っていた。もはや逃げられない。いや、はじめから逃げることなどできなかったのだ。 日が暮れるのを待ちながら、数年来思いもしなかった家族のことを思い出してはむせ |
【訳註】一部に大変反社会的かつ非道徳的な部分がありましたので掲載を自粛しました。
■最後に紹介するのは、わたしのところに届いた手紙ですが、その内容からいって本稿に掲載すべきものに思われます。解説は後回しにしてとにかく読んで頂きたいのです。
| (前略) ところで、このことは先生の研究と直接つながりがあるかどうか判らないのですが、このところ妙に気になることがありますので、是非ともご相談したいのです。 ことの起こりは私の幼少時代にまで遡ります。 当時、私の両親は毎年夏休みになると、母の実家のある山形へ家族で出かけたものでした。確かあれは、私が九歳の時だったと思います。 その年も例年通り山形の家へ行きました。母の実家はずいぶん山深いところで、長い間バスに揺られて行くのでした。ふとバスの窓から道路の両側に迫る森の中に目をやると、木々の間にバスと並んで走る真っ黒い人影が見えました。人間にしては少し不格好だし、猿のようにも見えません。やがて人影は一つまた一つと増えてきました。私は隣に座った母の袖を引っ張って、あれは何かと尋ねようとしましたが、母とともに窓の外を見ると何もいませんでした。 母の実家についてそのことを話すと、父も母も寝ぼけていたのだと笑いましたが、祖母は「それはきっとダンバダさんのお使いじゃよ」といいました。私がダンバダさんとは何かと尋ねると、祖母は困ったような顔で「ダンバダさんはダンバダさんじゃ」とだけ答えました。 その夜のことです。 私は夜中にトイレに起きました。なにしろ田舎の家ですから、トイレは母屋から少し離れたところにありました。 用を足して布団へ戻ろうかとすると、何処からか不思議な音楽が聞こえてきました。辺りを見回すと近くの山の中にほの明るく光っているところがありました。昼間に探検した結果、その辺りに神社があったのを思い出しました。私は何かのお祭だと思い、一人で山の方へ向かいました。 神社の石段を駆け上がり、境内の方を見た私は、一瞬冷水を浴びせられたような感じがしました。境内では篝火に照らされた村人が社の前にひざまずき、音楽に似た呪文を詠唱していました。村人の中に奇妙な人影……昼間にバスの中で見たダンダバさんのお使いがいたのでした。真っ黒で、ヌルヌルしていて、そして何だか生臭い臭いが漂ってきました。私は慌てて頭を引っこめ、恐るおそる儀式を覗きました。私の目は黒い影に注がれました。社の両側に、ひときわ大きな「お使い」が立っていました。「お使い」の顔は人間の顔のパロディーで、非常に離れた両目は飛び出ていて、半開きの口はへの字に裂け、口の中は尖った細かい歯がぎっしりと生えていました。 儀式に何か動きがあり、村人たちが立ち上がった時、その中に私の祖父母とさらに母親の後ろ姿が見えました。私は安堵を覚え母を呼びました。振り向いた母の顔は……顔は……! 離れて飛び出た目と、パックリ裂けた口。明らかに「お使い」の特徴が交ざっていたのです。さらに振り向いた村人全ての顔が同様でした。 私は絶叫して走り出しました。私は家に帰り、布団に潜って震えていました。やがて母が帰ってきましたが、何も言わずに寝てしまいました。私はまんじりともせずに朝を迎えました。 翌朝、母も祖父母もいつもと変わらず、私は昨夜の出来事は夢だったのだと思いました。翌年から、母は一人で田舎へ帰るようになりました。 何故、今頃このようなことを言い出したかと申しますと、最近このことをよく夢で見るのです。それだけでなく、夜中に目がさめると何処からともなく例の音楽的詠唱が聞こえて来るような気がします。そして、何より私自身、何故かしばしば母の実家のある山形に行きたいという強い欲望に駆られるのです。しかし逆に、行ったらもう戻れないのではないかという恐怖が先にたちます。 先生のご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いします。 |
手紙をもらったあと、わたしは彼に会ってきました。実は彼には地方公演の際に一度会っていたのですが、あらためて会ってみて、その変貌ぶりに驚きました。以前は比較的色白だったと記憶しているのですが、何やら病的な黒さが染みつき、目はギョロリとしていて、口も心なしか大きくなったようでした。そう、まるで彼のいう「ダンバダさんのお使い」のように。わたしは一瞬背筋が凍る思いでした。そして、その顔は何処かで見覚えがありました。記憶の糸をたどって行く内に、以前写真で見た佐田原唐志さんの奥さんである鹿子夫人と何処となく似ていることに気づきました。夫人は佐田原氏とともに失踪して行方不明なのですが、その後の調べで彼女も山形県の出身だと判りました。わたしにはこのことが単なる偶然だとは思えません。
その後手紙の差出人との連絡は取れなくなってしまいました。