|
Vol.1  |
ニュースだよ、ニュウーースだよ。 魔術王の驚くべき交替劇 ダークウッドの森の地下深く、一般にダークサイドと呼ばれ、住人の闇エルフからはティランデュイル・ケルサスとして知られる都市がある。この悪夢のごとき様式の都市の中心には、〈ケリスリオンの宮殿〉エイユー・リンデール・ケリスリオンが辺りを睥睨する死神のように建っている。 エイユー・リンデール・ケリスリオンの会議室に、評議会シェルン・ケリスリオンの五人と、ひとりの謎めいた闇エルフ――仮に〈闇の祖〉と呼んでおく――が集まっていた。 闇エルフの支配者たるアイルドン・ケリスリオン王は落ち着きなく王の着く席に坐り、死に脅える老人のように目の前の不遜な男〈闇の祖〉に視線をさまよわせている。 ヴェリコーマ・エンデュール・ケリスリオン皇女は、そんな兄を侮蔑するように冷たい笑みを浮かべていた。すべてを把握しているかのような自信に満ちた態度であった。 ガラスリム家の兄妹、アストリア皇子とリア皇女はふたりでひそひそと囁きあい、ときおりどちらかが冗談でも言ったのか笑い声を漏らした。 メネル・イシルキール皇子は興奮を隠せぬ様子で、手持ち無沙汰に愛用の曲刀の柄を握ったり撫でたりしている。 部屋の入口近くに立っていた〈闇の祖〉は、威厳あふれる様子でアイルドンのいる席へ歩み寄った。 「ここはわたしの席だ。おまえの占める場所はもうこのティランデュイル・ケルサスにはない」 「な、何を言うか、無礼者めが。王に向かってその態度、死罪に値するぞ」アイルドンが声を震わせて言った。 「わたしはヴィライデル・ケリスリオン、最初の王にして永遠の王である」〈闇の祖〉の声が会議室に朗々と響き渡った。 「はるか昔の人物ではないか。僭称に決まっておるわ」 「そうかな。ほかの者に聞いてみてはどうだ」 「ヴェリコーマ! そなた、まさかこのような輩の申すことを信じるのではあるまいな」アイルドンは〈闇の祖〉から目をそむけ、平生最も信用していない妹のほうを見た。 「わたくし、〈黒の九賢者〉に意見を求めましたが、何ら疑いをさしはさむ点はないそうです。兄上も御存知のとおり、〈黒の九賢者〉はティランデュイル・ケルサスにおいてこれ以上はないという力を有した魔術師たちですよ」 ヴェリコーマ皇女は組んだ腕を解くこともなく、冷ややかに答えた。 アイルドンは、ヴェリコーマが「陛下」ではなく「兄上」と言ったことに気づいていた。 「アストリア、リア、これはおまえたちの仕業か。悪戯にもほどがあるぞ」アイルドンは自分に言い聞かせるようにつぶやいた。 「悪戯……偉大な祖の御名を借りてかね。従兄弟殿の偏執ぶりには愛想が尽きるというものだ、なあ、リア」 「まったくですわ、兄様。ケリスリオン家の名を汚しているのはどちらかしらねえ」 ガラスリム家の兄妹は声をたてて笑った。 「に、偽者にちがいない。そうであろう、な、メネル皇子」 メネル・イシルキールはアイルドンをねめつけると、曲刀を見事な早業で引き抜いた。 「おれはそんなことに興味はない。確実に言えることは、このおかたが血の飛沫と剣の閃きに満ちた戦場へおれを導いてくださるということだ。老いぼれに用はない」 アイルドンは椅子から跳び上がり、痩せ細った両手を振り回して叫んだ。 「曲者ぞ! キャムカーネイヤーの近衛は何をしておるか、出合え、出合えい!」 「無駄なことだ。カルハロス家の五本指はわたしに忠誠を誓った」と、〈闇の祖〉。 「馬鹿な、キャムカーネイヤーが仕えるのは闇エルフ族全体とこの都市に対してのみのはず……そうか、リア、貴様の差し金か。夫のタラグルを引き入れて――」 リア・ガラスリムは呆れたように答えた。 「あら、おつむのほうまで老いてしまったのかしらね。答えは御自分でおっしゃってるじゃありませんか。キャムカーネイヤーが仕えるのは闇エルフ族全体とこの都市に対してのみ。では、闇エルフの祖でこの都市の建設者、ヴィライデル・ケリスリオン陛下に仕えぬはずがありませぬ」 「妹よ、みだりに陛下のお名前を口にしてはならぬ」と、アストリア。 「これは失礼をいたしました、陛下。お許しください」 「かまわぬ。この哀れな老人に理解を促すためであろう。そろそろ呑み込めたはずだが……」 〈闇の祖〉が老王の方へ一歩踏み出すと、アイルドンは後ずさりしようとして足がもつれてしまい、後ろへひっくり返ってしまった。 「わしを弑するつもりか。よ、よせ」 「シェルン・ケリスリオンは五人と決まっているそうだな。そうなると一人消えてもらわねばならん」 「し、死にたくない……助けてくれ、頼む」 「ほう、では〈血の牢獄〉セレグバンド行きを望むか。おまえが命じて作った牢獄だと聞いているぞ。自分で味わってみたいかね」 アイルドンは追いつめられた小犬のように悲鳴をあげた。 「あそこは厭だ、あそこへ送られるくらいなら死んだほうがましだ!」 「そうか。だが、わたしにはわが裔を殺す趣味はないのだ。これを使うがよい」 〈闇の祖〉は懐から短剣を抜き、アイルドンの足元へ投げ放った。禍々しいルーンの刻まれた黒い刃の短剣は、床に突き刺さり、ぶるんと震えた。 「自分で命を絶つ自由を与えてやる。感謝することだな」〈闇の祖〉は言った。 アイルドンは諦めたように長いため息をついた。 「寛容なことだ。わしは他人の手にかからずにすむわけか」 「動脈を縦に長く切り裂くのがこつだ。えぐるようにやれ」 〈闇の祖〉はそれだけ言うと、くるりと評議会の四人の方へ向きなおった。 アイルドンは床から短剣を引き抜くや、〈闇の祖〉の背に突き立てようと襲いかかった。次の瞬間、アイルドンの右手が見えない力で強いられたように、握った短剣を自らの首に突き入れた。 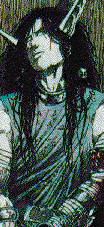 「愚かな。わたしの短剣に呪詛がかけられていないとでも思ったか」 「愚かな。わたしの短剣に呪詛がかけられていないとでも思ったか」〈闇の祖〉は振り向きもせずにそう言った。 「き……きさまは狂っておる……わしの玉座は狂気の持ち主によって脅かされる……マイユールがそう告げたのだ……」 「それはおまえ自身のことさ」 アイルドンはごぼごぼと断末魔の声をもらすと、倒れ伏した。 「予言は成就した」 〈闇の祖〉、すなわちヴィライデル・ケリスリオンは表情ひとつ変えず、席に着いた。評議会の四人は王に臣下の礼を表した。新たなシェルン・ケリスリオンがここに成立したのである。 |
戻る