| ■第3回 |
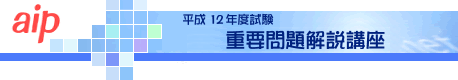
| (問10−1) 私人による公物の時効取得について、国有財産法では、行政財産について法律行為による私権の設定を禁止し、違反行為を無効とするとともに、時効取得も禁止していることから、公物についての時効取得は認められない。 |
| (問10−2) 私人による公物の時効取得が認められる場合があるのであるから、国または公共団体が、私有の公物につき時効取得することが認められる場合もあるとされている。 |
| (問10−3) 私人による公物の時効取得について、公物の所有権は国公有たる私有たるとを問わず私法上の私的所有権であるから公用廃止前でも、何ら負担のない所有権を時効取得できると解するのが最高裁判の判例である。 |
| (問10−4) 私人による公物の時効取得について、公物であっても、長年の間事実上公の目的に使用されず、公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合など黙示の公用廃止があったとみられる場合には、行政上の明確な公用廃止の意思表示がなくても、時効取得できるとするのが最高裁判所の判例である。 |
| (問10−5) 私人による公物の時効取得について、公共団体に所有権を移転することが予定されていた予定公物を、国から譲り受け、それが無効であることを知らないで占有していた者に、時効取得を認めるのが最高裁判所の判例である。 |
| (問11−1) 行政事件訴訟法に関し、「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟および越権訴訟をいう。 |
| (問11−2) 行政事件訴訟法に関し、行政庁の不作為を争うことはできない。 |
| (問11−3) 行政事件訴訟法に関し、取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から3ヶ月以内に提起しなければならない。 |
| (問11−4) 行政事件訴訟法に関し、取消訴訟は、必ず審査請求を経てからでなければ提起することができない。 |
| (問11−5) 行政事件訴訟法に関し、取消訴訟は、処分又は裁決の相手方に限って提起することができる。 |
| (問12−1) 行政手続法および行政手続条例では、法律または条令の規定に基づかない行政指導は許されないものと定められている。 |
| (問12−2) 行政手続法は、地方公共団体の行政指導には適用されない。 |
| (問12−3) 行政手続法は、法律に基づく地方公共団体の行政処分には原則として適用される。 |
| (問12−4) 行政手続条例は、地方公共団体における行政処分だけを対象とする。 |
| (問12−5) 行政手続条例が、地方公共団体における行政手続について、行政手続法と異なる内容の定めをすることも許されないわけではない。 |
| ■さて、何問正解できましたか・・・迷ったらQuickStudyをお試しください。【メニューへ戻る】 |