| ■第20回 民法3 |
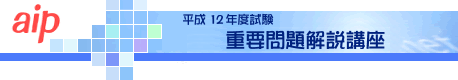
| (問29−1) 債権者取消権(詐害行為取消権)に関し、債権者は、債務者の財産から満足を得られない場合には、債権取得前に債務者が行った贈与契約を詐害行為として取り消して財産を取り戻すことができる。 |
| (問29−2) 債権者取消権(詐害行為取消権)に関し、不動産が二重に譲渡されたため、第一の買主が不動産の引渡しを受けることできなくなった場合には、第一の買主は、債務者と第二の買主との間で行われた売買契約を詐害行為として取り消すことができる。 |
| (問29−3) 債権者取消権(詐害行為取消権)に関し、債務者の財産状態が離婚に伴う相当な財産分与により悪化し、債権者の満足が得られなくなった場合には、債権者は財産分与を詐害行為として取り消すことができる。 |
| (問29−4) 債権者取消権(詐害行為取消権)に関し、債務者が第三者に金銭を贈与したことにより、自己の債権の満足が得られなくなっただけでなく、他の債権者の債権も害されるようになった場合には、取消債権者は自己の債権額を超えていても贈与された金銭の全部につき詐害行為として取り消すことができる。 |
| (問29−5) 債権者取消権(詐害行為取消権)に関し、債権者は自己の債権について、詐害行為として取り消したとしても、受益者から取り戻した財産から他の債権者に優先して弁済を受けることはできない。 |
| ■さて今回は、民法の3回目で、債権者取消権に関し民法424〜425条からの出題です。1〜2問目は条文からそのままの出題、3問目は判例からですが、財産分与の性格を考えると納得できると思われます。4問目と5問目は相反するような規定ですが、総債権者の為に自己の債権の限度内で取消し請求できると覚えましょう。 【メニューへ戻る】 |