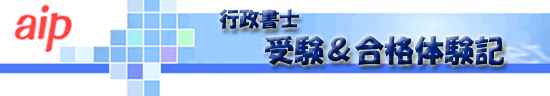
| ■行政書士試験 合格体験記4(Bさんの受験当日〜受験勉強のアドバイス) | |
|
(平成12年度合格 21歳学生 受験歴一回 人文学部出身 受験地青森県) 4.試験日当日 10月22日、8時に受験票・筆記用具・時計・自作テキストをかばんの中に入れ、家を出発、12時に試験会場へ到着(集合時間12時30分)、張り詰めた空気の中、13時に試験が開始(試験時間は、15時30分までの、2時間半)。試験開始の合図ととも に、問題用紙を開く音が試験会場に響き渡りました。 一通り問題を解き終わり、時計を見ると試験終了まで30分近く残っていたので、問題の見直しとマークシートへのマークミスの確認、そして自分が正解していると確信できる問題にチェックを入れました。そのチェックの数が法令20+3問と一般教養12問で、 不安だった一般教養が半分以上チェックできたので、試験終了後は達成感を久しぶりに味わい、試験日は私の誕生日でもあったので忘れられない1日となりました。 5.試験内容 法令科目、択一式は基礎法学3、憲法4、行政法4、行政手続法3、行政不服審査法2、地方自治法4、税法2、行政書士法4、民法4、戸籍法1、住民基本台帳法1、商法2、労働法1の合計35問、記述式は憲法、行政法、行政手続法、行政書士法、民法の各1問 の合計5問で、今まで出題されたことのないような問題が並び、例年より難しく感じました。一般教養、択一式は漢字2、文章問題4、政治経済時事12、理科1、数学1の合計20問で、漢字・文章問題で点数を稼ぐことができ、比較的簡単でした。 6.合格発表 年が変わって、平成13年1月15日、ドキドキしながら県庁のホームページを開き、「行政書士合格者発表」をクリックすると、私の受験番号が合格者9名の中にありました。あまりにもうれしくて、家族や友達が仕事中・授業中にもかかわらず、家族や友達の携帯 電話へ一斉にメールを送りました。 7.受験勉強のアドバイス 行政書士試験にかかわらず、法律資格試験全般に言えることですが、試験に合格するには、条文・判例・過去問が重要です。行政書士試験の判例は過去問でカバーできますから、条文と過去問をしっかり勉強しましょう。今年のように難しいと思われる試験でも、過去 問さえ押さえておけば、合格点は確実にとれます。短期間で合格したい人にとって、過去問を中心とし、条文を参照しながら学習できるAIPのQuickStudyの学習システムは、まさに試験勉強を合理的に行える教材では、ないでしょうか。QuickStudy はCD-ROMによる 学習ですから、参照条文が詳しく載っており、記述式への対応のためにも最適です。 私は、行政書士試験に合格できたのも、過去問を繰り返し解いてテキストへ書き込み、試験にでるところだけを重点的に勉強できたからだと思います。 8.最後に 私は6月に行政書士事務所を開業しました。みなさんも、街の身近な法律家として、行政書士事務所を開業してみませんか。平成12年度から、試験が新形式となって合格率も急に高くなり、今が合格しやすいときです。QuickStudyの学習システムで1日も早くみな さんが合格し、そして登録して下さることを、お待ちしています。 | |