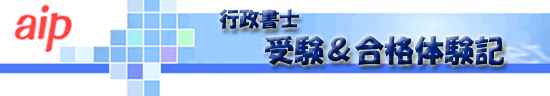
| ■行政書士試験 合格体験記 (Dさんの受験動機から模擬試験での挫折まで) | |
|
(平成13年度合格 43歳技術職 受験歴二回 工学部出身) 私も、自分の合格の体験を皆さんに伝えるべく体験記を書かせていただきます。 まず、行政書士と私の出会いですが、5年前に近所の知らない方の自宅に行政書士と社会保険労務士の看板を出したのを見かけ、なんだろうと興味を持ったことです。その看板には、○○許可申請とかいくつかの代表的な業務が書いてあったのを覚えています。その頃はそれ以上は気にしなかったのですが、その2年後会社ではリストラの嵐が吹き、400人いた工場の従業員が250人に減るに至って、資格としての行政書士を知り自分でもチャレンジすることにしました。 しかし、既に年齢は40歳になっており、記憶力も低下が実感されていて、学習したことが頭に残るのかがとても心配でした。特に、工学部出身で法律には中学で憲法を習った以外に縁が無く、なじめないかもしれない不安もありました。幸い、このエーアイ企画のホームページのQ&Aや合格体験記を読んで勇気づけられ、まず本屋で過去問集を買いました。もちろん、最初は問題を読んでも全く答えが分かりませんでしたが、模範解答と解説とを読んでいくとだんだんと分かるようになってきました。 しかし、法律の全体像がつかめないため、次に小型の六法全書を購入しましたが、民法は文語体の上カタカナ表記で読み難くすごく時間が掛かった記憶があります。でも技術の仕事で培った粘り強さ??で、ゆっくりと前進することはできました。 最初の受験のときは、無謀にもこの過去問集と小型の六法全集のみの学習で本番に突撃しましたが、やはりドンキホーテでしかなく、結果は見事な不合格でした。過去問集は何度も学習していたので、やり直すと問題を読まなくても答えが分かる程になっていたため、自分では実力がついたと誤解をしていたようです。法令問題は3割弱しか正解できず、記述式に至っては零点でした。 ただ救いは、一般教養が結構できて8割弱を正解できたことで、翌年への展望が開けました。これで法令が5割強できていれば合格ラインに達すると感じたのでした。(きっと普通の受験生が聞いたら「なんと楽天的なやつだ」と思うことでしょうが。) 初年度の試験が終わり、不合格が間違いないと確信した私は、早速11月から通信教育に取り組むことにしました。私は地方在住でいわゆる予備校が近くになく、残業も多いので通学は無理とあきらめ、また純粋の独学ではスケジュール管理に不安があったため、とにかく一番安い通信教育を探して申し込みました。(きっと普通の受験生が聞いたら「教材を値段で選ぶなんてなんて馬鹿なやつだ。」とお怒りのことでしょうが、ケチな性格ですのでお許し下さい。) ここでまず、学習戦略をたてることにしました。自分は残業が多くあまり学習時間がとれないことは分かっており、1日1時間として残された11ヶ月でせいぜい330時間がやっとかと見積もりました。巷では1000時間以上必要、できれば1500時間は欲しいと言う人もありましたので、その落差をどう埋めるかが勝負と考えました。 そこで学習のポイントを短時間で効率的に勉強できる方法とし、クイックとい名前に惹かれて、エーアイ企画のQuickStudyを申込しました。(きっと普通の受験生が聞いたら「教材を名前で選ぶなんてなんて馬鹿なやつだ。」と思うことでしょうが。) QuickStudyにはおまけにクイック六法なる法令集がついてきて、これも結構便利で学習効率の向上におおいに貢献しました。 短期合格の大研究を読み、学習時間は家族の協力を得て作るものだと悟り、受験すること自体にあまり賛成していない女房を苦労してくどき、一年限りとの約束でなんとか協力の了解を得ました。その内容は、家族サービスは最低限に、一家団欒も短くて我慢してもらうこととになりました。 次は残業ですが、幸か不幸か不況で残業が原則禁止となり、大幅に残業時間を減らすことができました。(収入もですが。)これらの結果、平日1日2時間、休日には5時間の学習時間が確保できる見通しとなり、あとは自己管理能力次第の状況を確保しました。 学習の大きな流れは通信教育の課程に従い法令毎に学習をすることとし、学習の要点の把握と理解度向上のためにQuickStudyを使う形を考えました。この法令別問題は条文の順番に問題が整理されているため、法令の頻出箇所が見えてくるのが便利でした。 学習パターンとしては、以下の三段構えの構成を採用しました。 (1) 最初に学習範囲を区切りその範囲の過去問をQuickStudyで学習する。もちろん最初は何を聞いているのか分からない場合が多いのですが、気にせず解答し解説を読みます。何問かこなしていくと、その範囲での頻出部分が見えてきました。 (2) 次に、通信教育でその範囲の学習をする。学習をするといっても教科書を読むということ以外にないのでが、この過程でその範囲の必要知識の全体像が見えてきます。しかし、教科書を何度読み返しても理解できない要素も多く残りますが気にしないで先に進みました。 (3) 三段目に、同じ範囲をQuickStudyで二度目の学習をして吸収した知識の確かさをチェックするようにしました。ただ正解・不正解に一喜一憂するのではなく、自分で考えた解答の背景が解説と一致しているかどうかまでを確認するようにしました。 6月には通信教育も一ヶ月遅れで修了し一通りの知識は付いたと思い、腕試しに模擬試験を受けてみました。結果はトータルで5割に満たないもので、自分の知識がまだまだらである事が判明し二回目の挫折を味わいました。また、覚えたと思った箇所も結構忘れており、物忘れの激しい年齢のハンディも感じました。 学習時間も意志の弱さからか当初計画時間の6割程度しか確保できておらず、ワンチャンスしか与えられていない私に、模擬試験により学習体勢の立て直しを迫られる結果となりました。 | |