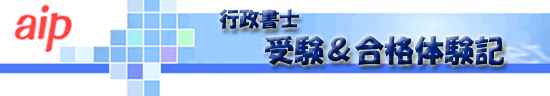
| ■行政書士試験 合格体験記 (Eさんの受験動機から学習時間の作り方まで) | |
|
(平成14年度合格 44歳無職 受験歴二回 国文学部出身) 1 受験動機 私は30歳代の頃から、これからは何か資格がないと危ないとは思っていたものの、自分の怠慢と、リストラされてもまず次の仕事を探すのが先だと思っているうちに結局ズルズルと過ごしてきてしまいました。 しかし、4番目の会社をリストラされたのが42歳の時で、さすがに仕事も見つからず、何が何でも(資格を取らなければ)と言う状況に追い込まれたのでした。 2 学習方法 郊外に住んでいた私は、失業中なので予備校のある市内までの交通費も出せず、独学でやるしかありませんでした。 1年目は5月にリストラされてから、まず8月の社会保険労務士試験を目指しました。そして、行政書士試験の準備は社労士試験の終わった後の9月と10月しか出来ませんでした。当然ながら、準備不足で両方とも落ちてしまいました。 2年目は時間があるので両方を併行して勉強できると思っていたら甘かった。結局8月までは社労士にかかりきりで、行政書士はまたしても9月と10月の2か月で突貫工事とあいなりました。 3 教材 2年目はまず受験本をいくつか読んで、作戦を練り直すことから始めました。その結果、資格試験は学校の入学試験などとは異なり、まず過去問を徹底して検討することが大切だと分かりました。事実、社労士試験でもそのやり方で手ごたえがありました。 テキストは東京法経学院「行政書士合格パスポート」を使用。(ただし、時間が無いので業務法令の2冊だけで、一般教養は買いませんでした)。 過去問はもちろんQuickStudyを使用。パソコン初心者の私はインストールこそ手間取りましたが、シンプルで扱いやすく十分に活用させてもらいました。慣れれば1日で1年分をこなすことができ、QuickStudyが無ければ合格できなかったでしょう。 4 学習時間の作り方 インターネットで採点して社労士試験がほぼ合格だと分かり、大変悩んだのですが9月と10月の2か月は行政書士試験の準備に専念することにしました。さらに1年間のロスをするよりはと決断したのですが、当然ながらその間は無収入で家族には大変迷惑をかけました。 どうしても雑用があったりして、学習時間は1日平均5時間ぐらいだったと思います。どこへでもテキストを持っていって、例えば病院の待ち時間など空いた時間にとにかく読むようにしました。 | |