受信機の性能に関して、「3S」という言葉が、かつて無線の雑誌によく記載されていました。
ご存知の方も多いと思います。これは、「感度、選択度、安定度」を表す英単語の頭文字が
いづれも「S」なので、三つ合わせて「3S」と表記されたようです。
昔、真空管が主役だった頃、メーカー製のリグも「LC」のVFOでしたから、周波数「安定度」は重用でした。
ラグチュウしていると、お互いに動いてしまい、スタンバイの都度、ダイアルを回していましたね。
交信相手に、「周波数が動いたよ。」と言ったら「動くからVFOだよ。」の返事。???
さて、現代のメーカー製のリグの周波数「安定度」は抜群ですね。自作の場合でも、FET等を使えば
昔の真空管のリグより安定度の良いVFOも製作可能です。
それから「感度」や「選択度」についてですが、私自身ある程度は理解し、測定出来るつもりなのですが
「IMD」については、よく分かりませんでした。ところが今回、受信機のIMD測定の必要が生じたため
チャレンジしてみることにしました。
ARRL発行のハンドブック(通称アマハン)に記載されているIMD測定方法を参考に
18MHz帯QRPトランシーバー「FUJIYAMA」の受信IMDを測定してみる事にします。
尚、測定に使用する機器の内いくつかは、自作してみます。
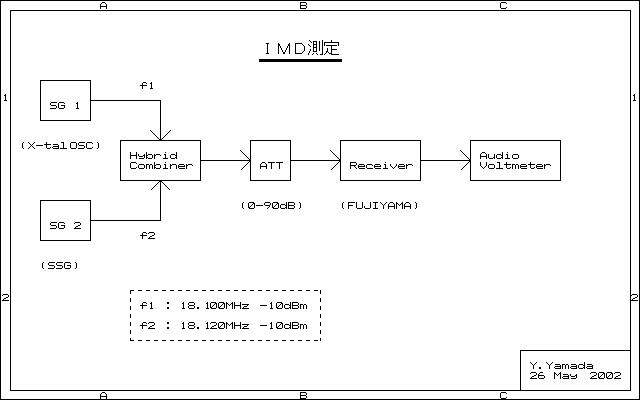
測定は2台のSGから20KHz離れたRF信号(−10dBm)をハイブリッド・コンバイナーに入力し
ステップATTを通して受信機へ入れ、AF出力端子のレベルをミリバルで読み取ります。
ところで、私はSGを1台しか所有していません。そこでSG(1)の代わりに、手持ちの水晶(18.100MHz)で
出力−10dBmの発振器を製作しました。下はその回路図です。
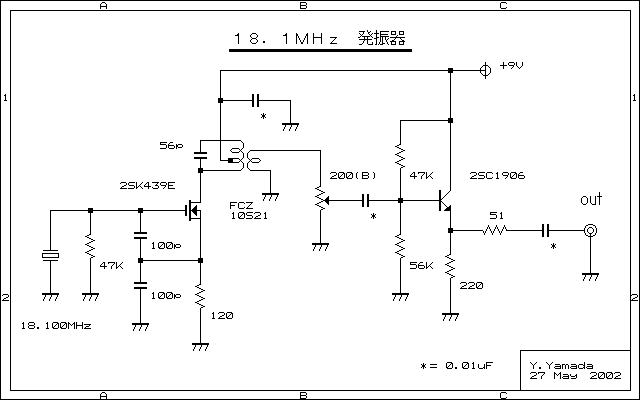
下の写真は生基板上に組んだ18.1MHz発振器[SG(1)]。
製作後、発振周波数を測定してみると、18.098MHzでした。
IMD測定には20KHz離れたもう一つの信号が必要ですから
SG(2)[手持ちのSSG]の発振周波数は18.118MHzにします。
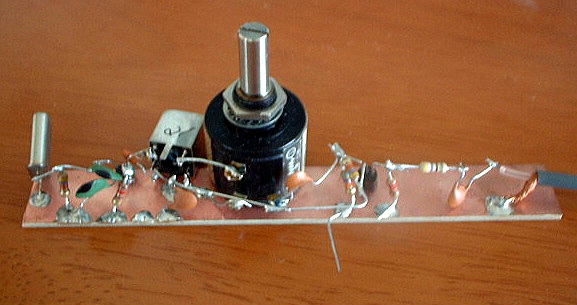
次に製作したのが、下の写真のハイブリッド・コンバイナー(3dBハイブリッド)。
本当はシールド・ケースに組み込まなければならないのですが、今回は生基板上に組んでみました。
詳細は「トロイダル・コア活用百科」をご覧下さい。
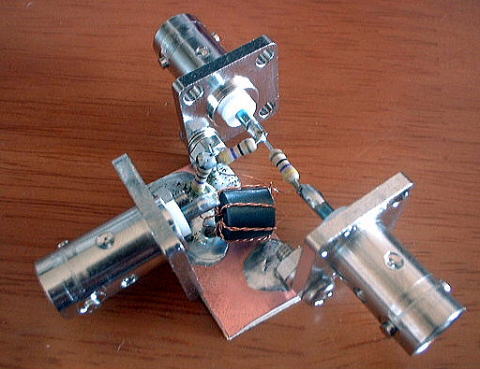
ハイブリッド・コンバイナーの100MHzまでの周波数特性。
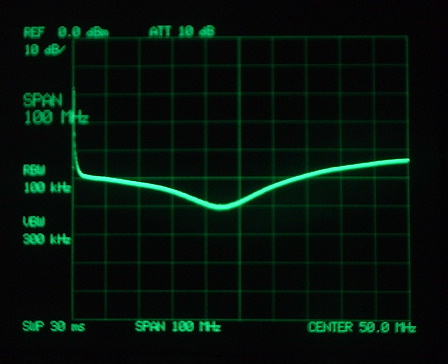
ハイブリッド・コンバイナーにSG(1),SG(2)2台からのRF信号(18.098MHzと
18.118MHz、共に出力−20dBm)を入力してスペアナで出力を見たところです。
縦は一目盛10dB、横は一目盛10KHzです。20KHz離れた2つのRF信号が
きれいに合成されているのが、よくわかりますね。
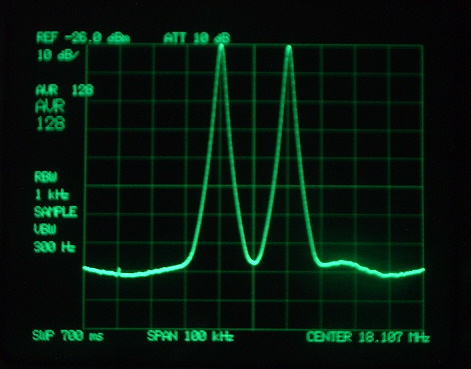
それでは、IMD測定の前に受信機のノイズ・フロアーを測定してみましょう。
SGと受信機の間にステップATTを入れ、AF出力端子にミリバルをつなぎます。
SGの発振周波数を18.100MHz(出力−100dBm)に、受信機の受信周波数も
SGに合わせます。モード(フィルターの帯域)はSSB、CWどちらでもOKですが
測定中は変更しないようにします。
最初はステップATTの減衰量を最大にしておき、少しづつATT量を減らしていきます。
そして、AF出力が3dB増えた所でATT値を確認します。
私のFUJIYAMAの場合、ステップATTが38dBの時でしたから
ノイズ・フロアー = −100dBm−38dB
= −138dBm となりました。
各測定器を前出の「IMD測定」のように接続します。2つのRF信号を、f1=18.098MHz
f2=18.118MHzとしましたので、3rd IMDは (2f1−f2)と(2f2−f1)から
18.078MHzと18.138MHzに現れることになります。
それでは、受信周波数を18.078MHzに合わせて、ステップATTの減衰量を最大にします。
次に、少しづつATT量を減らしていきます。AF出力がノイズ・レベルから3dB増えた所で
ATT値を確認しましょう。
私のFUJIYAMAの場合、ステップATTが49dBの時でしたから
IMD ダイナミック・レンジ = ノイズ・フロアー − IMD レベル
= −138dBm − (−49dBm)
= −89dB となりました。
アマハンを参考に受信IMDの測定方法を勉強してみました。古くて校正していないSGと
自作の簡易測定冶具の組合せですから、測定値には誤差があります。
あまり数値は気にしないようにしましょう。HI。
それよりも実際にワッチしてみて、自分の感性にあった受信部がベストですね。
その点、FUJIYAMAは私にとって最も相性の良いQRPトランシーバーです。