| 園名の「ルンビニ」は、お釈迦さまがお生まれになった地名です。 園章は、お釈迦さまの誕生の伝説をもとに、「純白の象」をデザイン したもので、象の背飾りには、 「栴檀(せんだん)は 双葉(ふたば) より芳(かんば)し」 の故事にならって、双葉が配され、その上には、 王冠がのっています。 |
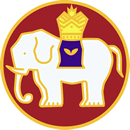 |
| 仏教聖典に説かれている「お釈迦さまの生涯の伝説」の一部をご紹介します。 |
|
|
| 「園名と園章」「園 歌」「教育方針」「沿 革」「事業報告」「財務状況」「学校評価報告書」が載せてあります。 事業の概要は、「行事と写真」「職員紹介」のページを参照してください。 |
| 園名の「ルンビニ」は、お釈迦さまがお生まれになった地名です。 園章は、お釈迦さまの誕生の伝説をもとに、「純白の象」をデザイン したもので、象の背飾りには、 「栴檀(せんだん)は 双葉(ふたば) より芳(かんば)し」 の故事にならって、双葉が配され、その上には、 王冠がのっています。 |
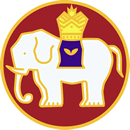 |
| 仏教聖典に説かれている「お釈迦さまの生涯の伝説」の一部をご紹介します。 |
|
|
|
|
「正しく 強く 親切な」人格に輔成することを本園の教育精神とする。 |
|
|
|
昭和 5年 5月12日 「沼津積善会」(代表者 林彦明)の事業として設置認可を受ける。 |
|
昭和 5年 7月 1日 開園式を行う。 園長林彦明、主事林輝彦、教育顧問に高楠順次郎、 |
|
昭和 5年 9月 3日 林彦明 浄土宗大本山百万遍知恩寺(京都)法主に選任される。 |
|
昭和10年 4月 1日 林輝彦(彦明長男)が園長に就任する。この間、上村義秀、天岫接三が |
|
昭和20年 7月16日 夜半の空襲により、園舎、教具、書類等全て灰燼に帰する。 |
| 昭和20年 9月 9日 林彦明 遷化(満77歳)。 |
|
昭和20年11月 1日 林輝彦 焼跡に急造建物を築造する。 |
|
昭和23年10月25日 林輝彦 旧海軍工廠の建物の払い下げを受け、名取栄一、宇野秀吉、 |
| 昭和30年 7月 1日 開園25周年記念式典を挙行する。 |
|
昭和37年 6月27日 園の管理運営組織を学校法人に改める。理事長に園長林輝彦、理事に |
| 昭和41年11月15日 林輝彦 文部大臣表彰を受ける。(幼稚園教育功労) |
| 昭和42年11月 3日 林輝彦 静岡県表彰条例による県知事表彰(教育文化功労)を受ける。 |
| 昭和43年11月27日 林輝彦 文部大臣表彰を受ける。(教育功労) |
| 昭和45年11月 1日 林輝彦 (社)静岡県私立幼稚園振興協会の初代理事長に就任する。 |
| 昭和47年 4月29日 林輝彦 勲五等雙光旭日章を受ける。 |
| 昭和47年10月27日 有志の協賛を得て、新園舎が竣工する。 |
| 昭和50年10月29日 林輝彦 遷化(満73歳)。 |
| 昭和50年11月10日 林茂樹(輝彦長男)が理事長・園長に就任する。 |
| 昭和52年 6月25日 林茂樹 静岡県私立学校審議会委員 ( 〜 平成10年 6月30日) |
| 昭和55年 7月 1日 開園50周年記念式典を挙行する。 |
| 昭和59年 5月15日 林茂樹 静岡県私立幼稚園振興協会理事( 〜 平成12年 5月16日) |
| 昭和61年10月21日 林茂樹 静岡県教育委員会教育委員 ( 〜 平成6年10月20日) |
| 昭和63年 7月 1日 園舎屋根を全面改築する。 |
| 平成 元年11月 1日 林茂樹 静岡県教育委員会教育委員長 ( 〜 平成2年10月31日) |
| 平成 3年10月30日 林茂樹 文部大臣表彰を受ける。(私立学校教育功労) |
| 平成 5年11月 1日 林茂樹 静岡県教育委員会教育委員長 ( 〜 平成6年10月20日) |
| 平成 6年 5月17日 林茂樹 静岡県私立幼稚園振興協会副理事長( 〜 平成12年 5月16日) |
| 平成10年 1月11日 沼津市消防長から火災予防活動と火災予防思想普及の表彰を受ける。 |
| 平成12年 7月 1日 開園70周年記念式典を挙行する。 |
| 平成12年11月 3日 林茂樹 藍綬褒章を受ける。(教育振興功績) |
| 平成14年12月20日 宮崎政子教頭 逝去(満91歳)。勤続53年。 |
| 平成15年 7月30日 国土交通省沼津河川国道事務所長から海岸美化愛護の表彰を受ける。 |
| 平成17年 8月31日 園舎の耐震補強工事が完了する。 |
| 平成19年 7月31日 国土交通省中部地方整備局長から海岸美化愛護の表彰を受ける。 |
| 平成21年11月 3日 林茂樹 旭日雙光章を受ける。(元 静岡県教育委員長) |
| 平成22年 6月 5日 開園80周年を記念して、園庭の芝生化に取り組む。 |
| 平成22年 9月 1日 開園80周年記念事業として、大型遊具及びグランドピアノを購入する。 |
| 平成25年 8月21日 各教室と事務室にエアコンを購入し設置する。 |
1 理事会・評議会の開催 令和 6年 5月11日(土)理事会・評議員会 令和 5年度事業報告並びに決算について 令和 6年度事業計画並びに予算について 学校評価について 令和 6年12月27日(金)理事会・評議員会 学校法人ルンビニ幼稚園の寄付行為の変更について 評議員の選任について 令和 7年 3月22日(土)理事会・評議員会 令和 6年度補正予算について 令和 7年度事業計画並びに予算について 2 監事監査 令和 6年 5月11日(土) 当法人の令和 5年度の業務並びに財産についての監査 3 学級及び園児数(令和6年5月1日現在) 年少 1学級 1人 年中 1学級 3人 年長 1学級 7人 合計 3学級 11人 4 教職員数 園長以下教員 6人 5 施設・設備関係 消防用設備点検 グランドピアノ調律 園舎、遊具塗装工事 園舎屋根防水塗装工事 園庭西側 白門簡易錠設置 照明器具交換取付工事 跳び箱修理 |
令和6年度 資金収支計算書
令和6年4月1日 〜 令和7年3月31日
|
収入の部 |
|
支出の部 |
||
|
科 目 |
決 算 額 (円) |
科 目 |
決 算 額 (円) |
|
|
学生生徒等納付金収入 |
374,325 |
人件費支出 |
22,210,321 |
|
|
寄付金収入 |
97,100 |
|||
|
補助金収入 |
34,044,252 |
経費支出 |
9,194,184 |
|
|
受取利息・配当金収入 |
10,823 |
|||
|
資産売却収入 |
0 |
補助活動支出 |
1,396,071 |
|
|
補助活動収入 |
1,228,090 |
施設関係支出 | 0 | |
|
雑収入 |
385,410 |
設備関係支出 |
650,000 |
|
|
前受金収入 |
30,000 |
資産運用支出 |
0 |
|
|
その他の収入 |
2,528,801 |
その他の支出 |
15,675,838 |
|
|
資金収入調整勘定 |
△ 2,453,662 |
資金支出調整勘定 |
△ 714,622 |
|
|
当年度収入合計 |
36,245,139 |
当年度支出合計 |
46,365,721 |
|
|
前年度繰越支払資金 |
32,524,453 |
次年度繰越支払資金 |
22,403,871 |
|
|
収入の部合計 |
68,769,592 |
支出の部合計 |
68,769,592 |
|
令和6年度 事業活動収支計算書
令和6年4月1日 〜 令和7年3月31日
| 教育活動収支 | ||||
|
事業活動収入の部 |
事業活動支出の部 |
|||
|
科 目 |
決 算 額 (円) |
科 目 |
決 算 額 (円) |
|
|
学生生徒等納付金収入 |
374,325 |
人件費支出 |
22,210,321 |
|
|
寄付金収入 |
97,100 |
経費支出 |
9,968,072 |
|
|
補助金収入 |
34,044,252 |
補助活動支出 |
1,396,071 |
|
| 補助活動収入 | 1,228,090 |
減価償却額 |
773,888 |
|
| 雑収入 | 385,410 |
|
||
|
教育活動収入計 |
36,129,177 |
教育活動支出計 |
32,178,393 |
|
|
|
教育活動収支差額 |
3,950,784 |
||
| 教育活動外収支 | ||||
|
事業活動収入の部 |
事業活動支出の部 |
|||
|
科 目 |
決 算 額 (円) |
科 目 |
決 算 額 (円) |
|
|
受取利息・配当金 |
10,823 |
借入金等利息 |
0 |
|
|
収益事業収入 |
0 |
その他の教育外活動支出 |
0 |
|
|
教育活動外収入計 |
10,823 |
教育活動外支出計 |
0 |
|
| 教育活動外収支差額 |
10,823 |
|||
|
経常収支差額 |
3,961,607 |
|||
| 特別収支 | ||||
|
事業活動収入の部 |
事業活動支出の部 |
|||
|
科 目 |
決 算 額 (円) |
科 目 |
決 算 額 (円) |
|
|
資産売却差額 |
0 |
資産処分額 |
0 |
|
|
その他の特別収入 |
0 |
その他の特別支出 |
0 |
|
|
特別収入計 |
0 |
特別支出計 |
0 |
|
| 特別収支差額 | 0 | |||
| 予備費 | 0 |
|
||
| 基本金組入前当年度収支差額 | 3,961,607 | 前年度繰越収支差額 | △30,201,359 | |
| 基本金組入額合計 | 0 | 翌年度繰越収支差額 | △ 26,239,752 | |
| 当年度収支差額 | 3,961,607 | 事業活動収入計 | 36,140,000 | |
| 基本金取崩額 | 0 | 事業活動支出計 | 32,178,393 | |
貸 借 対 照 表
(令和6年3月31日現在)
|
科 目 |
金 額 (円) |
|
科 目 |
金 額 (円) |
|
固 定 資 産 |
32,512,252 |
固 定 負 債 |
0 |
|
|
有形固定資産 |
10,391,002 |
長期借入金 |
0 |
|
|
土 地 |
4,427,000 |
退職給与引当金 |
0 |
|
|
建 物 |
2,811,379 |
流 動 負 債 |
1,513,170 |
|
|
構 築 物 |
648,003 |
短期借入金 |
0 |
|
|
教育用機器備品 |
132,442 |
未 払 金 |
714,622 |
|
|
管理用機器備品 |
1,131,408 |
前 受 金 |
30,000 |
|
|
図 書 |
1,240,770 |
預 り 金 |
768,548 |
|
| 特定資産 | 20,000,000 | 負債の部合計 | 1,513,170 | |
| 減価償却引当特定預金 | 20,000,000 | 第1号基本金 | 78,096,367 | |
| 施設設備引当特定預金 | 0 | 第4号基本金 | 4,000,000 | |
| みなし退職引当特定預金 | 0 | 基本金の部合計 | 82,096,367 | |
|
その他の固定資産 |
2,121,250 |
当年度消費収支差額 | 3,961,607 | |
|
電話加入権 |
110,000 |
前年度までの消費収支差額 |
△ 30,201,359 | |
|
協会預け金 |
2,011,250 |
基本金取崩額 |
0 | |
| 流 動 資 産 | 24,857,533 |
翌年度繰越収支差額 |
△ 26,239,752 | |
| 現金・預金 | 22,403,871 | 純資産の部の合計 | 55,856,615 | |
| 未収入金 |
2,453,662 |
|||
| 資産の部合計 |
57,369,785 |
負債の部、基本金の部 |
57,369,785 |
|
|
減価償却額の累計額 |
67,595,365 |
|||
財 産 目 録
(令和6年3月31日現在)
Ⅰ 資 産 の 部 |
|
|
科 目 |
金 額 (円) |
|
固 定 資 産 |
32,512,252 |
|
有形固定資産 |
10,391,002 |
|
土 地 沼津市千本緑町2−7 443.43㎡ |
4,427,000 |
|
建 物 |
2,811,379 |
|
構 築 物 |
648,003 |
|
教育用機器備品 |
132,442 |
|
その他の機器備品 |
1,131,408 |
|
図 書 |
1,240,770 |
| 特定固定資産 | 20,000,000 |
| 減価償却引当特定預金 定期預金(静岡銀行本町支店) | 20,000,000 |
| みなし退職引当特定預金 定期預金(静岡銀行本町支店) | 0 |
|
その他の固定資産 |
2,121,250 |
|
電話加入権 |
110,000 |
|
協会預け金 預け金(社団法人静岡県私立幼稚園振興協会) |
2,011,250 |
|
|
|
|
流 動 資 産 |
24,857,533 |
|
現 金 |
0 |
|
預 金 普通預金(静岡銀行本町支店) |
22,403,871 |
|
未収入金 県・市補助金 |
2,453,602 |
|
資 産 の 部 合 計 |
57,369,785 |
| Ⅱ 負 債 の 部 |
|
|
科 目 |
金 額 (円) |
|
固 定 負 債 |
0 |
|
長期借入金 |
0 |
|
退職給与引当金 |
0 |
|
流 動 負 債 |
1,513,170 |
|
短期借入金 |
0 |
|
未 払 金 私学共済掛金 ほか |
714,622 |
|
前 受 金 入園料前受金 |
0 |
|
預 り 金 源泉税、私学共済掛金 |
768,548 |
|
負 債 の 部 合 計 |
1,513,170 |
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 1 保育の計画性 | |||||||
自己評価 A ・園の教育方針・教育理念の「正しく、強く、親切に」について理解、共感している。折にふれて具体的に話をして日常生活につながるような伝え方をした。行事などで園長先生が話してくださることで、自分自身も再認識して、子ども達一人ひとりの育ちに反映できるように考える機会となった。 ・教育要領については、幼児期に育ってほしい10の姿について照らし合わせて考えてきた。年度途中も学期ごとには教員間で共有して振り返り、子どもの様子を確認するようにした。また、忙しい日々の中でも個々の子どもを振り返って、関わり方に生かしていきたいと思い過ごしてきた。 ・指導計画や週案は、基本的には前年度のものを軸にしたが、園児数がクラスによって少人数になったことで、これまでの保育の良いところも取り入れながら、今の子ども達に沿った内容を考えるようにした。 ・同じ学年を受け持つことで、昨年度の指導計画やこれまでの週案をよく見直しながら、自分の経験も生かすよう努力した。一学期に二学期の行事までの見通しも教員間で出来る限り立て、検討や準備をするようにした。 ・週案には保育の反省や子どもの様子を記入したが、その日の保育を一日の終わりや週、月ごとにも振り返りやすくて良かった。様子を記入する際に、10の姿について触れることができたらと今年度も考えていたが、日常的にはあまり浸透することができなかった。 ・年少クラスには一時預かりの子が不定期で入り、登園も個人差があったので、週案は立てづらいこともあったが、なるべく進度に差が出ないように心がけた。 ・週案を教員間で回覧することで、他のクラスの活動や子どもの様子、各教員の視点などを知り、新たに気づくことも多く確認しやすかった。また日頃関わりが少ない子どものことや、その後の気になっていた様子を知ることができて、その子への関わり方のヒントになることも多かった。 ・一年を通し、子ども達が主体的に動けるように環境を設定したり、声かけをすることを意識した。制作活動などで「こうしなければ」という想いが今まではあったが、今年の子ども達の豊かな発想のおかげで、柔軟に考えられることが増えた。 ・ポイントだけおさえて自由にしたところも多く、個性が出て良かった。朝登園した時に、物を置く、ボードに描くなどすることで活動を楽しみにしている様子も見られた。 ・日々の保育を振り返っているが、声かけについて改善できない所もあったので、他の先生や専門機関に相談したこともあった。今後もより良い働きかけを目指したい。 ・制作において計画や工程の面ではスムーズにできることが増えたが、素材の相性まで考慮できずに、制作を行ってから気づくこともあった。放課後に修正することもあったので、効率の面でも試作の段階で気づけると良かった。 ・運動あそびなどは、苦手なことにも挑戦できるようにカードを作ったり、楽しめる働きかけを心がけた。メロディオンと共に、一、二学期に比べて三学期は取り組む機会をあまり持てなかった。 ・子ども達の流行を知り、あそびに必要な廃材や道具を用意した。活動できる時間配分も考えながら、子ども達が満足できるような提供の仕方を考えた。 ・一人ひとりのことを考えて、時計や立ち位置、座る位置に印をつけたり、絵カードを利用したりして、視覚的にも集中しやすい環境に配慮した。 また、机と椅子の高さが合わせずらい子どもには、足台を作って調節した。・季節の変化は、壁面を変えることやごっこあそびなどで伝え、外では園庭や畑の植物・食物をとおして、また水あそびなどをとおして感じられた。 ・畑やプランターで野菜や花を育てる活動を引き続き行い、種や苗植えの後には、水やりをしながら様子を観察した。自分が植えた場所などを覚え楽しみにする姿も見られた。収穫して、園や家で美味しく食べた。 ・今年度も異年齢の友だちと様々な場面で交流した。年下の友だちに優しく関わる様子や、年上の友だちに積極的に関わる姿が見られた。 ・保育活動としては、運動会、音楽会をとおして縦割りで行う内容もあった。大変なこともあったが、上の学年の子ども達の面倒見が良く助けられることが多かった。 ・来年度も学年によって人数に偏りがあるので、縦割り保育の良い部分を生かして、今後の保育に役立てたい。 |
|||||||
| 学校評価委員 A 自己評価からは、園の教育方針「正しく、強く、親切に」を日々の保育に反映させる真摯な姿勢が伝わり、具体的な話し方や日常生活とのつなげ方に工夫が見られる。教育要領や「育ってほしい10の姿」を意識し、定期的な振り返りを行っている点が評価できるが、日常的に「10の姿」に触れる機会をさらに増やすことが必要である。 少人数クラスに合わせた柔軟な保育計画や、制作活動、運動遊びにおける子ども達の主体的な取り組みを引き出す環境設定が工夫されており、子ども達の豊かな発想を尊重する姿勢が感じられる。素材の相性や計画段階での確認を更に強化すれば、効率や完成度が向上する。 個々の子どもに対する配慮も細やかで、視覚的な環境作りや特別な支援が必要な子どもへの対応が素晴らしく、安心感を与えている。また、異年齢交流や縦割り保育にも積極的に取り組んでおり、今後はさらに年齢間の交流を深める工夫が求められる。 全体的に、子ども一人ひとりを大切にし、環境や活動に工夫を凝らす姿勢が評価される。今後は振り返りや計画段階での工夫を更に深め、個々の子どもに対するアプローチを一層丁寧に行うことが求められる。 |
|||||||
| 2 保育のあり方・園児への対応 | |||||||
| 自己評価 A ・健康面では、毎朝親子共検温にご協力いただいた。子どもの様子は直接保護者から聞き、体調の変化に注意して、子ども自身にも様子を聞きながら、帰りにも伝えられるようにした。 ・保育中も気になる場合は、すぐに検温したり、他の先生にも様子を見てもらい、状況によってすぐに連絡をして迎えに来てもらうようにした。 ・子どもがかかりやすい病気の症状など、季節によって流行もあるので、その時期のニュースなどからも情報を得たり、他の教員や保護者とも情報交換をした。個々によって配慮する体質などの症状もあるので、個別の一覧表を作り全体で共通認識をもつようにした。 ・うがい、手洗いを徹底したが、鼻水や咳症状の風邪が流行る時期もあった。 ・マスク着用は緩和される中で、園や個々の状況を見て、個別に着用をお願いするなどの対応もした。 ・食事中は仕切りを置いたり距離を保ちつつ、飛沫などに十分注意しながら、会話は楽しんだりと和やかな時間になるように心がけた。 ・給食業者と連携をとり、給食の食材で子どもが飲み込みにくい物は、誤嚥防止のために細かくしてもらうこともあった。また、保護者にも伝えて協力を求めた。食事中も十分配慮するように努めた。 ・安全面では、外あそび中の友だちや固定遊具との接触や、単独でも転倒をするなどの怪我があった。室内でも机や玩具に接触などして打撲などでの怪我があった。大きな怪我につながる前に声かけをしたり、環境構成にも配慮した。 ・部屋の移動でテラスを走ってしまう場面が多く見られ、出合頭にぶつかりそうになることがあったので、その都度注意してきたが、引き続き気を付けると共に、有効な環境構成などを考えたい。 ・怪我をした際には、まず子どもが安心できるように対応しながら、状況を把握するようにした。また、各保育室の救急セットを活用して、素早く対応するとともに、必要に応じて保護者に連絡して病院へ受診した。 ・怪我や病気などの対応の仕方が、教員によっては不安に感じるという声もある中で、今年度はAED講習に参加できたので、緊急時の対応を実践形式で学ぶことはとても良かった。 ・病気や怪我の様子を継続して確認することが時々不十分で保護者に正確に伝えられなかったこともあったので、教員間で連携をして共通認識ができるよう心がけた。 ・衛生面では、朝や放課後の清掃や、食物に触れる時など、消毒などの管理に配慮した。門や遊具、部屋のおもちゃなど多数の接触が考えられる所も、できるだけ消毒した。門の入り口には消毒液を用意した。 ・園庭や室内での環境構成などに十分に配慮し、日々安全面を確認したり、教員の死角に子どもが行かないように注意して柵を置いたり、一緒に行動するなどした。また、死角の箇所や、普段足を踏み入れない箇所も放置はせずに見通しを良くするなど、衛生面や防犯面を意識して対策をした。 ・園庭入り口の門の上部にも留め具を取り付けて、園児だけでは開閉ができないようにした。また裏口の出入り口の留め具も複数増やした。 ・避難訓練などは、活動にゆとりのある時期(特に二学期後半以降)や時間帯に集中してしまったが、園外の建物に避難する訓練も実施できた。日頃からもっと教員自身の自覚が必要だと思うので、いかなる時にも迅速に判断して子ども達を守れるようにしたい ・訓練の成果で、机の下にしっかり潜ったり、ライフジャケットを素早く着 用することができるようになっている。まずは子ども達自身が少しでも自分で身を守れるように訓練していきたい。 ・備蓄品や落下防止対策などは随時確認して、劣化している物を交換した。今後も定期的に確認していく。 ・子ども理解については、一人ひとりの性格を理解して、子どもによって指導の仕方を変えるようにした。言葉だけでなく、視覚からも意識して子どもが活動できるように工夫した。 ・女の子は特に大人っぽい所もあるが、まだコントロールが難しいので介入に仕方も難しかった。しかし色々な行事などを経て子ども達の様々な面を見ることで、どんな姿もその子であって成長の過程であるから、指導するというよりも一緒に考えたり向き合うという対応に徐々に変わった。 ・初めてのことをどのように説明したら分かりやすいのか、より子どものイメージを膨らませるためにはどのように援助したら良いのか考えてきた。 ・子どもの様子を見た時に、前後の行動の理解が必要であれば他の先生や本人、または他の子どもに聞いたり、日々の様子を振り返りながら関わるようにした。 ・家庭での様子や過ごし方を保護者に聞いたり、園での様子も伝えることでお互いに理解できることも多かった。園で聞けなかった子どもの気持ちを保護者から聞くこともあったので、今後も話すことを大切にしたい。 ・なかなか自分から言い出せない子には自分から言えるように励ましたり、逆に言い過ぎてしまう子には相手の気持ちも想像して考えるよう指導した。 ・一人ひとりと向き合うことについては、行事前など少なくなってしまったが、できるだけスキンシップを多くとり同じ目線であそんだり、見守るべき時はしっかり見守り援助することを心がけた。 ・関わる際に、言葉選びを意識したが、無意識にくだけ過ぎた言葉遣いになってしまうことなどあったので十分気をつけたい。 ・見えない所で活動している子どもにも声かけをして、教員が見守っていることは感じるようにして、子ども同士の関わり方に気をつけるようにした。 ・子ども同士のトラブルには、おもちゃの貸し借りやお互いの話し方など原因がいろいろあった。様々な場面で、教員が間に入り話し合うことで、両者の意見をしっかり聞いてお互いに納得できるように働きかけた。 ・年齢などにもよるが、なるべく自分で伝えられるようになってほしいと願い、教員が間には入るがその後は子ども達に任せるようにした。すると子ども達同士で解決している様子も多く見られて良かった。 ・時に保育活動に入ることを拒む子どもへの対応に悩むことがあった。担任一人では対応できない日も続いたりしたので、他の教員が対応するなどしながら、子どもにとって何が大切か、日々を楽しく過ごせるように配慮した。 ・外部の先生の助言を聞く機会もあり、それにより子ども達を多面的に捉えたり、保護者との情報共有がよりスムーズになり、先の見通しが立てやすくなった。 |
|||||||
| 学校評価委員 A 健康面では、毎日の検温や体調確認、保護者との連携をしっかり行い、季節ごとの病気や症状にも柔軟に対応している。うがいや手洗いの徹底、誤嚥防止策も実施し、子どもの健康を守るための配慮が行き届いている。安全面でも、遊具や室内の事故防止に努め、環境構成を見直している点が評価される。 緊急時対応については、AED講習を受け、迅速な対応ができるようになった。今後は、他の職員との協力体制を強化し、より効果的な緊急時対応を目指すべきである。 避難訓練や防災対策が進んでおり、子どもたちが身を守る方法を学んでいる点は非常に重要である。今後は、訓練をよりリアルなシミュレーション形式にして、さらに効果的な訓練を実施することが求められる。 子ども理解と指導方法については、個々の性格に応じた対応がなされており、子どもたちの成長を見守りながら一緒に考え、向き合っている。今後は、発達段階に応じた指導方法をさらに工夫し、子ども一人ひとりに最適なサポートを強化することが望まれる。 トラブル解決においては、子ども同士の意見をしっかり聞き、納得できる解決策を導く姿勢が評価される。今後は、子どもたち自身に感情を表現し、解決策を考える力を育むための工夫を増やすべきである。 全体として、健康・安全管理、緊急対応、子ども理解において高いレベルでの取り組みが見られる。今後は、職員間での情報共有をさらに強化し、安全管理やトラブル対応の改善を意識しながら、子どもたちの成長を支えていくことが求められる。 |
|||||||
| 3 教師としての資質・能力・良識・適正 | |||||||
| 自己評価 A ・研修会は、対面やオンラインで様々な分野の内容も学び、日々の保育を改めて考えることもできた。また子どもへの対応も見直す良い機会になった。 ・保育者として必要な知識や技能をある程度は身に着けているつもりでも、実践していないと忘れていたり劣ることもあるので、定期的な確認、実践の必要性を感じた。 ・幼稚園教諭として、マナーや言葉遣いなどに気をつけてきた。また、挨拶などを明るく元気に行うようにしたり、自分のクラスだけでなく、全園児やその保護者、未就園児親子などと積極的に関わるように心がけた。 ・「ありがとう」「どういたしまして」を当たり前に言うことができるように、常に自分自身が意識して言うようにして、子ども達にも浸透している。しかし、忙しくて教員間などで伝えそびれてしまうこともあったので、誰に対しても感謝の気持ちをしっかり伝えるようにしたい。 ・仕事の段取りでは、期限が決まっている仕事でも直前までかかったり、時間に追われることがあった。試作などが遅れてしまうことがあったので、先の見通しをしっかり立てるようにしたい。 ・一時預かりの子どもをその都度受け入れることで、今までにあまり無かった配慮点や問題点も出てきたので、次年度の生かしたい。 ・非常勤の先生もいる中で、仕事の分担、振り分けが上手くできないこともあったので、先を見通しながら限られた時間を有効に使えるようにしたい。 ・当番の仕事も含めて、自分にできることを進んで見つけて早めに取り組むように心がけた。また長年同じ方法で行ってきた様々なことも、更に改めて見直して取り組みやすくした。今後も折にふれて見直していきたい。 ・保護者や教員同士での連絡事項の伝達などを、忙しさで忘れてしまったり、内容が曖昧なままになることがあったので、すぐにメモを取ったり伝達したり、その日の内に振り返りをした。そこで未対応のことが見つかれば、すぐに対応して、伝達後の確認もしっかり行うようにした。 ・教員間の話し合いでは、情報交換、情報共有の場になるようにお互いの意見や考え、クラスの様子を伝え合うようにした。 ・他のクラスのこと、全体のことも把握できるように努力してきたが、忙しい時こそコミュニケーションをとることが大切だと実感した。非常勤の教員も含め、短時間でも積極的に話し合えるような環境づくりを更に心がけたい。 ・今年度も忙しさに時間に追われることが多かったが、早め早めに一つひとつの事案に向き合うようにすることで、新たに準備が必要でも余裕がもてるので、今後も心掛けたい。 |
|||||||
| 学校評価委員 A 研修会を通じて保育の実践や子どもへの対応を見直し、学びを日々の保育に生かしている点が評価される。知識や技能の定期的な確認と実践への意識があり、改善に向けて積極的に取り組んでいる姿勢が好ましい。マナーや言葉遣い、子どもとの関わりに意識を向け、「ありがとう」「どういたしまして」の言葉を浸透させる姿勢は教育者として模範的。しかし、情報伝達に遅れが生じることがあり、確実な連絡が求められる。段取りの遅れや時間に追われる場面もあり、先を見越した計画立案が必要。非常勤教員との連携や仕事の分担についても工夫が必要で、限られた時間の有効活用を意識した努力が求められる。教員間の円滑なコミュニケーションや情報共有の強化が今後重要で、さらに成長が期待される。 |
|||||||
| 4 保護者への対応 | |||||||
| 自己評価 B ・保護者とは、年間をとおして家庭や園の様子を伝え合うなどして、コミュニケーションを多くとるよう心がけた。 ・今年度も面談を5月に行い、家庭や園での子どもの細かな様子を伝え合った。普段は、登園時に時間のある際には日常の子どものことを些細なことでも話題にして話すようにした。登園時間によって話せることが少ない保護者もいるので、タイミングを見て話すようにした。 ・行事の時間や流れ、保育活動の内容などで把握できていないことがあったが、手紙の再確認や他の先生に聞くことで、保護者にも伝えられた。 ・教員の認識不足で、先に保護者に曖昧な内容を伝えてしまうこともあったので、しっかり確認してから伝えるように気をつける。 ・子どもの気になる点について保護者に家庭での様子を詳しく聞いたり、園としての考えを伝える時には、先々の成長、年齢も見据えながら時期を考えて行ってきた。一年をとおして子どものことをより深く理解し合う機会を作ることができた。 ・内容にもよるが、一学期になるべく情報共有しておければ、二学期以降によりスムーズに話ができると感じた。 ・今後も子ども一人ひとりの成長をサポートできるように、保護者の気持ちにも配慮しながら、相手の立場に立った言葉の表現で伝えられるように心がけたい。 ・今年度も年間をとおして、様々な保育活動が保護者のご協力のもと無事に行えて良かった。 ・保護者からの話は、必要に応じて教員間で共有することで、より多面的に捉え理解を深めるようにした。要望などに対してすぐに返答できないことは、園長先生に確認をして丁寧に対応するよう心がけた。 ・園からの手紙などでお知らせしたことも、配布から時間が空いたりすることで再度保護者から確認されることがあったので、活動の直前などにも門に掲示したり口頭で伝えて再確認するようにした。 ・今後も園から発信している様々な事柄について、在園の保護者はもちろん、他の保護者にもどのように伝わっているのか、もっと積極的に確認して改善点などを見つけて次年度に生かしたい。 |
|||||||
| 学校評価委員 A 保護者との積極的なコミュニケーションを通じて、情報交換を大切にしている点が評価される。面談や登園時に日常の様子をタイミングよく伝え、情報の正確さに配慮している。行事や要望への対応も適切で、今後は早期の情報共有が求められる。手紙やお知らせの配布においても再確認を徹底し、今後は情報がどのように伝わっているかを確認し、改善していくことが課題となる。総じて、保護者との信頼関係を築く姿勢が評価され、さらに深めていくことが期待される。 |
|||||||
| 5 地域の自然や社会とのかかわり | |||||||
自己評価 B ・今年度も感染症の配慮をしながらも、地域のお年寄りと交流をもったり、園の行事に様々な方々が参加してくださるという取り組みが多くできた。 ・小学校見学も実施できて子ども達もとても喜んでいて良かった。 ・未就園児親子の来園は、一年をとおして特定の方々の利用が多かった。 その都度の対応を充実させられるよう努力した。 ・普段から教員全員が未就園児の顔と名前を把握できるように情報を共有したり、積極的に声をかけたが、タイミングで難しい時もあった。未就園児と在園児の関わりは外あそびや体験保育、行事などでもつようにした。 ・ひよこ組の活動準備などは、今年度も一部の教員に任せがちだったので、全体でアイデアも出しながら取り組んでいきたい。 ・地域の方々には、園行事や園の環境整備のために協力していただくことは今年度もいろいろあり、とても感謝している。園としても、地域に協力できることを積極的に考えてもっと関わるようにしたい。 ・園外保育や降園時には、いろいろな場所で声を掛けていただくことも多かった。今年度は駅周辺への園外保育も実施できて、近隣の公園や香貫山へのお別れ遠足などでも関わることができた。 ・子ども達は、積極的に挨拶をする様子が見られるが、恥ずかしがったり、友だちとの話に夢中になってしまう子どももいるので、教員が率先して元気に挨拶ができるよう心がけた。 ・園外に行く際に、子ども達は様々なことに興味を持っているので、周りにある施設や自然について、自分自身がもう少し知識を持てたらと感じた。 ・引き続き、降園時や園外保育中の地震なども想定して、避難場所や避難方法などを確認するようにしたい。そして、地域の方とも、災害の時などにもスムーズに助け合うことができるような関係作りを心がけたい。 ・安全面では、徒歩で危険な場所など無いか日頃から気をつけて見るようにして、確認することや改善できそうなことは各関係機関と連携して行うようにしたい。 |
|||||||
| 学校評価委員 A 今年度は感染症対策を講じながら地域との交流を深める取り組みが進んだ。小学校見学や地域の高齢者との交流を通じて、子ども達の学びや喜びが得られた。未就園児との関わりを積極的に行い、情報共有を進めたが、タイミングによる課題もあった。 園外保育や挨拶の場面では、教員が積極的にリードし、子ども達の積極性を引き出したが、さらなる知識の充実が求められる。地域との連携も強化し、災害時の助け合いの関係づくりを進める姿勢が良い。安全面でも危険箇所を注意深く確認し、改善を進めている。今後も地域との連携を深め、子ども達の学びの充実と安全管理に努めていくことが期待される。 |
|||||||
* 結果の表示方法 A 十分達成されている B 達成されている C 取り組まれているが、成果が十分でない D 取り組みが不十分である |
Ⅳ 本年度の重点課題の総合的な評価結果 令和5年5月8日から、新型コロナウィルス感染症が感染症法上の5類に移行した。そうした中で、教員は保護者とも密に連絡を取り合い、良い保育ができるよう日々資質向上に努め、開園以来変わらぬ教育目標に基づき、園児一人ひとりの個性を尊重し、心の豊かさを育むよう努めることができていることを評価する。また、協調性と社会性の獲得により、保護者の信頼を得ることができていることを評価する。 平成22年6月に行った園庭の芝生化により、園児たちが園庭を思いっきり走り、転げ回れるようになり、大いに体を動かすことできるようになった。今後も環境整備に努め、園児たちの体力向上を促していただきたい。また、平成23年1月に園長が住職である乗運寺が取得した当園向いの土地(約100坪)を無償で借り受け、その土地を畑として利用し、季節ごとに園児たちと共に種々の野菜づくりに挑戦し、その結果、本年度も食育としての効果だけでなく、土に親しむことで、心身共に豊かな成長に寄与している。 平成26年2月に、県私学振興課と、防災の専門家である常葉大学の阿部郁男教授の指導によって、津波避難タワーの設置を中止し、津波避難場所を乗運寺の隣にある4階建ビルから、園の道路を挟んで斜め向かい側にある3階建て「齋藤保幸税理士事務所」へ変更した。今後も園児たちの避難がより迅速にできるよう、常に防災意識をもって避難訓練を行っていただきたい。また、地震や津波等の緊急時の避難誘導をスムーズに行うため、より一層、地域との協力体制を強化し、園児たちの安心安全を確保していく努力をつづけていただきたい 。 平成30年度は、ブロック塀及び園庭の記念碑(国旗掲揚台)の撤去、それに代わるフェンスの設置を行った。今後も園児たちの安心安全のため、環境整備に努めていただきたい。 平成31年度は、公益財団法人静岡県グリーンバンクの芝生管理活動支援事業費補助金を申請し、草刈り機や肥料などと共に、電動の芝刈り機を新たに1台購入し、合計2台での芝刈りが出来るようになり、より芝生の管理体制が充実したことを評価する。 令和2年度、3年度も同補助金により、芝刈用品等を購入したが、今後も芝生の管理を続けていってもらいたい。 本年度も、新型コロナウィルス感染症が全国的に広がり、静岡県でも感染者が多く出ていたが、教員一同が衛生管理に努め、園児たちにうがい手洗いの徹底などを指導し、卒業式の日を無事に迎えられたことはなによりであった。 令和2年度から、経常費補助金を受給する私学助成園から、施設型給付費を受給する幼稚園となった。それにより経営面で改善がみられたことを評価する。 令和3年度には、防災用品として、発電機等を購入した。今後も、ハード面とソフト面、両方で、災害につよい園となるよう努めていってもらいたい。 令和3〜5年度には、ICT補助金を活用し、ノートパソコンやタブレット等の購入をおこなった。これからも事務の効率化などに活かしてもらいたい。 令和5年度に、新たに安全特別対策事業費補助金を活用し、登降園に関するシステムのための機器を揃えた。来年度以降活用し、園務の改善に活かしてもらいたい。 令和6年2月5日に、約半世紀にわたって理事長・園長を務めてこられた林茂樹氏が逝去した。心からご冥福をお祈りするとともに、林茂樹園長が大切にしてきたものを守り、少子化の中であるが、創立100年を目指して頑張っていただきたい。 |
Ⅴ 今後取り組むべき課題 ○園児の獲得 具体的な取り組み方法 園児数の減少の原因について、通園バスを用いていないこと、そして地域全体の子育て世代の減少 であろうという意見があった。しかし、当園へ通園させている保護者は、徒歩通園を推奨して、 通園バスを用いていない当園の方針を高く評価してくれている。よって、バス運行に頼るのではなく、 今後も保育内容の充実や、未就園児への園の開放により、園児の獲得を目指していただきたい。 また、ポスターや掲示物、ホームページ、SNSを積極的に活用し、園児獲得に努力していただきたい。 ○災害時の対応 具体的な取り組み方法 地震や津波などの災害に備えて、平成24年度にライフジャケットと避難用のワゴンを購入した。 ライフジャケットを園児たちが自分で着けるられるように訓練しているが、年長、年中の園児に 関しては自分一人で装着ができるようになっている。今後も、訓練を重ねて、いざという時に 園児たちと自らを守れるよう努力していただきたい。 また、平成26年度から、津波避難場所をより素早く避難できるよう「齋藤保幸税理士事務所」 に変更した。 今後も緊急時に園児たちの安全が確保できるよう、教員一人ひとりが常に意識し、冷静に 避難誘導できるよう避難訓練を欠かさずに行っていただきたい。 令和3年度には、発電機等を購入した。今後もハード面、ソフト面で防災に取り組んでいただきたい。 ○新型コロナウィルス等の感染症への対応 具体的な取り組み方法 平成31年度末、中国で新型コロナウィルス感染症の発生が確認され、日本にもその感染が広がった。 幼稚園としては、消毒やうがい手洗いの徹底はもちろん、園内の衛生管理や園児たちの 健康管理に努めながら、保育を続けてきた。そして令和5年5月8日をもって、感染法上の分類が 季節性インフルエンザと同等の「5類」に移行した。引き続き園児たちの健康を見守りつつ、 安心安全の環境を提供しながら、園児たちにとってよりよい保育ができるよう努めていただきたい。 |
Ⅵ 学校関係者評価委員会からのコメント 園児の減少に関しての取り組みに今後も期待する。園の保育方針や内容に関しては内外から評価されており、 今後も同様の努力と向上心をもって取り組んでいただき、地域の発展にも寄与していただきたい。 「子育て支援」「預り保育」「障害児教育」が充実していることを高く評価する。 なお、6月5日の「世界環境デー」に毎年実施している「千本浜海岸の清掃」は、国土交通省から高い評価 を受け、平成15年に沼津河川国道事務所長から感謝状が授与され、平成19年には中部地方整備局長から感謝状 が授与された。 海岸美化愛護運動に寄与し、地域の社会奉仕活動として評価されたものであり、環境教育の推進と奉仕の 心を育む教育の一環としてぜひとも継続していただきたい。 平成22年6月に行った園庭の芝生化により、温度上昇の抑制やCO2の削減、砂埃の軽減等、環境面での 改善だけでなく、園児たちが園庭を思いっきり走り、転げ回れるようになり、大いに体を動かすことによる 体力の向上にも良い効果が期待できることも大いに評価できる。 また、園長が住職である乗運寺から平成23年1月より無償貸与された土地を利用しての野菜づくりは、 園児の健全な育成に大いに役立つものと高く評価する。 地震や津波などの災害に備えて避難訓練を繰り返し行い、教員はもちろん園児たちにも場面場面で臨機応変 に対応できるよう指導していただいている。また、平成24年度にライフジャケットを園児用として40個、 教員用として8個購入し、着脱訓練も行っている。加えて、歩くのが遅い子どもや怪我をしている子どもを 想定し、避難時の移動用としてワゴンを購入して実際に訓練にも使用していることを高く評価する。 近年、夏の気温上昇が大きくなっているため、園児たちの体調に悪影響が出ないよう、平成25年8月に エアコンを各教室に設置し、気温がある程度高くなってきた場合には、従来の扇風機と併用して使用し、 園児たちが熱射病にならないよう対応がなされている。また過度にエアコンを使用することで体温調節が できなくならないよう、教員が温度管理に気を付けていることを高く評価する。 平成26年2月に、県私学振興課の職員の方と、防災の専門家である常葉大学の阿部郁男教授に避難訓練の 様子を見ていただき、「ルンビニ幼稚園のある地域で想定される津波の最高浸水深は、海抜6mであり、 より短時間で高いところへ避難できることが重要である」との指導をうけ、平成26年度から、これまでの 乗運寺の隣にある4階建ビルへの避難から、園の道路を挟んで斜め向かい側にある3階建て「齋藤保幸税理士 事務所」への避難に変更された。今後も、園児たちの避難が迅速にできるよう、常に防災意識をもって 避難訓練を行っていただきたい。 平成26年度、新たに講堂正面の天井にレールをつけ、紺色の暗幕を設置したが、今後、音楽会だけでなく 各式典でも使用することで、行事の飾りつけや雰囲気づくりにも活用していただきたい。 平成28年度から、桃中軒の全面協力により、選択制の弁当給食を週3日から週5日とし、保護者に利用 しやすいよう努めていることを評価する。 平成28年度、各クラスの電子ピアノを一部新しくし、よりよい保育が出来るよう環境整備に努めている ことを評価する。 平成30年9月、国及び県からの指導により、ブロック塀と園庭の記念碑(国旗掲揚台)の撤去を行い、 併せて代わりのフェンスの設置を行った。今後も園児たちの安全を守るべく、環境整備に努めていって いただきたい。 平成31年度末から日本全国に広がった新型コロナウィルス感染症であるが、この感染症への対応は、 来年度以降も継続的に必要になるものと考えられる。国や県、市などとも協力しながら、補助金も活用し、 園児たちの安心安全のため、対策を講じていってもらいたい。 令和2年度から、ルンビニ幼稚園は子ども・子育て支援新制度における施設型給付を受ける幼稚園へ 移行した。制度上の分類はこれまでの私学助成園とは異なるが、変わらない教育理念や教育方針を理解して いただける家庭の子どもたちのために、本来あるべき幼児教育の充実発展に今後も努力していただきたい。 令和3年度には、災害時に備えて、発電機等を購入した。今後も防災用品の充実に努めてもらいたい。 令和3年〜5年と、県のICT化支援補助金を活用して、パソコンやタブレットを購入した。 園業務の効率化や、保護者との連絡、園の広報など、さまざまなことに利用していってもらいたい。 令和5年度に、新たに安全特別対策事業費補助金を活用し、登降園に関するシステムのための機器を 揃えた。来年度以降活用し、園務の改善に活かしてもらいたい。 令和6年2月5日に、約半世紀にわたって理事長・園長を務めてこられた林茂樹氏が逝去した。 心からご冥福をお祈りするとともに、林茂樹園長が大切にしてきたものを守り、少子化の中であるが、 創立100年を目指して頑張っていただきたい。 |