

| XPを使い易く快適に! |
WindowsXPからPCを使い始めた人は「こんなもの」と気にならないだろうが、それ以前のOSからXPに移った人にはLunaのテーマには違和感を感じた人も多いのではないだろうか、私の第一印象も「なんだこれ、使いにくい!」であった。
その上、動きも鈍い!同じPCにマルチブートでインストールしてあるWindows98SEの方が動作の歯切れも良く、慣れもあっただろうが格段に使い易く感じた。その結果、トラブルも無かったことからXPへの本格移行までにはかなりの時間を要した。
XP本格使用となったのは私の回りでXPユーザーが増えたこと、SP2導入と同時に手を加え動作の改善が出来たことであった。
長年使ってきた無印XPでは数多くのアップデートによる障害か?不都合な箇所も生じ始めていたことからリカバリーを実行して再設定した。その時の記録(全てではないが)を友人や家族向けに文書化し、これに画像も加え分かり易くしてみた。
なお、ここに記載した設定変更は私と私の家族の使用環境に合わせて行ったものの主要部分であり、全ての人に当てはまるものではない。
書かれていることを参考に設定変更し、不具合を生じても責任は取れないので自己責任での実行となるのは当然かと思う。
また、使用している画像も表示を軽くしたいことから一部を切り取って使用してるため分かりにくいかもしれないが操作手順文章の補助的なものと理解して欲しい。
設定の基本的な考えは、重く切れの悪いWindowsXPの動作改善とバックアップなどの管理を容易にするためのパーテーション分割とシステムとデータの分離である。
 |
「Luna」から「Classic」へ |
 |
| 1.[画面のプロパティ]からの設定変更 |
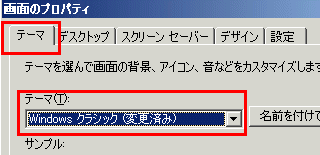 (図 1−1) |
[テーマ]タブ 「デスクトップ」を右クリックし表示されるメニューからプロパティをクリックすると「画面のプロパティ」のウインドが表示される。 「テーマ」を「Windowsクラシック」に変更する。(図 1-1) |
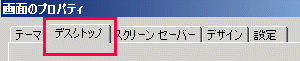 (図 1−2) |
[デスクトップ]タブ |
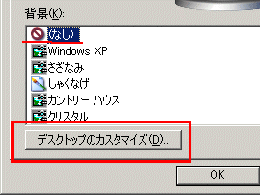 (図 1−3) |
「背景」を草原から(なし)に変更。 ※)壁紙(背景)使用も個人の自由だが、壁紙を読み込む分だけ起動に時間がかかるので私は使用していない。 「デスクトップのカスタマイズ(D)」ボタンをクリックすると(図 1-4)画面となる。 |
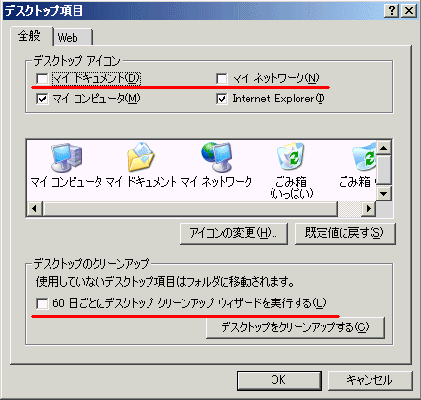 (図 1−4) |
|
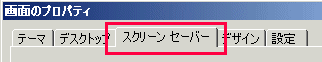 (図 1−5) |
[スクリーンセーバー]タブ |
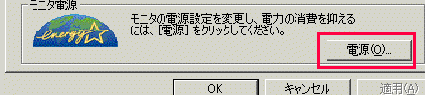 (図 1−6) |
「電源(O)」をクリック、「電源オプションのプロパティ(図 1-7)での設定となる。 ※)スクリーンセーバーについては、「(なし)」の方がパフォーマンス的には望ましいと言われているが、好みで設定すれば良いと思う。 |
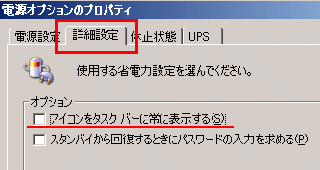 (図 1−7) |
「詳細設定」タブで「アイコンをタスクバーに常に表示する(S)」のチェックを外す。 ※)タスクトレイのアイコンも少ない方が良い。 |
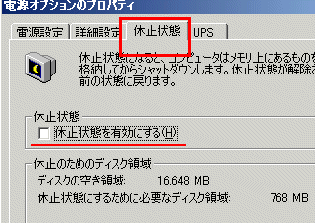 (図 1−8) |
「休止状態」タブでは、休止状態を使用しないのなら「休止状態を有効にする(H)」のチェックを外す。 チェックが入っていると%systemroot%にhiberfile.sysという名前の巨大なファイルが作られる。 ※)hiberfil.sysはハイバネーション用ファイルで、コンピュータが休止状態に移行する時にメモリの内容をファイルに保存するために使用されるファイル。(このPCの場合は768MBと表示されている) なお、このhiberfile.sysファイルはシステムファイルなのでフォルダオプションの設定によっては表示されない。(フォルダオプションでの設定参照) |
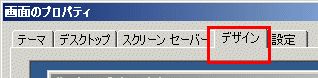 (図 1−9) |
[デザイン]タブ |
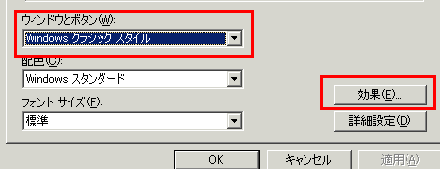 (図 1−10) |
「ウインドウとボタン(W)」を「Windowsクラシックスタイル」に変更。 「効果(E)」ボタンをクリック。(図 1-11画面となる) |
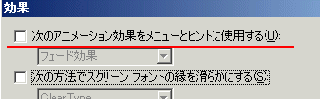 (図 1−11) |
「次のアニメーション効果をメニューとヒントに使用する(U)」のチェックを外す。 ※)[コントロールパネル]=>[システム]でアニメーション効果を無効にしても残っている項目である。 |
| 2.[タスクバーのプロパティ]からの設定変更 |
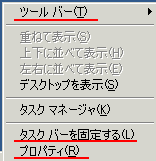 (図 2−1) |
「タスクバー」を右クリックすると左図(図 2-1)のようなメニューが表示される。 メニュー最下部の「プロパティ」をクリックして設定を行うのだが、「タスクバーを固定する(L)」のチェックはここで外しても良い。 最上部の「ツールバー」をクリックすれば(図 2-2)のメニューが表示されるので、ここで「クイック起動(Q)」にチェックを入れても良い。 |
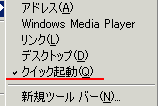 (図 2−2) |
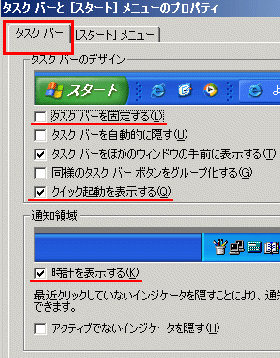 (図 2−3) |
メニュー最下部の「プロパティ」をクリック左図(図 2-3)のウインドが表示される。 「タスクバーを固定する(L)」のチェックを外し、「クイック起動を表示する(Q)」のチェックを入れる。 ※)(図 2-1)(図 2-2)でチェックを操作していれば上記操作は不要となる。 「時計を表示する(K)」にチェックを入れる。 ※)時計表示不要ならチェックも不要。 ※)Win9Xではタスクトレイ・アイコン一個でリソースを2%〜3%消費していた。XPではリソースの心配はないがパフォーマンスには影響するので少ない方が良いはず。 使い勝手とのかね合わせで、私は音量調整のスピーカー・アイコンと時計のみの表示としている。 |
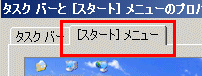 (図 2−4) |
[スタート]メニューのタブでは下側にある「クラシック[スタート]メニュー(M)」にチェックを入れ「カスタマイズ(C)」のボタンをクリックする。 表示されるウインドから好みに合わせて詳細オプション(図 2-6)のチェックを操作する。 |
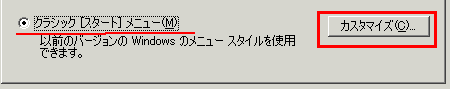 (図 2−5) |
|
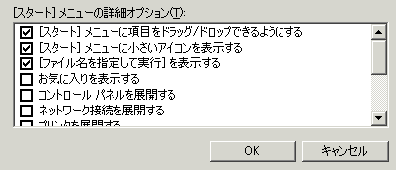 (図 2−6) |
![]()
タスクトレイ・アイコンについて。
タスクトレイにアイコンがあるということはプログラムが起動しているor働いているという印、必要もなく差し支えないならやはり削除する方が良いと思う。
削除にはプログラムの設定の違いから以下の四つの方法となる。
スキルに合わせて無理の無い範囲で削除しておくことが望ましい。
1.上記の「時計」や「電源」のように設定オプションやプロパティからアイコン表示のチェックを外せるもの。
2.プログラムのスタートアップに登録されているショートカットを削除するもの。
3.システム構成ユーティリティのスタートアップからチェックを外すもの。
4.Windowsサービスやレジストリの設定や記述の変更を要するもの。
| 3.[エクスプローラ&フォルダオプション]からの設定変更 |
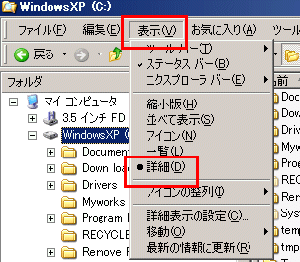 (図 3−1) |
エクスプローラを起動させツールバーの「表示(V)」より「詳細」にチェックを移す。 ※)「縮小版」など他の表示がよければ、好みの表示形式でかまわない。 |
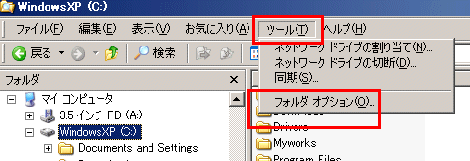 (図 3−2) |
ツールバーの「ツール(T)」より「フォルダオプション(O)」をクリックする。 |
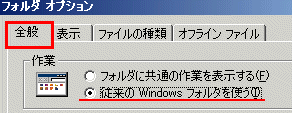 (図 3−3) |
フォルダオプションでは「全般」タブの「作業」で「従来の Windows フォルダを使う(I)」にチェックを入れる。 ※)これにより、コントロールパネルの表示も従来の表示スタイルに変更される。 |
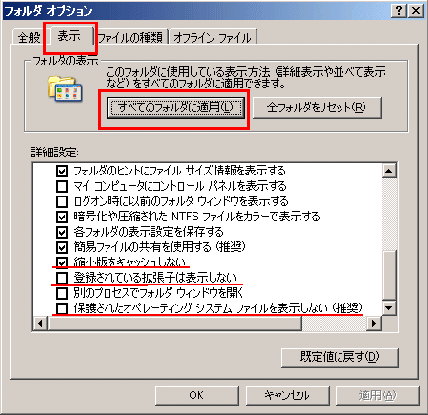 (図 3−4) |
フォルダオプションでは「表示」タブの詳細設定で以下の項目にチェックを入れる。 ・「すべてのファイルとフォルダを表示する」にチェックを入れる。 ・「登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外す。 ・「保護されたオペレーティングシステムファイルを表示しない(推奨)」のチェックを外す。 ・「縮小版をキャッシュしない」にチェックを入れる。 (サムネイル表示を高速化するためのキャッシュファイル(Thumbnail.db)を作成させないため。) 最後に「すべてのフォルダに適用」ボタンをクリックして「OK」で終了する。 ※)これは私の設定であり上記設定で絶対に削除してはいけないシステム・ファイルも表示されるようになるので自己責任で設定して欲しい。 |
| 4.[コントロールパネル]からの設定変更 |
 |
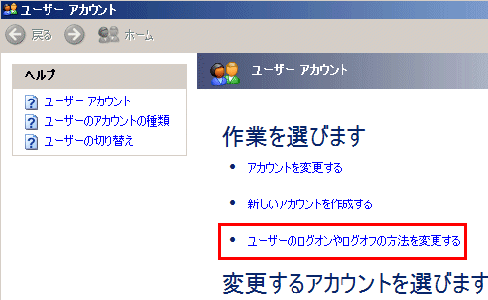 (図 4−1) |
「ユーザーのログオンやログオフの方法を変更する」をクリックする。 |
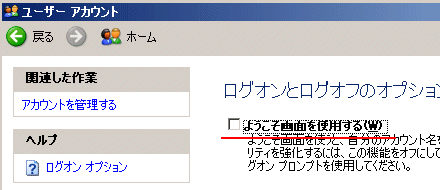 (図 4−2) |
「ようこそ画面を使用する(W)」のチェックを外すことで起動・終了時ダイアログもクラシックスタイルとなる。 起動時のパスワード入力が煩わしい人は後述の「窓の手」などのソフトを使用して自動ログオン設定にすると良い。 |
 |
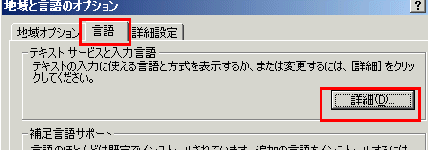 (図 4−3) |
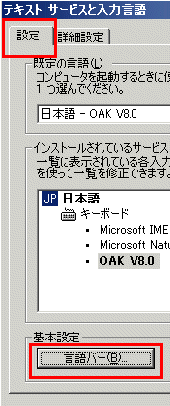 (図 4−4) |
「地域と言語のオプション」からは図の様に「言語」タブ =>「詳細(D)」=>「設定」タブ=>「言語バー(B)」と辿っていき「言語バーの設定」で(図
4-5)の様に「言語バーをデスクトップ上に表示する(D)」と「言語バーアイコンをタスクバーで表示する(A)」のチェックを外すとタスクトレイから言語アイコンが消える。 ※)このチェックを外すことで、使用しているIMEによっては使いにくくなることも予想されるので使用者の好みで設定変更すること。 (不都合が生じた時点でチェックを戻せば良いだけだが・・・) ちなみに、私が使用しているIME(OAK)では全く不都合が無い。 |
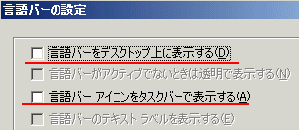 (図 4−5) |
 |
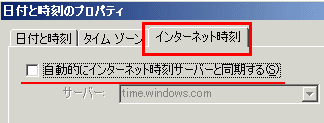 (図 4−6) |
「インターネット時刻」タブから「自動的にインターネット時刻と同期する(S)」のチェックを外す。 ※)同期設定が一週間に一度でもあり、フリーソフトの「AdjustClock」を使用し任意に起動させ時刻合わせしていることから私はチェックを外している。 |
 |
| 詳細設定 |
|
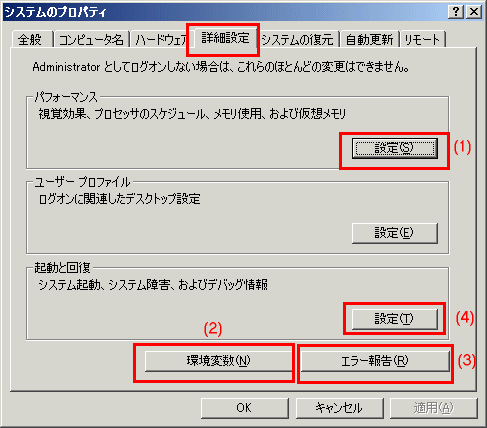 (図 4−7) |
「詳細設定」タブからは左図のように4ヶ所のボタンをクリックしてからの設定となる。 |
| (1)パフォーマンス・設定(S) |
|
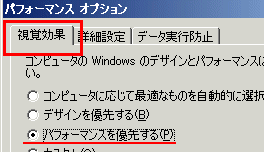 (図 4−8) |
「視覚効果」タブにて「パフォーマンスを優先する(P)」にチェックを入れる。 |
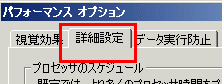 (図 4−9) |
「詳細設定」タブから、下にある「仮想メモリ」の「変更(C)」ボタンをクリックする。 |
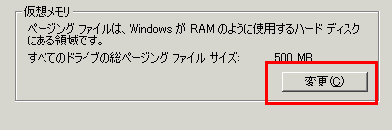 (図 4−10) |
仮想メモリのPagefile.sysはデフォルトではsyustemroot(通常はCドライブ)に置かれ、初期サイズが搭載メモリの1.5倍に設定されている。 サイズが可変だと最大サイズに設定されている値まで随時拡張されるためハードディスクの断片化が発生する。 搭載メモリ量が多ければ(1G以上)ペーシングファイルなしの設定でも良いといわれるが、私の場合は500MBに固定してTEMP専用ドライブの「E」に移してある。 私のPCの搭載メモリは768M、搭載メモリ量に比例したサイズが設定されるので、変更しなければ1150Mがペーシングファイルに使用される。 500MB設定の確たる根拠は無いのだが・・・、現状不具合は発生していない。 変更方法は設定変更したいドライブをフォーカスさせ「カスタムサイズ(C)」にチェックを入れ、初期サイズ・最大サイズの窓に変更したいサイズの数値を入力し「設定(S)」ボタンをクリックする。 削除したい場合はサイズに「0」を指定するだけである。 |
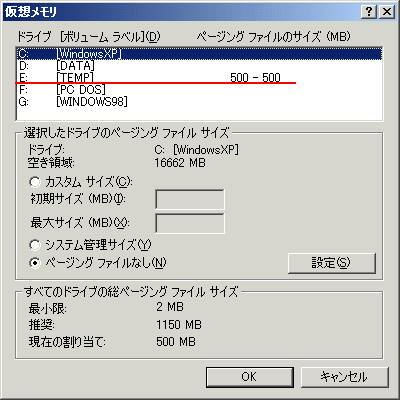 (図 4−11) |
| (2)環境変数(N) |
|
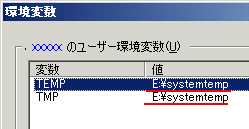 (図 4−12) |
「環境変数(N)」のボタンをクリックすると、「xxxxユーザーの環境変数(U)」の窓で設定変更が出来る。 この環境変数に指定されているTEMPフォルダは、通常はWindows\TEMPに置かれ圧縮ファイルの解凍やCDのコピーなどの作業領域となっていて時にはゴミファイルが数十MBも溜まっていることもある。 システムの入ったドライブに置きたくはないので、先のペーシングファイル同様にTEMP専用ドライブにフォルダを作って設定変更してある。 私は「窓の手」を用いてTEMPフォルダ内ファイルの自動削除設定を行っている。 |
| (3)エラー報告(R) |
|
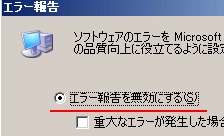 (図 4−13) |
「エラー報告(R)」ボタンをクリック、「エラー報告を無効にする(S)」にチェックを入れる。 |
| (4)起動と回復・設定(T) |
|
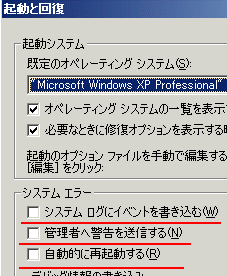 (図 4−14) |
「起動と回復」の「設定(T)」ボタンをクリックし、「システム エラー」の項目にある「システムログにイベントを書き込む(W)」、「管理者へ警告を送信する(N)」、「自動的に再起動する(R)」の三項目のチェックを外す。 なお、これらの項目にチェックを入れておくとペーシングファイルのサイズが2MB以上必要となる。 ペーシングファイルのサイズを0MBに設定する場合には要注意の項目である。 |
| システムの復元 |
|
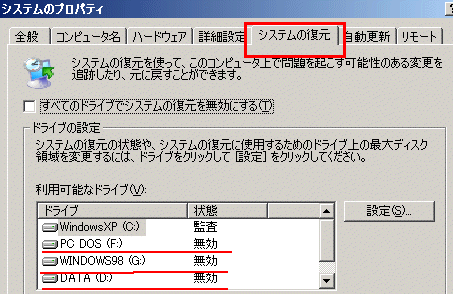 (図 4−15) |
デフォルトでは全てのドライブが監査対象となっている。 システムの復元では復元時にファイルの不整合が発生することもあり、完全な物ではないので、市販のバックアップソフトを利用している場合など「すべてのドライブでシステムの復元を無効にす(T)」にチェックを入れシステムの復元を停止しても良い。 また、停止しない場合はシステムとは関係ないドライブまで監査対象になっているので、不必要なドライブの監査を無効にしても良い。 システムの復元で使用される領域は最大各ドライブ容量の12%が設定されているので、ドライブ 容量によっては減らしても良い。 設定変更は、「利用可能ドライブ(V)」の窓から変更したいドライブをフォーカスして「設定(S)」ボタンをクリック、表示されるウインドから「このドライブのシステムの復元機能を無効にする(T)」にチェックを入れる。または「使用するディスク領域(D)」でスライダーを動かしてサイズを変更する。 |
| リモート |
|
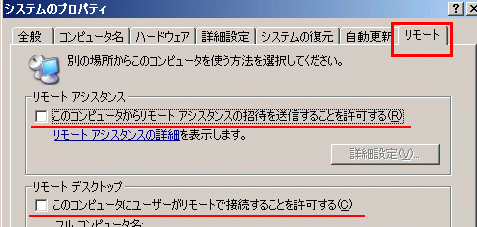 (図 4−16) |
「リモートアシスタント」、「リモートデスクトップ」の機能を使わないならチェックを外しておく。 |
 |
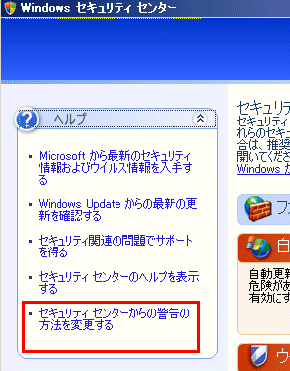 (図 4−17) |
ここでの設定はユーザーの使用環境や考え方で違いが大きいしセキュリティにも関わるので参考としてもらいたい。 「ヘルプ」欄の「セキュリティセンターからの警告の方法を変更する」をクリックすると下図(図 4-18)画面が表示される。 |
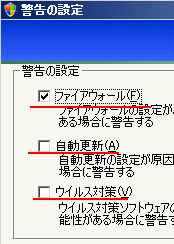 (図 4−18) |
私の場合警告が煩わしいので、「ファイアーウォール(F)」のみチェックを残してある。 Windows UpdateではUpdateによる不具合も数多く経験していることから、内容を確認して適用したいので「自動更新」も外してある。 |
| 5.その他の設定変更 |
| ワトソン博士の解雇? | |
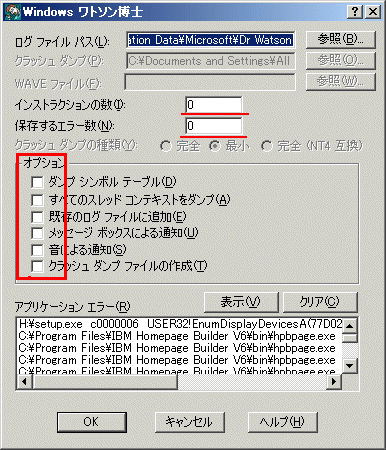 (図 5−1) |
[スタート]=>「ファイル名を指定して実行(R)」から「drwtsn32」と入力し「OK」をクリックすると左図のような「ワトソン博士」のウインドが表示される。 「ワトソン博士」が何者かと調べると「システムとプログラム の障害を検出し、ログファイルにその情報を記録します。」ということであった。 私はエラー情報をログに残されても対処出来ないのでワトソン博士は解雇することにした。 「ワトソン博士」の解雇方法は左図のように「インストラクションの数(T)」と「保存するエラー数(N)」を「0」に、オプションののチェックは全て外す。 こんな博士がPCの中に住んでいることを知らない人も多いのではとも思われる。 |
| 6.不要Windowsサービスの停止 |
※設定変更は「コントロールパネル」=>「管理ツール」=>「サービス」or
「マイコンピュータ」右クリック=>「管理」=>「コンピュータの管理」=>「サービスとアプリケーション」=>「サービス」より、項目をWクリックor右クリック=>プロパティで行う。
・WindowsXPのテーマ(ルナ) : Themes
スタートアップ:自動 状態:開始 => スタートアップ:無効 状態:停止
※クラシックスタイルに変更してもサービスは働いているので無効にする。
・エラー報告 : Error Repporting Service
スタートアップ:自動 状態:開始 => スタートアップ:無効 状態:停止
・リモートデスクトップ(使用しないなら): Terminal Service
スタートアップ:手動 状態:開始 => スタートアップ:無効 状態:停止
・リモートからのレジストリ編集 : Remote Registry
スタートアップ:自動 状態:開始 => スタートアップ:無効 状態:停止
・ユーザーの切り替え(使わないなら) : Fast User Switching Compatibility
スタートアップ:手動 状態:開始 => スタートアップ:無効 状態:停止
(SP1では自動)
・分岐リンクトラッキングの実現(ドメイン参加では必要) : Distributed Link Tracking Client
スタートアップ:自動 状態:開始 => スタートアップ:無効 状態:停止
・インターネット時刻 : Windows Tiome
スタートアップ:自動 状態:開始 => スタートアップ:無効 状態:停止
※コントロールパネル=>[日付と時刻]から「インターネット時刻」から自動的にインターネット
時刻と同期する」のチェックを外している場合。
・無線LANの自動構成機能 : Wireless Zero Configuration
スタートアップ:自動 状態:開始 => スタートアップ:無効 状態:停止
※無線LAN機能がないor使わない場合。
| 7.「窓の手2004」、「Tweak UI」を使っての設定変更 |
・自動ログオン
「窓の手」:[ログオン(1)]で「自動ログオンする」にチェックを入れる。
※「ログオフしても強制的に自動ログオン」にもチェックを入れる。
「Tweak UI」: [ログオン]=>「自動ログオン」で「自動的にログオン」にチェックを入れる。
・Tempファイルの削除
「窓の手」:[ログオン(2)]で「ログオン時にTempフォルダ内を削除」にチェックを入れる。
※「ログオン時に以下の履歴を削除する」より「最近使ったファイル」にチェック。
・[スタート]メニューのカスタマイズ
「窓の手」:[スタートパネル]で「スタートメニュー項目を使用不可(隠す)にする」より「ヘルプ
とサポート」にチェックを入れる。
「Tweak UI」: [エクスプローラ]で「[スタート]メニューに最近使ったファイルを表示する」のチ
ェックを外す。
「窓の手」からの設定変更
「窓の手」:「パフォーマンス」
メモリー関連
「カーネルを常に物理メモリー上に配置」にチェックを入れる。
「ファイルキャッシュサイズ」==>64MBに設定。
「窓の手」:「システム」
「起動時にNumLockをオンにする」にチェックを入れる。==>通常はBIOSでON設定となっているが・・
「窓の手」:「自動実行」
不要な自動実行プログラムは削除しておく。
「窓の手」:「デスクトップ」
「ごみ箱アイコンを隠す」にチェックを入れる。
「窓の手」:「エクスプローラ」
「マイコンピュータから共有ドキュメントを隠す」にチェックを入れる。
==>「Tweak UI」の同操作は
「マイコンピュータ」
「このコンピュータに保存されているファイル」のチェックを外す。
「窓の手」:「ウインドウ」
コモンダイアログのプレスバーの設定を各ドライブとした。
「最少化時のアニメーションをやめる」にチェックを入れる。
「Tweak UI」での同操作:「ダイアログボックス」=>「カスタムプレスバー」
「Tweak UI」を使っての設定変更
「エクスプローラ」
=>「ショートカット」
ショートカット・アイコンの矢印を「なし」にチェック。
「[スタート]メニューに最近使ったファイルを表示する」のチェックを外す。
「マイコンピュータ」==>「特別なフォルダ」で
「お気に入り」と「マイドキュメント」のドライブ変更。
「共有ドキュメント」のフォルダアイコンの削除=>
「マイコンピュータ」の「このコンピュータに保存されているファイル」のチェックを外す。
| 8.XPの高速化にお薦めのフリーソフト |
[TuneXP]
アクセスの早いHDDディスクの外周にシステムファイルを移し、さらにデフラグを実行するこ とでWindowsXPの起動時間を短縮するソフト。日本語化ソフトも入手可
[PageDefreg v2.3]
Windows標準のディスクデフラグでは解消できないレジストリやページングファイルの断片化を
解消し、最適化するソフト。
デフラグなどの日常的なメンテを加えていけば起動時間に変化は少ない。
しかし、終了時間は・・・私の同一メーカーでスペックもほぼ同程度の2台のPCにおいても常時使用しているPCでは遅くなっていく。
起動時の10秒の違いはストレスにはならないが、即終わりたい終了時となるとかなりのストレスとなる。
高速シャットダウン対策としていろいろ探した結果、以下の方法で効果があった。
現在でも6秒程度でシャットダウン出来ている。
私の行った高速シャットダウン対策。
1.レジストリーの整理。
[EasyCleaner] DL・インストール・実行 158個のレジストリー削除、.[NTREGOPT]
DL・インストール・実行 レジストリーの最適化を実行。
2.MSサイトより [User Profile Hive Cleanup Service] をDL、インストール。
上記対策後4ヶ月を経過するがシャットダウン時の時間に変化は無く快適に使用出来ている。
上記ソフトの入手先URLを記載しておくが、使用はあくまでも自己責任で願います。
[TuneXP]
http://cowscorpion.com/system/tunexp.html
[PageDefreg v2.3]
http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/utilities/PageDefrag.mspx
[EasyCleaner]
http://cowscorpion.com/Cleaner/easycleaner.html
.[NTREGOPT]
http://www.altech-ads.com/product/10001071.htm
[User Profile Hive Cleanup Service]
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1B286E6D-8912-4E18-B570-42470E2F3582&displaylang=ja
| 9.システムとデータ分離 |
Cドライブの容量節約&システムとデータの分離でバックアップを効率的に
私の使用法は原則C・D・Eの三分割(小容量HDDの場合は2分割)。
CドライブはOSとアプリのみで容量は10GBに設定、必要なアプリもインストールしているが使用領域は約4.5GBで済んでいる。
Dドライブはデータ、C・Eに割り振った容量の残り全てを設定している。
Eドライブは一時ファイル用ドライブ。インターネット一時ファイルや仮想メモリのPagefile.sysはこのドライブに設定変更してある。CD/DVDライテイング・ソフトの作業フォルダの設定もこのドライブにしてあることから容量は10GB程度を設定してある。
幾らドライブを分割しデータを分離しても「HDDがクラッシュすれば同じこと」と言う人もいるがバックアップやその管理も容易になると思っている。
デフォルトで%Systemroot% に置かれる主なデータ及び容量消費ファイル類には以下の物がある。
1.システム復元用のデータ
2.マイドキュメント
3.インターネット一時ファイル
4.お気に入りデータ
5.メールデータ
6.アドレス帳
7.仮想メモリのPagefile.sys
8.作業用一時ファイル(フォルダ)
「1.」はシステムの一部として扱い、残りは他のドライブに移動させる。
プロパティなどの設定で他のドライブに移せるもの。
・マイドキュメント
[設定方法]
[マイドキュメント]を右クリック=>プロパティ=>ターゲットフォルダの場所=>移動、から他のドライブに指定。
or Tweak UI の特別のフォルダで移動。
・インターネット一時ファイル
[設定方法]
ツール=>インターネットオプション=>全般タグ=>インターネット一時ファイル・設定、から他のドライブに指定。
・メールデータ
[設定方法]
ツール=>オプション=>メンテナンスタグ=>保存フォルダ、から他のドライブに指定。
・仮想メモリのPagefile.sys
[コントロールパネル]=>[システム]=>[詳細設定]から「パフォーマンス・設定」=>「詳細設定・仮想メモリ・変更」から他のドライブに変更。
・作業用一時ファイル(フォルダ)
[コントロールパネル]=>[システム]=>「詳細設定・環境変数」からxxxxユーザーの環境変数のフォルダを変更。(xxxxは登録ユーザー名)
「窓の手」の「ログオン(2)」より「ログオン時にTempフォルダ内を削除」にチェックを入れておく。(自動削除)
ソフトorレジストリの書き換えで他のドライブに移動可能なもの。
・お気に入りデータ
「Tweak UI」の「マイコンピュータ・特別なフォルダ」=>「場所の変更」で設定可能。
レジストリでの変更は。
「HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders」を開き、右フレームにある「Favorite」と言う文字列をダブル クリックして、データの値に移動先の「お気に入り」のフルパスを入力。
・アドレス帳の保存先
レジストリで変更。
「HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\WAB4\Wab File Name」を開き、右フレームにある「(既定)」と言う文字列をダブル クリックして、データの値に移動先のアドレス帳のフルパスを入力。
| 10.バックアップ方法他 |
OSのバックアップ
Cドライブのバックアップは専用ソフトを使用している。
現在、私の使用しているソフトはAcronis True Image 8.0。マルチブートのWindows98SEでも使え、なかなか具合が良いものと感じている。
ドライブのバックアップ・イメージをDドライブに作成・保存、同時にDVD−RWにも焼いている。
(2〜3回前の物まで保存し、古いイメージは削除してメディアは再使用)
データのバックアップ
データは容量が大きくなるので光学系のメディアでは枚数も多くなり管理も大変となる。やはりHDDのバックアップはHDDへとなる。
過去の経験からPCは故障するものという考えで常に予備システム用PCを設けているので、LAN接続されている予備PCのHDDへミラーリング・ツール(フリーソフト)で同期させている。
RAIDも良いが、この方法なら古いPCも活用出来るしHDDクラッシュ以外のPC故障にも対応出来る。
機器
PCを長年使用していてHDD交換などで余分なHDDを保有しているならばIDE=>USB変換アダプタは持っていても良い物と思う。(HomeNews16
「USB接続リムーバブル・ディスク」で紹介)
2,000円前後の価格で購入出来るし、2.5インチと3.5インチの両方のHDDに対応している。
私のPCは古く性能も悪いのだが、ここに書いた設定を実行したことで起動・終了も早くなり動作の歯切れも改善され快適に使用出来ている。
起動時間はHDD・CDDを交換することで改善されることもある。
HDDは回転数、CDDは古いものだとUDMAのモードが低く起動の足を引っ張り遅くする。他にはグラフィック・カードでも違いが出た。
ネットで見るとXPは全体的なトラブルは少ないが起動不可となって困ることが多いようだ。原因がはっきりしていれば回復コンソールで修復可能だが原因不明となるとリカバリーしか方法は無い(修復セットアップもあるが)。HDDクラッシュ後にデータが・・・といった人も相変わらずいるようで、バックアップだけは常に心がけておきたい。