 |
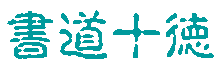 |
 |
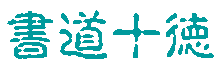 |
其の1 「心を豊かにし、人格を陶冶(とうや)する」
古来、「書は人なり」といいならわされている。
また、「字に久徳有り」という言葉もある。
書かれた文字には、その人の性格や雰囲気が如実に表されるものだと言う。
先人たちが残した歴史や文化は尊い・・・
文字や書の心を真摯に学ぶことにはじまり、創作技術や人格を自然に育んできた。
書道は、実用性に富む一方、精神の深さ、美しさを表す造形芸術である。
「読み・書き・パソコン」の今こそ、心ときめく書道の魅力を多くの人と分かち合いたい・・・。
こんな思いから書道の十徳なるものを考え、想像する。
其の2 「主役・脇役・湧かせ役、ハレの場面を引立てる」
「茶の湯の茶室で“掛物(茶掛け)ほど第1の道具はなし・・・」”は、千利休の語録「南坊録」にある言葉である。
茶室で欠かせないのが、*亭主の心を表すと言われる床の間の掛け軸である。
家庭やオフィス、オフィシャルの場面に飾られた書面は、その環境・空間に美しさをもたらし、人に安らぎや感動を与える。
ところで<ハレ(晴れ)>とは、特別に改まった日・華やかな場面をいい、普段・日常を<ケ(褒)>という。いずれも社会・生活の場を幅広く含めたい。
書は、あるときは主役、又あるときは脇役・湧かせ役として活きる、不易の日本文化である。
*ここでは、お茶会の主催者をさす。
其の3 「能筆は一生の宝、教養度の物指しとなる」
文化功労者で書家・成瀬映山先生が「書作のみちくさ」の中で、「作品にはその人の知識や趣味、愛好しているものが反映される」と語っている。書を学ぶものとして教養の裏打ちの大切さを思う。
かつて中国の科挙試験には書法(書道)があったように、また、日本の武家社会に祐筆が置かれていたことからも、書は教養度を計る一つの物差しとして重視され、能筆は尊ばれてきた。
パソコン全盛時代の今日でも、ビジネスやプライベートの場面で手書きは受け入れられている。希少価値の高い能筆は、「七難を隠す」一生の宝となる。
其の4 「実用性と芸術性、不易の魅力を育む」
其の5 「脳を鍛え、創作の楽しみ、夢とロマンが広がる」
其の6 「礼儀作法を高め、精神力を涵養する」
其の7 「歴史や文化への造詣(ぞうけい)、知識が深まる」
其の8 「嗜(たしな)むほどに奥深く、生涯の友となる」
其の9 「道を志すに年齢なし、経験は力となる」
其の10 「技(ぎ)は人を凛(りん)とさせ、芸は身を助く」
|
by.山中俊樹
(書道研究「青象会」会員、日本書道教育協会事務局長、静岡県中小企業研究会会員、NPO「SOHO・アット・しずおか」会員、静岡県教育委員会男女共同参画アドバイザー)
|