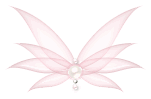
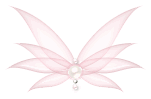
ゴールデンボウル
物語の始めに…
周の隣の部屋に越してきた瞳、彼女がいつ越してきたか?
たぶん佐倉の家を出てすぐは、友人の所にでも身を寄せたのだろう。
で、千秋にあった時はまだ友人の所で、この後何処に住もうかと考えていた時期で、
(周のマンション高そうだし賞金があっても今後の事考えるとね〜まず住めないよね。
それに隣が空いていた偶然とか元の家の目の前とかいろいろ問題はあるけど、それは余所においといて…)
彼が恋愛感情があるといってくれていたが、一美と別れると言ったわけでもないしなぁ…ただ、周の性格から浮気は出来ない事知ってたし、側にいたいとは思ったよね、きっと。
で、あのボーリング対決の前辺りには周の部屋の隣に越してきた事になるのかな?
その後社長の葬儀とかあって、日曜日の朝にでも、あのベランダでああいった会話が生まれるわけだけど、ちょっと時間の経過を見ると苦しいか…(笑)
でもその辺はお話ですから、あまり深く考えると面白くないし、適当に流しましょう♪
と言うことでベランダでのキスからの続きです。
「キス上手いよね」
「そう?」
「あの時もそう思った」
「どの時?」
「忘れたの〜?、貴方がうなされたフリして私に迫った時」
「ああ、あの時」
「あの時はもう好きだった?私のこと」
「どうかなぁ…、目の前に貴方がいて、唇があって、キスしたかった…」
「まあ、正直な事」
瞳は周の視線を避けて青空を見上げた。
「いったいどこで練習したの?」
「練習なんかしないよ」
「嘘、相手だっていたし」
「…」
周は青空を見上げたままの瞳の腕を取った。
「このうさたんが、こんなにヤキモチ焼きだとは知らなかったよ、はぁ〜…貴方だって相手がいたでしょう…」
「私はちゃんと…」
瞳の口はとんがったまま、次の言葉を言おうかどうか考えていた。
「ちゃんと…?」
そこへ周が瞳の口まねして言ったものだから、瞳はいよいよムッとしてる。
周の口もとんがったままだ。
「私はちゃんと寝室の鍵閉めたままだったわよ」
「じゃ、キスは?」
「えっ!」
間髪入れない周の声に瞳の声は裏返った。
「僕のキスが上手いって事は、誰かと比べたからでしょう?違う?」
周はニヤニヤして言った。
「そ、それは…」
「ね、僕たちはおあいこだ。だからこの話はもうしない。僕だって帰ってきた一美にはキスしかしてない…」
「ホント?」
「ホント」
「ウソ〜ォ…、そんな事信じられない!貴方だって健康な男だし、あんなに待ちこがれた彼女が帰って来たのよ。それがキスだけなんて。それに貴方が良くても向こうはそうじゃないでしょう!」
「女性にも性欲があるって事?」
周は何処までもどこ吹く風ってスタンスを崩さない。
「そ、そうよ!」
「じゃあ、貴方にもあるわけだ」
「ど〜してそう話をそっちに持ってくのぉ…」
「だって、うさたんが気にするからさ。じゃあ、今晩行こうか、僕?」
「誰が!、貴方なんか…もう、いいわ、フン!」
瞳はそう言うとさっさと部屋の中に入っていった。
残された周は苦笑いをして、「ゴールデンボウルにでも行くかな…」と小声で呟くのだった。
ゴールデンボウルに行くと、黒田のいたバーカウンターが外された跡に置かれたゲーム機に数人の女の子が群がっていた。
それをフロントの竹上が嬉しそうに眺めている。
「どしたの竹さん、あれ?」
「芥川さん、僕にも分からないっすよ」
「俺が入れたゲーム機の選択がよかったのさ」
どこから現れたのか、辺見は芥川のすぐ後ろに立っていた。
新しく社長になった辺見は相変わらずスーツに身を固めた格好で、地上げ屋の頃と少しも変わらない風貌だ。
それを見た竹上は一瞬顔をしかめてから、猫なで声を出した。
「社長〜、ここはいいですからどうぞ上にいて下さい。柴原もいますから、人は足りてます。な、柴!」
急に話を向けられた柴原は、一瞬目をしばたかせた後、竹上に肘でこづかれながら急いで話を合わせた。
「そ、そ、そ、そうです。大丈夫です」
心と裏腹に、二人の顔は満面の笑顔だった。
「上にいてもよ〜、やることがにゃいんだよ…」
「じゃどうです。僕と対決でもします」
周は竹上と柴原にウインクをしながらそう言った。
「どうですか、慣れました社長業?」
「いやいやなかなかね〜、ま、親父の遺言だし、俺がガキだった頃に繁盛してたようにこのゴールデンボウルを賑やかにしたいよ、スターも出来たことだしさ…」
「あの〜、それってもしかして僕の事?」
辺見はストライクを取ったにこやかな顔で頷いた。
「ですよね〜ハハ」周はため息を漏らす。
そう言えば、留守電に雑誌社からの取材の依頼が入っていた。
寝ぼけ眼で夢のように聞こえはしたが、いや面倒なので夢であって欲しかったのだが、それは紛れもない事実だった。
「どうした、青年、調子悪いな〜、この調子なら俺の勝ちだにゃ〜♪」
辺見は勝っているので、機嫌がいい。
芥川はどうやら朝の瞳との一件といい、今日はついてないらしい。
スコアが全てを物語っていた。
「あの〜、芥川さんですか?」
可愛らしい声に振り向くと、そこには先程までゲームに興じていたあの若い女の子たちが、目を輝かせて立っていた。
「は、はい、そうですが…」
「きゃ〜、やっぱりカッコイイ〜〜!!、私達近くの高校に通ってるんですけど、TV放送見てからどうしても会いたくて、今日は集まって 来て見たんです〜!
ね、どんなスプリットでも取っちゃえるし、ストライクもバンバン出せるんでしょ?見せて下さいよ〜、あ〜あの金色のボールで投げる所もいいなぁ…」
女子高生たちは、当の本人の芥川そっちのけで大いに盛り上がっている。
「コーチとかしてもらってもいいですか?」
女の子達の中で一番可愛い子が、キーキャーしてる友人達の輪から抜け出して芥川を上目遣いで見上げた。
「あ、うん、じゃあ、このゲームが終わってからならちょっとだけ…」
芥川は辺見の顔を見ながら答えた。
「さ、じゃあ、あそこに行ってシューズとボールを選んでもらって来て」
辺見の声に促されて、女子高生は足取り軽くフロントに向う。
「あ、由梨〜!抜け駆けして〜〜、ホントもう、いつだってそうなんだから…」
事の成り行きを見守っていた数人も由梨に続く。
これじゃあ何人に教えなきゃならないのか?
芥川は両手を胸の前で開いて見せ、苦笑する辺見にお手上げのポーズをした。
「あの〜何処に立てばいいんですか〜?」
「あ〜こんなに残っちゃった…これってどうやって取るんですか〜?」
「あん、このボウル重い〜!、腕が折れそう〜!!」
女子高生達は遠慮がない。
些細な事でも芥川を呼ぶ。
特に由梨は積極的だった。
質問の最後に必ず上目遣いで芥川を見るのだった。
日曜日の朝そうそうから周とケンカした瞳はマンションの部屋でブツブツ言っていた。
「なによ、どうしてあれから隣は静かなの?あったまきちゃう!どっか行ったのかしら?…きっとゴールデンボウルね。どーしてあたしを誘わないのよ!」
瞳は今ケンカした事を忘れたらしい…。
「私も行ってみようかな?」
しばらく頭を冷やした瞳はそう言って部屋を出た。
「竹さん、今日も暑いわね〜」
瞳はそう言いながらフロントでいつものように鍵をもらった。
でも竹上の注意はここにあらずのようで、レーンの方ばかり見ている。
その視線を瞳が追う。
「何あれ?」
瞳は周が沢山のキャピキャピギャルに囲まれ鼻を延ばしてる姿を見て、下がった血圧がまた上がったようだった。
「芥川先〜生〜!」
あちこちからこう呼ばれるのも悪くない。
瞳に相手にされなかった分、周はここで気持ちを盛り上げていた。
「あんなに評判がいいなら、青年にスクールの講師のバイトでも頼むかな…」
いつの間にか瞳の横に立っていた辺見が、まんざらでもない様子で思案顔してる。
苦虫つぶしたような顔してるのは瞳だけだった。
「フン、なにさ、若きゃいいってもんでもないのよ。テクニックは私の方が上よ…」
「そうよね、元人妻だったんですもの…」
「は?」
瞳が声の方を振り向くと千秋が立っていた。
「千秋さん、何言ってんの?私が言ってるのはボーリングの事よ」
「あら、そうなの?あたしはまたてっきり…」
「え、てっきりってじゃあ、何?」
今度は晶の声がした。
「え、そりゃテクニックって言えばアレよアレ」
「千秋さん!」
どっかトーンの違う声が混じったと思ったら、柴原が血相を変えて走って来た。
「千秋さん、晶さんに変な知恵つけないで下さい。そんな事に興味持ったら僕はどうすればいいんですか!」
「いいんじゃない、バリエーションにとんでて…これから飽きないわよ」
邪魔ばかり入る会話に嫌気がさした瞳は、事なしげに答えた。
「やっぱり瞳さん、あっちの事だったのね…」
そう嬉しそうに答える千秋はどこまでも天然だ。
「バリエーションで飽きないの?柴原は知ってんだ、今度教えてよ〜!」
晶の無邪気さは時として罪である。
柴原は耳まで真っ赤になって、しどろもどろになってしまった。
そう千秋と晶と柴原がキャーキャー騒ぐのを尻目に、瞳の視線は矢のように芥川に注がれている。
「先生?どうかしたんですか?」
「え、いや、ちょっと今、寒気が…」
「風邪ですか?あ〜じゃあ、今度看病してあげる〜」
最近の高校生は大胆極まりない。
このままじゃあ、マンションの住所さえ聞きかねない勢いだ。
「大丈夫、これでも丈夫なんだ…このくらい何でもない…」
そう言って振り向いた周は寒気の元を発見した。
「うっ…、やっぱ、何でもなくない…」
そーっと回れ右で元に戻った周は、この先の展開を思って涙が出そうだった。
「僕はこれから用事があるからね、ささ、君たちもまたにしよう…」
「え〜これからどっかに遊びに行こう!ね、せんせ」
「そんな事出来ないよ〜またね、あ、また今度来たらコーチしてあげるからさ、それでね勘弁して」
「な〜んだ、つまんないの。せんせ、これからデートなの?」
「いいや、それはないと思う」
「あら、けっこう寂しい生活なのね」
「そうなんだよ…」
高校生達はちゃかしている風だが、周の反応は思ったより深刻だった。
そしてその賑やかさが消えると周は疲れ切った表情でカウンターに鍵を返しに向かった。
「芥川さんもう帰るの?」
「ああ、竹さん、うん今日は帰る。あの〜それで、さっきまでここいたあの人はどこに行ったか知ってる」
「あの人?って誰すっか…」
「竹さん、相変わらず鈍いですね。あの人って言ったらあの人ですよ」
「柴、知ってるの?」
「ええ、さっき恐い顔して帰りました。でもどーして1ゲームも投げないで帰ったんでしょう」
柴原のその質問に答えないまま、芥川はゴールデンボウルを後にした。
「は〜マンション帰るの恐いな〜…僕泣きそう」
芥川はあれこれと言い訳を考えながら、トボトボと歩き出した。
マンションの鍵の音が鳴らないように周は慎重にドアを開けた。
もう夕暮れが近いので、辺りがひっそりとしていたからだ。
「ああ今日はもう、瞳に会うのは止めよう…」
周はそう心に誓った。
でも、音も立てずに電気もつけずに部屋でじっとしているのは苦痛以外の何物でもない。
さすがにお腹も減ってきた。
グーグーなる腹の虫の音までは、いくら周でも消すことが出来ない。
「このまま寝るのもな〜、なんだか寂しい…、あ〜いっそ開き直ろうか?」
人間、お腹が空くと他の事はどうでもよくなるものだ。
周は立ち上がると部屋の電気をつけ、冷蔵庫を開けた。
冷えたビールをクッと喉に流し込むと、自然に笑みが漏れる。
考えてみれば、自分は何もやましい所はない、一美の事についても、女子高生の事についてもだ。
「堂々としてればいいんだよな〜!!」
周はゆでたスパゲティにオリーブオイルとバジリコを混ぜながら、鼻歌を歌ってる。
テーブルにお皿を運ぶ頃には、CDまでかけて楽しそうだ。
そうして一口スパゲティを口にほおばった時、玄関のチャイムが鳴った。
その音で周は急にさっきまでの自分を思い出した。
そう、すかっりビクついていた自分だ。
「あの〜どちら様でしょうか?」
ことさら丁寧に言ってはみたものの、それで相手の気持ちが変わるわけでもない。
「あたし…」
ドスの利いた瞳の声がした。
「あの〜今日ちょっと具合が悪いので、明日じゃどうでしょう?」
「鼻歌や音楽がするのに具合が悪いの?」
「ハハ、お耳の聞こえいいんですね〜、まだまだお若くてよかった」
「いいから早くここを開けなさい!」
「そんなぁ、脅迫ですか?」
「誰が脅迫よ〜!!」
まだ一口しか食べてないのに…
周は冷たくなってしまうだろうスパゲティを見つめた。
未練いっぱいだ。
「じゃあ今、食事中だからちょっとだけ…」
開けたドアの奥で「私は食事も出来なかったわよ…」
引きつった顔の瞳がそう答えた。
「まあまあ、お腹が空くとカリカリするし、ほら、丁度スパゲティ出来た所なんだ、ちょっと食べない?」
周は瞳をソファに座らせると、自分の為に作ったスパゲティを瞳に勧めた。
瞳の鼻先でいい匂いが漂う。
そういえば、何も口にしていなかったので今にもお腹が鳴りそうだった。
「そう、じゃあ、ちょっと味見だけね…でも、それが済んだらちゃんと話聞かせてもらうからね…」
瞳の言葉からはまだ刺々しさが抜けない。
でも、差し出されたお皿を手に持つと、ちょっと表情は和らいだようだった。
「どう?」
「うん、ちょっと味が薄いかしら…」
「えっ!それで薄いの?」
「だからちょっとよ、そう言ったじゃない」
「まったく素直じゃないな〜、美味いなら美味いって言えないの?」
「…」
周は瞳の返事を待っていた。
だが、反撃の言葉は瞳の口から出ない。
出たのは瞳の嗚咽だった。
「あ、まって、そんな、ほら、まだ食べなきゃね…、お腹空いちゃうし、ほら瞳、なんで泣くんだ…」
うろたえる周を尻目に瞳の声はますます大きくなっていく。
「ひっく…ひっく…」
フォークを持ちながら泣く姿ははっきり言って迫力はない、がしかし、今の周にはそんな事を突っ込む余裕もなかった。
「瞳ぃ…泣くなよ。俺、困ってしまう…」
「あなたが、ひっく…、悪いのよ、ひっく…、若い子に、ひっく…、囲まれて、ひっく…、にやけて、ひっく…、ひっく…」
「だからそれはね、成り行きで、全然勘違いだって…」
「私、年上だし、ひっく…、ピチピチじゃあないし…」
「そんな事、気にしてないだろ」
「だって…ひっく…」
「俺は瞳だから一緒にいたい、瞳だから側にいて欲しい」
「ホント…」
「ホント」
「これ…」
「何?」
「美味しい」
「そうだろ、じゃあ、ちゃんと食べて…、俺コーヒーでも入れるから」
周は落ち着きを取り戻した瞳に安心しながら、台所に向かった。
「あの…」
周の背中に瞳が声をかける。
「どうしたの?」
「周って…呼んでもいい」
「えっ…」
振り返った周は2つのコーヒーを手に持ったまま、まじまじと瞳を見つめた。
「どうしたの急に…、あ、でも別にいいよ、周でも周ちゃんでもあなたでも…」
「周ちゃんは嫌、同じ風に呼びたくないし、私の方が年上だし、あなたじゃ、ちょっとね〜倦怠期入りそうだし、だから周がいい、周と対等でいたいから」
「俺は最初から瞳って決めてた、俺にとっての『ひとみ』は今思えば、ずっとこっちの瞳だったからさ、呼んでいたのは一美じゃなくてきっと瞳だった…」
テーブルに置いたコーヒーの匂いが二人を包む。
マグカップを持った二人はカチンと乾杯を交わすとやっと穏やかな表情で笑顔を浮かべた。
「ところで、どう、あっちの具合は?」
「えっ、なんの具合?」
「あんまり我慢してると良くないよ」
「だから何よ?」
「朝の話」
「朝の話?」
瞳は全然訳が分からずキョトンとしている。
「だから〜」
そう言うと周は瞳のカップをテーブルに置いて、自分のカップもその隣に置いた。
そしておもむろに瞳のあごに手をかけて自分の方を向かせると、ゆっくりと唇を近づけた。
「俺も我慢してると体に良くないし…」
「もう、周、あなたって最低」
二人は抱き合いながら笑いあった。
「もっとムードのある誘い方出来ないの?」
「出来ない」
周がきっぱり言うとさらに二人は声を上げて笑った。
「お腹も空いてるし、頂いてもいいかな?」
「それもムードなしよ、周。でも私がスパゲッティ食べちゃったからしょうがないわね…」
今度は瞳がお返しのキスをした。
その合図で、周の手はもぞもぞと動き出した。
「いい感触」
「こら、もう、黙って、真面目にしましょう、記念すべき最初の夜なんだから…」
「え〜、だからこそ燃えなきゃ〜!もう僕、燃えちゃうよ〜!」
「きゃ〜周、ちょっと待ってよ、こら、バカ…」
「うん、やっぱいい感触」
「だから、もう電気ぐらい消してよ〜〜!」
その声でやっと立ち上がって部屋の灯りを消した周は
「愛してる、瞳。これからもずっとね…」
そう呟いて瞳を抱き上げた。
「そう、それでいいのよ、やれば出来るじゃない」
「でも重い…早くベットに行きたい…」
「こら、それが余計なのよ…もう、周ったら…」
その晩、周の部屋は笑い声と甘い声が夜通し入り交じった賑やかな夜になったようです。
さて、この2人、大丈夫なのでしょうかねぇ。。