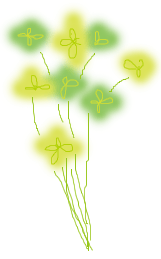
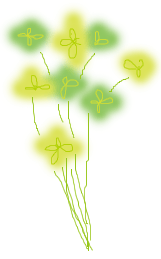
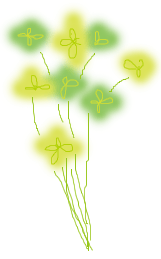
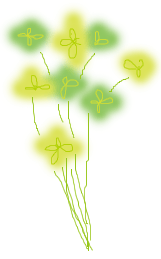
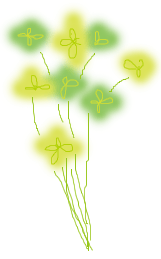
僕の腕の中には、まだ温もりがある。
でも、その温もりの主は、もうこの世にはいない。
ほんの少し前に彼女は逝ってしまった。
遠いどこか、そう…虹の橋の向こうへ。
僕は腕の中で眠っている彼女にそっと最後のキスをした。
すると、それまで止まっていた感情があふれ出すかのように、涙が零れた。
僕は泣いた。
1人きりの部屋で、誰にもはばかる事なく。
そして、それは嗚咽になって、誰もいない部屋に満ちていった。

僕が最初に彼女に会ったのは、大学の食堂の端にある赤いポストの下だった。
学生証の写しが必要だという親からのメールで、面倒だと思いながらもコンビニでコピーを取った僕は、それを封筒に入れここまで出しに来たのだ。
パタン。
ポストの中へ封筒を入れると、僕はそのまま食堂へ向かった。
1歩、2歩、3歩、そして4歩目を踏み出すとき背後から僕は呼び止められたのだった。
「ニャン」
それは小さな声だった。
でも悲しいかな耳が良い僕には届いたのだ。
だが、振り向いてみるとどこにもそれらしき姿はない。
そこにあるのは赤いポストと、それを取り巻くように盛り上がる茶色や黄色くなった枯れ葉だけだ。
空耳か?
そう思って再び歩き出すと、彼女は最後の力を振り絞って声を上げた。
枯れ葉の中から、今にも消えそうな命の声を。
僕は動物を飼った事がない。
だから、最初それを見た時は正直うろたえた。
積まれていた枯れ葉を手で払うと、そこに居たのは茶色の猫だった。
目も鼻もぐちゃぐちゃで、お腹がペチャンコに潰れた猫はそれでも首を上げようとする。
僕は猫がそんな状況だというのに、手が出せないでいた。
情けないことに、弱った猫を目の前にして途方に暮れるばかりだった。
そんな様子の僕を、他の学生達が物珍しいものでも見るような目を向けながら、それでいて早足ですぐ傍を通り過ぎる。
関わりを持ちたくない、学生ならそう思うのは当然だ。
僕だってそうだ、こんな所に立ち止まっていていったい何になる。
でも、どうしてもこの場所から動けない。
1時間ほどそうしていただろうか。
空がゆっくりと日を落とし始めた頃、僕は不意に肩を叩かれ顔を上げた。
「迷っているなら助けてあげれば?」
その人は見たことも無い人だった。
「食堂からずっと見てたけど、おやつの時間もだいぶ過ぎたし、もう食べる気もないんでしょ?だったら考えることなんて無いじゃん」
あっけらかんとそう言い放つと、その人は踵を返した。
僕はその物言いにムッとした。
僕は別に、おやつと猫の命を計っていたわけじゃない。
確かにここで手を差し伸べるのは簡単だ。
でも、その後はどうする?
お金だってかかるし、第一誰が飼うんだ。
僕は腹立たしさに押されるようにして立ち上がった。
そして何も見なかったかのようにその場を離れた。

