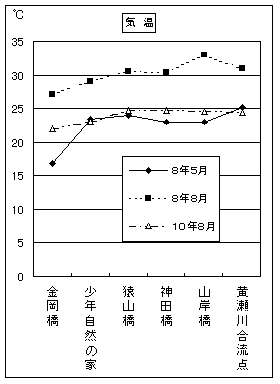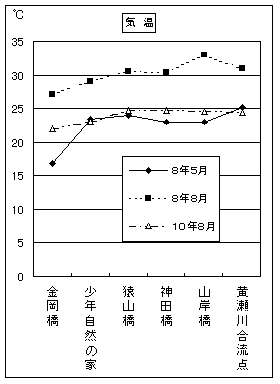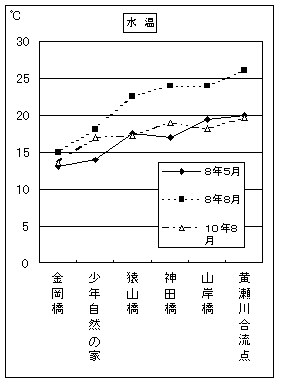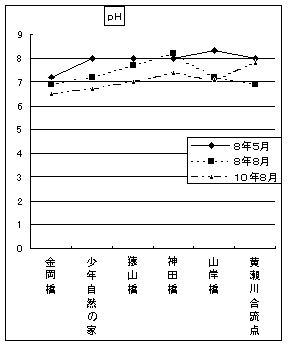(2)気温・水温・pH
気温
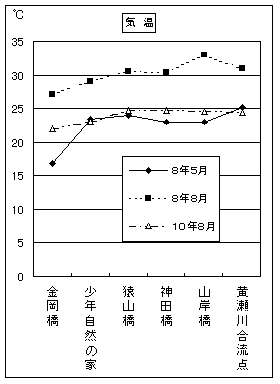
同じ8月でも平成10年は曇りで、平成8年の5月と同じくらいの気温でした。
全体に気温が金岡橋と少年自然の家が低く、それから下流で次に高くなっています。
気温は一般に100mの標高差で0.6℃の差がありますが、桃沢川の上流と下流
では気温差ほどの標高差はありません。
これは標高差以上に周囲の環境が影響していると思います。
上流では樹木など緑が多く、木陰があり、葉の蒸散作用によって気温が低くなり、
下流ほどアスファルトやコンクリートが増え、気温が上昇するのだと考えられます。
(測定は100℃のアルコール棒温度計を日陰で使用。陰のないところでは測定者の
体で陰を作り、50cm以上体から離して測定しました。どの場所の調査でも必ず
5分たってから目盛りを読んでいます。)
水温
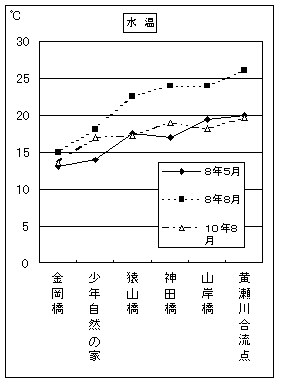
水温は気温の影響を受け、水源からわき出てから時間が経過した下流ほど温度が高くなります。
金岡橋でそれほど差がなかった水温が、気温の高い平成8年8月の下流で大きく上昇しています。
水温は河川水のバクテリアや藻類の活動に影響し、水中での化学反応の速さも左右すると思われます。
また、酸素など気体の溶解度は水温が高くなるほど小さくなり、水質に影響を与えます。
(測定は100℃のアルコール棒温度計を直接河川水に入れて5分後に記録しました。)
pH
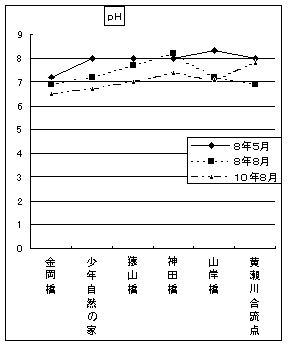
pHは酸性・アルカリ性の強さを示す尺度です。7が中性で数字が大きくなるとアルカリ性が、
数字が小さくなると酸性が強くなります。
pHは6.5〜8.5が望ましく、桃沢川は今回調査したすべての地点でこの範囲でした。
下流に向かってpHがわずかに高くなる傾向があります。
水温の上昇に伴って水中の二酸化炭素が減少すればpHが高くなりますが、汚水の流入など、
それ以外の原因も考えられます。
平成10年は平成8年の2回の調査と比較してやや低い値になりました。水量の増加が原因か
どうかは分かりません。
(pHメーターは平成8年に2点校正のコンパクトpHメーターを使用し、平成10年は
1点校正のpHメーターを使用しました。調査の現場で測定します。)