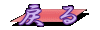| あこがれ / 愛 |
|
「おや?見慣れない船が停泊しているな。」 昼食を終え、二つの空の弁当箱を抱えて小次郎の事務所を出た弥生の目に いつもはそこに存在していない大きな船が飛び込んできた。 普段、昼休みには二つの弁当箱を片手に小次郎の所へ通っているため、 例え事務所周辺で『違和感』を目にしたとしても、大抵無視できるような余裕があるのだが今日に限っては事情が違う。 もしかすると目の前に停泊している船が、忌まわしい惨劇が繰り広げられた あの『トリスタン号』を髣髴とさせる立派な船だったからかもしれない。 「ああ、何処かの福祉団体の船らしいぞ。 『コンタクト』とか言ってた……かも?」 正しくは『コンティニュー』である。 ミセス・サンディの元、世界中を飛び回る(?)福祉団体『コンティニュー』。 芸術家・タレント・スポーツ選手といった民間への露出度の高い人達から 地方の名士や政治家といった県や国の政策に直接関わる人まで、その福祉活動はありとあらゆる方面に影響力があり、 今やコンティニューの活動に関わることが、一個人の立派なステータスになると言われるくらい。 例えば、チャリティーコンサートに呼ばれた歌手はその後のCDの売れ行きやコンサートの集客が大幅に上がったり、 またチャリティー活動の広告塔に指名されたスポーツ選手は世界的に名が知れて、活躍の場が広がる結果となったりするのだ。 その団体が小次郎と弥生の住む街にやってきたのである。 「そういえば朝のニュースで観たような気がする。 近日チャリティーイベントをやるとか言ってた福祉団体か。 それに先駆けて今夜はウェルカムパーティがあるとかで、 政治家や芸能人やスポーツ選手が大勢招待されているらしいな。」 「ウェルカムパーティ……」 小次郎は『ウェルカムパーティ』という言葉に反応し、 手を顎に当てて俯き何かを思い出そうとするような仕草を見せた。 「……どうしたんだ小次郎?」 「うーん……」 小次郎の変化に気付いた弥生が声を掛けるが、この様子ではすぐに思い出せなさそうである。 長くなりそうだと予感した弥生は、バージニアスリムを取り出し火を点けた。 燻る紫煙越しに捉える小次郎の姿。 俯き加減で手を顎に置き真剣に何かを考えているスタイルを眺めていると、 弥生の胸には極々自然に『かっこいいな』という言葉が浮かんだ。 (バ、バカ!何を考えているんだ!!) そんな自分が気恥ずかしくなり再びタバコを口にする。 そして自分を落ち着かせるように静かに一息吐いたところで、小次郎が手をポンと打って顔を上げた。 晴れやかな顔は「何か」を思い出したらしいことを物語っていた。 「ああ、理由はよく分からないんだが俺の所に招待状来てたの思い出したんだ。 そのウェルカムパーティってやつ。」 「な、なんだって!?」 衝撃の事実に驚く弥生。 ウェルカムパーティに『招待されていた』ことを驚いたのは勿論だが、 そんな大事なことを『忘れてしまっていた』ことにも驚いていた。 「なんで小次郎が招待されてるんだ。」 「俺に聞かれても分からないぜ。 差出人は団体名で個人名は書かれて無かったからな。 『コンタクト』なんて福祉団体に知り合いいないし、団体に恩売った覚えもないし……。」 どうやら小次郎にも心当たりは無いらしい。 弥生と小次郎の普段の会話に『コンティニュー』のコの字も上がった試しはなく、当然弥生にも心当たりはない。 二人とも頭の上にクエスチョンマークが3つくらい出ていそうな顔をしていた。 だが、今のままでは考えても答えは出ない。 真相を知るためには『招待を受けること』が一番手っ取り早いのである。 だから弥生は小次郎の意向を伺うことにした。 「で、小次郎は行くのか?」 「うーん、2名までならOKみたいなんだが生憎一緒に行く奴が……」 『2名』という言葉に耳をピクリと反応させる弥生。 ……と同時に『生憎一緒に行く奴が』という言葉に少し憤りを覚えたりもしたのであるが、 ここで怒ってしまうのはプライドが許さないため敢えて遠回しに話を進めるようにした。 「あー、こほん、私、今日は仕事定時で上がれそうなんだが。」 「あれ?誘って欲しいのか?」 ……あまりに露骨な遠回しっぷりだったらしい。 まあ、探偵という職業柄と女性の扱いに慣れている小次郎に対し小細工が通用する筈もないのだが。 しかしこういう時の弥生は驚くほどに頑固である。 「そ、そんなわけないぞ。 ただ『定時で上がれそうだ』と独り言を言っただけだ。 ……まあ、小次郎がどうしてもって言うなら一緒に行ってやらないこともないけど。」 最後の部分はフェイドアウトされて小次郎にはよく聞き取れなかった。 要するに頑固というか強気というか、とにかく素直に『連れていって』と言えない弥生。 気難しくて普通なら敬遠されそうだが、小次郎にとっては嫌いな性格ではなかった。 素直になりたいけどなれないところがまた可愛かったりするのである。 「・・・・・・」 「・・・・・・」 しばし沈黙が流れる。 その間、顔を赤らめてソッポを向きながらも、 小次郎の反応が気になるのだろう、弥生はちらちらと小次郎に視線を投げていた。 勿論、その視線に気付かない小次郎ではない。 一瞬『もう少しからかっても面白いかもしれない』という考えが彼の頭を過ぎったが、 午後の仕事に支障をきたして弥生の機嫌を損ねる結果になるのは目に見えているので却下。 素直に自分の気持ちを伝えることにした。 「ま、たまにはこういうのもいいかな。 一緒に行くか?」 と、言って弥生の頭を撫でる。 「……うん。」 先程の素直になれない態度から一転、今度は至極素直な反応を見せる。 顔を赤くしているのは変わらないが表情ははにかむような笑顔。 『ああ』ではなく『うん』といういつもと違う返事。 自分の前だけで見せてくれる誰も知らない弥生の可愛い一面。 こうやって自分に心を許してくれることが小次郎は嬉しかった。 自分が弥生にとって特別な存在だということがはっきりと分かるのだから。 「ちょっと待ってろ、招待状を持ってくる。」 行くと決まれば長々と余韻に浸っている訳にもいかない。 名残惜しい、というかこのまま大人の世界へ突入したい気分の小次郎であったが、 それはまた別の機会にと諦め、招待状を取りに事務所へ戻った。 ・ ・ ・ 待つこと数分、小次郎が招待状を持って戻ってきた。 「スマン、『コンタクト』じゃなくて『コンティニュー』だった。 ・・・・・・しかし、本当に関わった覚えが無いんだよな。」 と言いながら上品な白い封筒を弥生に差し出した。 弥生はそれを手に取り、まず表の宛名を見る・・・・・・小次郎の事務所の住所と名前。 続けて封筒を裏返し送り主を確認する・・・・・・コンティニューという団体名とその本部住所。 確かに小次郎宛に送られたものであり、そして『コンティニュー』から送られたことしか分からない状況だ。 「中身に差出人が特定できるものはなかったのか?」 「あれば言ってるさ。」 小次郎故に差出人が過去に何かしらの関係を持った女性のため隠している可能性もあるが、 それなら鉢合わせする危険が伴うパーティに「一緒に行こう」などと誘うはずがない。 状況から今回は100%嘘を吐いていないと言えよう。 まあ、幸せ絶頂状態の今の弥生に小次郎を疑うようなことが考えられる筈もないのだが・・・・・・。 「開けていいのか?」 「ああ。」 小次郎に了解を貰って封筒の口を開けて中身を確認する。 そこには2つに折り畳まれた和紙の様な手触りの、これまた上品な招待状が一枚入っているだけだった。 書かれていることは非常に簡潔。 その手の教本から丸写ししたのではないかとも思える手紙用の挨拶文と、 パーティの日時・場所・招待人数が書かれているだけだ。 簡潔過ぎて新手の詐欺ではないかと疑ってもおかしくないような内容である。 たが、間違いなくパーティ会場に指定されている場所は 小次郎の事務所から海を挟んで向こう側に堂々と停泊している福祉団体コンティニューの船だった。 誰かに誘い出されているという可能性も否定できないが、さすがに今回に関してその線は薄いだろう。 まあ、幸せ絶頂状態の今の弥生に招待状を疑うようなことが考えられる筈もないのだが・・・・・・。 「19時開始だから……18時半頃に出れば十分間に合うか。」 招待状に一通り目を通した弥生がタイムスケジュールを考え始めた。 船が停泊している港までは車で5分足らず。歩いても15分あれば着くだろう。 「シャワー浴びて着替えることを計算に入れると 17時半には仕事終わらせた方がいいんじゃないか?」 「そうだな。 今日は特に急ぎの仕事はないから、その時間に上がるのも可能だと思う。」 弥生は頭の中で今日の仕事状況を整理してみたが問題はなさそうだ。 続けてパーティの準備について整理していたところ一つの疑問が浮かんだ。 「やっぱりドレスとか着た方がいいだろうな。」 そう、招待されたのはパーティである。 しかも各界のお偉いさんが集まる格式の高いパーティだ。 「ああ、正装の方がいいだろうな。 でもトリスタン号みたいなやつは勘弁してくれよ。」 「なっ!お、お前だってあのときは欲情してた癖に。」 弥生はトリスタン号での情事を思い出し顔を赤くして反論する。 小次郎にとっては忘れようとしても忘れられないトリスタン号であるが、 「はっはっは。俺はいつだって弥生に欲情しているぞ。」 「大声で自慢することじゃない!」 それよりも弥生の艶姿の方がより深く記憶に残っているらしい。 前向きな小次郎らしいといえばそれまでなのだが、 ここで事件のことを穿り返しても仕方がないという意識があるのだろう。 それはともかくとして、トリスタン号で着ていたドレスでは流石に弥生が浮いた存在になってしまうのは間違いない。 とは言え、残念ながら最近ドレスとは縁のない弥生であった。 「でも、着ていけるようなドレスが無いんだよな……。 よし!小次郎、今から買い行くぞ!」 「ええっ!!」 あまりに唐突で強引な誘いに思わず驚きの声を上げる小次郎。 「なんだ、小次郎は私がバブル期の名残を引きずっているような 時代遅れのダサいドレスを着ていてもいいと言うのか?」 「いや、そんなことはないんだが……」 「じゃあ構わないだろう♪」 普段はあまり見せない無邪気な笑顔で小次郎の腕に思いっきりしがみ付き、 そのまま街へ繰り出そうと小次郎の身体をグイグイ引っ張った。 「お、おい、仕事は?」 「午後は有給休暇だ有給休暇。 小次郎も午後は有給休暇だぞ。」 「ハァ……とんでもない所長だな……。」 小次郎はやれやれと言った感じで一つ溜息を吐いた。 だが、弥生の我侭に流されることが決して嫌という訳ではない。 むしろいつもと違う弥生の一面が見れてむしろ嬉しいくらいだった。 「……ま、いいか。」 「何か言ったか?」 「いや、何も。」 小次郎の答えに満足したという意思表示か、弥生は組んでいる腕に力を入れる。 そしてそれに応えるように笑顔を見せる小次郎。 その目の前の最愛の男が自分に向けた笑顔に一瞬で陶酔した弥生は、静かに小次郎の腕に頬を寄せた。 お互いに言葉はなくとも意思が通じ合った2人は、 そのまま仲良くセントラルアベニューの方向へ消えていった。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 「ちょ、ちょっと……大胆だったかな……」 腰まで伸びる深い切れ込みを気にしながら、弥生はパーティ会場で借りてきた猫のようになっていた。 午後の時間を丸々費やして店という店を巡り、散々悩んだ末に弥生は『チャイナドレス』を選んだのだ。 「それに頭もなんか落ち着かない。 こんな姿を小次郎以外の知り合いに見られたら大笑いされそうだ。」 ドレスだけでなく両サイドの髪の毛をお団子にした、如何にも『チャイナ』っぽい出で立ち。 普段したこともない、いや、弥生の人生において初めての経験である格好のため、 周りからの視線が全て『奇妙なモノを見るような視線』に感じてしまうのは無理もない。 「俺は似合っていると思うぜ。」 「そ、そうか……」 そんな自分の格好を気にしている弥生に対し、小次郎は簡潔にありのままの感想を伝える。 黒と言っても間違いではないような濃い紫色の落ち着いた雰囲気のチャイナドレスは 弥生の端整な顔立ちや髪の毛の色と見事な調和を成しており、確かに似合っていると断言できるものであった。 その言葉を受けた直後、一瞬で弥生の表情が嬉しそうなものに変わったのは予定通りだ。 小次郎の誉め言葉には相変わらず弱い。 「法条のチャイナドレス姿よりもグッとくるものがあるぞ。」 「なっ…… そ、そうだ!小次郎、サ、サラダ食べるか? わ、私が取ってきてやろう!」 誉められすぎて嬉しさが恥ずかしさに変わった弥生は、パタパタとバイキングコーナーへと駆けていった。 先程のチャイナドレスの切れ込みを気にしていた姿はどこへやら。 小次郎が誉め過ぎると別の意味で弱くなる弥生であった。 なお、ここで小次郎の言った『法条のチャイナドレス姿』とは、トリスタン号で見たものだと思われる。 ・ ・ ・ しばらくすると、山盛りにサラダを乗せた二人分の皿と、何種類かのパンを乗せた皿、 そして二人分のフォークを両手で器用に持ちながら弥生が戻ってきた。 「おい、本当にサラダしかないぞ。」 「身体にいいんだから頑張って食べろ。 お前は放っておくとすぐに食生活が偏るからな。」 「どうせなら肉も食いたかったなぁ……」 小次郎は渋々とサラダの皿とフォークを弥生から受け取ると、 文句を言いながらもとりあえず一番上に乗っている可愛いプチトマトを口に入れる。 その程好い酸っぱさを口の中で味わいながら、 小次郎は自分達がここに居ることの不思議さを改めて感じていた。 「やっぱり場違いだよな、俺達。」 「ああ……。」 この場合は不思議と言うよりも不自然と言った方が正しいのかもしれない。 何せ視界に入ってくる人という人が、小次郎や弥生でも知っている知名度の高い人ばかりなのだ。 そんな集まりの中の小次郎と弥生という存在は、明らかに不自然であった。 「見ろよあそこ、プロ野球選手の新城と朱星と……WBC日本代表監督のワンちゃんだ。 何故かドラサンズの井上和樹までいるぜ。」 「野球選手はよく知らないのだが、 音楽家の久石丈や坂元龍一、作家の西村恭太郎といった文化人の面々も招待されているんだな。」 その他にも、政治家、評論家、芸能人、プロサッカー選手、力士、プロレスラーなどなど、 何処を向いても誰かしら著名人が視界に入ってくる異様なパーティ会場。 これだけの各界の有名人を一同に集められる団体はなかなか無いだろう。 改めて『コンティニュー』の影響力というものを思い知らされた二人であった。 「お飲み物は如何でしょうか?」 と、パーティ会場を見回しながら感心しきっている2人へウェイターがお酒を勧めてきた。 品の良い年配のウェイターが持つトレイには、ワインとシャンパン、そしてビールの入ったグラスが乗っている。 「俺はシャンパンで。」 「じゃあ、私はワインを頂こう。」 「かしこまりました。」 注文を受けると、流れるような動作で小次郎にシャンパングラスを差し出した。 近くにあった円卓にサラダの皿とフォークを置き、それを小次郎が受け取ると、 同じく流れるような動作で上品に弥生にワイングラスを差し出した。 「ありがとう。」 負けじと弥生も上品にお礼を述べる。 そして手に持った皿とフォークを小次郎と同じように円卓に置き、差し出されたワイングラスを受け取っ…… トントン ……たところで、弥生は誰かに肩を叩かれた。 「なんだ?」 この場所に知り合いがいると思える筈もなく、当然相手が小次郎だと思い込んでいた弥生は、 いつものようにぶっきらぼうな返事をしながら振り向いた。 しかしその視線は小次郎ではなく、まったく予想もしていなかった人物を捉えた。 「こんばんわ、小次郎さん、弥生さん。」 「お久しぶりです。 あの時は本当に有難う御座いました。」 そこには黒のタキシードを着た端正な顔立ちの男性と、綺麗なフリルの青いドレスに身を包まれた可愛らしい女性、 ちょうど一年くらい前に『遠羽』という街で出会った二人の若者が立っていたのである。 「えっと確か……嘉納潤ちゃんだったかな?」 「はいっ! 覚えていて下さって嬉しいです。」 あの日、小次郎がガラの悪い男達から助けたという女性の名を、弥生はしっかり覚えていた。 恋人と会うのを心待ちにするあまり、待ち時間の1時間前に来てしまったこと、 自分達が喧嘩しているのを『仲が良い』と羨ましがったこと、 そして『また会う日』と次の再会を望む言葉を口にし、 小次郎と弥生に向かって笑顔で手を振り続けていたこと、 『嘉納潤』という女性が見せた可愛らしい姿が今でも鮮明に頭に思い浮かぶ。 「小次郎さんもお元気そうで。」 「ああ、君達も相変わらず仲が良さそうで何よりだ。」 小次郎もまた『真神恭介』という名をしっかり覚えていた。 彼の場合、潤との仲睦まじい姿を見たことも記憶に残っているのだが、 とある人物の身元を調査をしていた際、その関係者として『真神恭介』の名が挙がったことがあり、 どちらかというとそちらの方面から頭の中に記憶されていたという節がある。 まさかあのとき会った青年が、実は数々の事件を解決に導いた『凄腕探偵』だったとは思ってもいなかったのだから。 なお、小次郎がさり気なく君達『も』と言ったことに弥生は気付いていない。 「そういえば、君は探偵なんだってな。 後で知ったが驚いたぜ。」 「まだ見習いですけどね。 でも、小次郎さんも同業じゃないですか。 貴方の噂は遠羽の町まで聞き及んでますよ。」 「ははは、そんな大したもんじゃない。」 2人の凄腕探偵が談笑する。 彼らもある意味では『各界の著名人』と言えるだろう。 先程は場違いと嘆いていた小次郎であったが、実のところは相応の場所なのかもしれない。 「おいおい、私を仲間外れにするなよ。 私だって探偵事務所の所長をやっているんだ。」 と、そこへ拗ねた様子で声を掛けるもう一人の探偵。 弥生の事務所も探偵の世界では名が知れた事務所の一つである。 そう考えると、彼女にとってもここは相応の場所と言えるのかもしれない。 「あう、私だけ仲間外れです……。」 一人だけ探偵ではない潤がしょんぼりと呟く。 職業という枠で括ると一人だけ異なるのは確かだ。 「でも、冷静に考えるとお嬢ちゃんが一番凄いじゃないか。 盲目のピアニスト・嘉納潤、今や知らない人を探す方が大変だぞ。」 「そうだよ。 俺達には絶対真似できない潤ちゃんの立派な役割があるんだから。」 弥生と恭介がすかさずフォローを入れると、 「いえ、そ、そんなことは……」 潤は手をパタパタ振りながら言葉を詰まらせた。 どうも周りから持ち上げられるのは苦手な性格らしい。 「え、えっと、私、後でピアノを弾きます。 小次郎さんも弥生さんも是非聴いて下さい。 勿論、真神さんも……。」 「大丈夫だよ。 ちゃんと目の前で聴いてるから。」 そう言って恭介が誉めるように潤の頭を撫でると、彼女は頬をほんのり赤く染めて嬉しそうに目を細めた。 一歩間違うと『バカップル』と言われても仕方のないようなやり取りだったが、 この二人の場合は何故か微笑ましくて小次郎と弥生の表情も自然と笑顔になる。 (やっぱり可愛いな。) (確かに。) 盲目という状況に甘えることなく、恭介の隣を歩けるように一生懸命追いかける潤と その潤に自分の歩幅を合わせてを優しく包み込みながら見守っている恭介。 そういった二人のスタンスがあってのやり取りだからこそ、頬を緩めてしまうのだろう。 「ドレスが『青』だから頬を『赤』く染めると更に綺麗に見えるな。」 「そ、そんな……弥生さん……」 弥生が誉めると今度は真っ赤にして恥かしそうに俯いてしまった。 色彩感覚には乏しい小次郎は、弥生の誉め言葉の意味が分からなかったが、 潤のコロコロ変わる表情を楽しみながら、手に持っているピンク色の液体を喉に流し込んだ。 その時、ふと素朴な疑問が浮かんだ。 「そういえば、君達は誰に招待されたんだ? 俺の所に来た招待状は差出人が書いてなかったからな……。」 そう、この場所にいるということは二人も『招待されている』はずなのだ。 招待をした相手が誰なのか疑問に思うことは至極当然のことである。 最も、潤がコンティニューの人間だということを知っていれば疑問に思うことはないのだが。 「潤ちゃんはコンティニューの人間なんですよ。 だから招待する側の立場になりますね。 俺は一応部外者だから『潤ちゃんに招待された』ことになるのかな。」 「な、なんだって!!」 「な、なんだって!!」 小次郎と弥生の驚きの声がハモった。 潤が盲目のピアニストだということは知っていたが、 まさかコンティニューお抱えのピアニストだとは知らなかったのだから驚くのは無理もない。 「ってことは、もしかすると俺の所に来た招待状って……」 察しの良い小次郎が、ある一つの可能性に結びつく。 招待状を送ってきたのが目の前にいる女性だという可能性に。 「はい。 私から送らせて頂きました。」 ・ ・ ・ ・ ・ 何故、小次郎にパーティの招待状を送ることが出来たのか。 それは小次郎が『探偵』だったことが幸いした。 あの日、小次郎と弥生に出会ったことを恭介の上司にあたる鳴海誠司に話したところ、 すんなり「天城小次郎なら知ってるよ」という答えが返ってきた。 どうやら天城小次郎は『同業者』として、誠司所長が昔から一目置いている存在だったらしい。 頭脳明晰、鋭い嗅覚・勘、飛び抜けたフットワーク、女性に弱い、などなど 探偵としての力量とウィークポイントに関する情報は、同業である誠司所長の耳にも届いていたのだ。 しかもその小次郎の実力を頼りするため、小次郎の事務所に一度顔を出したことがあったお蔭で、 招待状を送るという話になったとき、住所がすんなり分かったという。 勿論、弥生が所長を務める『桂木探偵事務所』のことも知っていた。 こちらは探偵業を営んでいる限り、知らなければモグリであると言われるくらい有名な事務所だから当然なのだが。 恭介も『桂木探偵事務所』の名前は知っていたが、所長が弥生であることは知らなかったらしい。 ・ ・ ・ ・ ・ とまあ、こういった経緯で小次郎の元へ招待状を送ることができたのだと説明すると、 小次郎の頭の中にあったモヤモヤとしたものはすっきり晴れた。 普段の小次郎であれば、パーティ会場で恭介と会った時点で気が付いてもおかしくないのだが、 今日は弥生のチャイナドレス姿に見惚れていたため、それどころではなかったのかもしれない。 「なるほど、それなら納得できるぜ。 いやしかし……俺も有名になったもんだなあ。なあ、弥生。」 「お前の場合、どっちの意味で『有名』なのかは分からんけどな。」 勿論、良い意味と悪い意味ということである。 小次郎が探偵として優秀なのは百も承知の弥生であったが、 女癖の悪さに悩まされてきたのも事実であり、そんな皮肉を込めてそんな発言をした。 「そりゃ当然『良い意味』だろうぜ。 凄腕探偵・天城小次郎、今日も見事に難事件を解決! みたいな話が毎日のように届けられているはずだ。」 「どうだか。 女たらし探偵・天城小次郎、今日も綺麗な女に鼻を伸ばして犯人を取り逃がす! なんて方が多いんじゃないか?」 「なんだと! 俺がいつ綺麗な女に鼻を伸ばして犯人を取り逃がしたんだよ?」 「そんなのいつものことじゃないか!」 いつものやり取りからいつもの口論を始める小次郎と弥生。 以前会ったときと変わらぬ姿を苦笑いしながら見守る恭介と潤。 これはこれで4人が生み出す調和の取れた新しい空間なのかもしれない。 ……当然、周りの人間は4人に冷ややかな視線を送るのだが。 「まあまあ、2人とも落ち着いてください。 一応、うちの所長は誉めてましたから。」 騒ぎが大きくなってしまうのも問題だろうと思った恭介が仲裁に入る。 『一応』という言葉にどんな真意が隠されていることは敢えて触れないでおく。 「ふふふ、やっぱり小次郎さんと弥生さんは仲が良くて羨ましいです。」 「……」 「……」 そして潤に以前会った時と同じことを言われ、同じように毒気を抜かれる2人。 不毛な口論は一瞬で止まった。 このお嬢ちゃんには叶わないな、と2人が思ったのは言うまでもない。 「あ、潤ちゃんそろそろ時間だよ。」 恭介が腕時計を確認して潤に時間の到来を告げる。 「すみません、これからピアノの演奏がありますので失礼します。 あまり上手ではないですが、よかったら聴いてください。」 どうやらピアノの演奏時間が迫っているらしい。 「ああ、喜んで聴かせてもらうぞ。 お嬢ちゃんの演奏が生で聴けるなんて今日一番のサプライズだ。」 「頑張れよ。 恥かしい話、俺には音楽があまりよく分からないんだが、 耳に全神経を集中させて聴いてるぜ。」 夫々の言葉で潤にエールを送る。 このような場所では心にも無いお世辞も沢山飛び交うだろうと2人は分かっていた。 そんなありきたりな言葉を彼女に送ってはいけない。 だからこそ、飾り気の全く無い素直な気持ちをそのまま言葉にした。 「はい!」 潤はそのエールに応えるように元気よく返事をすると、小次郎と弥生に向かって頭を深々と下げる。 それに合わせて恭介も軽く会釈をすると、2人は寄り添いながらピアノが置いてあるステージの方へ歩いていった。 その後姿を眺めながら、小次郎と弥生は改めて日本の狭さと不思議な縁を実感する。 「まさかあのお嬢ちゃんが招待状を送っていたとは……。 やっぱり日本は狭いぜ。」 「ああ。 彼らとはこれからもいい付き合いができるといいな。」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ パチパチパチパチ! 会場に設置されたステージの上に盲目のピアニスト・嘉納潤が登場すると、 誰が音頭を取った訳でもなく会場内は拍手の渦に巻き込まれた。 盲目とは思えないほどしっかりした足取りでピアノへ向かう潤。 ピアノを弾くことが自分の役割、そして自分の生きる価値なんだ、という強い意志がその姿から伝わってくるようだった。 ……………… そしてピアノの横に立ちスタッフにマイクを渡された瞬間、 拍手の音に溢れていた会場が一瞬で静まり、誰一人として音を発しない静寂が会場を支配する。 このとき小次郎と弥生は、改めて盲目のピアニスト・嘉納潤の偉大さを実感した。 会場にいる誰もが、潤の言葉と演奏に耳を傾けようとしているのだ。 この様子を見る限り、潤の演奏が目的でパーティに出席した人間も少なくはないと予想できる。 例えどんな著名人がステージに立ったとしても、これだけの一体感を得ることは難しいだろう。 「本日はお集まり頂きまして誠に有難う御座います。 僭越ながら私、嘉納潤がパーティの余興に一曲演奏させて頂きます。 歓談の片手間でも構いませんので耳を傾けて頂ければ幸いです。」 これだけの人間の注目を集めても表情を一つ変えない堂の入った挨拶に 普段から大勢の前で演奏をしていることが覗える。 それだけでも彼女の社会的地位みたいなものを十分に理解することができた。 本当は面と向かって気軽に話が出来る人物ではないのではないか、 そんなことさえ考えてしまう小次郎と弥生であった。 「演奏する曲はジョージ・ウィンストンの『Longing/Love』、邦題は『あこがれ/愛』。 古い曲ですが、テレビなどで一度は耳にしたことがある曲かもしれません。」 確か20年位前の車のCMだったろうか。 切なく悲しい曲調がなんとなく弥生の記憶に残っていた。 「私はある出来事を切っ掛けに一人の男性に”あこがれ”を抱きました。 ですが、その時はあこがれの気持ちを抱いたままお別れすることになってしまったのです。 遠い異国の地でその男性の事を想い、悩み、悲しみ、苦しみ、胸が張り裂けそうになりました。」 小次郎と弥生はその相手が真神恭介であることがすぐに分かった。 ステージの近くに立っている恭介を見ると、顔を真っ赤にして恥かしそうに頬を掻いていた。 「その後、日本に帰ってきて男性と再会しました。 男性を前にすると、あれだけの胸の中にあった苦しみが一瞬で嬉しさに変わったのです。 私はそのとき、その男性に対する”あこがれ”の想いが、いつのまにか”愛”に変わっていたことを理解しました。 そして今……私は”愛”を育む幸せを噛み締めています。 本日はそのことを思い出しながら演奏致します。 ”あこがれ”と”愛”の想いがみなさまの心にも響くように……。」 挨拶が終わり手に持っていたマイクをスタッフに渡すと、潤は凛とした表情でピアノの前に座る。 そして静かに目を閉じて一つ大きな息を吐くと、綺麗な手が白と黒の鍵盤の上で流れるように動き始めた。 会場に異なる2つの音色が響き渡る。 切なく悲しい音色は、”あこがれ”を抱き、悩み、苦しんだことを。 穏やかで明るい音色は、”愛”する”愛”される喜びを知り、幸せを噛み締めていることを。 恭介と出会い、離れ、そして再会し、今は隣を歩いている潤の想いが伝わってくる見事な演奏だった。 ・ ・ ・ そんな潤の『想い』に支配された会場内で、 弥生もまた小次郎に対する”あこがれ”と”愛”を思い出していた。 小次郎にあこがれ、背中を追いかけた自分。 彼の隣を並んで歩ける女性になろうと必死だったあの頃。 隣を歩けるようになって初めて気付いた小次郎への愛。 彼の喜ぶ姿が見たいと、彼に愛されたいと、一生懸命だったあの頃。 浮気されたことも、突然別れる告げられたこともあった。 それでも心の中にある小次郎への愛は変わらなかった。 背中を追い続けた日々。 愛し愛され幸せだった日々。 浮気されても別れても変わらぬ愛で想い続けた日々。 潤のピアノの音色に乗せ、弥生の脳裏に蘇る数々の記憶。 (ああ、やはり私は……) 隣で静かに潤のピアノの音色に耳を傾けている小次郎にチラリと視線を移す。 その瞬間、心の中が温かく心地よいものに包まれた。 (……小次郎を愛してるのだな。) ・ ・ ・ パチパチパチパチ! 演奏が終了し、会場内は再び盛大な拍手に包まれる。 小次郎も弥生も潤に届くようにと大きな拍手を送った。 その拍手に応えるようにステージの潤は深々と頭を下げると、ステージの袖へと下がっていった。 拍手が収まると途端に会場はざわつき始める。 勿論、今の演奏に関する反応が殆どだ。 『素晴らしい』『見事』『天才』など潤の演奏に対する賛辞の言葉が飛び交った。 「凄いな、あのお嬢ちゃん。 音楽のことはサッパリの素人だが、今の演奏が凄いものだという事だけは俺でも分かる。 なんというか……痺れた。」 「……ああ。 ピアノの音色がこんなに心の中に共鳴したのは初めてだ。」 小次郎と弥生も同じように賛辞の言葉を呟く。 決してお世辞ではない、嘘偽りの無い本心からの言葉だった。 そして同時に、今日この場所で潤の演奏を聞けたことを幸せだと思った。 弥生の場合は別の意味でも幸せを噛み締めていたのであるが。 「小次郎さん、弥生さん。」 2人して演奏の余韻に浸っているところへ恭介が声を掛けてきた。 「おっ、色男。 これだけの人の前で盛大に愛を告白された気分はどうだい?」 小次郎がすかさずちょっかいを出す。 潤が挨拶で話した『想い人』がいま目の前にいる真神恭介だとは、会場にいる殆どの人間が知らないことだろう。 だが小次郎と弥生からすれば、潤は『世界的に有名なピアニスト』よりも『真神恭介を愛する女の子』である。 目の前でその愛を見せ付けられたら、その相手くらいからかっても罰は当たるまい。 「い、いや、まさかあんなこと話すとは思ってもなく…… そ、そうだ!少しだけ時間頂いても宜しいですか? 潤ちゃんがお二人に会いたいそうなので。」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 「潤ちゃん、小次郎さんと弥生さんを連れてきたよ。」 恭介に潤が待っているという部屋に案内されたとき、 潤はペットボトルのお茶を両手に抱えてコクコクと飲んでいるところだった。 「あ!ご、ごめんなさい!!」 慌ててペットボトルを口から離してテーブルの上に置く、 小次郎と弥生には何故潤が謝るのか分からなかった。 「別にお茶くらい飲んでも気にしないぞ。」 「で、でも、容器に直接口を付けて飲んでいたので……。 はしたないところを見られてしまいました。」 「……」 「……」 その答えに小次郎と弥生は唖然とする。 今時、そんなことを気にする人間がいるとは思えなかったからだ。 そもそもペットボトルはそういった手間を省くためのものではないのだろうか。 隣の恭介は慣れているのか潤に優しい笑顔を送っていた。 「まあ、その辺は俺達の前では気にしなくていいぜ。 と、それはさておき素晴らしい演奏だったぜ。 音楽なんてサッパリ分からない俺の心を震わせたくらいだ。」 「ああ、私の心も震わせたよ。 お嬢ちゃんの”あこがれ”と”愛”、ちゃんと伝わってきたぞ。」 「ありがとうございます。」 小次郎と弥生に先程の演奏を誉められ、潤の表情は申し訳なさそうな表情から一転して嬉しそうな笑顔に変わった。 「真神さん、小次郎さんと弥生さんに誉められてしまいましたよ。」 「よかったね。」 2人に誉められたことを少し興奮気味に話す潤。 その潤の頭を恭介は優しく撫でてあげた。 これが目の見えない潤とのコミュニケーションの一つなのだろう。 「そうだ、改めて御礼を言わなきゃいけないな。 お嬢ちゃ……いや嘉納潤さん、招待状ありがとう。 今日はパーティに参加できて本当に良かったぜ。」 「いえ、私も2人に来て頂いて嬉しかったです。 また機会がありましたら是非ご参加ください。」 小次郎は潤に向かってお礼を言うと、潤もそれに応える言葉を返す。 2人ともお世辞ではなく本心だった。 勿論、弥生も恭介も同じ気持ちであったことは言うまでもない。 小次郎と弥生、恭介と潤、お互いに出会えた喜びを実感していた。 探偵という職業である以上、何処かでその名を耳にする機会はあるかもしれない。 潤がピアニストとして世界で活躍する以上、嘉納潤という名を耳にする機会はあるかもしれない。 だが、こうやって4人が同じ場所に立つ可能性は限りなく低いもの、まさに『運命的な出会い』だった。 あの日、遠羽という町で出会うように導いてくれた神様に4人は心から感謝した。 「これからもよろしく頼むぜ。」 「ええ、小次郎さんもよろしくお願いします。」 2人の名探偵が熱く固い握手を交わす。 そのときに交わした視線は、お互いをライバル、いやパートナーとして認めるような『信頼』の意が込められていた。 いつかこの2人がコンビを組んで難事件に挑む機会があるのかもしれない。 そんな期待すら持たせてくれる熱い握手と眼差しだった。 「弥生さん。」 片や潤ちゃんは両手を口元に当てる『内緒話』をするジェスチャーをして弥生を呼び寄せた。 男2人には聞かれたくない話をしたいのだろう。 「なんだ?」 「えっと、弥生さんの”あこがれ”とか”愛”を思い出すことができましたか?」 「なっ!」 先程、潤のピアノの音色に乗せて小次郎への”あこがれ”と”愛”を思い出していたことを 見透かされたような発言に、弥生は驚いて思わず大きな声を上げる。 その弥生の反応に潤は最高の笑顔を返した。 「弥生さん、私達も頑張りましょう!」 「ああ。 私も負けないぞ、お嬢ちゃん。」 こちらも熱く固い握手を交わす。 いつかこの2人がコンビを組んだら……小次郎と恭介もタジタジになるだろう。 男を”愛”する女性はいつでも一生懸命なのだから。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ……なおこの日、小次郎が弥生の部屋に泊まっていったのは言うまでもない。 |
| コメント(言い訳) |
|
どうも、Zac.です。 年に一度のお祭り、EVEとMISSINGPARTSの交流戦小説。 今年もプロ野球交流戦の時期に合わせて発表することができました。 ……もうプロ野球交流戦は終盤ですけどね。 ちょっと思ったより文量が多くなってしまいまして……。 さて今回の話ですが、潤ちゃんの十八番であるピアノで想いを伝えるという 私のMISSINGPARTS小説の処女作『明日から始めよう』とコンセプトは全く一緒の作品です。 ただ、その対象が『恭介』ではなく『弥生』というところがちょっと珍しいところだと思います。 元々ジョージ・ウィンストンの『Longing/Love』を潤ちゃんに弾かせるという構想は随分昔からありました。 ただ、これを恭介に聴かせて自分の想いを伝えるのは『明日から始めよう』の二番煎じになってしまうので 結果的に今までずっと温めていた(もとい使えなかった)のです。 そしてついに今回、小次郎と弥生という格好の相手がいる交流戦小説で解禁の運びとなりました。 人間、何事も「慣れて」しまうと感覚が麻痺しまうものです。 ”あこがれ”とか”愛”も同じもの。 あのとき胸が締め付けられるくらい”あこがれた”ことも、 あのとき心の底から”愛しい”と思ったことも、 それが当たり前のようになって慣れてしまうと忘れてしまうこともしばしば。 私があれだけ桂木弥生に憧れ、そして桂木弥生に愛を誓ったことも、 その後8人も護りたい人が出てくればそりゃ忘れそうになってしまいますわ……それを否定するつもりはありません。 でも、何とか持ち堪えてますけどね。やっぱり弥生最高、愛してる、結婚して。 話が脱線しましたが、そういう気持ちを一番思い出して欲しい人って 私が好きなキャラの中では実は弥生なんじゃないかなとか思う訳です。 弥生はその場の勢いとか感情で小次郎を罵ったり拒絶したりするものの後で思いっきり後悔する、 というパターンが、水戸黄門の印籠の如く当たり前になってしまっています。 その辺、拒絶してから小次郎の”愛”に気付くのではなくその前に気付けよってことで ここは一つ潤ちゃんに協力して貰ったと、本作はそう解釈して頂ければと。 ちなみにジョージ・ウィンストンの『Longing/Love』はテレビでもよく流れます。 昔、車のCMやニュースの天気予報などで使われていたので記憶にある人は多いでしょう。 (最近、N○Kの深夜の台風情報において高確率で流れるような気がします。) CDは勿論、着うたでも配信されてますので、気になる人は是非どうぞ。いい曲ですよ。 あと、弥生のチャイナドレスというのは完全に私の趣(以下略) 【追記 2006/06/21】 大事なことを書き忘れましたが、話は昨年の交流戦小説の続きになっています。 最初にこっちを読んで「?」と思った方は、昨年の交流戦小説を読むと納得できるかと。 昨年のはEVEとMPの小説コーナーに置いてありますので興味があれば是非読んでください。 あと他に書き忘れていたこと諸々。 ・何故、招待状に差出人の名前を書かなかったか →所長が「その方が面白いだろう」と言ったから 差出人を推理する「探偵としての小次郎と弥生」を見たかったんじゃないかな、と 作中では全然推理してませんけどね ・弥生の萌えポイント →パーティ会場でも小次郎の食生活を気にする姿 サラダを嫌がる小次郎に無理矢理食べさせるところとか書きたかったのだが、 そこまでするとちょっと小次郎が子供っぽいを通り越してガキっぽくなるので止めました |