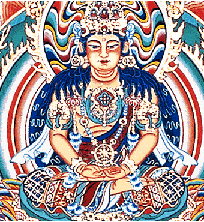 死ぬ夢はよく見る。しかし死んだ後の夢をみたのは初めてだった。
死ぬ夢はよく見る。しかし死んだ後の夢をみたのは初めてだった。夢の話 1999/5/17
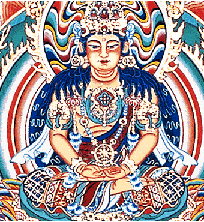 死ぬ夢はよく見る。しかし死んだ後の夢をみたのは初めてだった。
死ぬ夢はよく見る。しかし死んだ後の夢をみたのは初めてだった。
私はあることが原因で死んだ。
死んだ後私はまだこの世にいた。幼いころ過ごした住宅地の、野球場に向かう坂道の途中に私はいた。隣には女がいた。
女だけが私の存在を知っていた。「大丈夫だからね。」 女は私に声をかけつづけてくれた。なぜならその時私は恐怖と不安におののいていたからだ。私の肉体はもうこの世になかった。しかし精神だけは確実に存在していた。奇妙な感覚だった。体が無いのに意識はしっかりとしている。しかし私は以前この感覚を体験したことがあった。尿管結石で入院していた時、バイパスから尿が排出されるため、小便をしたくてたまらない感覚だけづっと続くにもかかわらず、ペニスからはまったく尿が排出されないあの気持ち悪い感覚、自分の肉体が精神と結びつかないあの感覚に酷似していた。
私は寂しくて、仕方がなかった。もう私はこの世に戻れないのだ。私は仲間はづれだ、もう誰にも相手にされない。絶望とはこのことだと思った。その気持ちを知ってか、女だけが私を理解してくれていた。大丈夫、大丈夫、ひたすらやさしいなぐさめの声を掛け続けてくれていた。私はここから離れて、別のところに行かなければならないことを直感的に知っていた。しかし、あまりの寂しさ故に、ここを離れることはとてもできそうになかった。女のもとに、いつまでもいつまでも、こうしてづっとたたずんでいたかったのだ・・・・・・。
チベット密教では、生前中に、死後すぐに現世を断ち切るためのあらゆる修行をするそうだ。両親、肉親、恋人・・・あらゆる現世の誘惑を断ち切って新たな旅にでる勇気を持つことが極楽浄土への第一歩であるらしい。夢の中で、死後の私はみごとに現世にしがみついていた。欲にまみれて生きているなによりの証拠だった。これじゃ極楽浄土に行くなんて夢のまた夢、三途の川で溺れて死ぬのが関の山じゃなかろうか。
いや、しかしリアルな夢だったなあ。私は自分が死んだらどうなるのか、この年で早くも知ってしまいましたよ。
世界の終わり 1999/5/19
 今日も夢の話。
今日も夢の話。
私は世界が終わる日の夢を見た。
私はその日、閑静な住宅街の十字路の真ん中に立っていた。夕食の支度に追われる主婦、公園から家路を急ぐ子供達、街灯がぽつりぽつりと点灯をはじめる。夕日が赤い。街が家庭を中心に動きはじめる或る日の夕刻だった。
突然、私の聴覚が奪われた。世の中のすべての音が消え去った。完全な沈黙状態、私は急激な環境の変化に軽い吐き気を覚えながら次に何かがおこることを予感した。
地面が猛烈な勢いで揺れはじめた。しかし正確に言うと揺れたのは地面だけではなく、空、海、大地のすべてが猛烈に振動を開始したのであった。そしてこの完全な沈黙状態の中から、唯一地割れの「ごー」 という激しい音だけが私に伝わり始めた。
はげしい振動と共に地割れの音は次第に大きくなり、しまいには私をすっぽりとつつみこんだ。私は何かものすごい力におしつぶされそうな恐怖でいっぱいになった。ここにいてはいけない、そう思って私は十字路を北に向かって目一杯走り始めた。誰一人表に出ているものはいなかった。私はたった一人、恐怖から逃れるために走り続けた。
しかし、私の聴覚のいたづらはそれだけではなかった。今度は、空中に飛び交っている電波のすべてが突然聞こえるようになってしまった。私はラジオ、テレビのすべての放送を一度に耳にした。それらは一様にこの世が今、崩壊していく模様をヒステリックに叫んでいた。「○○湾で大津波発生!死者は膨大な数にのぼる模様!!」「○○国は消滅の模様!」世界中は大パニックになっているようだったが、私は更にパニックに陥っていた。「つぶされる!!」この強烈な強迫観念から逃れるためにひたすら北をめざして走った。どこまでも一人だった。
パブ (2) 1999/5/21
 パブ遊び。いきなり看護婦姿であらわれた女、20歳。
パブ遊び。いきなり看護婦姿であらわれた女、20歳。
女:「私、御前崎出身でねえ、ちょっと前に焼津に出てきたの。」
COOL:「へえ、でも・・・パンツ見えてるよ。白いの。」
「(足を閉じる)・・・オーストラリアに行きたくてね、でも英語わかんないからさあ、この前NOVAに入会しちゃった。40万円もするのよ。」
「その胸の聴診器、貸してくんないかなあ。君の胸、ちょっと診察させてくれない、気になるんだよ。」
「あらエッチねえ。ちょっとだけよ。」
「冗談だよ。元気そうだから診るまでないよ、きっと。」
「ねえ、私だって今はこんな格好してるけど、本当はいろいろがんばっているのよ、わからない?」
「わかるけど、もっと生き方を考えた方がいいな。」
「どういうこと?」
「君は学生時代、一生懸命クラブ活動に励んでいた。勉強もしたね。卒業して焼津に出てきて、一人暮らしだ。今は水商売。練習好きで、本番に弱いタイプで、気が弱くて、人生をダイナミックに謳歌できない、そんな人だね、きっと。もっと大胆に一歩ふみだすべきだよ。」
「・・・・・・。」
「今はきっとね、自分で何をしていけばいいのかわからなくて悩んでいる、あせっているね。お金も底をついてきているし、はあ困った、男もとりあえずこりごりだ・・・とそんなところ、でしょ?」
「(顔色が変わる)・・・ちょっとどうしてそんなことまでわかるのよ。」
COOLはこう推理したのだ:へへ、驚いているな。あのな、なんで金出してこんなパブにきていると思ってんだよ、そのハトが豆鉄砲くらった顔がみたくてきているんだぜ。まず、18で焼津に出てきたなら当然一人暮らし、学生でなく仕送りはないから世帯主として税金、健康保険、年金をまともに払ってその上NOVAにも入っていれば当然お金はなし。日本の国はそんなに甘くないんだぜ。さらに、40万もの金をためながらそれを目的であるオーストラリア旅行に使わず、NOVAにつぎ込むのは間違いなく勇気がなくて気が弱いタイプ、練習はこつこつしても本番にちっとも挑まないタイプの典型だ。まあ勉強やクラブ活動をこつこつ続けてきて、社会にほおりだされてもまだなんとなく勉強しなきゃと思っている奴におおいな。あのな英語なんていうのは現地で習わないと身につかないものなんだよ。時間はあるくせにあんたの勇気のなさ故40万をどぶに捨てたのと同じことだぜ。そして海外に行きたいなんて言い出す女は十中八九今何をしていいかわからないからとりあえず環境を変えてなんか見つけたい、いいかえれば迷っているやつなんだな。おい俺はバーテンだぜ、それくらいの推理は朝飯前よ。どうだまいったか、もっとぐうの音言わせてやるぞこのやろ・・・。
「すごいのね、じゃあ今度お店遊びに行ってもいい?」
「え・・・なんでおれが店やってるの知ってんだ・・・。」
「だってこの前、別の女の子口説いてたでしょう。隣りにいたの、わ・た・しよ。気付かなかったの?あの子、うまくいったの、どう。」
「・・・・・・。」
うーんスランプだ。ネタが出てこない。
まあそれもあるが本当は音楽にうちこんでいるのだ。ブルースのフレーズが頭の中にあふれ出してくる。へへ調子良いぞ。ちょっと書く方はここらでちょっと中休みさせてくれい。また調子があがってきたら書き始めるからさあ。はは・・・すべて言い訳です。
ところで、またまた新コーナー開始!「UNCLE CAVES日記」 アメリカンフットボールの熱烈ファンであるUNCLE CAVES氏が贈るフットボール観戦記です。静大キャバリアーズをみんなで応援しよう!不定期にて連載予定。こうご期待。
 スランプの途中だが、どうしても言いたくなったので書いてしまうのだ。
スランプの途中だが、どうしても言いたくなったので書いてしまうのだ。
サッチー報道は、もう見てはいけない。
これは、野村沙知代さんに対する暴力だ。たまたま野村さんが強者なのでこの報道を自らの糧に変えることもできるだろうが、普通の人間なら自殺すら考えかねない行為であると思う。マスコミは面白いとみるやよってたかって個人のプライバシーを明るみにだし、事実と創作の区別なく騒ぎ立て、野村さんとは無関係な著名人のコメントをも引っ張り出してわめきたてる。要するにすべてのテレビ局は個人の私生活をおもちゃにして、食い散らかしているのだ。
おい、若貴の不仲の結末はどうなったのだ。例の整体使はいったいどんな悪事を働いたというんだ?
それからX(エックス)のトシだかがはまった宗教レムリアの教祖はどうした?さんざんわめいておいてこれで終わりか。トシを悪い宗教から救出するんじゃなかったのか?
マリアンの私生活暴いてどうするつもりなんだ・・。マスコミはそんなことをしてマリアンを追い込んで楽しいのか。
もう、なんでもいいのだ。できるだけ下品で、低級で非常にプライベートな話題が著名人に関するものであれば、よってたかっていじめまくってあきたらポイする、それが現在の日本のマスコミの体質だ。きっと恐ろしく暇なんだろう。もう、見てはいけない。
 シャンソンのピアノを弾いた。とある歌手のバックだった。凄かった。
シャンソンのピアノを弾いた。とある歌手のバックだった。凄かった。
凄かったって、愛の世界なのだ。もう、愛、すべてが愛、大人の愛だ。強烈にその愛の世界に引き込まれてしまう。なんたって歌詞の世界だ。日本語でああもはっきり愛を語られると、もうめろめろだ。
例えば、こんな感じ。
「愛の賛歌」では、「あなたのためなら、この黒髪も金に染めます・・・。」とくる。背徳のにおいが充満する。
「愛の流れの中に」では、「パリはなんて不思議な街なの・・・」で始まり、「・・・ナポレオン、ド・ゴールの兵隊たちの足音が聞こえる・・・」となる。パリの街並みを見て昔ここを行進した栄光の兵隊たちの足音を感じるというのだ。なんて不思議な街なの・・・。そして男と女は愛を語る、ああなんてロマンチックなことか・・・。
「ラノビア」ではなんと、「偽りの愛を十字架に誓う・・・許し給う・・・。」とくる。偽りの愛を十字架にだぜ、できるかい、たとえ偽りの愛でも十字架に誓えるなら本物だね。愛と理想のバーテンである私もこれにはKO。シャンソン界には愛のプロフェッショナルがあまた存在するようだ。
ところで私は、演奏中、不覚にも世界に引き込まれ涙を流してしまい、いかんいかん感情に流されてはいい演奏ができないと自己を律しようとすればするほど感動的になる自分のピアノにこれまた酔ってしまい、めろめろになってしまったために後半のピアノソロの部分では私は半ば狂ったように歌い上げ、最後のボーカルのビブラートを聞きながらすっかりこの背徳のシャンソンの世界に入り込んでしまった自分を感じていた。しかし、いかんのだ。この世界、なんか・・・いかん。私のような人間がはいってはいかん世界だ。私はピアノを弾き終わった後、店に閉じこもって大音量でストレート、アヘッドなジャズを聞きまくった。早く忘れなきゃ・・・。いやいや、危ない世界だ。
 沈黙の艦隊を完読した。マンガだ。とても長い話だったが・・・しかしすごいなこれは。
沈黙の艦隊を完読した。マンガだ。とても長い話だったが・・・しかしすごいなこれは。
最初は潜水艦のドンパチものかと思っていたが、話は潜水艦1隻が独立国家として成立し、その可能性をめぐっての猛烈な議論があり、世界の中の日本の存在理由が問われ、憲法9条が問われ、日米関係は完全に分裂し、まあ徹底的に政治とは何か、情報とはなにか、軍事力とはそして核とは何かが追求されていく、スゲー話だ。
なんたってアイデアが凄い。マンガのなかで日本の竹上首相は、自衛隊を常設国連軍とする案が提唱する。そしてこれが憲法第9条に違反しないという見解にいたる。なぜなら、憲法第9条では、国権の発動たる戦争において戦力を保持することが違憲であるので、国連軍となれば問題はないという解釈だ。すばらしい。他にも目のさめるような政治的アイデアがそこかしこにちりばめられている。
まあ、むつかしいことは抜きにしても、この話は非常に面白かった。私は海江田四郎艦長のこんな台詞が好きだ。艦が絶体絶命のピンチに陥る。
「艦長、だめです、逃げられません!」
「・・・・・・。」
「艦長!」
「・・・私はこの時が来るのを待ち望んでいたのだ。」
そして、奇跡の操艦が始まる。ピンチになってもうろたえず、これを待ち望んでいたのだ、と切り替えす余裕。いやー男たるもの、これくらいの器を持って生きていきたいねえ。
 初恋の話はまたもちょっとお休み。
初恋の話はまたもちょっとお休み。
焼津出身の女性歌手を今日はご紹介したい。
名前を鈴木亜紀という。もう、なにがなんでも応援してほしい。彼女はシンガーであり作曲、作詞者であり、アレンジャーだ。ピアノもうまい。デビューアルバム「とてもシンプルなこと」を聞いたがこれがよいのだ。なんせ独創的、才能を感じるんだなあ。私はやはりタイトル曲、「とてもシンプルなこと」が好きだ。「私は誰のものでもない、私のものでさえない、だけどあなたに愛される限り、あなたのもの・・・女に生まれて、ああ、よかった。」いい歌詞じゃないか、泣けてくるぜ。そう、愛の歌をありのまま、感じたまま、普通に唄えばそれは最高のラブ・ソングとなるのだ。
彼女の歌はジャンルにとらえきれない。サンバあり、ワルツあり、ロックありジャズ風あり・・・ブラジル音楽からは多大な影響を得たらしいが、ともかく独創的で飽きさせない。彼女の世界がある。これが本当に大事なことなんだなあ。今はまだでも、いつか時代が彼女の歌に振り向く時がくるかもしれない。彼女にはその可能性を充分に感じる。10月からパーフェクトTVのCMでCDの一曲め「幸運の女神」が流れることが決まったようだ。いよいよこれから彼女はメジャーになるかもしれない。なんせ、焼津出身だ、もう無条件で応援しちゃうもんね、がんばれよう、がんばって今年は紅白出場だ。メジャーになっても俺達のことを忘れるなよ・・・なんて声をかけてみたいねえ。
鈴木亜紀 「とてもシンプルなこと」 MIDI INC 1998 発売元 ポリグラム蕪式会社 8/10 藤枝 「ジェノバ」でライブあり。¥3,500 必聴!
 どーん
どーん
「だめだな、こりゃ。」
「いいや、10時からだね、人出るよ、待ちましょ、しゃあない。」
どーん
「客、何人いるかな?」
「いても一人だろ、こりゃ、一人でもいたらたいしたもんだぜ。けど10時過ぎりゃいそがしくなるかもしんねえな。」
どーん どんどん どおおん
「行っきてえよう。一発でいいから見せてくれよう。たのむからよう。」
「おめえ、ガキか?しっかり仕事しろ、こら。」
「・・・・・・」
今日7月31日ば安倍川の花火大会。街の呼び込み連中もあきらめ気分。営業中の私もあきらめ気分。花火の音が虚しく街に鳴りわたる。はあ・・・行きてえなあ。
 9/11からアメリカへ行く。アメリカへ渡るのはこれで4回目になる。
9/11からアメリカへ行く。アメリカへ渡るのはこれで4回目になる。
始めは、ニューヨークだった。
2度目は、ニューヨークだった。
今回もニューヨークを起点とする旅だ。
それだけニューヨークへ行くなら、お前はよっぽどニューヨークが好きなんだなと聞かれると答えはNoである。私は温かい南の島で体をやいていた方がよっぽど幸せだ。ニューヨークは全く冷たい街だ。人々の足取りは速く、英語ができなければ人間扱いされないし、チップの風習はわかりにくいし、物価は高い。肉はまずいし、パンはがさがさ。主食はマクドナルドだ。街はビービークラクションがうるさく、埃はまいあがった上に車は泥水をはねあげ、ひとたび寒波が襲うと気温はマイナス20度だ。こおりついて滑りやすくなった路面に足をとられて転倒し、転んで軽い脳震盪をおこしたこともあるし、交差点で自転車に乗る黒人と接触し互いにひっくり返ったこともある。タクシーに乗ると運悪く駐禁でつかまって多額の罰金をはらったばかりの運チャンで、たいへんご立腹らしくすごいいきおいで英語であたりちらされたこともある。ライブハウスで写真をとっていると、いきなり後ろから身の丈2mはあるかと思われる黒人に蹴飛ばされ、「見えねえ!」とどなられたこともある。それから・・・
なぜそんな街に行くのだ・・・?
旅の目的はいったいなんなのだ。
なぜ、旅に出るのだ?
それは、
行くべきところだからだ。
人生には「したいこと」と「するべきこと」がある。人には、「会いたい人」と「会うべき人」がいる。ニューヨークは私にとって、「行きたい街」ではなく「行くべき街」であると思っている。すべきことだからする。そんなことのために行動することが私は数多い。或る意味、つまらない人生かもしれない。しかし、するしか道がない。そこに何かがあるとは期待していない。ただ、空気を吸ってくるのみである。それが私の旅である。
 私の夢の一つは、勝利者インタビューをうけることだ。
私の夢の一つは、勝利者インタビューをうけることだ。
いやもうなんでもいい、勝利者インタビューというものをうけてみたいのだ。私は臆病者に加えて、大変負けず嫌いなため、試合というものをほとんどしたことがないが、勝利した時のインタビューのイメージはほぼ完璧にできあがっている。私はなにがしかのコンクールか試合に勝ち、控え室にて勝利者インタビューをうける。数多くのスポットとフラッシュを浴びて、私はインタビュアーから質問を受ける。その模様は当然全国に向けてON AIRだ。私は淡々と質問に答える。
「まずは、おめでとうございます。」
「ありがとう。」
「この喜びを、最初に誰に伝えたいですか。」
「私の両親と、私の家族だ。」
「振り返ってみて、今日の試合で一番苦しかったところはどこでしたか。」
「そういうところは存在しなかった。私はその時するべきことを一つ一つ確実に実行したにすぎない。私は自分の技術と精神力に自信と誇りを持っている。そして、いつ、どのような状況においても確実にそれを実行すること、これが私にとっての試合の意味のすべてである。」
「今日の対戦者についての感想をどうぞ。」
「彼は素晴らしい選手だ。しかし今日彼はミスを犯した。だから結果として私が勝利したのだと思う。」
「それではチャンピオン、次はどのようなことにチャレンジするおつもりですか。」
「・・・チャレンジするということには私は全く興味はない。私にはチャレンジするということは全く必要がないのだ。私はただ、一日一日を良く、正しく生きることにすべてを捧げているにすぎない。人を愛し、自然を愛し、そして私を育んだこの日本を愛することこそ私の人生のすべてである。何かに挑むということは私にとって意味のないことだ。しかし、私に挑んでくる者に対しては、私は命をかけてその者を叩き潰す。私には私の家族の威信を守責任と義務がある。だから私は命を捨てる覚悟をして戦いに勝利するのだ。繰り返すが私は毎日を良く、正しく生きることしか考えていない。」
「ありがとうございました。それではインタビューを終了します。」
・・・どうだ。完璧なインタビューだ。どんなコンクールやコンテストでも使えるぞ。言ってみてえなあ・・・。
過去、本当にこんな風に答えた奴がいる。ヒクソン・グレーシー その人だ。
 昔々、お客様に一風変ったオーダーをされる方がいらっしゃった。アジアンカラーのエキゾチックなワンピースに、細めのサングラス、世界各国を旅するのが趣味という女性だった。
昔々、お客様に一風変ったオーダーをされる方がいらっしゃった。アジアンカラーのエキゾチックなワンピースに、細めのサングラス、世界各国を旅するのが趣味という女性だった。
「えーっと、カンパリにちょっとコアントローを足していただけないかしら。氷はいれないでね。」
「かしこまりました。」
カンパリにホワイトキュラソーとは変った組み合わせだ。女性は2/3ほど飲む。すると次に意外なオーダーが入る。
「この飲みかけにジンと砂糖を加えてシェークしていただけないかしら。お願い。」
「かしこまりました。」
カンパリ、ジン、コアントロー、砂糖・・・。しかも飲みかけのリキュールをベースにカクテルを作るのははじめてだった。グラスをとって中の液体をどぼどぼとシェーカーにいれる。
「うん、おいしいわ。あなた、バーテン長いの・・・?へえ、私、バーテンさんって好きよ。うさんくさいところが。」
・・・あなたの方がよっぽどうさんくさいでしょう、それ。
「えーっと、じゃあこの飲みかけに氷をいれて、ブランデーを足して、ステア(混ぜること)してオレンジスライスを入れてくれないかしら。お願い。」
「かしこまりました。」
女性は同じく2/3ほど飲み、バーを後にした。待てよ。なぜすべて飲み干さないのだ。これは私に対するなぞかけか?と思いその飲みかけにウオッカを加え、一気に飲み干した。まずかった。
 初恋の思い出を語ってみたくなった。私の中で一番美しく、苦しい思い出だ。
初恋の思い出を語ってみたくなった。私の中で一番美しく、苦しい思い出だ。
私は中学1年生だった。校則で頭は坊主で自転車通学、田舎の田舎のど真ん中で青春時代を迎えていた。ニューミュージックの全盛時代で、アリスやさだまさし、松山千春や南こうせつや長渕剛が大ヒット真っ最中だった。あのころニューミュジックのミュージシャンたちは本当にかっこ良く見えた.。そしてその中でも特にさだまさしに私はいかれていた。彼の書く歌詞が素晴らしいと思ったし、アコースティックギターのあのかわいた生の音になんとも惹かれてしまったのだ。「海は死にますかあ〜山は死にますかあ〜」 詩人だ。海が死ぬだって?反戦だ!!当時はこの曲がいったい何を訴えているのか実は私にはさっぱりピンときていなかったが、この言葉の持つ迫力に私は完全に打ちのめされていた。よし、私は大学に入って、ギター持ってフォーク唄って、四畳半の下宿に住んで女と同棲して、小さな石鹸かたかた鳴らして、学生運動やりまくって成田闘争に参加して、ベトナム戦争に反対してピルを解禁して・・・やるぞやるぞやってやるぞ勉強して陸の王者慶応ボーイになってやるぞ、と支離滅裂な妄想と希望を胸に抱いて生きていた。まあ、結果的には6年後には大学に入り、4畳半の下宿に住み女もいたが、やった音楽はジャズだったし学生運動などダサいと決め込んで手をつけなかったわりには本多勝一なんかを読んでしまってベトナムなんかには心の中でやっぱり反対していた。夢は半分くらい達成していたようだ。
それまで、女の子を意識したことはただの一度もなかった。正確にいえば小学2年の時にアグネスチャンにいかれてしまって、あんな人がお姉チャンだったらなあと思い焦がれ、そのためぜんぜん関係なかったが友達の堀君にたまたまお姉チャンがいたので私は堀に多いに嫉妬し、やつの宝物だった力道山とナショナルキッドのめんこを数枚とりあげたりしていやがらせをしたりしたが、良く考えればそれはお姉チャンが欲しかっただけでアグネスチャンに恋をしたわけではなかった。また、小学4年の時私は突然赤色のGパンが欲しくなり、親を説得して真っ赤なGパンを購入して学校にはいていったら学校中のうわさになり、友達から「レッド」と呼ばれ一部大人びた不良の女の子たちからラブレターをもらったりチョコをもらったり、実際に待ち合わせして隣り町のT市までデートしたりしたがときめきなんかは全くなく、真っ赤なGパンをはきたかったのは西条秀樹のものまねをしたかったからだけだったのだが勘違いした女がたまたま何人かいて子供の私に勝手に恋をしたということだった。デパートの屋上の小遊園地でデート中わたしはパチンコゲームに夢中になり、気付いたら女は消えていたが私はいっこうにかまわずゲームに熱中していた。だから、女を女と意識したのはそれがはじめてだった。だから初恋なのだ。
名前を美子といった。肌の色が真っ白だった。(続く)
初恋(2) 1999/6/16 (1)はこちら
 名前を美子といった。肌の色が真っ白だった。
名前を美子といった。肌の色が真っ白だった。
彼女は美しい子だった。これはひいき目で見てそうだった分けではなく、誰が見てもそう答えるはずであった。その日、クラスで席替えがあり、私は一番後ろに座りたかったので、くじで運良く後ろになったやつの中で一番弱そうなやつをこづいて、出口付近の席を確保したところ隣りに座っていたのが美子だった。その瞬間まで、彼女の存在には気付いていなかった。
暑い夏だった。しかし、気持ちのよい風が吹いていた。美子はおとなしい子だった。彼女は数名の仲の良い友達とは仲良く話をしていたが、そうでなければ自分から話をするようなことはなかった。うつむいてじっとしているか、黙って本を読んでいることが多かった。まっすぐな髪の毛がか細い肩ににやんわりとかかっていた。女を感じた。生まれてはじめてのことだった。私はその本当に美しい少女になんとしても話かけたい衝動にかられたが、いったい何を話ていいのかまったくわからず、とりあえずいつものように数学の教科書を持ってくるのをわすれていたので見せてもらうために美子の席に自分の席をちょっとくっつけて、私は一人で興奮していた。
石鹸のかおりがした。嗅いでいたら授業が終わった。
「ねえ、教科書忘れたら、また見せてよ、いいよね。」
美子は黙ってうなづく。
これで調子づいた私は2日に一度の割合で教科書を忘れ続けた。あまり頻繁に忘れるので、あ、こいつ、美子にラブラブだあ、などと友人に囃し立てられ、まったくそのとおりだったが私は顔を真っ赤にして否定していた。美子の方も頻繁に教科書を忘れる私を疑うそぶりもみせず、いつものように私に教科書を見せてくれた。授業中、なんどか肩がふれあうこともあった。そのたびに興奮は緊張となり、美子に嫌われはしまいか・・・と恐れていた。
クラスに恵という女がいた。色が黒く、体は細かったがエキゾチックな魅力を持つ美しい女だった。恵はなぜか私のとる行動の一つ一つに非常な感心を寄せていた。音楽室にあったぼろぼろのフォークギターを私が弾いていると、なにかを私に求めるような目つきで私をじっとながめていた。彼女は自閉症だと言われていた。休みがちで、人と話すことは全くなかった。先生も授業で恵を指名することはなかったし、仮に指名されても口を開くことは決してなかったが、なぜか、或る日さだまさしをきどって書いた私の生意気な詩をよんで、彼女は感想をもらした。
「ねえ、これ、いいよ。」
「え、なんだって?」
「書いたの、全部、読ませて。」
私は大学ノートに書き溜めていた詩をすべて恵に読ませた。授業中彼女は一生懸命ノートを読みふけっていた。私はその当時、自分に詩の才能があると思い込んでいて、授業中だらだらと書いた詩が大学ノートを埋め尽くしていた。しかし内容はお粗末なものだ。中一のくせに政治の歌をうたい反体制をぎどっていたので、生意気なのにもほどがあり、そんなかわいくないガキが書いた詩は読む者すべてを不快にするはずだったし、実際友人に見せると全員がソッポをむいていたが、恵は違っていた。最初から最後まで何度も読み直してはぽつりぽつりと感想をもらしていた。ねえ、政治って、わかるの?どうして怒っているの?どうして大人が嫌いなの?恋愛を知らなかった私は恋愛の詩をまだ書けなかったため、私は生意気にも世の中に対する不満を並べた詩ばかり書きなぐっていたが、実のところ、父母に愛されすくすくと育った普通の家庭の私には世の中に対する不満など或る分けなかったのだ。
恵が口を開くのは私だけだったので、クラスの連中は不思議そうな目で私達を見つめていた。私もなぜ恵が私とのみ話たがるのかわからなかったが、なんせ初めての理解者だったので私は夢中になって詩の内容を説明していた。私は詩を読んでもらうよりもどちらかというと詩の説明を聞いてもらいたかったのだ。「少年の時一番必要なものは、ただひたすら話をきいてくれる友人である」と誰かが言っていたのを思い出す。恵は休み時間も放課後も、果ては授業中だって私が話さえせればその話を聞いていただろう。しかし私には美子のことが気になりだしてから、恵がちょっと疎ましく思えてきたことは事実だった。
或る日、授業がおわり大学ノートが恵から私のもとにかえってくると、最後のページに白黒写真が張り付いていた。A4サイズの私の顔だった。写真の中で私は席から硝子越しに外を見つめていた。なにか遠く将来を見つめているその姿は自分で言うのもなんだがなかなか美しかった。しかしよく見るとそれは写真ではなかった。絵だ。見事な絵だった。恵の絵は線を使用していなかった。すべて点だ。極細のサインペンを使ってすべて点で私の顔が描かれていた。あまりの細かさに一瞬目を疑ったが、写真とみまごうこのすばらしい作品の中に恵の才能が爆発していた。それは才能の質において、私の詩を書くそれと比べるられるようなものではないことは火を見るより明らかだった。なんじゃこれは!凡人の私は天才のこの仕業を見てまったく言葉を失ってしまった。衝撃は圧倒的すぎた。同時に私は過去に出会った自閉症者の豊かな才能を思い出した。小学一年の時出会った祖父江君は授業中立ち上がって椅子の上で突然踊り出す気違いだったが魚偏の漢字を含めて知らない漢字はなかったし、男子女子を問わず人に縄跳びを叩き付けていた鈴木君は時に教師にも殴りかかったりしたが、世界中の国名とその首都が言え、3桁の掛け算に鉛筆は必要なかった。たしか美術の時間、恵が描いた人物画は本当に普通の水彩画で、絵心のないこの私の作品よりちょっとうまい程度のものだったはずだ。なのにこれはなんだ!こいつ聞いたふりして俺を馬鹿にしていたのか、と思い本当にはらだたしくなった。凡人は天才の所業に嫉妬する、その典型だった。と同時に私はちょっとしたいたずらを思いついた。(続く)
初恋(3) 1999/6/20 (1,2)はこちら
 と同時に私はちょっとしたいたずらを思いついた。
と同時に私はちょっとしたいたずらを思いついた。
小宮は、名前は小宮だったが中一にして身長が178センチある大男だった。体格もがっちりしており、カオリ、という3つ上の女とつきあっているといい、SEXも経験ありだともっぱらのうわさだった。或る日、国語の授業で、自由発表というのをやったことがあったが、皆が自分の趣味や夢を語ったりした中で、小宮は「女の口説き方」について発表した。国語の教師は丸山という、大学を卒業したばかりの小柄でかわいらしい女教師だった。小宮は堂々と自分の女の落とし方について語った。おそらくカオリを落とした時のやり口をそのまましゃべっていたのだろう、暗闇で突然抱きしめてキスをする、そのやり方しか知らなかったと思うがなんせうまくいった時の話のため生々しく、説得力があった。女生徒はクスクス笑いながらも、興味深く小宮の話を熱心に聞いていた。しかし話はだんだんエスカレートして、パンツのはがし方から胸のもみ方までに至りはじめた。丸山は危険を感じて小宮を制しようと思った。しかし話が話で、誰の発表より面白い。だからただ単に制するわけにはいかなかった。丸山は考え、そしてこう言った。
「ねえ、小宮君、じゃあ一度私を口説いてみてよ。」
「いいんですか、先生。みんな見ている前で。恥ずかしくないんですか。」
「・・・・・・いやいや、そういうことじゃなくって・・・。」
「僕はぜんぜん恥ずかしくないですよ、先生。それに、そういうことじゃないって、意味が分かりません。そうだ、兄貴がやってるお好み焼き屋があるんですけど、今日いっしょにいきませんか。安いですよ、ねえ。」
「・・・・・・そういうことじゃないっていってるでしょ・・・。」
小宮は本気で丸山を口説き出した。先生のことが好きでした、デートがしたい、遊びに行きませんか?小宮は自分の意志を明確に示して押しまくった。丸山は小宮に少しづつにじりよられ、だんだん歯切れが悪くなり、徐々に女の部分を見せはじめた。「・・・え、何を言っているの、小宮君。」「そんな、あなたと付き合えるわけがないでしょ。」「まだ中学生なのよ・・・。」 生徒達の面前であることが小宮にとって好都合だった。丸山は逃げることができなかった。小宮は少しずつ丸山の方に歩み寄った。丸山の顔は少し紅潮しているようにみえた。178センチある大柄の小宮が小柄な丸山を抱くところを想像することができないでもなかった。生徒は全員つばを飲みこんでいたと思う。しどろもどろに陥った丸山を確認して、最後に小宮はこう言った。
「先生、真面目に口説かれたことないでしょ。女は男の真面目さに弱いんだよ。わかった?」
小宮は丸山を利用して、女の口説き方をみごとに説明した。小宮は普通の中坊ではなかった。私は小宮をうらやましく思っていたが、小宮もどうも私の行動に関心を寄せていたようだった。或る日、小宮が私を誘った。
「なあ、今日、実はさあ、美加の家に遊びに行くんだけど、いっしょに来ないか・・・。」
小宮の一言にNOという分けはなく、私は美加という一つ上の女の家に遊びに行くこととなった。美加の家は私の自宅の近所だった。小宮が呼び鈴を鳴らすと、Tシャツに単パン姿で美加が現れた。美加の部屋に通されると、女友達が一人遊びに来ていた。4人が一つの部屋で何をするんだろう・・・。緊張で心臓は爆発しそうだった。(続く)
初恋(4) 1999/6/20 (1,2,3)はこちら
 緊張で心臓は爆発しそうだった。
緊張で心臓は爆発しそうだった。
美加の母親は細身の美しい人で、喫茶店に勤めていた。正確にいえば、母親は喫茶店でアルバイトをしている時にそこのマスターとできてしまい、それが原因となって両親は離婚していた。独身子持ちとなった美加の母はマスターからその喫茶店を買い取って、借金に苦しみながらも女手一つで美加達を養っていた。この美加の部屋から母親の働く喫茶店は、間に2級河川の小さな川をはさんで、眺めることができる。営業中を告げるパトライトが派手に回転していた。だからその間には美加の家には母親がいないのだ。美加は母親似で、母親はスレンダーで美加はグラマーだったが二人とも目鼻立ちがはっきりした、西洋風の美人だった。美加は長女で、下に浩一という弟がいた。そして両親が離婚している家庭によくある話だが、美加もまた不良のレッテルを貼られていた。小学6年のころから、美加は万引きで補導されていた。田舎のパン屋で菓子パンを盗んで見つかっても、どなられるだけで補導されたりすることはまずないのだが、美加は最近出来たチェーン店の菓子屋で、浩一と二人で万引きを働き、見つかってつかまり母親はよく学校に呼び出されていた。しかし私の知っているかぎり、美加の万引き癖は高校にはいっても直ってはいなかった。私は高校の購買で、菓子パンを盗んで背中に回して、セーラー服と地肌の間に隠し入れる美加の姿を見たことがある。こんな時の美加に声をかけることはできない。しかし、普段話をする時の美加は、目が輝き、好奇心が旺盛なひとりのお姉さんだった。
美加の部屋はきれいに整頓されていた。しかし、ショッキング・ピンクのじゅうたんがひかれ、セミ・ダブルのベットが置かれ、数多くのぬいぐるみと派手なポスターに囲まれたこの部屋は、私にとって刺激が大きすぎ、私は、ここはいてはいけない場所ではないのかという罪の意識と常に戦う必要があった。隣りの小宮は何食わぬ顔でだされたポテト・チップスを食べながらもう一人の女と話し込んでいた。裕子と名乗ったその女は小宮の話に引き込まれ、常にけらけら笑っていた。美加は茶菓子をだしたり音楽を変えたり急がしかったが、落ち着くと私の隣りに座って、話に加わり始めた。トランプゲームをし終わると、小宮が切り出した。
「なあ、浩一の部屋、空いてるんだろ、今。」
「・・・うん。」
「ちょっと隣りの部屋、貸してもらっていいかな。裕子、行こうよ。」
小宮は裕子を連れて、隣りの浩一の部屋に消えていった。美加は迷惑そうなそぶりをみせたが、小宮の言い出すことを否定することはできないようだった。私達は二人っきりになった。かかっているハード・ロックのボリュームをあげて、美加は私に話かけた。
「これ、しってる?」
「知らない。」 私はハード・ロックを聞いたのはこれが初めてだった。不良の臭い、男と女、SEX・・・・・・。これはなんなのだ。
「キッス、って知らないの。かっこいいでしょ。ほんとに知らないの、遅れてるわね。」
キッスというのは名前は知っていた。しかしそれは不良が聞くもので、私は聞いてはいけないものだと思っていた。しかし、今はその不良と話しているのだ。しかし・・・刺激が強すぎた。私は何もいうことができなくなった。言葉を失った私の顔を面白そうに覗き込んで、美加は話はじめた。このね、口から吐いてる血はね、本物の鶏の血を使っているのよ。この人、かっこいいでしょ、ジーン・シモンズよ。私ね、セクシーな男が好きなの、キッスばかりじゃじゃなくて、ジャパンも好きよ・・・・・・。
セクシーだ、血だ、ジャパンだ、この女の興味は私と全く違うものであるようだった。美加は更にボリュームを上げた。それは音楽を聞きたかったためではなく隣りの部屋からかすかに喘ぎ声が聞こえたせいであったかもしれなかった。ハード・ロックが鳴り響く部屋のなかで、Tシャツ、単パンのきれいなお姉さんを前に、私は不思議な気分に浸っていた。美加は私に質問した。
「ねえ、キスって・・・。」
キッスではなかった。
「したことある?」
「ない・・・です。」
「そう・・・よね。小宮君の友達だったの、あなた。」
小宮とは友達というほどの仲ではなかった。思えば今日の出来事は小宮がしかけたことだったが私は夢の中にほうり込まれたようなものだった。だいたいなぜ小宮が私を誘ったのかよくわからなかった。気付いたら女と二人っきりになっている。ピンク色の薄い口紅をつけて目の前に座っているこの女は私といったいなにがしたいんだろう。なにがしたいんだろう・・・と私は一生懸命に考えていた。具体的には何も話すこともすることもできず、私は黙ってうつむいているしかなかった。黙っていたら、小宮と、顔を赤らめた裕子が帰ってきた。(続く)
初恋(5) 1999/6/25 (1,2,3,4)はこちら
 黙っていたら、小宮と、顔を赤らめた裕子が帰ってきた。美加が窓の外を眺めると、いつからだろうか、パトライトの回転が消えていた。この回転が消えるとだいたい一時間後くらいに美加の母親が帰ってくる。小宮と私は急いで帰り支度をはじめた。裕子は小宮といっしょに帰りたがったが、小宮はそれを拒んだ。なぜなら、小宮は今日、私に話があったのだ。小宮は本当に凄い中一だった。なんの話があるのかは知らないが、とにかく私との話を有利に進めるために、私にこうして女をあてがったのだ。普通の男が、大人になってサラリーマンとしてようやく覚えるようなことを、こいつは中一にして既に実践していた。接待された側の私など、女を前にして何をしていいのかわからないような年に・・・だ。しかも小宮はちゃっかり隣りの女に手をだし、おいしいところを味わっている。こんな奴は他に知らなかった。
黙っていたら、小宮と、顔を赤らめた裕子が帰ってきた。美加が窓の外を眺めると、いつからだろうか、パトライトの回転が消えていた。この回転が消えるとだいたい一時間後くらいに美加の母親が帰ってくる。小宮と私は急いで帰り支度をはじめた。裕子は小宮といっしょに帰りたがったが、小宮はそれを拒んだ。なぜなら、小宮は今日、私に話があったのだ。小宮は本当に凄い中一だった。なんの話があるのかは知らないが、とにかく私との話を有利に進めるために、私にこうして女をあてがったのだ。普通の男が、大人になってサラリーマンとしてようやく覚えるようなことを、こいつは中一にして既に実践していた。接待された側の私など、女を前にして何をしていいのかわからないような年に・・・だ。しかも小宮はちゃっかり隣りの女に手をだし、おいしいところを味わっている。こんな奴は他に知らなかった。
小宮は隣りの学区の出身で、小学校は別だった。しかし私の住むこの街の小学生や中学生で、小宮のことを知らない者はいなかった。合同体育祭というものがあり、年に一度、町内の3つの小学校の代表が集まり学校対抗で競技をする。当時から身長が175近くあり、がっしりした体格の小宮は体力においても他の小学生を圧倒的に凌駕していた。「旗取り」では小宮の周りに群がる小学生どもに対し、まるで世紀末覇王のようにたちはだかり、旗を取ろうと棒をよじ登るやつらの首根っこといわず、パンツといわずむんずと掴み取って方々へ投げ散らしていた。「学校別対抗リレー」ではアンカーだったが、1/3周ほどのリードを奪われて小宮はアンカーとしてバトンを受け取ったにもかかわらず、一気に抜きかえし逆に1/4周程のリードを残して優勝した。要するに、ヒーローだった。友人によると小宮は無口だったらしい。無口というより、彼が口を開いたところを見た人は誰もいなかったということだ。中学に入ってから彼は話をするようになった。なぜかはわからない。その小宮が今日は私に話があるという。
「美加と・・・した?」
「何をだよ。」
「キスだよ。キス。」
「するわけねえだろ。」
「ばかだなあ・・・しとけよ。」
「・・・・・・。」
「でもなあ、おい。」
「なんだよ。」
「お前、美子のこと・・・好きなんだろ。」
「・・・・・・。」
「あのな、いい方法があるんだ。」
小宮にいい方法があると言われると、それは本当にいい方法であるような気がした。
「今度、秋に合唱コンクールってのがあるだろ、兄貴から聞いて知っているんだけどな・・・・・・。」
小宮の口から合唱コンクールなんていう言葉が飛び出て少々妙だった。
「あれでな・・・・・・俺にドラムたたかせてくれよ。」 (続く)
初恋(6) 1999/6/25 (1,2,3,4,5)はこちら
 「あれでな・・・・・・俺にドラムたたかせてくれよ。」
「あれでな・・・・・・俺にドラムたたかせてくれよ。」
小宮の計画は、こういうものだった。文化の日近くに行われる校内合唱コンクールの伴奏をバンドでやってみようというのだ。エレキギターさえ持ちもまなきゃ大丈夫だぜ、と小宮はいう。ピアノを美子にやらせて、お前はギターで、エレクトーンをだれか他の女の子にやらせてベースラインをつけて、俺がドラムだ、立派なバンドのできあがりだ・・・と小宮は興奮ぎみに構想を語った。小宮の兄貴は名古屋のライブハウスでドラムを叩いていた。奴の家のガレージにはドラムセットが常設してあり、どうせ、兄貴の影響をうけて、女に声援を飛ばされかっこよくもてもての兄を見て自分もそうなりたいと思ったに違いなかった。そこで、クラスで唯一、コードというものを知っていて、ストロークとアルペジオができて、音叉を使ってギターのチューニングもなんなくできたこの私に話を持ち掛け、思いを一気に具体化しようとしたのであった。
美子をピアノにするから・・・小宮の一言で私は舞い上がっていた。
あの子のピアノで、自分がギターを弾く、その状況を想像するだけで私の胸は充分に苦しかった。信じられないことだが、当時の私はそういう意味では本当に純粋だった。例えばこんなことが当時の私の頭を支配していた。「夕日ケ丘の総理大臣」というTVドラマがヒットしていた。岡田奈々の女教師ぶりにあこがれたりしたがその話の内容はともかく、テーマソングの歌詞に私はひかれていた。「手のひらに澄んだ水をすくって、お前の喉に流し込む、そんな不器用で、強くやさしい、つながりはないものか・・・。」私はなんどもなんども、美子の喉に澄んだ水を流し込む様を想像した。美子はその真っ白で汚れのない顔を私に向け、うす赤い唇をそっと開く。私はそっとその口の中に澄んだ水を注ぎ込む。その瞬間、美子は私の一部になっていた。澄んだ水は美子のすべてを溶かし、私は美子のすべてを手にいれることができた。それが私のしたいことのすべてだった。しかし今になって考えると、この行為は究極のエロティシズムであったかもしれない。大人になってロマン・ポランスキーの「テス」という映画を見た。確かナスターシャ・キンスキーが演じる美しい田舎娘が貴族の青年に弄ばれるえぐい映画だったと思うが、唯一はっきり覚えているのはその貴族が娘の口に、一つづつさくらんぼを食べさせるシーンがある。貴族の青年のなすがままに、さくらんぼを口に含まされる娘。その時娘は貴族に支配され、犯され、貴族とは生きる世界が違う田舎娘であることを自覚させられるのだ。このようにエロティシズムは純粋であればあるほど刺激的だ。この映画のワンシーンと同じようなことを私はひたすら想像していた。澄んだ水を美子ののどに流し込む自分を想像して、私は自慰にふけった。さらに想像の中で彼女が弾くピアノが自分のギターとハーモニーを作り出し一つになり溶けていく。その様を想像することは、彼女の肉体を想像することと同じだった。本来音楽には、不埒なものを含めて、人の様々な想像を喚起する力がある。少年のころの私は、今よりももっと敏感に音楽の本質を感じていた。もう、なにがなんだかわからなくなってしまっていた。ただ、小宮の「美子をピアノに・・・。」という言葉に興奮していた。
恵にしかけたいたずらは簡単だった。一片だけ恋愛の詩を書いたのだ。その恋愛の対象が美子を指していることは明確だった。本当にちょっとしたいたずらだった。いたずらになるかどうかもわからなかった。しかし恵は完全に私に対して心を閉ざした。もう二度と会話をすることはなかった。彼女は独りになった。そして学校にも来なくなった。
ひぐらしがうるさくなると、夏休みになった。私は夏休みが大嫌いだった。長すぎるのだ。友人に会えない一ヶ月半をいったいどうやって過ごせばいいのだろう。ありあまる時間と夏の暑さは少年であった私の頭をゆるやかに破壊していた。休みのあいだ中美子への思いと、小宮の計画の真偽に対する不安が私の中で渦を巻いて、胸をしめつけていた。照り付ける日差しの中、私はよくぶらぶらとあてもない散歩に出かけた。5Km 6Kmひたすら歩き続ける。隣りの学区までふらふらするのは日常だった。しかし、この散歩には目的があった。美子とどこかで出会わないかという期待を秘めていた。しかし、だれひとりとして出会うことはなかった。少年時代は恐らく人生でもっとも孤独な時ではないかと思う。私は誰にも必要とされず、意志を実現する力も持たない愚かな一つの自意識だった。孤独な自意識は人から言葉を奪っていく。私はどんどん人と話をすることが苦手になっていった。外に対する言葉を失った人間はその分内に対する言葉を使い自分を責め続ける。思春期の始まりだった。ひたすら自分を責め、もうだめだ、死んでしまう・・・。と思いはじめたとき、涼しい風が吹き始め、過ぎ行く夏は同時に苦しかった夏休みの終わりを告げた。
新学期に最初に見た美子はそれまでになく美しかった。まっすぐな髪の毛は休みの間に更に伸びて、女性らしさがいっそう増していた。夏だというのに一切日焼けをしていない美子の肌は他の女生徒達と比べても一層白く美しかった。もう、声をかけることはできなくなっていた。美子に会えなかった一ヶ月半の間に、私の思いは極限にまで達していた。好きだ・・・。この一言が言えれば楽になれる。しかしそれは不可能だった。私はひたすら秋の合唱コンクールの時期が来るのを待ち続けた。何がなんでも小宮と協力して、バンド結成の計画を実現しなくてはならない。それだけが私のすべてだった。しかし小宮はその後、計画について私に告げることは一度としてなかった。だからわたしもまた、小宮とその計画について語るのを避けた。それほど大切な計画だった。日ごとに神々しく見え始めた美子を痛切に意識しながら、私は本当に切ない思いで秋の訪れを待った。
ところで、「青春」とはなにか、考えたことはあるだろうか。
私は、とても明確に「青春」を定義ずけることができる。(続く)
初恋(7) 1999/7/11 (1,2,3,4,5,6)はこちら
 私は、とても明確に「青春」を定義ずけることができる。
私は、とても明確に「青春」を定義ずけることができる。
私にとって青春とは、「傷つく時代」だ。美子との恋愛によって始まった私の思春期への入り口が、私の青春の始まりだった。私はあらゆる言葉に傷ついた。誉められて傷つき、けなされて傷つき、ばかにされて傷つき、もちあげられて傷ついた。要するにどんなことを言われたとしても傷つく可能性があった。だからあらゆる人達を憎み始めた。先生、友人、両親、親戚・・・。すべての人達が絶妙のタイミングで私の心にナイフを入れようとする。私は必死にそれを防ぐ。或る日、一番簡単明瞭な防御手段は、しゃべらないことではないかと思い、次の日から失語症に陥ったこともある。しかし、言葉を失ったおかげで他人から防御することは容易になったが、今度は完全な孤独に陥ることとなった。そんなことの繰り返しだった。人はそうして自意識の葛藤をくりかえして、少しずつ他人との距離を保てるようになる。そして或る日気付くのだ。
「いつまでも傷ついちゃいられねえぞ、まったく・・・。」
私の青春時代の終わりは、この確信に至り、我慢することを少しだけ覚えた時だった。25歳の夏だった。いっしょにテニスをした中で飛び切りの美女がいたが、いつもなら飛びついていたところを、まあこの女は先輩に譲っておこう、とちょっとだけ我慢をした時私の青春時代は終わった。我慢ができる心は傷つかない、ゆとりのある心は傷つかないものだ。青春はその時に終わる。そして大人からみれば、青春なんてまったくくだらないものだ。なんせ何もしない。なぜなら何かすると傷つくからだ。ろくすっぽ意志を持たず、言い訳がやたら多く、実行力も実力もないくせに自慢が多い、それが青春期の人間に多い特徴だ。なぜならそれは傷つきたくないからだ。自分を等身大以上に見せること、そしてそう思い込むことに至力を尽し、野獣のようにひたすら女を追い求める青春期の人間。それは社交心、公共心、愛国心、愛、そういったすべての価値のある人の営みを阻害する。孤独はそうした排他的な心から生まれているのだということに気付き、いつまでも傷ついちゃいられねえぞと開き直って立ち上がった時、人は青春時代と決別することができる。ようするに、青春などというものとは、早くきっぱりと縁を切ってしまうことだ。引きずってはいけない。生涯青春なんて言うおやじがいるが、まあどうみても歴戦のおやじが言っているからいいけれど、本来青春は辛くて苦しいものなのだ。生涯背負わされたら人生真っ暗だ、きっと。
この話は、14歳で始まった私の青春時代の入り口の出来事だ。火の出るような思いが続いた日の出来事を大人になった今冷静に描いているつもりだが、本当はこんなにわかり易く説明のつくものではなかったような気がする。皮膚を切って血が吹き出している人間の痛みをどんなに冷静な筆致で描いても、その痛みは伝わらないだろう、そんなことと同じだと思う。しかしだからこそ書きたくなった。いったい、どんな物語が書けるのかな・・・。
秋の訪れは、小宮のドラムセットと共にやってきた。(続く)
初恋(8) 2000/2/10 (1,2,3,4,5,6,7)はこちら この話、久しぶりですが、やっぱり最後まで書かないと・・・
 秋の訪れは、小宮のドラムセットと共にやってきた。
秋の訪れは、小宮のドラムセットと共にやってきた。
小宮は兄貴から借りたドラムセットを音楽室の奥に設置していた。友人の安道がその設置を手伝っていた。楽器というのはやはり一つの魔力を持っている。音楽室に転がっている古ぼけたガットギターにしたって眩しい光を放っているのだ。それがおおがかりなドラムセットとなればなおさらだった。安道は目を輝かせながらドラムセットを設置していた。小宮が私に話かけた。
「じゃあ、明日朝早くから練習するか、ドラム、うるせえからな、中止になったら面白くねえし。」
小宮は慎重だった。そりゃそうだ、先生達が登校する前に練習すれば文句を言われることは無いに決まっている。
次の朝、メンバーが集まった。フォーク・ギターが私、小宮がドラム、副級長の女の子がエレクトーン、安道はなぜか見学に来て、ピアノは美子だった。課題曲と自由曲があったが今では口に出すのも恥ずかしいような曲だ。当然、練習自体に大きな意味があった。この編成だ、当然PAなんかないし全員が音を出した瞬間小宮のドラムの音にすべてがかき消されて、なにも聞こえない状態で皆が必死に演奏した。しかし、この時おそらく全員が興奮していた。ドラムのサウンドの迫力は今まで体験したことがないものだったし、なによりこの時味わったものはある種の恍惚感で、それはある作品を生み出した時に味わう、人間の本質的な衝動であったに違いない。そして美子が私に語りかけた。
「ねえ、私、おかしかったかなあ。」
おかしかったもなにも、美子のピアノはなにも聞こえなかった。小宮のドラムのせいで自分の音すら聞こえていないのだ。
「もうちょっと大きな音で弾いた方がいいと思うよ。」 私はばかなアドバイスをした。しかし本当に夢にまで見た美子との会話が正夢となった。
メンバーの中で私が最も音楽に長けているとされていたが、私はコードをちょっと知っていただけで、実は本当にこの中で音楽がわかっていたのは私ではなくエレクトーンの副級長だったと思う。彼女はリズムが走りぎみの小宮に対し「ねえ、合わせることをちょっと考えようよ。」といってみたり、「小宮君音大きくない?」なんてやんわりと牽制を加えていた。小宮はなかなか言うことをきかなかったがそれでもいつしかいくらかはマシになっていった。
私は美子と同じ空気を吸っていることに心から満足していた。こちらから話かけることはできなかった。なぜなら今度こちらから話かけると、それはすべて愛の告白になってしまいそうだったからだ。私が美子に話したいことは半年前から一言だけだった。「好きだ。」この一言だけ言えばそれで終わりなのだ。しかし、絶対に口にすることはできなかった。私は美子からの質問を待ち続けた。美子から質問がきた時だけ私は彼女と話ができる。そんな関係にいながら、私は充分に幸福だった。
ある日、小宮が機転を利かせて、私と美子だけを音楽室に残して練習を切り上げてしまった。秋風が身を切る音楽室の中、私は美子と二人きりとなった。美子も音楽室を出ようとはしなかった。私からの言葉をなにか待っていたに違いなかった。しかしやはり私は何も語りかけることができなかった。沈黙が二人を支配した。どうすればいいんだろう・・・沈黙にたえきれなくなり土壇場で私の口を突いて出てきた言葉はピアノを手持ち無沙汰につま弾いていた美子にとっても意外なものであったに違いない。
「ぼくはーよびかけはしなーいー・・・」
それは、課題曲の歌だった。私はどうしようもなくなり、無言で固くなった唇をひんまげてなんと課題曲を歌ってしまったのだ。瞬間、えらく後悔した。しかしその時美子はやさしく、私といっしょにその歌を唄ってくれた。そして土壇場で私は美子に救われたばかりか、今度は至福の喜びを味わうこととなった。寒い音楽室で二人は課題曲を唄った。私は熱唱した。すべてをそこに込めたかったのだ。美子は驚いていたが、かわいらしい歌声を私の変声期中のだみ声の上に重ね合せた。私は歌いながら、どんどんのぼりつめていった。課題曲の後は自由曲で、そのあとはアリスやさだまさしのヒット曲で・・・なんでもよかった。美子はわからないところはハミングで、そしてわたしはわかるところにはギターをつけて熱唱した。いっしょに歌を唄うだけだった。しかしそこに私のすべてがあった。あとは美子を抱きしめたいという衝動を抑えるのに必死だった。愛について唄った歌をラブ・ソングと言うが私は違うと思う。愛する者に唄った歌はすべて、ラブ・ソングなのだ。
コンクールは優勝した。そりゃ、気迫と練習量が他のクラスとは段違いだったから当たり前だった。指揮者の級長は大喜びしたが私は美子とのひとときがもう過ごせなくなることにひたすら失望していた。小宮はバンドを組もうとか言い出したが、2度とドラムといっしょにやる気にはなれなかった。やっぱり、うるさいのだ。
コンクールが終わると冬が訪れた。美子の姿が見えなくなる大嫌いな冬休みが明け、3学期が訪れると、美子は学校に来なくなった。(続く)
初恋(9) 2000/2/10 (1,2,3,4,5,6,7,8)はこちら
 コンクールが終わると冬が訪れた。美子の姿が見えなくなる大嫌いな冬休みが明け、3学期が訪れると、美子は学校に来なくなった。
コンクールが終わると冬が訪れた。美子の姿が見えなくなる大嫌いな冬休みが明け、3学期が訪れると、美子は学校に来なくなった。
学校に来なくなった理由は簡単だった。美子は盲腸炎にかかったのだった。長期の入院となったのである。うわさでは3学期はほとんど登校しないだろうということだった。私は学校にやってくる意味をすべて奪われ、無口の上に不機嫌が重なって友人からもずいぶん嫌われた。
ただひとり、小宮だけが私を察した様だった。
「おい、お見舞行こうか。美子の・・・・。」
小宮の一言を、むろん私が断ろうはずも無かった。思えばバンドをやろうといったのも、音楽室で二人きりになったのも、そして今回、お見舞い行こうと手を差し伸べてくれたのも小宮だった。いったいこいつはどうしてこんなに大人なんだろうと考えながらも、小宮の好意に甘えるしか私には手が残されていなかった。
平日の夕方、私は部活動をさぼって小宮と近所の公園で待ち合わせをした。夕日が美しい冬の一日だった。ここから自転車で、美子のいる病院へいく。私は再び、どうしようもなくせつない思いでいっぱいとなった。もし二人きりになれたなら、もしなれたなら、今度こそ「好きだ。」と言ってみよう・・・そう心に誓ったのはこれで一万回目であったが、今日はその決意にも価値があった。なんせ、今から会えるのだから。小宮はなにも言わなかった。病院につくと、玄関で二人は立ち尽くし、小宮が私に声をかけた。
「なあ、俺、ここにいるからよう、お前一人でいってこいよ。美子ぜったいお前のこと好きだぜ。」
ばかやろう何言ってんだいっしょに来いよ、とやりあってみたが小宮は最初からこうするつもりいたのだ。私は押し切られてひとりで病院の玄関を空けることとなった。病院内に充満しているナフタレンのにおいは外界を隔絶した空間を創り出したと同時に、私の中に流れる時間の流れを変えた。俺は、何をしているのだ。ここは、どこなのだ。小宮と、そして美子との様々な出来事とは無関係に、今、私はここに存在していた。私は今、美子に会いに行かなくてはならない。それが、私のすべてだった。私は受付で部屋を聞き、夢遊病者のように美子に導かれるまま、美子のいる病室を目指していた。美子にあって私は何をするべきか、それは全くわからなかった。ただ、「会う」ということだけが絶体だった。私には生活のすべてが「絶体」であるように思えてならなかった。美子は私からすべての選択肢を奪った。美子が導くまま、私は生きるしかすべがなかった。
年と共に人は少しずつ何かを失い、絶体であることができなくなる。幼かったころの自分を振り替えると、顔から火が出るようなこっぱずかしい思い出と共に、常に絶体であり続けた自分にどこかあこがれに似た感情を抱くことがある。過去の自分にあこがれるとは妙なことだが、振り返った先、そこにはあったはずの何かがまだ失われていない自分が存在しているのだ。わたしは「あのころ」を振り替える時、湧き出てくるイメージはあのナフタレンの臭いと病院の廊下である。あの時、私は見えない美子に導かれ、ふらふらと病院の廊下を歩いた。導かれるまま夢遊病者のように美子を求めたことが、私が絶体であったことを確証する。何も失われていない私の若い命は、更に絶体になるために一つの命を心から求めた。それが初恋だった。
春が訪れて中学二年になると、美子とはクラスが別になった。その後も美子と顔をあわせることがあったが、お互い話をすることは一度もなかった。しかし、ただ一度だけ、美子が友人といっしょに快活に笑っているのを見た。その時、私の初恋は終わった。快活に笑う美子は私の知っている美子ではなかった。もう彼女となにかを共有することはできないと思った。別れではなかった。終わったのだ。私は美子を失い、あてもなく歩くことしかできないまま、青春の森へと深く迷い込んでいった。(終わり)