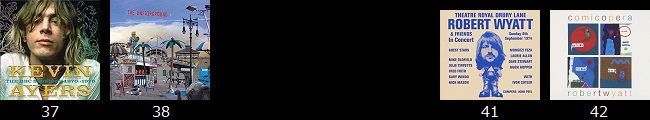
|
31 |
JOY OF A TOY |
1969 |
★★★ |
|
1st Album 1枚だけで Soft Machine を辞めてしまった Kevin Ayers さんのソロ第1作.バックに Mike Ratledge ・ Robert Wyatt ・ Hugh Hopper の Soft Machine の各氏と David Bedford 氏が参加しています.アルバム・タイトルの "Joy of a Toy" ("Soft Machine" が女体を意味するスラングであることを考えると,非常に意味深なタイトルではありますが)とゆ〜のは, Soft Machine のファーストに収録されていた何とも妙な魅力をもったインスト・ナンバーですが,このアルバムには同曲は収録されておらず,続編(?) "Joy of a Toy Continued" が収録されているのみで,それも全く違ったナンバーであるのは流石ですが,一部ガッカリ.... (どっちなんだ?).名曲 "Lady Rachel" が収録されているので,この人の作品の中では比較的有名な方らしいです. Soft Machine のファースト・アルバムでは,この人ほとんどバッキングに徹していて,リード・ヴォーカルはほとんど Robert Wyatt 氏が取っていたのですが,このアルバムを聴いてみて納得.と言っても,別にこの人の歌が下手だとか声が悪いとかっていうことではなく,むしろ渋くていい声なのですが,あのアルバムのサウンドには Robert Wyatt 氏の少々頼りなげの声の方がマッチしていたと思うのです.でもこの人がリードをとったバージョンも聴いてみたかった気もします. |
|||
|
32 |
SHOOTING AT THE MOON |
1970 |
★★★★ |
| 今回はソロではなく,バック・バンド The Whole World を率いての意欲作.パーソネルは David Bedford (Kbd) ・ Lol Coxhill (Sax) ・ Mixk Fincher (Ds) ・ Mike Oldfield (G/B/Vo) の各氏ですが, Kevin さんは曲によって Guitar と Bass を Mike さんと交代しながら演ってます.後にマルチプレイヤーとして活躍された,若き Mike Oldfield さんとの共演が楽しめます. | |||
|
33 |
Whatevershebringswesing |
1971 |
★★★ |
| 再びソロに戻っての3作目.バックを David Bedford (Kbd) ・ Mike Oldfield (G/B) ・ Dave Dufort (Ds) 他の各氏が勤めている他, Robert Wyatt さんが1曲のみ表題曲の "whatevershebringswesing" に Backing Vocal で参加されているのが嬉しかったのです. | |||
|
34 |
BANANAMOUR |
1973 |
★★★ |
|
このアルバム昔,『いとしのバナナ』(笑)とかって日本語のタイトルがついていたらしいですが,何とかならんかったのかしら?このセンス.この作品では Soft Machine 脱退後かなりの年月を経過していることもあって,内容的にはかなり独自の世界を構築している訳なのですが, Mike Ratledge さんはしっかりサポートに参加しております. Soft Machine では Robert Wyatt 氏のバックに徹していてほとんど表面に現れなかった彼のヴォーカルは,よく言えば個性的,悪く言えば好き嫌いの分かれる声だと思いますが,私は結構好きです. |
|||
|
35 |
The Confession of Dr. Dream |
1974 |
★★★★ |
|
Soft Machine にはまっていた高校生の頃,初めてリアルタイムで聴いた Kevin Ayers さんのソロ・アルバム.友人がカナダに行った時に買ってきたのを聴かせてもらいました.初めて聴く彼のヴォーカルは,やはり最初ちょっと違和感ありましたが,すぐに慣れたというか好きになりました. Soft Machine 時代の傑作 "Why Are We Sleeping?" をアレンジした "It Begins With A Blessing / Once I Awakened / But It Ends With A Curse"(再発 CD 買ったら,『往きはよいよい帰りは怖いのバラード』なんて日本語タイトルがついてました)が入っていることもあって,この方の初期作品の中では一番好きなアルバムです. |
|||
|
36 |
JUNE 1, 1974 |
1974 |
★★★★★ |
|
元 Soft Machine,Roxy Music,Velvet Undergrounnd という3大変態バンドの脱退組が4人も集まったことから,『悪魔の申し子たち』なんて邦題がつけられ,そのタイトルだけが何故か一人歩きしてしまったという希有な例.このアルバムのことな〜んにも知らない人でも,『悪魔の申し子たち』ってタイトルもしくはフレーズはどこかで聞いたって人が多いと思います.アナログ・ディスクのΑ面には, Eno 2曲, Cale 1曲, Nico 1曲がバランス良く配置され,おどろおどろしい世界を構築していたのに対し,Β面は Ayers 一色,このメンツの中では変に明るく健康的なイメージを与えているという不思議と言えば不思議なアルバム. Special Guest として, Mike Oldfield, Robert Wyatt のお二方の名前がクレジットされております. |
|||
| 37 |
Sweet Deceiver |
1975 |
★★★ |
|
初期 Soft Machine の無機質とも感じられる音が大好きな私にとっては,「嘘?」と思ってしまったすご〜くポップなメロディがつまったアルバム.この人確かにメロディ・メイカ〜としての才能ある人だとは思いますが.違う.... ああ,1975年か〜? やっぱり Rock 終焉期の作品ですね〜? キレイすぎます.何となく興味なくなっちゃって,この後のアルバムはほとんど聴いてません. |
|||
|
38 |
Alive in California |
2004 |
★★★ |
|
という訳で, '80 〜 '90 年代のこの人の作品ってあまりというかほとんど聴いてなかったんですが,世紀が変わってからこのアルバム見つけて,すご〜く懐かしい気分がして買ってみました.こ〜ゆ〜タイトルついてますが,音源は '93 年ロサンゼルス(ソロ)と '98 ・ '00 ロサンゼルス・サンフランシスコ(バンド)のコンサートを収録したものらしいです.やっぱり『軽い』感じは否めませんが,ソロ初期の曲も収録されているので, '70 年代にひたっている Della としては,嬉しいリリースでした. |
|||
|
39 |
THE BBC SESSIONS 1970 - 1976 |
2005 |
★★★★ |
|
やっぱりこの時代ですよね? 何もかもが渾沌として美しかった1970年代前半の貴重な音の記録.本当に面白い時代だったんですよ.... 特に1970〜72年の音源を収録した Disc1 の猥雑さは格別です. |
|||
|
40 |
THE UNFAIRGROUND |
2007 |
★★★★ |
|
1992年の "Still Life with Guitar" 以来15年ぶりとなる,ソロ・アルバム15作目だそ〜ですが,見事に軽いです.ここまで書いていて,初期 Soft Machine(特に1枚目)のサウンドの魅力って,『渾沌とした軽さ』だったのでは,とふと思いました.このアルバムでも,随所に初期 Soft Machine を髣髴とさせるフレーズ等が随所に現われていて,思わず懐かしさを感じてしまいました.年齢だね. |
|||
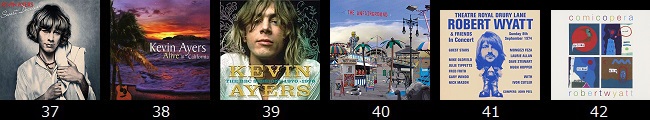
|
41 |
THEATLE ROYAL DRURY LANE |
2005 |
★★★★★ |
|
まあよくもこんな貴重な音源を30年以上も隠しておいたもんだね....というのが正直な感想です.タイトル通りの内容ですが,ゲストがすごい, Mike Oldfield ・ Julie Tippetts ・ Fred Frith ・ Gary Windo ・ Nick Mason ・ Mongezi Feza ・ Laurie Allen ・ Dave Stewart ・ Hugh Hopper ・ Ivor Cutler ・ John Peel .... もちろんこの時点ですでに Robert 氏は下半身不随になっていたので, Soft Machine 時代の華麗なドラミングは聴けないのですが,この人の声ってやっぱりヘンな魅力があります.バックを固めるミュージシャンたちのプレイも壮絶.もっとも,リアルタイムでリリースされていたら,他の Soft Machine 関連の作品同様,こんなに話題にはならなかったかも.... だったとしたらやはり30年待ったのは正解ですか? |
|||
|
42 |
comicoperarobertwyatt |
2007 |
★★★★ |
|
こちらは Robert Wyatt 氏の4年ぶりのソロ・アルバム.15年ぶりの Kevin Ayers 氏といい,この人といい,元 Soft Machine のベテランの創作意欲が嬉しい2007年末でした.21世紀に入ってから再評価著しい方々ですが,聴く方が歳とっているにも関わらず,この人たちって才能の衰えを感じさせない.やっぱり凄い人たちだと思うよ.作品は3部作のオペラ仕立て.不協和音も健在です(笑). |
|||