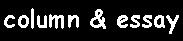
 『インディーズ世代の文化』
text by yasuhiko
ある日、ふとTVの深夜番組を見ているとインディーズ・ミュージックのランキングを
並べて紹介するといった内容の音楽番組がはじまった。最近のミュージック・シーンとい
うものにすっかり疎くなっていた僕は、もうエスタブリッシュトされたメジャーの音楽に
何の疑問も感じなくなって、ずいぶん経つ気がする。ただドラマの主題歌やタイアップで
何百万枚も売れる日本のアーティストには、そのセールスが示すほど興味が持てないとい
った程度だった。
ひと昔前の、音楽雑誌のレビューを見てCDを聴き漁ったり、ライブ・ハウスに通って
辿り着くお気に入りの音楽と違って、今は情報のスピードも量も違うのだから、一口にイ
ンディーズ・ミュージックといっても取り巻く状況は変わっていて当たり前だろうなと思
いながらも、期待することもなくその番組を見ていた。
暫く経つと僕は、その番組がおもしろくて仕方なくなっていた。
ほんの数十秒のアーティストの紹介で流れてくる音楽と映像に、それがどんなジャンルで
あっても、すごく興味を持ったし、自然と顔がにやけてくるのだ。
その理由の一つは、どのインディーズ・アーティストにも、どこにそんな製作費がある
んだというくらい立派なプロモーション・ビデオなり、ライブ映像が付いていて、今のこ
のマーケットが充実していることが示されていたし、それを自分が意外なほどすんなり、
嫌悪感もなく受け止めていたからだと思う。
音楽以外の創作も含めて、僕はインディーズの活動というものにどこか自己満足と、近
寄り難いプライドとか、いじけた暗いものを自然と感じていたはずだった。あるいは、ビ
ジネスとして成立する創作への隔てられた壁だったかもしれない。プロとアマの違いみた
いなつまらないこだわりみたいなもの。
そして、もう一つ。TVの画面に写し出された地方都市の地下街の映像を見て、僕は吹
き出しそうになった。ストリート・ミュージシャンの活動を追ったレポートは所狭しとひ
しめきあって場所を確保し、歌っている人々、ダンス、スケートボードなどなど、すごい
賑わいである。そのパフォーマンスを囲んで盛り上がる人々の楽しそうな顔はインディー
ズ世代ともいえるこだわりのない人々のそれだった。世代というより文化を紡ぎ出す人々
というべきだろうか。
もともと、創作する人間は自分がいいと思えるものしか創っていないはずである。それ
『インディーズ世代の文化』
text by yasuhiko
ある日、ふとTVの深夜番組を見ているとインディーズ・ミュージックのランキングを
並べて紹介するといった内容の音楽番組がはじまった。最近のミュージック・シーンとい
うものにすっかり疎くなっていた僕は、もうエスタブリッシュトされたメジャーの音楽に
何の疑問も感じなくなって、ずいぶん経つ気がする。ただドラマの主題歌やタイアップで
何百万枚も売れる日本のアーティストには、そのセールスが示すほど興味が持てないとい
った程度だった。
ひと昔前の、音楽雑誌のレビューを見てCDを聴き漁ったり、ライブ・ハウスに通って
辿り着くお気に入りの音楽と違って、今は情報のスピードも量も違うのだから、一口にイ
ンディーズ・ミュージックといっても取り巻く状況は変わっていて当たり前だろうなと思
いながらも、期待することもなくその番組を見ていた。
暫く経つと僕は、その番組がおもしろくて仕方なくなっていた。
ほんの数十秒のアーティストの紹介で流れてくる音楽と映像に、それがどんなジャンルで
あっても、すごく興味を持ったし、自然と顔がにやけてくるのだ。
その理由の一つは、どのインディーズ・アーティストにも、どこにそんな製作費がある
んだというくらい立派なプロモーション・ビデオなり、ライブ映像が付いていて、今のこ
のマーケットが充実していることが示されていたし、それを自分が意外なほどすんなり、
嫌悪感もなく受け止めていたからだと思う。
音楽以外の創作も含めて、僕はインディーズの活動というものにどこか自己満足と、近
寄り難いプライドとか、いじけた暗いものを自然と感じていたはずだった。あるいは、ビ
ジネスとして成立する創作への隔てられた壁だったかもしれない。プロとアマの違いみた
いなつまらないこだわりみたいなもの。
そして、もう一つ。TVの画面に写し出された地方都市の地下街の映像を見て、僕は吹
き出しそうになった。ストリート・ミュージシャンの活動を追ったレポートは所狭しとひ
しめきあって場所を確保し、歌っている人々、ダンス、スケートボードなどなど、すごい
賑わいである。そのパフォーマンスを囲んで盛り上がる人々の楽しそうな顔はインディー
ズ世代ともいえるこだわりのない人々のそれだった。世代というより文化を紡ぎ出す人々
というべきだろうか。
もともと、創作する人間は自分がいいと思えるものしか創っていないはずである。それ

 
|
|