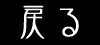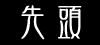| おねだり潤ちゃん |
|
「今日はここで終わりにしようか。」 「はい。」 先程まで二人で顔を寄せ合って読んでいた点字本を閉じた。 両手を上にあげて軽く伸びをしてみると硬直していた全身の筋肉が一気に解されていく。 身体はずっと同じ体勢、しかも手は常に本の上という肉体的に過酷な条件下で本を読んでいるのだから当然だ。 さすがに潤ちゃんと一緒に読む以上、いつものように寝そべって本を読むと言う訳にはいかない。 そう、俺は少しでも潤ちゃんと一緒のモノを共有できるように点字を勉強することにしたのだ。 普通のカップルならテレビを見たり映画を見たりゲームをしたり、部屋で一緒に過ごす方法は沢山あるが、 目の見えない潤ちゃんの場合は出来ることがかなり制限されてしまう。 だったら俺の方が潤ちゃんに合わせてあげることで、 お互いの時間を少しでも共有できるようにすればいいのではないか、そう思ったことが切っ掛け。 以降、点字の勉強の一環として潤ちゃんと一緒に点字本を読む時間を取るようになったのである。 だからと言って簡単に慣れるものではない。 点字本を読み始めた当初に比べればずっと楽に読めるようになったのは実感できるが 今でも潤ちゃんに教えられながらのたどたどしい読書になってしまう。 「ごめんね、俺が読むのが遅くて。 潤ちゃん一人ならとっくに読んでいるんだろうけど。」 「いえ、そんな。 真神さんと一緒に読む方が楽しいですから気にしないでください。」 俺のペースではかえって潤ちゃんの読書の妨げになってしまっているのではないかと謝罪するが 彼女はそれを否定する言葉と共に満面の笑顔を返してくれた。 その笑顔に嘘はないと思う。 ただ、確実に足を引っ張っていることが分かる自分にはやはり心苦しい。 どうしてもネガティブな感情を抱いてしまう。 「もう少し早く読めるように頑張って勉強するよ。」 「はい……それはそれで嬉しいのですけど……」 「けど?」 「真神さんの先生ができなくなってしまうのはちょっと寂しいです。」 潤ちゃんは頬を少し赤く染めながら素直な心の内を打ち明けた。 おそらく今の彼女は『教えることの面白さ』を身をもって体験しているのであろう。 実際、潤ちゃんの教え方は優しくて丁寧だ。 教職を目指したら生徒に愛される立派な先生になったに違いない。 教壇に立って熱弁を振るう潤ちゃんの姿を想像してみる……うん、かなり似合っていると思う。 まあ、潤ちゃんが楽しいのであれば俺ももう少し出来の悪い生徒でいようかな、そんなことを考えた。 「……真神さん?」 「いや、何でもないよ。 学校の先生になった潤ちゃんを想像したら似合ってるなあと思っただけ。」 「わ、私には、無理ですよ……」 返事がないのを不思議に思った潤ちゃんが俺の名前を紡いだので その沈黙の間に想像していたことを包み隠さず教えてあげた。 彼女は赤く染まった頬を更に赤くし、開いた両手をパタパタと軽く横に振りながら反論する。 「大丈夫だよ、潤ちゃんなら。 潤ちゃんが先生だったら俺はずっと生徒でいたいくらいだよ。」 「……そ、そ、そんな……」 今度はパタパタと振っていた両手が膝の上に移動し、その膝を掴むような体勢のまま顔を俯かせてしまった。 そんな一つ一つの反応が可愛いらしい。 「教え方は丁寧だし、優しいし、それに… 「え、えっと、それよりも那波さんと透矢さんはどうなってしまうのでしょう!!」 咄嗟の照れ隠しなのか、俺の話を遮って現在読んでいる本の内容に話題を切り替えてきた。 これ以上続けると逆に可愛そうかなと思った俺はその話に合わせてあげることにした。 「うーん、どうなるんだろうね。 しかしこの『すいげつ』は話が難しくて……先が読めないよ。」 可愛らしい女の子の絵とこれまた可愛らしいフォントを使ったタイトルが表紙に描かれた『すいげつ』という本は その可愛らしさからは想像できないほどの難解な内容だったため、いつもより増して本を読む速度が遅かった。 元々は絵本だったという謳い文句もあり簡単に読めるだろうと思って買ってきたんだけど……。 「雪さんの存在もイマイチ分からないしなあ……」 グウ〜 と呟いたところで俺の腹の虫が鳴った。 時計を見るとちょうど23:30、よい子はとっくに寝ている時間だ。 ご隠居の家で夕食をご馳走になったのが17:30くらいだったから、 最後に食べ物を口にしてから既に6時間近くが経過してしまっている。 年寄りの早い夕食に合わせてしまうとこれがあるんだよな……。 「そういえばおなか空かない?」 「少しだけ空いてます。」 潤ちゃんも同じくお腹を空かしているとのことなので、ここは一つ夜食を提案することにした。 「じゃあ、何か食べようか。」 「もう時間も遅いのでは……」 「普段からあまり夜食は食べない?」 「夜食はまったく食べないです。 大晦日に『年越し蕎麦』を食べるくらいでしょうか。 木原の家にいるときからずっとそうですね。 兄さんはもしかすると私が寝た後に食べているかもしれませんが。」 そりゃ木原の家で「ちょっと摘み食い」なんて気軽に食堂行けるはずないよな。 その前に潤ちゃんが夜食を食べているところなんて全く想像できないのだけど。 「でも、このまま寝ようとすると逆にお腹が空いて寝れないかもしれないよ。」 「……確かにそうですね。」 俺もあまり夜遅くには食べたくないんだけど かと言ってお腹が空いたまま寝ようとしても逆に寝付けないことが多いのも事実だ。 過去、何度も苦しんだことがある。 潤ちゃんの口振りからしても俺と同じような経験があるのだろう。 「少しだけお腹に入れようか。」 「真神さんがそう仰られるのであれば。」 彼女が『俺に任せる』というのは9割9分9厘の確率でオッケーという意味だ。 了解が取れたという前提で話を進めよう。 「じゃあ、何か食べたいものある?」 「いえ、特には………あ」 さすがに食べたいものをただ漠然と聞くだけでは難しいだろうと思った矢先、 潤ちゃんは突然何かを思い出したような声を挙げた。 「なに?」 「その……牛丼……」 そうきたか。 潤ちゃんと出会った頃に話した夜でも食べられる牛丼のことをまだ覚えていたんだ。 ただ、残念ながらあのときとは違って…… 「牛丼かぁ。 かなりいい案なんだけど、残念ながら輸入規制が掛かっていて今は牛丼が食べれないんだ。」 「あうぅ、それは残念です……。」 潤ちゃんは心底残念そうな反応を見せた。 おそらくずっと食べてみたかったんだろうな。 俺は牛丼フリークではないので牛丼屋から牛丼が消えたときも別段何も思わなかったが、 さすがにこの時ばかりは牛肉の輸入規制を恨んだ。 他に食べるものはないかと考えを巡らしてみる。 『筋肉ラーメン』とか屋台のラーメンなんかも夜食としては捨て難いのだが、 さすがにこんな夜遅くに潤ちゃんを連れて外に出るのは申し訳ない。 家の近くにはこの時間でも気軽に食べられるような店はないし……。 となると、俺がコンビニで何か買ってくるのが無難なのかな。 いや、待てよ。 「そうだ、サッポロ一番のみそ味があったんだ。」 これは数ヶ月前に俺が風邪引いて寝込んだとき哲平が買ってきてくれたものだ。 当時は「風邪を引いているときにインスタントラーメンを持ってくる」という哲平の思考回路が本気で信じられなくなり、 一度徹底的に脳味噌をリストアしてやろうかと思ったが、それも今に至っては心より感謝せねばなるまい。 「サッポロいちばん??」 「インスタントラーメンだよ。 食べたことない?」 案の定、潤ちゃんは首を横に振った。 さすが俺と違う世界に住む住人だけはある。 今時インスタントラーメンを食べたことがない人の方が珍しいのではないだろうか。 「でも、横浜中華街のラーメンは食べたことあります。」 ……ゴメン、それは気軽にラーメンなんて呼んではいけないものだと思う。 あまりの生活観の違いにインスタントラーメンを出すことを躊躇しかけたが、 まず先に潤ちゃんの分を作って食べさせてみればいいだろうと思い直した。 それで口に合わなかったら俺が変わりに食べればいいことだし。 「作ってあげるからちょっと待っててね。」 「は、はい。」 食べたことのない物に対する期待と不安の入り混じった目をした潤ちゃんを尻目に俺は台所へ向かった。 ・ ・ ・ 台所に入るとまずは具になるものを探そうと冷蔵庫を開けてみた。 『桃屋のメンマ』くらい入ってるかもしれないと期待したが、そこには若干の調味料とビールが数本入っているだけ。 具になりそうなものは何もない。 「潤ちゃんゴメン、具がなんにもないや。」 台所から顔を出して潤ちゃんに『素ラーメン』になると告げる。 「真神さんに作って頂けるなら何でも食べます。」 いつの間にかベットの上に座っていた潤ちゃんが大胆な発言をする。 何でも食べるって……例えばここで七味唐辛子を沢山入れたラーメンを出したとしても食べるのだろうか。 そんな意地悪なことを思い付いたが、それはすぐに頭の中から消した。 そもそも彼女の発言は俺を純粋なまでに信用しているからこそのものだと思うから。 例え冗談でも彼女の純粋な気持ちを踏み躙るようなことをしてはいけない。 ……哲平が同じことを言ったら絶対に試していただろうけど。 ポットのお湯を鍋に入れ、ガスコンロの火を点ける。 程無くして鍋がグツグツと煮え始めてきたのを確認すると、 戸棚に入っているサッポロ一番を取り出し、乾燥麺とスープの素を入れた。 麺が茹で上がるまで手持ち無沙汰になってしまったため部屋を覗いてみる。 先程確認したときにはベットの上に座っていた潤ちゃんだったが、今度はベットの上に身体を横たえていた。 さすがに潤ちゃんも疲れたのかな。 「疲れた?」 「えっ!!! いっ、いえ、だ、だ、だ、だ、大丈夫ですよ!!!」 潤ちゃんに声を掛けてみると、かなり慌てているのが分かる返事をしながら ガバッと勢いよく体を起こして再び床の上に正座する。 もしかするとベットの上に横になっていることが『だらけている』と思ったのだろうか。 別に俺の部屋の物は自由に使って貰って構わないと伝えてある。 ベットの上に寝転がろうが構わないのに。 やっぱりこれが持って生まれた『お嬢様』の気質なんだろうな。 俺は潤ちゃんの一連の反応を微笑ましく思いながらガスコンロの前に戻った。 しばらくして麺が茹で上がったので中身をラーメンどんぶりに移し変え、潤ちゃんが待っている部屋へと運んだ。 「できたよ。 熱いから気をつけて食べてね。」 テーブルの上にラーメンを置き、続いて潤ちゃんに箸を持たせてあげた。 「では、いただきます。」 丁寧に頭を下げていただきますをすると、 どんぶりの中からたどたどしく麺を掬い上げる。 どうやらインスタントラーメンに限らず汁物の麺類にはあまり慣れていないらしい。 そして掬い上げた麺をそのまま口の中に運ぼうとした。 「あ、そこで一度麺を冷ました方がいいよ。」 「はい。」 ハフハフ 潤ちゃんは俺に言われた通り麺を冷まそうと息を吹きかける。 しかしこんな何気ない動作一つ取っても、彼女がやると上品さが滲み出るようになるんだな。 あまりに隙が無い姿を目の当たりにして感心するとともに少しばかりの悪戯心が芽生えた。 「お客さん『へー』より『ふー』の方が効率いいですよ。」 「……?」 「ご、ごめん……。」 昔ある漫画で読んだネタを振ってみたのだが、当然潤ちゃんには分からなかったようだ。 哲平ならここで『死んだおふくろにも教えてあげたかった』と返してくれるんだけど。 「あ、食べて食べて。」 「いただきます。」 恐る恐る麺を口に入れた潤ちゃんは口をモゴモゴと動かす。 一瞬キョトンとした目をしたが、すぐさまその表情は満面の笑みに変わった。 「どう?」 「これ、美味しいです!」 「でしょう。 夜に食べるチキンラーメンとかサッポロ一番って何故か美味しいんだよ。」 ハフハフ……ズルズルズル ハフハフ……ズルズルズル 目をキラキラと輝かせながら休む間もなく夢中で麺を口の中に入れていく。 どうやら潤ちゃんも気に入ってくれたようだ。 「じゃあ俺の分も作ってくるからゆっくり食べててね。」 美味しそうに食べる潤ちゃんを見て安心した俺は 自分の分を作るために再び台所へ戻った。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 「さて俺も食べる…ってあれ?もう食べちゃったの?」 先程とまったく同じ工程で作ったインスタントラーメンを抱えて部屋に戻ると 潤ちゃんは既に箸をテーブルの上に置いた状態で行儀よく座っていた。 「はい、ごちそうさまでした。」 先程と変わらない満面の笑みとともに礼のあいさつを返す。 見ると汁も殆ど飲んでしまった様子だ。 俺の分を作るまでそんなに時間はかからなかった筈だが。 そんなにお腹がすいていたのか、それとも余程美味しかったのか。 ……両方のような気がする。 「喜んで貰えて良かったよ。」 「こんな美味しいものが世の中にあるなんて知りませんでした。 真神さんは毎日食べているのですか?」 「はは、さすがに毎日は食べないよ。 身体にはあまり良くないと思うから。」 「でも、なんか羨ましいです。」 「うーん、浩司さんとしてみたら食べさせたくないんじゃないかな。 だからインスタントラーメン食べたって浩司さんには言わないでね。 『潤にそんなもの食べさせるな!』って怒られちゃうかもしれないから。」 インスタントラーメンを嗜むことを羨ましがられたのはおそらく生涯初めてだろう。 通常、インスタントラーメンを食べるという行為は、 給料前の苦しい財政時にお世話になるとか、どうしても腹が減って寝れないときに夜食として食べるとか、 主に何かしらピンチな状態または節約しなければならない状態に陥っているときの一つの選択肢だ。 それと同レベルの生活環境下にない潤ちゃんにその辺の事情が分かる筈ない。 下手したら皮肉にも取れ兼ねない発言であったが、純粋に彼女はとんでもないご馳走だと思っているんだろうな。 さて俺も伸びないうちに食べてしまおう。 ズルズルズル ・・・ ズルズルズル ・・・ ズルズルズル ・・・ 視線を感じ顔を上げてみる。 立ち上る湯気を挟んで向こう側には真剣な顔でこちらをじっと見つめる潤ちゃんが。 「どうしたの?」 「え? いえ、何でもないです……」 当然潤ちゃんの目には何も映っていない。 だが、その目は確実に何かを訴えかけていた。 そんな彼女の様子を不思議に思いつつも再びラーメンに取り掛かる。 ズルズルズル ・・・ ズルズルズル ・・・ ズルズルズル ・・・ やはり視線を感じる。 顔を上げてみるとやはり真剣な顔でこちらを見つめる潤ちゃん。 これはもしや…… 「もしかして足りなかった?」 「えっ!? ち、ち、違います、そんなことは……」 「じゃあ食べちゃうね。」 「……あ」 わざと突き放すような態度を取ってみたところ、すかさず名残惜しそうな反応が返ってきた。 やっぱり足りなかったんだ。 「ん?どうしたの。」 「あの、真神さんが宜しければ一口だけ……」 言葉は少し遠慮がちだが、期待に満ち溢れた目をして俺のラーメンをおねだりする。 まるで散歩に連れて行く前の子犬のように、今にも『ワクワク』という擬態語が伝わってきそうな表情だった。 そんな顔をした潤ちゃんのお願いを俺が無下に断るはずもなく、 まだ半分くらい麺が残っている俺のラーメンどんぶりを彼女の目の前に移動させた。 「はい。 全部食べていいよ。」 「ありがとうございます!」 潤ちゃんはお礼を言って箸を取ると、俺のラーメンを美味しそうに食べ始めた。 たどたどしく麺を掴み、上品に麺を冷まし、口に入れて満面の笑みを見せる。 その一連の様子を眺めていると自然に俺の頬が緩んでしまう。 お腹は物足りないけど心は満たされた、この日はそんな夜だった。 |
| コメント(言い訳) |
|
どうも、Zac.です。 どうして夜中に食べるサッポロ一番の味噌ラーメンとチキンラーメンは美味しいのでしょうか。 いつも「夜遅くに食べると太るぞ」と自分自身に警鐘を鳴らすのですが、あの美味しさの前には全く無意味に終わります。 ま、要するにそんな私のライフスタイルをそのまま描いたような話です。 「Zac.の夜食はサッポロ一番の味噌ラーメンなんだな」と思って頂いて構いません。 事実、台所の戸棚には常にストックが用意してありますし。 これ実は『潤恋歌』を書くときに思いついたネタの一つなんですが、 このとき既に別の食べ物に纏わる話を書き上げていたので回避することにしました。 潤ちゃんが「インスタントラーメンを食べた事が無い」というのは極端な気がしますが 仲良く食べて美味しかったで終わりじゃつまらないのでそういうことにしました。 まあ24時間営業の牛丼屋を知らなかったくらいだからギリギリ許容範囲かな。 とりあえず「恭介の食べている分も欲しがる」というのを書きたかったので満足。 だからタイトルもストレートに『おねだり潤ちゃん』で。 実際におねだりしている部分なんてほんの数行しかありませんけどね。 読み返してみると、食欲旺盛な潤ちゃんだなあとか思ってしまいました。 今度書くなら「恭介が潤ちゃんを食べてしま(以下略) ちなみに今回もさりげなく交流戦仕様だったり。 相手は牧野那波率いる『水月』です。 サイドストーリー『みずかべ』で那波が書いている絵本『すいげつ』を使わせて頂きました。 こんなのさりげなさ過ぎてちっとも分かりませんが。 というかこれは交流戦じゃないだろう、と。 ところで「お客さん『へー』より『ふー』の方が効率いいですよ」のネタが分かる人いますかねえ。 まあこれが分かるということはそれなりの年齢の方かと思いますが。 |