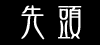| 琥珀色の靄(もや) |
|
「こちらが写真です」 私は封筒に入った写真をクライアントに提出した。そこには深夜のホテルに腕を組んで入っていく二人の男女の姿が映っている 赤ら顔で笑っている男性の年齢に対して傍らで腕を組んでいる女性の方はかなり若い 側を通りかかった人ですら「不倫」という二文字を思い浮かべるであろう、そういう意味では典型的な構図と言えなくもない 「・・・・・・・・・」 静かにその写真を手に取って暫く眺める年配の女性。今回のクライアントであり、写真の男性の妻である 「御主人に間違いありませんか?」 配慮、とか遠慮、という言葉から最もかけ離れた言葉で確認を促す 「ええ・・・主人ですわ・・・」 クライアントは半ば呆然とした面持ちでこちらの質問に答えた こういう時の反応はクライアントによって様々で、怒り出す、泣き出すといった反応はまだ良い方に分類される 頑なに信じない人もいればそちらから頼んでおきながら私に怒り出す人も珍しく無い この人のように呆然とする人も勿論いた 「・・・」 沈黙だけが主導権を握るこの空間は居心地と言う点では最悪だが、こちらも黙るだけなので余計な気苦労は必要ない (だけどこの時こそまさに、つくづく探偵業がイヤになる瞬間だな) 彼はそう言っていた。 「贅沢言わないでちゃんと仕事しなさい!」と返す私自身ですらその考えには二つ返事で賛同したい気持ちを抱えている 「私が居ながら・・・私が居るのに・・・」 聞き取れない程の小さな声で独り言を呟く女性 仕事には感情を持ち込まないよう訓練された私だが、胸の奥にある苦々しい物の存在は否定できない 今この瞬間に神様とやらが願いを叶えてくれるのなら、私は「早く帰らせてください」とお願いするだろう が、私からの報告はこれだけではない 「こちらに御主人がこの女性とお会いしていた詳しい時刻と場所を記しています」 メモの切れ端にはこの二人が会っていた店の名前や時刻やらが克明に記されている 「第二週と第四週の金曜には必ずお会いしているようです」 彼女からの話によると決まってこの日には上役連中と飲みに行って帰りが遅くなるということだった 「それで・・・」 何かぶつぶつと呟いていた目の前の女性だったが、ようやくこちらに話しかけてきた 「この・・・この女の名前と住所は?」 「御住所はお教えすることはできませんが、御名前の方は・・・」 「名前は!?何て言うの!!」 「勤めているクラブでは麗子という源氏名で・・・」 「レイコ・・・レイコ・・・レイコ・・・」 目から涙をボロボロ流しながらも眼光だけは不気味に輝かせながら何度もレイコの名を呟く女性 彼女の望んだ事とはいえ、これが私たちのやった事の結果なのだ (しかもそれがオレたちの食い扶持と来たもんだ・・・因果な商売だよ) 彼の言葉を借りるとそういう気持ちになる だが最後に私はもう一つの言葉をかけなければならない 彼女を慰めたりいたわる為の言葉では無く、調査の報酬の話なのだ あの時から探偵事務所で働き出して何度と無く経験してきた瞬間だが、何時になってもこの時ばかりは気が滅入る (そこで滅入らなくなったら一人前のロクデナシだな)と彼は言ってくれたけど・・・ この時にゴねたり反発するクライアントも少なくない 今回の女性は料金に関してはすんなり折半が付いた・・・というより、意識が既に目の前の私や料金ではなく、レイコという女性に向けられていたからかもしれない 一通りの報告を終えて席を立つ。最後に私が軽く礼をしたことに気付いたのだろうか 彼女はソファに座ったまま依然として女性の名前を呟き続けていた ◆ ◆ ◆ 「・・・はぁ・・・ただいま」 今日は何故か事務所のドアがやけに重たく感じられた 「おう、ご苦労さん」 「クライアントへの報告、済ましてきたわよ」 「お疲れさん、コーヒーでも飲むか?」 「ええ・・・ありがと」 暫くしてコーヒーの薫りが事務所に漂ってきた。彼の煎れるコーヒーはいつも私の気持ちを落ちつかせてくれる 「・・・ふぅ・・・」 ソファに深く腰掛けて溜息を吐く。折角のコーヒーの薫りを掻き消すようにあの女性の姿が思い出されてならない 「どうした?」 カップをテーブルに置きながら彼は声をかけてきた。砂糖は入れずに、ミルクをほんの少しだけ・・・私の好きな、いつものコーヒー 「え?・・・ええ、ちょっと疲れちゃって・・・」 「そうか。なんなら明日は休みでもいいぞ。疲れはお肌の天敵だからな」 「あのねぇ・・・・でも休みはいいわ。私、まだまだ若いんだし」 クククと笑いながら彼はコーヒーをすすった 「心配してくれて、ありがと」 「ふん、従業員にダウンされちゃ困るからな」 少し顔を赤くして、照れくさそうにもう一口コーヒーをすする姿・・・私の胸に温かい物を注いでくれる、いつもの彼・・・ その姿を見ると胸に痞える苦みを彼に聞いて欲しくなった 「今日ね・・・」 空になったカップを掌で弄びながら静かに呟く 「ん?」 優しい表情で私のほうを見つめる彼・・・なんだか余計な心配をかけそうな気がして言葉が止まる 「・・・やっぱり・・・いい」 じっと私の顔を見つめた後、軽く笑って彼は立ちあがった 「氷室、たまには酒でも飲むか?」 「・・・え?」 「酒の力を借りなきゃ言えない事もあるさ」 棚の上に置いてあるウイスキーを手にしてこちらを振り返る 「酒、飲めるよな?」 「え、ええ・・・一応」 そう言えば小次郎と二人でお酒を飲むなんて事は久しく無かった気がする もともと彼はそんなに酒を好む方じゃないし、私も昔の名残でアルコール類は意識して飲まないようにしているから (何時如何なる場合でも思考が働くようにするため非番の時でもアルコールは摂取しないこと) 以前そういう風に訓練された。もっとも法条さんなんかは平気で無視してそうだけど・・・ 彼が普段は飲まないお酒を勧めたのは私の言いたい事を感じ取ったからかもしれない その少し不器用な優しさが、今はとても嬉しい・・・ 「ほい」 薄く入れたウイスキーは事務所の暗い照明に良く似合っていた。案外ここはバーにしてもいい感じかもしれない そう思って軽く事務所を見回したけど・・・やっぱり前言撤回。これじゃあお客さんは来ないわね クスクス笑ったのを見て、彼は私の顔を覗きこんだ 「なんだあ?何が可笑しいんだ?」 「ううん、ちょっと、ね」 チン、とグラスが重なる音が響く。久しぶりに喉を通るアルコールは少し新鮮な感じすら覚えた 暫くは他愛も無い話で笑い合う二人 敢えて私が言おうとしたことを聞かないのは彼の優しさ その気持ちに甘えてグラスを重ねる私・・・いつも、そう。何時の間にか彼に甘える自分と、そのことに安らぎを覚える自分がいた 彼が居ないとダメになってしまった私・・・そうさせた彼の気持ちは本当に嬉しくて・・・でも残酷で・・・ 愛すれば愛するほど、離れてしまう事を恐れるようになってしまう (もしも彼が居なくなったら、もしも彼があの女性の所に行ってしまったら・・・) 今までは考えもしなかった子供地味た恐怖。そのたびに私は彼の胸にしがみつき、離れまいと強く抱き締めてきた 夜が明けて、目が覚めて、私の隣で寝息を立てる彼を見つめる度に、私は例え様のない幸せと安堵を感じる 昨日と同じ今日を迎えられた事への喜び、今日とは違う明日を迎えるかもしれない恐怖 その中で彼の温もりだけがいつも私を受け入れてくれた ◆ ◆ ◆ 「今日ね・・・」 数杯目のグラスを重ねた後、頬に幾分かの熱を感じながら事の顛末を話した 久しぶりのお酒の所為もあってか何時になく口調に力が入っているのが自分でも分かる 「そりゃ災難だったな」 力無く笑いながら彼は答えてくれた いつものようにフンと笑い飛ばさないのはお酒の所為だろうか、それとも私の所為だろうか・・・ (・・・私だったら・・・) とは思わなかった、と言えば嘘になる そんな風に彼を憎む事が出来れば・・・私の思いがその程度の物だったら・・・ 彼が私を愛してくれなかったら・・・あの女性だけを愛しているのなら・・・ 胸の奥に痞える苦しみが徐々に大きくなってくるのが分かる 不安、恐怖、悲しみ、嫉妬・・・そんな単純なもの?だったらこんなにも苦しくなるの? ウイスキーを飲み干してグラス越しに彼を見つめる だが、そこには居るはずの彼の姿が無かった 「?」 次の瞬間、私の掌から空のグラスが落ちた。床に落ちたグラスの乾いた音が事務所に響く 「・・・」 さっきまで目の前に居た彼が、今は私を後ろから抱き締めている 「こじろう・・・」 「・・・」 熱い いつもの子供地味た恐怖を救ってくれる彼の温もり。それよりももっと熱いものが私の身体を駆け巡っているのを感じる 私を抱く腕に力が入った。痛みを伴う程強く抱かれているわけでもないのに何故か身体が動かせない 首筋に置かれた唇の感触。瞬きをする目蓋にすら重さを感じるような、身体中を支配するこの不自由さ 自然に身をよじりそこから逃れようとするのに、その行く先すら塞がれて捕らわれたい私が居る・・・ 不意に喉の奥から漏れた私の声に反応して彼の腕から少し力が抜けたような気がした その腕を強く掴み返し、首を左右に振る・・・たったこれだけの動きなのに額からは汗が流れている 前身の力を振り絞ってようやく顔だけを彼の方を向き返らせることができた時、私達の唇が重なった ・・・ 汗を含んだ二人の長い髪が絡みつく 吐息だけで火傷をしそうな夜・・・ この熱さが私の不安を焼き尽くしてくれるなら、身体ごと焼き尽くして欲しい それが叶わないなら、せめて彼の中の不安を、私の中の恐怖を少しでも燃やして欲しい 思いが火種になるのなら、消えることが無いのなら・・・ だったら・・・ 少しでも長く、この身体を焦がしていたい・・・ ◆ ◆ ◆ 「小次郎?」 「ん?」 「またお酒、飲みましょ」 ああ、と返事をした後、彼のひんやりとした手が額に乗せられる 「たまにはいいもんだろ?」 「ふふふ・・・そうかもね」 私の髪を優しく撫でながら彼は小さな声で呟いた 「氷室、オマエやっぱりそっちの顔の方がいいぞ」 「え?」 「・・・何でも無い」 「じゃあ、聞かなかったことにしといてあげる」 「ふん・・・」 少し照れくさかったのか、彼はぽんと私の頭を叩いてシーツに深く身を沈めた 眠ろうとする彼の手を握って小さな声で呟く 「今日は・・・ありがと」 「・・・おやすみ」 事務所の明かりが消えても私たちは手を握り合っていた いつもの彼の温もり・・・それを胸に押し当てて目を瞑る 「おやすみなさい」 |
| 四方山話(言い訳) |
|
どうも、毎度の氷室バカtalkでございます。
今回、以前話に上がっていた「氷室が酒を飲むシチュエーション」を小説にしてみましたが、
らぶらぶいちゃいちゃな小次郎-氷室とはまた違った今回の二人。 読んで下さった皆様「コイツの頭の中って一体どうなってんだ?」と思ってくだされば幸いで御座います。
|