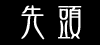| 私の傍に |
|
私はあの時の光景を忘れる事は無いだろう いつもと同じように起きて、いつもと同じように朝食を取って いつもと同じように支度をして、いつもと同じようにマンションを出た いや・・・いつもとは違う所があったな・・・ 小次郎の様子が何かおかしかった もっとも後になって考えてみればの事であって、 その時の私は(また他の女のことでも考えているんじゃないか)程度にしか思わなかったのだが 事務所に着いてからだって全くの日常の通りだった いつもとおなじように書類に目を通して、パパにサインを貰って・・・ パパだっていつもと変らなかった 数時間後にはあんなことになるだなんて思ってもいなかったんじゃないか 時計の針が12時を刺そうとしていて、そろそろ昼食の事を考え始めていたその時、事務所のドアが開いた (クライアントが訪れる予定は無かったのに) と、その時私は感じた しかし彼らの姿を見て、そしてその独特の雰囲気を肌で感じたとき 何故か背筋に冷たい雫が落ちたような、そんな感覚に捕われていた 不安になって傍に居た小次郎を見つめた その時の小次郎の表情・・・今でも忘れない 長い髪の下で隠れていた表情は一見平静を装ってはいたものの、心の何処かでこの来訪者を拒絶したがっている 私にはそう見えた 探偵という仕事柄、謂れの無い抗議や反発の為に事務所に押しかけてくる連中は少なくは無い そういうヤツらは小次郎が、パパが追い払ってくれたのだ きっとこの連中もすぐに小次郎が追い払ってくれるだろう、と思って でも何処かいつもと違う雰囲気に言い様の無い抵抗を感じていた 「桂木源三郎は?」 紺色のスーツを来た長身の男が私に尋ねた 「失礼ですが、どちら様で?」 その問いに彼らは一枚の書類で答えた 細かい文字で記されている文章はよく覚えていない ただ冒頭に見える「逮捕状」の文字が、やけに現実離れしたものに感じられた 「桂木源三郎は?」 別のスーツの男が再び切り出してくる この男はスーツの色とネクタイの色が合っていなかったことを覚えている どうしてそんなことを覚えているんだろう・・・顔ははっきりと覚えていないのに 今思い出しても、その男の顔には三文字の漢字が刻まれている風にしか思い出せない 「逮捕状・・・?」 訳もわからずに呟く 所員たちもざわめいていたはずだ。なのに・・・ なのに私の横に立っていた小次郎と、背後で声を立てたパパの二人だけは落ちついていたように思えた 「私が桂木ですが」 振り向くとパパが立っていた 予想外の侵入者たちにも動じることなく対応するパパ ちらりと私の方を向いて軽く微笑んだ (心配することはない) そういう表情だった その後小次郎の方に向かって何か小声で呟いたような記憶があるのだが、それは聞き取れなかった 「・・・・・・・・・」 スーツ姿の侵入者たちは私に見せた「逮捕状」をパパにも見せて、幾つかの質問をしていたようだ その言葉に頷くパパ (一体何を・・・) 無意識に私は小次郎のジャケットを握り締めていた こういう場合、必ず侵入者たちに食って掛かる小次郎がどうして黙っていたのか あの時の私にはわからなかった ただジャケット越しに、小次郎の腕が震えていた感触だけが今でも手の中に残っている 「署まで来ていただけますかな?」 その言葉に頷いたパパはすっと両手を差し出した (??) 一瞬そのパパの行動が意味する所を理解できなかった テレビの刑事ドラマなんかでは当たり前のように行われる動作 それが今、私の目の前で、私のパパに対して行われている そして・・・テレビでしか見たことの無い、鈍い銀の光沢を放つ腕輪のような物がパパの手に掛けられた 「・・・パパ?」 泣きそうな、でも笑いそうな言葉でパパに声を掛けた 心の何処かでカメラを担いだ人物を期待していたような・・・あまりにも唐突で、芝居地味ていた一瞬の出来事 笑いそうな声の原因は、そこにあったのかもしれない 「後は頼んだぞ」 それが、私が最後に聞いたパパの言葉だった 私はただ、何もわからないままに小次郎の腕を握り締めていた 小次郎はパパを連れていく彼らに近付きもしなかった。もしかしたら視線すら逸らしていたのかもしれない でも小次郎の腕の震えだけが、今でも手の中に残っている・・・ ◆ ◆ ◆ それから数日間のこともよく覚えていない あの晩、小次郎が告げた言葉も実を言うと曖昧にしか記憶されていないのだ 「オレがおやっさんを・・・」 いや、切り出し方は「すまない」だっただろうか。それとも「弥生」と私の名を呼んだのだろうか 私はただ呆然と座っていただけだった パパの後姿と、腕に掛けられた手錠と、目の前の小次郎の言葉 それらが私の中で一つになるのには随分と時間がかかった 何時の間にか小次郎は私の部屋から居なくなり、事務所から居なくなり、何人かの所員たちも居なくなり・・・ そこで始めて私は気付いた いや気付かせたのは二階堂クンだったか・・・ 私のことを「所長」と呼んだのは彼が最初だったんだ 「いいですか、所長」 と私の手を取って彼は話しかけてきた 「小次郎は・・・あの男は、貴方の父を売ったんですよ」 「・・・うそ・・・」 「嘘じゃありません。警察に通報したのはあの男です」 「・・・うそ・・・」 「あの男は、自分の名声の為に、恩師を裏切ったんですよ・・・」 呆然とする私の手を握って耳元で囁く彼の声は、 それでもどこか、まだ現実離れしたもののように私には聞こえていた 「でも心配しないで下さい」 弥生さん、と私を呼んだのも彼が最初だった 「弥生さん、貴方はこの二階堂が守って差し上げますよ」 「・・・小次郎が・・・パパを・・・」 「そうです。あの男は貴方を散々利用して、そして貴方の父を・・・」 気付いたときには私は彼の頬を叩いていた 目からは止めど無く涙が流れていたのも覚えている 「・・・す、すまない、二階堂クン」 「・・・信じられない気持ちも分かります。小次郎のやりくちは巧妙でしたからね でも、しっかりしてください。これからは弥生さん、貴方がこの桂木探偵事務所の所長なんですよ」 「私が・・・所長?」 「そうです。そして不肖・二階堂進、貴方を守る為なら・・・」 そういって彼は私の唇を奪った 「や・・・」 「貴方を守る為なら協力は惜しみませんよ・・・」 ・・・ それからの事務所は忙しかった クライアントの依頼キャンセル、マスコミの電話、辞めて行く所員への対応・・・ 「業界大手の有名探偵事務所所長逮捕」 そういう見出しで新聞の一角を賑わした事もある もっとも数ヶ月後には再び同じような事態に直面するのだが、一回目のこの時にはその二階堂クンが居た 彼の口利きで苦情や電話は減少し、しかも以前と遜色無い程の依頼を持ち込んでくれたのだ 彼には感謝している その目的がこの事務所と、私にあったことも十分理解していたが、 彼が居なくては私はパパと小次郎の居なくなった事務所を支える事は出来なかっただろう だが彼は、二階堂クンは小次郎じゃなかった 私を支え、慰めてくれても彼は小次郎じゃなかった 以前、車の中で二回目に唇を奪われた時に彼が囁いた言葉 「これで小次郎もおしまいですよ・・・」 あの時私は、彼の視線の先を知った 彼もまた小次郎の存在が忘れられないのだ それは私の中の小次郎の存在が遂に消える事が無かったように、 抱く感情こそ違えども、彼の心の中にも小次郎が居続けたのだろう もしも、彼の小次郎に対する感情が私と似通っているものだったら 私たちは、ここにはいない、心から消す事の出来ない男の為に、お互いを抱いていたかもしれない ・・・私には、彼の要求を拒否する権利なんて無かった 私を支え、事務所を立て直してくれた彼が私を求めたら、私は私としてではなく、所長として彼に応えなくてはならないのだ だが本当は・・・触れられる事すら苦痛だった そして耳元で小次郎の名を囁かれるたびに、彼に対して醜い感情を抱いたこともあった 殺意というほどはっきり形に現れるものではなかったが、 少なくとも『私の目の前から消えて欲しい』と思ったことは一度ではない だけど事務所を支える為には彼の力は無くてはならない 彼の思いは私の弱みに付け込んだものであることもわかっていた 小次郎への敵意が奥底に潜んでいた事もわかっていた でも、だから尚更、私は拒む事が出来なかった 彼と唇を重ねる事で、彼の中のオマエに対する敵意を共有できればと考えた この苦痛を小次郎の所為に置き換える事でオマエを憎もうとすら考えた 彼に抱かれる事は無かったが、彼に嬲られ続けた私は、それでもずっと小次郎のことを考えていた 『どうして私の傍に居てくれないんだ』 こんな苦痛を感じるようなキスで私の口に触れて欲しくなかった こんな苦痛を感じるような声で私の名を囁かないで欲しかった こんな苦痛を感じるような声で小次郎の名を囁かないで欲しかった どんなに小次郎を望んでも、オマエは来てくれなかった だから私は出来もしないのにオマエを憎む事を選んだ 憎む事で忘れる事が出来たならどれだけ楽になれただろうか オマエでもない男に抱かれる事ができたならばどれだけ楽になれただろうか ◆ ◆ ◆ 二階堂クンの死体を見た時、私は涙が出なかった その凄惨な死体、何かに納得のいかないようなあの目 彼が私の知らない所で何を行っていたのか、詳細はわからないが想像はつく 彼が私を支えたのは、事務所と私が目的だった事は知っていた それでも彼は私を支えてくれたのに、私は涙を流せなかった しかも心の何処かでこう囁く私が居た 『これで苦痛から解放される』と囁く私が・・・ 『これで小次郎の元に会いに行ける』と囁く私が・・・ そのことに気付いた時、自分がどれほどイヤな女か 自分がどれほど酷い女か、鏡を見るほどにありありとわかった 死体を見ても、彼の死を目の当たりにしても涙一つ流さない私 これが二階堂クンじゃなくて小次郎だったら私は躊躇うことなく後を追うだろう 一人の人間が殺されている、悲惨で悲しむべき状況を目の前にして、私は彼じゃなくて、小次郎のことを考えた 何をどう考えてもオマエの事しか思い浮かばない 小次郎の声、小次郎の顔、小次郎の息、小次郎の唇 そしてパパが逮捕された時に、私の手の中で感じた小次郎の震え あの時、どうして小次郎は震えていたんだろう 二階堂クンが言うように私を利用したのなら、どうして私の元を去ったのだろう わからない・・・何故小次郎はパパを突き出したの? どうして私の傍に居てくれなかったの? どうして小次郎を憎み、怨むことができないの? どうして私の心から消えてくれないの? 酒で少しでも忘れる事が出来るなら、そう思ってパパの秘蔵の酒に手が伸びた だが酔うほどに、強がっていた自分が薄れるほどに小次郎のことしか思い浮かばない 声が・・・聞きたい・・・ 貴方に・・・会いたい・・・ 小次郎に・・・抱いて欲しい・・・ 自然に受話器に手が伸びた オマエから貰った名刺を見て番号をプッシュする 番号を一つ一つ押すたびに涙が流れてくる 彼の死を目の当たりにしても涙なんか流れなかったのに オマエの電話番号を押すだけで涙が流れるなんて・・・ 自分の中のイヤな女への憎悪が込み上げてくる こんな私を見たら、小次郎はどう思うだろうか いや蔑まれてもいい。兎に角オマエの声が聞きたい・・・ 「はい、天城探偵事務所」 「ば〜ろ〜」 ◆ ◆ ◆ 「小次郎?」 目を覚ますと小次郎の姿は無かった (そっか・・・仕事に戻ったのか・・・) さっきまで小次郎が寝ていた場所に顔を埋めて、息を大きく吸う ベッドのシーツからは、まだ昨晩の小次郎の香りが残っていた 残っているのは香りだけじゃない 髪には小次郎の手の感触が・・・髪だけじゃない、手に、足に、胸に小次郎の感触が残っている 唇には少しざらついた小次郎の唇の感触が残っている 体には小次郎の重みが残っている 抱き合ったのは寂しいから、だけじゃなかった 求める場所にオマエが居て、応えて欲しい時に応えてくれて 涙を流しては拭ってくれて、優しく接して欲しい時に居てくれて 触れたい時に居てくれて、触れてほしい時に触れてくれて・・・ 数ヶ月前までは当たり前だったことが、今はこんなにも愛しい パパが死んで、二階堂クンが死んで・・・でも小次郎は傍に居てくれた 「そうだ・・・シチューを作ってあげなくちゃ」 でも、今はもう少しだけこの心地よい気だるさに身を任せていたい 『今でもオマエにどう接したらいいかわからないんだ 触れると壊れそうで、でも触れないと何処かに行ってしまいそうで・・・』 私は・・・何処にも行かない 小次郎に触れられて壊れるのならそれでもいい だから・・・私に触れていて欲しい。これからも、ずっと・・・
|
| 四方山話(言い訳) |
|
続けて氷室バカtalkによる弥生セット二作目で御座います。
これもまた「いちゃいちゃしないシリアス」を意識して書いたんですけどねえ、
なんていうか私の書く氷室や弥生は「私を抱いて!!」なんだそうです。 読んで下さった皆様、「コイツ頭おかしいんとちゃうか?」と思ってくだされば幸いで御座います。
|