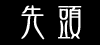| 振り向いて欲しい人 超えたいアイツ |
|
闇が広がる部屋に、1人で居る。 別に闇なら明かりを点ければ振り払える。 だが…心に広がる虚しさは、この部屋に広がるどうしようもない孤独は…振り払えないんだ。 この部屋には女性を招待した事もある。友人と談笑した事もある。その時は孤独なんか感じなかった。 でもそれは…永遠じゃ無い。皆何時かは帰って行く。それが親友でも恋人でも…皆去って行く。 宴の後に取り残された僕の胸に残る物は…楽しき記憶と、余韻と、…寂しさだ。 …ちっぽけな部屋のくせに、何でこんなにも広く感じるんだろうな… 自分で自分に出した問の答えを出せぬまま、僕は気に入りのワインを一気に口に含んだ。 …不味い。 どうしてこんなにも不味く感じるのだろう?いつもと同じ味なのに……。 「クソッ」 誰に言うのでも無く、何が悔しいのかも分からず、僕はそう呟いた。 …違うな。 何が悔しいかなんて分かっているんだ。 ただ、考えると自分の存在を消し去ってしまいたくなるくらい、悔しいんだ。 どうしても届かない想いと…どうしても乗り越えられない壁 自分があまりに弱い存在だと思い知らされる、2つの眩しすぎる光… 振り向いて欲しい人がいる 長く美しい髪に少し気の強そうな面持ち。初めて会った時は仕事一筋の強い女性だと思った。 だが、日々同じ仕事をしていると彼女の言葉の中に深い優しさが滲み出ている事に気付いた。 初めて1人で仕事をこなせた時、「おめでとう二階堂君。これで君も一人前の探偵だな」 と言って僕に微笑んでくれた時、満足に彼女の顔も見れずまともな返答も出来なかった。 僕が彼女に心を奪われたのは…その時だ。 だが彼女の側には…どんな時でもいつもアイツがいた。 普段は側に居なくても、彼女が必要とした時には必ず側に居る。…そんな感じだ。 僕の想いは、ただの一方通行でしか無かった。 間に割って入ろうにも、僕が入り込む余地が無いほど…2人の絆は固かった。 端から見たらもうケンカ別れするだろうという険悪なムードになっても、それは変わらなかった。 超えたい奴がいる アイツは僕の先輩だった。探偵としての目標でもあった。 だが…僕はアイツの存在がたまらく悔しい。 好きになった女性の恋人だったからじゃ無い。 その性格が気に食わない訳じゃ無い。 アイツが…たまらなく大きく、眩しい存在だったからだ。 僕は、アイツに負けない探偵になりかった。 だからこそここまで頑張ってこれたと言われたら否定は出来ないだろう。 努力に努力を重ね、仕事もいくつもこなした。それなりに優秀な探偵だと言われるようにもなった。 ……それでも、アイツは僕の遥か先にいる存在だった。 どんなに努力してアイツに近づこうとしても、アイツは倍のスピードで僕を引き離す。 …フッ、永遠に居眠りをしないウサギとカメだな…。 榊原 真という家出少年を探し出すという案件があった。 アイツが引き受けた依頼だったが、僕もその案件を担当したいと申し出た。 アイツと勝負がしたかったからだ。 簡単な仕事だと思っていた。 これならアイツにも勝つ見込みがあると思っていた。 …だが、この案件は僕が考えていたようなちっぽけなものでは無かった……。 誰にでも移植可能な遺伝子を持った少年。 そしてその臓器をフィルブライトが欲していた。 所長代理から聞いた事の真相だ。 だが、僕も探偵の端くれだ。それが他人に見せても良い真相だという事くらい気付いた。 それも真相だが、全てを話してはいない。他にもっと深いものがある。 恐らくそれは彼女も知らされていない。 真相は、ただの家出捜索だと思っていた僕と違い 真の真相にたどり着いたアイツ…小次郎だけが知っているのだろうな…。 「…申し訳ありませんでした。所長代理」 「ん?いきなりどうしたんだ二階堂君」 「僕は…真相に近づく事すら出来なかった無能な探偵です」 今の僕は情けない顔をしているのだろうな。 他の所員も驚いた顔をしている。あの自信満々の二階堂が…とでも思っているのだろう。 ただ彼女だけは…穏やかな表情をいていた。 だがそれがたまらなく自分が情けなく感じる要因だとは、彼女は知らない。 「気にしなくて良い。二階堂君は優秀な探偵だ、うちには欠かせない程の…」 「しかし!」 「小次郎の事を気にしているのか? だったら気に病むことは無い。あのバカが特殊なんだ。小次郎と…」 「失礼しますッ!!」 「ちょ…二階堂君!?」 僕は驚いている彼女の言葉を無視し、外へと走り出した。 いや…逃げ出していた。 『小次郎と二階堂君を比べるのは間違っているよ』 そう彼女の口から言われるのは、堪えられないだろうから……。 分かっている。アイツは天才なんだ。 そして自分の才に溺れる事も無く、努力も惜しまない。 僕がアイツに抱く感情は…劣等感、敗北感、悔しさ、…そして憧れだ。 不思議と、妬みという感情が湧いてこない。 そんなものが湧いてくる余裕が無い程、僕はアイツに負けているのかも知れないな。 そして…初めて会った時から僕はずっとアイツに憧れている。今も変わらずに。 アイツのような探偵になりたい。アイツのように輝いてみたい。 だが…決定的に僕と小次郎の差を見せ付けられた事件が、前にあった。 それは、浮気調査だった。 ただの浮気調査なら話は簡単だったのだが…暴力団の組長の浮気捜査だった。 しかも、その組は武器密売、麻薬取引等と…黒い噂が絶えない大きな組だった。 当時まだ新米の域を出ていない僕がこの案件に関われたのは、小次郎のサポートとしてだからだ。 その時僕はやっきになって小次郎を超えたいと思っていて、小次郎の意見も聞かずに単独で行動した。 そして、浮気現場を写真に収める事に成功した。 …その時は嬉しくて辺りへの注意が散漫だった…。 「グッ!」 突然、後頭部に衝撃が走った。 振り返ると、組員らしき男が数人立っていた。裏路地に当たる、人気の無い場所…絶体絶命だった。 「誰かは知らんが…ちと厄介なものを見てしまったな。これがバレると組の存続に関わるんでね」 「う…浮気現場が存続に関わるのか…?」 僕は揺らぐ意識を懸命に留めて話し掛ける。 見つかったら時間を稼いで逃げ出す機会を探し出せ。もし無ければ作り出せ。 …小次郎に教わった事だ。 「浮気?そろそろ頭がおかしくなったか?」 「ん〜お前よりはましなんじゃないか?」 「!?」 …あれ? さっきまで僕に話し掛けてた男が消えた…?いや、寝たのか…?こんな場所で…? やばい…意識が……。 ……薄れゆく意識の中、僕が見たものは、横たわる数人の男と長髪の男の姿だった……。 * * * * 「…!?」 「お、気が付いたか?」 …気を失っていたのだろうか。 気付いたら僕は近くの公園のベンチに寝かされていた。 そして、誰かが僕の頭の上…ベンチの隣に座っているのを知った。 「小次郎…?つっ!」 「おっと、まだ動くな。後頭部を殴られたばかりなんだからな」 「……」 「しかし…、なんであんな無茶をした?あの辺りは組員が見張っていて危険だとは知っていただろ」 「…あれから…どうなったんだ?」 「質問を質問で返すな。俺の質問に答えたら答えてやる」 「…お前を出し抜いて、認めさせてやりたかったんだ」 「弥生を…か?」 「お前をだ、小次郎。僕は…お前以上の探偵になりたい。だから」 「…なんか、えらく素直だな。頭でも打ったか?」 「…打ったんだよ」 「あ、そうか〜それで今日の進君は変なのかぁ」 「…質問には答えた。今度は僕の質問に答えてもらおうか」 「お前を襲った兄ちゃん達は全員まだ居眠りしてるだろうさ。 とりあえずばれたらヤバイから、『正義の私服警官参上!』って張り紙しといたぜ。 うまくいけば警察と全面戦争して、警察がしょっ引いてくれるだろ」 「…バカかお前は」 「後先考えずに敵地へ突っ込んで行った何処かの誰かさんよりはマシさ」 「……」 「ま、お互い様という事で許してやるよ」 「…僕を許すというのか?下手すればお前も危ない事になったのに」 「…だが、五体満足でここにいる。大切なのは『そうなるかも知れない』では無く、 『そうなった』だぜ?」 「だが…」 「いやー危険だけど確かにあそこは良い場所なんだよ。 兄ちゃん達が居眠りしてる間に浮気現場もバッチリだぜ♪ お前がああしてくれなかったらこうは行かなかっただろうからな」 「ちっ…抜け目の無い奴だな。だが、僕だって写真を取った」 「へ?ちょっとそれは変じゃないか、浮気相手が来たのってお前が伸びてから数分後だぜ?」 「な!そんな筈は…」 「ま現像したら分かるだろ。とにかく、一度病院へ行くぞ」 「………」 「あ、まだ動けないか。 …ほら」 「…何のつもりだ?」 「肩貸してやるって言ってるんだよ」 「余計なお世話だ。1人で大丈夫だ……」 「嘘言うな。歩く事さえままならないくせに。…ほら!」 「………ふん」 さっきまでは青空が広がっていた筈なのに…もう、辺りは紅く染まっていた。 その中を…僕は小次郎の肩を借りて、歩き出していた……。 「…小次郎」 「ん?」 「…礼を言っておく」 「ふっ…気にするな」 「だが……」 「んあ?」 「僕は…お前が嫌いだ」 「…ヘイヘイ……」 * * * * 『○△組の麻薬密売の現場を桂木探偵事務所が押さえる!』 そんな記事が出たのは数日後の事だった。 僕が取った写真は浮気現場等では無く、麻薬密売の現場だったのだ。 そしてその事で一躍僕はスターとなった。 …だが、これっぽっちも嬉しく無かった……。 「二階堂、小次郎。ご苦労だったな」 あまり事務所に居ない所長が、珍しく事務所で僕たちを呼び出した。 今回の事は桂木探偵事務所を一躍有名にする事になり、依頼が今まで以上に殺到する結果となった。 お陰で所長自らも働かなければいけない状況になったので、こうして所長もここに居るという訳だ。 「俺はただ言われた通り現場を押さえただけだぜ。 苦労したのは二階堂だ」 「…いや、小次郎がいなければ今ごろ…。 それに…あんなのはただの偶然だ。無事依頼をまっとうしたのは小次郎だ…」 「ふむ、まぁ確かに二階堂は依頼をまっとう出来なかったな。 だが…偶然とは言え、小次郎以上の成果を上げたんだ。もっと喜んだらどうだ?」 「…依頼に、大きいも小さいも無いと教えてくれたのは…所長でしょう?」 「おっと…そうだったな…」 「僕が偶然現場を押さえてなければ、小次郎が押さえてますよ。…偶然では無く必然的に」 「おいおい…それは過大評価だぜ?俺はそんな…」 「まだ言うか小次郎ッ!貴様はいつもそうだ!僕よりいつも上にいるのに……お前は!!」 「お…おい二階堂!何処へ行く!? …出て行きやがったぜ…一体何なんだあいつは?本当に頭打っておかしくなったか…」 「分からんのか小次郎?」 「何が?」 「ふぅ…お前は経験無いだろうが、 あいつはお前をライバルとして、目標にしているんだ。 お前のような探偵になりたい。お前のように強くなりたいと…。 だが、あいつはいつもお前との決定的な差を見せ付けられ続けている。 どんなに頑張っても、どんなに努力しても、お前はいつも上にいる。 恐らく小次郎の才能を1番認めているのは私でも弥生でも無い、二階堂自身だ。 二階堂は確信しているんだ。お前なら偶然じゃなくても、麻薬取引を押さえる事が出来たと。 自分は偶然でしか出来ない事でも、お前なら必然でこなしてしまう…。 それを認めなかったお前に憤りを覚えたのだ。 …つらいぞ?自分が目標にしている男に埋める事が不可能なくらい差がある事を認めるのは…」 「……。 …おやっさんも…あったのか?そんな事が」 「ん?…まぁお前より少しは長く生きているからな…色々あるさ」 「そうか…」 (乾いた綿のように私が教えた事を吸収するお前の才能と、 私では癒す事の出来ない弥生の悲しさ、寂しさを癒してやれるお前に対してそう感じた事がある、 などどは言えんな……) 事務所内で立ち尽くす男を見て、所長は軽く微笑んだ。 常に分かっていた。 僕では小次郎を越える事なんか出来ないと…。 彼女を振り向かせる事なんて無理だと…。 アイツを越える事と、彼女を振り向かせる事は、同じ事なんだ。 どちらかを達成すれば、もう片方も叶う。 いや、両方達成しないとどちらも叶わない……。 あの2人は…僕にとって眩しすぎるんだ…。 それでも、懸命にどうにかしようと2人の間で必死にもがく、笑えない道化師…それが僕だ。 辺りの静寂が、部屋の闇が、どこか心地よく感じて来た。 こうして1人でいると、まるで世界には自分一人しか存在しないのではないかという錯覚に襲われる。 そうだったらどれだけ楽な事か…。眩しい光を目の辺りにしなくて済んだのに。 例え、一生の孤独が付き纏おうとも。 なのに…何故だろう? まだ自分の気持ちを捨てる事が出来ない。 彼女を振り向かし、アイツを越えたいという気持ちが…。 窓を開け、バルコニーに出てみた。 夜風が吹く、静寂の世界。 だが街の光が未だ人が生きていると教えてくれる。 …ふぅ 考えるのに疲れたようだ。 僕は、今の想いがあったからこそ…ここまでこれたんだ。 この気持ちを捨ててしまったらどうなるか、なんて恐ろしくて想像出来ない。 …しばし、この気持ちに付き合ってみるのも、悪くないか……。 確かに、彼女を振り向かす事は出来ないのかも知れない。 でも、だからといってこの気持ちが変わる訳じゃ無い。 この気持ちは、答えて欲しくて想っているだけじゃ無いのだから…。 確かに、アイツを越えるのは無理かも知れない…今のままでは。 アイツ…小次郎の方法を真似ているだけでは、一生追いつけない。 だったら、小次郎とは別の方法で小次郎の隣まで上り詰めれば良いんだ。 そして……いつか越えてみせる……。 …なんだ、結構単純な答えじゃないか。…あんなにも悩んでたのが、バカみたいだな…。 僕は、自分で自分を笑った。 部屋に戻り、また気に入りのワインを口にしてみる。 ……どういうわけか、今までで1番…美味く感じた…… |
| 四方山話(言い訳) |
|
EVEシリーズのお笑い担当と化している二階堂進。 その進君のシリアスな心境を…と思って書いてみました。 時間軸的には、ZERO直後ですね。 文中でも書いてある通り、一方的にライバル心を燃やしているわけですが 彼が1番小次郎の事を認め、そして目標にしていたように感じました。 妬んでいるというよりも越えたい目標として小次郎を見ていたんじゃないかな…と。 あの時道を踏み外さなければ良い人になってた『かも』知れないのに…惜しい人を亡くしました…。 そしてこの小説はなんと『今まで必ず出ていたあの2人(特に赤い彗星の方)』が名前すら出てない! これはかなりの快挙かも…意図的にそうした訳なんですけどね。 |