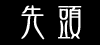| Lady in the hand |
|
今日も静かなあまぎ探偵事務所 既に夕方を迎えようとしていたが、今日かかってきた電話はたったの二本・・・ そのうちの一つは倉庫家賃の催促電話で、もう一つは所長御用達のバーからの電話である 要するに今日も依頼の電話は無かった、というわけだが、 それがもはや当たり前になりつつある所に世の無常を感じずにはいられない所長サマであった 視線を移せば端末の前に座りこんでディズプレイを覗きこんでいる所員が一人 当初はマシンを使った小遣い稼ぎだったはずが、これが何時の間にやらこの事務所の主流になりつつある イリーガルな方法で企業の極秘情報を入手したり、個人のデータを改ざんしたり、あの時のように架空のパスポートを作成する事も少なくない その「幅広い」業務内容のおかげでそのテの世界では結構有名になりつつあり、 最近の氷室はディスプレイの前に座る時間の方が断然長くなっている 探偵としてのプライドなどというやつはペット探しやら浮気調査などでハナから存在しない まだしもマシンを使った仕事の方がスリリングでやりがいがあると言う点でここでも所長は世の無常を感じざるを得ない (やることがない・・・とくれば、オレサマ自慢のアレを手入れするとするか) ソファに寝そべっていた小次郎はやおら起き上がって腰に差してあった銃を取り出した グロッグのカスタマイズバージョン。彼が長年愛用している銃である 既に愛着すら湧いているこの無機質な「彼女」は手入れを怠ると途端に機嫌を悪くする その分普段から手間隙かけてかまってやれば向こうからこちらの期待に応えるようになる・・・それが銃というものらしい (そこが弥生や氷室とは違う点だな) と思わざるを得ない 何しろ銃と違って気ままワガママなくせに、向こうからかまってかまってとせがんで来るのである じゃあかまってやれば期待に応えるかというと・・・これがまたそうでもない かまった挙句にそれを当然のように思う。それがこの「彼女」とは雲泥の差だ、と一人可笑しがる小次郎だった (もっともグロッグと違って撃つのはオレの方だが・・・) などとお子様にはさっぱりな含み笑いを浮かべていた小次郎に氷室が声をかけてきた 「何よ、また銃の手入れ?」 「また、とは随分だな。こまめに手入れしないとすぐに機嫌が悪くなるんだぞ」 「ふ〜ん・・・機嫌がねえ」 「ちゃんと愛情をかけてやればそれにきちんと応えてくれる。それがコイツの良い所さ」 「私の髪と同じようなものかしら」 「髪?」 意外な例えに振り向くと、そこには氷室の長い髪があった 確かにこれもきちんと手入れしなければすぐにダメlになるものなのかもしれない 「銃を髪に例えるとはなかなかの詩人サマだな」 「だってそうでしょ?優しくいたわってあげないとダメなんだから」 「ま、そうかもしれんがな」 そう言うと小次郎は幾つかの道具を机の引出しから取り出した どうやら銃の手入れに必要なモノらしいが、それがどういうものであるかは氷室にはいまいちピンと来ない 以前訓練で習ったくらいだからおぼろげには覚えているのだが、結局任務で使う事など皆無に等しかったし、 それも随分と昔のことのように思えてきたのが一番の理由なのかもしれない ソファに座りこんだ姿勢で作業に没頭する小次郎を背中から覗き込む 彼女の見てきた小次郎は普段は飄々としていて隠された目は常に穏やかなものに見えたのだが、 時折背筋がぞっとするほど冷たい光を帯びる事があった 彼が銃の手入れをする時もそれに近い目をする 無論中途半端な気持ちで触れて良い物ではないことは分かっている それでも、どこか・・・ 「ねえ、小次郎」 「あ?」 「答えたくないなら別に構わないけど・・・その銃で、人を・・・」 「ある」 たった二文字の返答にどれほどの重みと苦しさが込められているのだろう わかってはいたが、それでもどこかこの道具を抑止力としてのみ使っていて欲しかったという気持ちを隠すことは出来ない だからどう、というものでもない。彼が人を撃った事があるからと言って氷室の中の愛情が失われるものでもない だけど、また少しだけ彼との距離が遠くなったような・・・そんな気持ちが胸の中をちくちくと刺して来る ソファの後ろから小次郎の肩を抱いた 分かち合えるものでなくてもその重みを彼一人に背負わせたくなかった そして、その少し遠くなったように感じた距離を取り戻したかった 「始めて人を撃ったときのことは今でも忘れないさ」 銃の手入れをしながら、肩に重みを感じながら小次郎は呟く 「撃った後の反動、体中が震える感覚、そして一人の命を奪った事の衝撃・・・どれも忘れられるものじゃない オレはそれが恐くてたまらなかった。だから二度と人の命を奪う為に撃つまいと思った。なのに・・・」 手入れが済んだ「彼女」の、細くて華奢なフォルムを眺める 銃と言うにはあまりにスレンダーなその姿こそが「彼女」の最大の魅力であり、ともすれば危険な誘惑にもなり得る・・・ そんな所が離れられない理由の一因なのだろうか 「なのにこうして銃を手入れする」 銃を見つめる目には何時の間にか普段の穏やかな光が戻っていた 離れられない危険な「彼女」に対する眼差しじゃない 氷室の知っているいつもの小次郎の目。氷室を見つめるいつもの小次郎の目 「コイツがなければ今オレはここに居る事はできなかった」 「・・・」 「だからせめてコイツを嫌ったりはしない。 コイツは人の命を奪える忌むべき存在であると同時に、それ以上にオレと、オレの大事なものを守ってくれる存在なんだ」 「・・・小次郎」 「ははは・・・どうしようもない言い訳だな。結局オレは銃を手入れしてまた撃つんだ やたらと撃ちまくる目玉のおまわりさんのほうがまだ救われる」 渇いた笑いが事務所に響く 結局それは何処まで行っても都合の良い言い訳に過ぎないことは小次郎自身が一番わかっていた そんな言葉を何よりも嫌っている彼が、それでも口に出さずにはいられない・・・ 肩を抱く氷室の腕に力が入る 小次郎の気持ちが分かっているから、その重みを彼だけに背負わせたくないから (今は・・・私が傍にいるから・・・) 「なあ」 「ん?」 「氷室は銃を持たないのか?」 「私?」 「ああ・・・見た事も触った事も無いってわけじゃないだろ?法条みたいに所構わずぶっ放す事は無いにしても」 「そうね。訓練だってちゃんと受けたわよ。これでも射撃の成績はAなんだから」 「どうする?マスターに頼めば手に入るんだが」 「さっきの電話はそれ?」 「ま、そんなとこだな」 手入れの済んだ銃を腰に差す 有れば有るで邪魔くさい存在だが、無ければ無いで腰の辺りが妙に落ちつかない 小次郎と「彼女」とはそんな微妙な関係でもある 「浮気調査やペット探しには縁の無いシロモノだが・・・どうにもそうは行かないのがこの事務所のステキな所なんでな」 「大使館の時みたいに撃っちゃうわけ?」 「もう一回侵入することがあったらオレが撃ち抜いたシャンデリアを確認しとくか。ちゃんと経費で修理したのかどうか」 「・・・小次郎はどう思う?」 「そうだな。セコい役所と違って大使館だからすぐに直したんじゃないのか」 「違うわよ、銃のこと。私が持つ事をどう思うの?」 氷室は肩を抱いた後ろから覗き込むようにして顔を近付けた 幾分か真剣な表情になっているその顔をちらっと見て、ふっと笑いながら小次郎が言葉を続ける 「技術的な面や精神的な面で参るようなカワイイ性格の持ち主じゃあなさそうだからなあ」 「・・・怒るわよ」 「無くて困る事はあったとしても、オマエならあって困ることは無いんじゃないか?」 「それって私の事信用してくれてるんだ」 「ま、何と言っても元エージェント様だからな。氷室なら間違いないと思う」 「ありがと。でも使わないに越した事はないわ。それでいい?」 「オレだってそう思ってるさ。やたらと『イクイクちゃ〜ん』とか叫ぶのは神経がどうかしてる証拠だぜ」 「法条さんが聞いたら怒るわよ」 「怒りたきゃ怒ったらいいさ。本当の事言ってるだけだ」 「ふふ・・・じゃあマスターさんにお願いしといてね」 「了解」 「でも、できれば貴方に守って欲しいな・・・なんて・・・」 「守ってやるさ」 (・・・え?) 「守ってやる。『そいつはタリスマン代わりに持っとけ』ってのはいけ好かないアイツのセリフだがな」 「・・・ありがとう、小次郎」 「礼はいらないさ。どうせ代金は氷室の給料から天引きなんだから」 「・・・」 「やっぱ怒る?」 「事務所のお金で買うんじゃないの?」 「一緒の事さ。どうせ依頼が来ないんだからな」 「・・・優先順位を間違ってるようにしか思えないわね・・・」 「かもしれんな」 「わかったわ。小次郎が買ってくれるんだもの。銃でも指輪でも同じよね」 「オレが買ってやるのか!?」 「いいでしょ?今まで気の利いたプレゼントなんて数えるくらいしか貰った事ないんだから」 「はぁ・・・おねだりされるのは嫌いじゃないが、銃をねだられるのは何と言うか・・・」 「あら。じゃあダイヤの付いた指輪をお願いしましょうか?」 「オレにそんな甲斐性があるわけないだろ」 「わかってるわよ。冗談」 「それはそれで物悲しい、か・・・」 ◆ ◆ ◆ 「ただいま」 「あら、おかえりなさい・・・って何?その紙袋?」 「この前言ってたタリスマンさ」 「あ・・・」 「マスターなかなか気前が良くてな、『グロッグの弾の方もサービスしときますよ』だと」 紙袋に手を突っ込んでごそごそっと音を立てる まるでリンゴか酒瓶を取り出すような感じで中から銃を取り出した 「ほれ」 「ほれって、そんな簡単に手渡されても・・・」 「やっぱ抵抗あるか?」 「そんなの無いわ、とは言えないわね。あそこを辞めた時以来なんだもの」 「ふーん・・・そうか」 「コルトの45口径・・・随分骨っぽいんじゃない?」 「まあ別に拘ったわけじゃないからな。マスターが最も手に入りやすいヤツを頼んだだけさ」 いつか習った通りに銃を構えてみる 両手に伝わる重みと鉄の感触。目を瞑れば養成学校の訓練室がありありと思い浮かばれて来るようだ 「お、流石構えは完璧だな」 軽い感嘆の息を漏らした小次郎の方に向かって氷室は少し口元を綻ばす その少し照れた微笑はどこにでもある恋人同士のそれに近い ・・・もっとも女性の手に握られている物が銃で無ければ、の話だが 「実際に当たるかどうかは別問題だけど、こうやってきっちり構えるのも抑止力としては大きいわ」 「まあ、ガタガタ震える手で構えてもナめられるだけだからな」 『でも・・・』と言う言葉と共に氷室の顔から淡い微笑が薄らいでいく 『やっぱり重いわね』と続けた後に浮かんだ微笑は、さっきのものとは違って無理に浮かべたようにも見えた ・・・のは小次郎の思い過ごしかもしれない 「どうせなら試しに撃ってみるか」 「知り合いとかに頼んで射撃場を借りるの?」 「んなこと、このオレサマがするわけないだろ」 「い・・・!」 「隣の空き倉庫でぶっ放すんだよ」 「だ、ダメよ!誰かに見つかったら通報されるわ。防音設備もあるわけないのに」 「こ〜んな辺鄙な海岸倉庫、夜ならともかく昼間なんて誰も来やしないさ」 「そりゃそうだけど・・・」 「もしかしたら余程の物好きが昼間から居るかもしれんが、まあそれはそれで・・・」 「・・・今更だけど小次郎の神経の太さを疑うわね」 「おう。神経も銃も太い太い!」 「はぁ・・・」 事務所の隣に立つ空き倉庫の入り口には既にカギなどというものは存在しない そこは時に不良の溜まり場となり、浮浪者の宿となり、刺激を求めるカップルの愛の褥(しとね)となり・・・ そして時に自称天才探偵の射撃訓練場ともなるようであった 誰にでも開放された自由な空間と言っても的を外した表現ではないだろう もっとも最近は隣の倉庫に誰か住み出したようだということで、この自由な空間に立ち寄る物も少なくなってきた 故に最近では「隣の倉庫の住人」が、ここの主な使用者ということになっているらしい ガン!と入り口の重い扉を蹴破ると、そこにはいつ廃棄されたかわからない資材が山積みになっている 案外明るいのは照明設備が整っている訳ではなくて天井に空いた穴の所為であろう 床には何かを燃やした跡やら多種多様のゴミ、スプレーの缶等々・・・ここで何が行われていたかを推察できる証拠には事欠かない 視界に飛び込む賑わいにも増して氷室の感覚に訴えてくるものは辺りに漂う匂いだった 古資材やらゴミやらの匂いもさる事ながら、恐らくはシンナーの匂いと、そして硝煙の匂いが彼女の感覚を刺激する 「・・・と。物好きカップルの一つくらいは居るかもと思ったけどなぁ」 小次郎の顔を見つめる氷室の雑雑な表情には、この場の状況に対する不快感と、 そしておそらくはそれに慣れきって平然としている小次郎に対しての気持ちの現れであったに違いあるまい 「・・・」 「残念ながら先客はナシだ。思う存分撃ってくれたまえ、氷室クン」 「撃ってくれたまえって、標的すら無いじゃないの」 「ああ、それか。向こうの壁に的をペイントしてあるだろ?」 「??」 小次郎の指差した先には壁に描かれた丸い的と、その向こう側にはおそらくは人を意識したと思われるいびつな絵が描かれている 「んで、ここがオレサマのいつもの立ち位置。大体これで10mってとこか」 「あ、あなた、ここで何時も銃を撃ってたわけ??」 「なんだ気がつかなかったのか?週に2、3回くらいはトレーニングしてるんだぜ」 「あっきれた・・・」 「な?いつも一緒に居る氷室ですら気がつかないんだ。何処かで誰かが見てるなんて事は無いから」 ふっと笑って氷室の肩に手を置いた 「思う存分、撃ってくれタマエ」 ぽん、と肩に置かれた手が氷室の気持ちを和らげる 確かに試し撃ちとは言え数年振りの実弾なのだ。知らずの内に力が入るのも無理は無い (肘は絞るように、両手でしっかり支えて・・・) 何時か聞いた通りの言葉を頭の中で呟きながら銃を構える 頭の中で響く声の主はあの時の教官の声に似ていたが、他にも何処からか声が聞こえてくるようだった そちらの声の主は彼女自身の声に酷似していた・・・というよりは彼女自身の声であるのかもしれない (今の私に必要な物なのかしら・・・) (視線の先は必ず的の中心の一点を捉える事) (でも・・・この先使わないで済むことが許されるの?) (銃の衝撃に備える為、そして神経を研ぎ澄ます為に撃つとなったら息を止めて・・・) 引き金を引く。思いのほか小さな音が倉庫内に響く チュイン!と火花が散って、壁に書かれた的の中心に近い所が少しだけ削れた 「ほぉ」 後ろで小次郎が声を上げた。予想以上の氷室の腕に感心している様子だ タン、タンと3発ほど続けて音が響く そのどれもが的の内側に当たっており、何の訓練も無く数年振りに撃ったにしては上出来の腕前である 余程訓練の時にきっちりしていたのだろうと思うと、いかにもそれが氷室らしくてどこか微笑が浮かぶ小次郎だった 「・・・ふぅ・・・」 5発ほど撃った所で氷室は大きく息を吐いた。辺りに漂う微かな硝煙の香りがあの頃を思い出させる もっともそれはあくまで的を狙っただけのものであり、今もそれを忠実に思い出しただけに過ぎない もし実際にこれを使うようなことがあれば、その時は的ではないモノを撃たなければならないだろう 当然じっと動かずに居てくれるものでもないし、今のように動作の一つ一つを思い出す余裕すら無いかもしれない 今のような射撃が、果たしてその時になって十分に発揮できるかどうか いや・・・そんなことよりももっと考えたいことがある (この重さ、体に返って来る衝撃・・・本当に私に必要なものなのかしら・・・) 几帳面な氷室らしく、きっちり安全装置をかけた事を確認して銃を袋の中にしまいこんだ 小次郎は相変わらず倉庫の入り口付近で氷室を見つめている 「お見事。とても数年振りとは思えなかったぜ」 「ふふ、ありがと」 軽く微笑んでお互いを見つめ合う 差し出された紙袋を軽く頷いて受け取る小次郎 氷室は目を瞑り、彼の胸に額を押し当てるようにして寄り掛かる 「氷室」 「・・・うん」 「返して構わないのか?」 「ええ、私にはもう必要無いわ。今の私の腕には重すぎるもの」 「そうか」 「小次郎はそれで構わない?」 「ああ。オマエが考えて決めたことだ。必要の無い物をムリヤリ持たせる程オレもお節介じゃないさ」 「それにこんな重いもの身につけてたらペット探しの邪魔になるだけだわ」 「ははは、違いない」 「じゃあ、悪いけどマスターさんに返してくれるかしら?」 「わかった。まあさっきの弾代くらいは請求されるかな」 「それとも私が行きましょうか?」 「ん?」 「そのまま小次郎に突っ返されたらマスターさんも気の毒でしょうから・・・」 「それじゃあ今から行くか」 「小次郎も?」 「帰りに何処かでメシ食って帰るのも悪くないだろ」 「そうね。勿論小次郎の奢りでしょ?」 「・・・ま、いいか。ダイヤの指輪ねだられるよりは安いもんな」 「あら。何か言った?」 「気のせいだろ?まだ反響で耳が戻ってないのさ」 「ふふ、ウソばっかり」 ◆ ◆ ◆ 「いらっしゃい。ああ、小次郎さんですか」 「こんばんわ」 「氷室さんも?やだなぁ、夫婦お揃いで来るような店じゃないですよ、ウチは」 「自分の店だろう?それに誰が夫婦だ、誰が!」 「ごめんなさいマスター。これ、お返しするわ」 「ああ、さっきのコルトですね。お気に召しませんでした?」 「ううん、そうじゃなくて・・・私には必要ないモノだってわかったから・・・」 「なるほど、そうですか・・・小次郎さん」 「あ?」 「やりますねぇ。流石です」 「何だ何だそのニヤけた笑いは・・・」 「い〜え、別に・・・わかりました。氷室さんの出した答でしたらそれで間違いないんでしょう」 「ごめんなさい・・・」 「そんな構いませんよ。そうでしょ?小次郎さん」 「だからオレに聞くなっての」 「でも、そうですねぇ・・・さっきの弾代くらいは請求させてもらいましょうか」 「ああ。こっちもそのつもりさ」 「流石小次郎さん、話が早い。じゃあ、折角ですからもう一つ・・・」 「あの、他に何か?」 「折角ですから何か頼んでくださいよ。それで手を打ちましょう」 「頼む?酒をか?」 「他に何頼むんです?あっちの方は暫く必要ないんじゃないです?」 「オマエ、さっき自分で『ウチの酒は不味い』って言ってただろうが」 「失礼ですねー。そんなこと言ってませんってば」 「同じだ、同じ。この店で酒なんか頼めるか・・・」 「あら、いいじゃない。折角なんですもの。そうでしょ?マスター?」 「そうそう。氷室さんの言う通り。折角の夫婦水入らずなんですから」 「・・・今度言ったらグロッグで撃ちぬくぞ・・・」 「やだなぁ。テれなくてもいいじゃないですか」 「・・・ジントニックだ」 「私も同じやつで」 「かしこまりました。少々お待ち下さい」 口の端にニヤけた笑いを浮かべたままでマスターは奥へと消える どうにもバツの悪そうな小次郎を見つめていると自然に笑みが浮かんで来る・・・ そんな小次郎が可愛いから、そんな自分が嬉しいから笑みはまた浮かんでくるのだろう 「ふふふ」 「はぁ・・・」 「何よ、溜息なんか吐いちゃって」 「知るか・・・とっとと酒飲んで出るぞ」 「いいじゃないの、たまには」 「どうせ飲むなら事務所でビール飲むのも同じだろ。わざわざここの賞味期限過ぎたような酒なんか飲めるか」 「もう・・・ムードのかけらもないわねぇ」 「ここ以外のバーだったらどこでも出るさ」 「ふふふ、それもそうね」 顔に浮かぶ微笑を曇らせて氷室は呟く 眉を少しだけ寄せて顔を伏せる仕草・・・小次郎の前以外では片鱗も見せない、本当の彼女の一部分 「でも、今日は少し飲みたい気分だわ・・・」 「あ?」 「まだ少し、さっきの感触が残ってる」 「氷室・・・」 「本当は、もう小次郎にも銃なんて持って欲しくは無いの」 「・・・」 「さっき倉庫で試し撃ちした時、貴方の肩の傷の事を思い出したわ」 「あの時の、か」 「ええ・・・確かにあの時、小次郎が銃を持っていなかったら私たちは死んでいたかもしれない だけど、助かったけれど、貴方の肩には大きな傷が残ったわ あの時の肩の傷口、今でも忘れない・・・私を守ってくれたんだもの・・・ だけど、叶わないかもしれないけど、小次郎には二度と・・・」 そっと氷室の手の上に自分の手を置いた ひんやりとした手に少しだけ震えを感じる・・・ 「大丈夫だ」 「あ・・・」 「オレにはコイツが居てくれる。目の前のヤツくらいは守ってやれる 信じてやらないとな、コイツのことを」 「だけど・・・」 「心配するなって。オマエが言った通りペット探しには不要なだけだから」 「・・・そうね、信じないと」 小次郎の首に手を回して抱きつくように唇を重ねる お互いの手は重なったままだったが微かな震えは既に収まっていた 予想外の奇襲に慌てる小次郎の視界の隅には努めて気配を消そうとして近付いてくるマスターの姿があった 「お、おい・・・」 「ジントニック」 「ぬな!!」 「お待たせしました」 「おい、氷室!おい!」 「ごゆっくりどうぞ。私は奥に居ますから」 「・・・」 「小次郎?」 「・・・ジントニック、来てるぞ・・・」 「え?あ、やだ・・・ちょ・・・これって・・・」 「・・・」 「・・・」 店内に流れるピアノジャズ。カウンターには男が一人、女が一人 二人の目の前にはすこしきつい芳香が印象的なカクテルが二つ 店の奥では笑いを堪えるマスターが一人 カクテルの水面には、天井で回る扇風機の羽と、 まだ飲んでもいないのに真っ赤な顔をした女の顔が映っている |
| 四方山話(言い訳) |
|
どうも。毎度毎度の氷室バカtalkでございます。 何だか久しぶりの氷室-小次郎夫妻モノを書きました。 ネタの大元はサターン版burst errorのおまけCDにあったと思いますが、 氷室が銃を構えているラフ絵を見て、って感じですかね。 弥生も氷室も「EVE」に関してはかなり深入りしてる人物だと思いますので、 自身に来るであろう事態というヤツをそれなりには意識してると思います。 そんな感じで今回氷室に銃を持たせてみて、んでもって拒んでみましたが、 皆様の中ではどんな感じになっておりますでしょうか? 最新作TFAの一画面でプリーチャーに襲われる弥生が、 恐る恐るながらも銃を構えているシーンがありましたので、 次作では彼女達にも何かしらの覚悟が課されるかもしれませんね。 読んでくださった皆様、 「相変わらずコイツってバカだよね」と思ってくだされば幸いです。 |