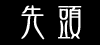| そこに居る夏 |
|
夏 連日続く灼熱地獄 それに伴って電気代の方もうなぎ登りになる時期だが、まあそれはそれで喜ぶ人達がいるのかもしれない だがしかし、ここに一人「電気代の節約」という名の下で文字通りの地獄を体験している人物がいた 「あ〜〜つ〜〜い〜〜」 汗ばんで乱れた髪の数本がうなじにかかっている 目にする時と場所によってはコレ以上無い色っぽい光景であるはずだが、 それを期待するにはあまりにもシチュエーションが違いすぎた 「と〜〜け〜〜る〜〜」 だらしなく舌を出しているのは、そこから熱を発散させようと言うイヌの習性に似ているものなのだろうか 机に突っ伏し朦朧とした視線で上司の方に視線を向けている女性の姿がある 机の上には一時間ほど前から一文字の文字数も増えていない報告書が、 彼女の汗ばんだ腕の所為で悲しそうにふやけている 「本部長〜〜、し〜〜に〜〜そ〜〜うぅぅぅぅ」 視線の先には「管理職特権」で個別の扇風機を宛われている甲野の姿がある ダンディ中年を自称するこの男は流石に夏場でもスーツをビシっと着こなしているのだが、 それに負けずにキリリとした態度を保ち続けるのもダンディたらんとする彼の意気込みなのだろうか それとも個別の扇風機から送られてくる風のおかげなのだろうか 「あ〜〜〜。セントラルアベニューで評判のイタリアンジェラードが食べたい〜〜」 「・・・」 「ジェラ〜〜ド〜〜。バニラでもモカでもいい〜〜」 「まりなくんさぁ・・・」 部下から投げ掛けられる怨嗟にも似た言葉に堪りかねた甲野が声をかけた 「我々は仮にも警察官なんだよぉ?もうちょっとビシっとしなさい、ビシっと」 最近伸ばし始めたというヒゲが扇風機の風に当たってそよそよ靡いている このうだるような暑さの中ではヒゲですら憎らしい いや、そもそも特権として与えられた扇風機を我が物のように占領しておいて、 カワイイ部下にはその恩恵をこれっぽっちも分け与えてくれないその根性からが憎らしい ・・・が、その言葉を発する気力すら湧いてこない・・・ じーーーー 「ちょ、ちょっと何よ、その恨めしい目は」 「ジェラード〜〜」 「今は勤務中」 「じゃあ勤務明けにビヤガーデン〜〜」 「今は給料日前」 じーーーーー 「そーんな目で見ても駄目なものはダメ。だいたい一昨日も私にビール奢らせたでしょ?」 「カワイ〜イ部下の為に上司がポケットマネーを出すのはあ〜た〜り〜ま〜え〜〜」 「そこは否定しないけどね・・・幾ら何でも大ジョッキに7杯は飲み過ぎだよ」 「身体が水分を欲するの〜〜」 「『頼むの面倒だからメニューの上から下まで持ってきて』って言ってガツガツ食べたのは誰よ?」 「身体が栄養を欲するの〜〜」 「飲むだけ飲んで、食べるだけ食べて『甲野すぁん、愛してるわぁん』って言ったのは誰だい?」 「う”〜〜〜」 「おかげで私は今月の残り、毎日ほか弁でお昼を過ごさなくちゃならないんだよ?」 「う”〜〜〜」 「とにかくジェラードもビールも駄目。仕事に集中集中」 「だったらせめてクーラーくらい点けてよ〜〜」 「仕方ないじゃない。署の方で節電だって言って部署事に日替わりで冷房止めてるんだから」 「何もこんな暑い日に止めなくても〜〜」 「最近は内にも厳しく、が求められてるからねぇ」 「あ〜〜、何か事件でも起きないかしら〜〜。そうすれば冷房の効いた会議室に集まれるのにぃぃぃぃぃ」 「不謹慎な発言しないの」 「う”〜〜〜」 それっきりまりなは言葉すら発しないようになった 心身共に溶けきったな、と甲野は見る しかし実はそうではなかった 確かに「身」の方は溶けていたかもしれないが、「心」の方は現状を打破するための様々な策を打ち立てている ・・・要するにどうやってサボるかを考え出しているのだが (そうだわ!!) 数分の沈黙の後、天啓にも似た良案を閃いたまりなはガバっと起きあがった 「本部長!!」 「なな、なにかね?」 「今から高畠に会って来ます!」 「へ??」 『つまり』と訳の分からない接続詞から演説は始まった 「先日の殺傷事件の被害者には不審な点がまだまだ存在しておりまして、 この謎を徹底的に究明しないことには市民の皆様、果ては国民の皆様が安心して夜も眠れないのではないかとワタクシ案じておりまして、 であるから、一刻も早い解決へ辿り着くために今は被害者の状態を確認するのが最良且つ最善かと思いついた次第でありますですます!」 「・・・」 じーっとまりなの顔を見つめる甲野 彼女の狙いは鑑識の冷房にあるのは明白だが、ここでそれを咎めればこの後どのような出費が・・・いやいや仕返しがあるかわからない 「ま、いいでしょ」 「はい!不肖法条まりな、国民の皆様のために全力で頑張って来ます!」 「(・・・他への体面ってのもあるから早々にお願いよ・・・)」 「(本部長♪愛してるワ♪)」 ウインクを一つ残して意気揚々と部屋を出るまりな 甲野はふぅと溜息を吐いて彼女の遠ざかる背中を見つめていた (『甲野すぁん』じゃないだけマシかな・・・) ◆ ◆ ◆ 「高畠ー!邪魔するわよーーん!!」 「やぁ、いらっしゃい」 「ふわぁぁぁぁぁ、すっずし〜〜〜〜い」 「・・・いきなり本音が出るんだね、法条は」 「だってこの暑さの中、『節電だ!』っちゅーんで冷房ナシよ!」 「まあ署長の考えそうなことだけどね」 「全く・・・下々の恨みとかは考慮に入れてないのかしら?」 「今年の暑さはかなりのもんだからね。下々の恨みより目の前の電気代なんだろ」 「だったら所長室の冷房も切ればいーじゃないの」 「指揮を下す将官は何時も安穏とした司令室を好むのさ」 「何様のつもりよ!全く!!」 「我等が署長サマ」 「所長室の冷房のファンに警棒でも突っ込んでやろうかしら」 「これ以上始末書が増えたら甲野さんもいよいよヤバくなるね」 「・・・ちょっと」 「ん?」 「人のストレスの発散に一々つっこまないでくれる?」 「こりゃどうも」 「アンタはいいわよねー。一日中こんな涼しい部屋で過ごせるんだから」 「確かに涼しいよねえ。なんなら法条もここで過ごしてみるかい?」 「・・・遠慮しとくわ・・・」 「大丈夫だよ。どっかのゲームみたいに死体が起きあがったりしないからさ」 「それもそうだけど、アンタと一日中居るのもぞっとしないわね」 「・・・そりゃどうも・・・」 ここは鑑識課の安置室 まりなの同僚高畠が「住む」一室である 保管しているモノのおかげで一年中室温は低めに保たれているし、部屋の存在理由が故にこの部屋に近付く者も殆どいない まさに穴場中の穴場。サボりにはうってつけの空間であろう しかしそれも同僚である高畠が居るからこそだということはまりなも承知している (・・・でなければ誰が好き好んでこんな気味悪い部屋にやって来るっていうのよ・・・) 「法条、お茶でも飲むかい?よく冷えた麦茶があるけど」 「お、いいわねぇ。出来れば泡の出る麦茶がいいんだけどなぁ♪」 「それ、この前も言ってなかったかい?」 「分かってるんなら置いときなさいよねー」 「むちゃくちゃ言うなぁ」 「じゃあ今度来たときに泡の出る方を出してくれたらちゅーしてあげるわ。これでどう?」 「いいねぇ。じゃあよく冷えた日本酒だったら?」 「ワタシをあげちゃう♪」 「・・・明日酒屋でも回ってみようかな・・・」 「言っとくけど、酔い潰れたアンタを私が襲うんだからね」 「いいなぁ、それ・・・」 ドゲシ! 「・・・痛い・・・」 「つべこべ言わずにお茶!」 「へいへい」 冷蔵庫からラベルのないペットボトルに入った麦茶とよく冷えたコップを取り出す 空になったボトルにお茶を入れているとは随分と主婦地味た所だが、 設備やらの為に始終節約を強いられている鑑識の人間にとっては最早当然の行為なのだ まだしもビーカーやフラスコに入っていないだけマシよね、とはまりなの偽り無い心境だろう もっともそこに慣れきったあたりがサボりの回数と比例していることの証明でもあるわけだが・・・ 「はい、どうぞ」 「さんきゅー。喉カラカラだったのよねー」 グイっとコップを煽ってんぐんぐんぐ・・・ 「ぶはぁ〜。美味しかったぁ〜。やっぱ日本の夏には麦茶よね〜」 「もう一杯いる?」 「もっちろん♪二杯目こそがうまさの真髄よ!」 コップに注がれる麦茶の音、続けて響く喉の鳴る音、飲み干したコップを机に力強く置く音 どの音も静かなこの部屋ではよく響いた 「ふぅぅぅ!さいっこう!!」 「ははは・・・麦茶で最高とは光栄だね」 「それにしてもよく冷えてるわねぇ。やっぱここの冷蔵庫は強力なのかしら」 「いや、それを入れていたのは普通の家庭用のヤツさ」 「あらそう?」 「幾ら何でも死体保管用のヤツに食べ物は入れないよ」 「アンタなら平気でやりそうだけど」 「まあ急速に冷やしたいときはやるけどね・・・って冗談だよ、冗談」 「どうだか・・・」 「でも確かに家のヤツに比べたら効きはいいねえ」 「でしょ?やっぱ消費電力の差かしらねえ」 「いや・・・」 高畠は眼鏡をクイっとかけ直し、やたらと真剣な口調で話し出す 薄暗い照明に照らされた眼鏡のレンズが不気味に光り、口端を形良く吊り上げる彼特有の笑みが浮かんで来る 「やっぱりアレじゃないかな・・・」 「あ、アレって何よ」 「法条もわかってるだろ?この部屋独特の涼しさだよ」 「う”・・・」 「幾ら冷房が効いてるからってこの涼しさは尋常じゃないよね」 「そ、そうかしら・・・」 「あの冷蔵庫だって随分と古いやつだからねえ。ボクが来る前はひょっとしたら違うものを冷やしていたのかもしれないし・・・」 「や、やめてよ・・・十分涼んだんだから・・・」 「いやぁ、その麦茶もいつの間にか冷蔵庫の中にあったんだよね・・・ボクは入れていないのに・・・」 「だ、誰か他の人が持ち込んだんでしょ・・・?」 「それが他の誰に聞いても憶えが無いって言うんだ。ひょっとしたら・・・」 「いやぁぁぁぁぁ!」 ドゲシ! 「ぐはぁっ!!」 「あ、ごめんごめん。当たっちゃった?」 「うふふ・・・法条のパンチって効くなぁ・・・」 「しっかし、それにしても何処かしら気味の悪い冷蔵庫よねえ」 「そうかな?」 「絶対そうよ!なんかこう、低く呻いている感じもするし」 「それはどの冷蔵庫もそうだよ」 「中に何が入ってるのかしら・・・まさか・・・」 と言ってやおらに冷蔵庫の中身を物色し始めた 『まさか』と一応は怖がっているものの、その直後には物色し始めるあたりが彼女の動物的とも言える行動の原型なのだろう しかも心の何処かで謎の病原菌の詰まったシャーレとかを期待しているのだ そんな辺りを踏まえての物色だと言うことを承知しているのはこの署内では高畠と甲野くらいなもので、 後に甲野が「猛獣使い」の称号を与えられるようになったのも、まりなのこの純然たる好奇心を熟知していたからであった 「何よフツウじゃない・・・ってアレ?」 「うん?」 「んふふふふふ〜。高畠くーん。いいモノがあるじゃないかね」 「?」 満面の笑みと共に振り返ったまりなの右手にはよく冷えた缶が握られている 「ああ、それか」 「何よ何よ。ちゃんとお酒、あるんじゃないの」 「それ、確か先週鑑識の先輩が本庁の方にお呼びが掛かったときのお祝いで飲んだときのヤツさ」 「いい具合に冷えてるじゃな〜い」 「ボク、お酒は飲まないからね。だからと言って捨てる訳にもいかないし・・・で、そこに入れてたのかな」 「お酒って言ってもこれチューハイよ。ジュースみたいなもんじゃないの」 「まあ法条にとっちゃあ、日本酒も水みたいなもんだろうけど」 「言うわね〜ってあまり反論できないところが情けないんだけどさ」 まりなは急にしなを作って、お尻で冷蔵庫のドアをパタンと閉めた 「ねぇん、高畠さん?」 何故か瞼を半開きにして同僚の名を呼ぶ やたらとお尻を振って彼の近くまで歩み寄ると、ひんやりとした缶を高畠の頬に軽く当てた 缶の反対側ではまりなも頬を当てている。勿論瞼は半開きのままで 冷蔵庫の奥から発見したチューハイを手にして後のこのイカれた言動 彼女が何を言わんとしているか、何を欲しているか・・・それを瞬時に理解できるのも署内では二人に限定されるのではないだろうか 「何だい?」 「私ぃ、喉渇いちゃったの」 言い寄られている方は『さっき麦茶を2杯も飲み干したじゃないか』と言った目で空になったコップを見つめている 「そしたら冷蔵庫にぃ、ジュースがあったのぉ」 「で?」 「飲んでもいいかしらぁ?」 「ジュースを?」 「そ、ジュ・ウ・ス♪」 「どうぞ。暑い夏にはよく冷えたジュースだよね」 「うふふ〜ん。ありがと!」 プシっ!と言う音が室内に響く 小さい缶の飲み口からは炭酸のシュワシュワと言う音が少しづつ漏れ聞こえている まりなはその小さい音の一つも逃すまいとする勢いで中の「ジュース」を口に含んだ 「それにしても美味しそうに飲むねえ」 「あら、高畠はお酒全然ダメ?」 「飲めないわけじゃないけど、美味しいとは思えないなあ」 「一口飲んでみる?」 「いや、遠慮しとくよ」 「折角なんだから飲みなさいよ。勤務中に隠れて飲むのが美味しいんじゃない」 「・・・中学生みたいだね」 「いいからいいから!なんならまりなおねーさんが飲ませてあげましょうか?」 二口目を口に含んだかと思うと、おもむろに高畠の唇を狙ってキスをした (!!?) あまりに予想外の出来事に硬直する高畠。口の中のあちこちではじけている炭酸が少し痛い 仕掛けた方はイタズラが成功した子供のような笑みを浮かべて口元をぐいっと拭っている 一方の仕掛けられた方は一瞬の口付けが終わっても尚呆然としたままで動けない 口の端からは少しジュースがこぼれだしているのに、それすら気付いていないらしい こくん ようやく口の中のジュースを飲み込めた時に出た小さい音はまりなの耳にも届いた 「どう?美味しいでしょ?」 「え・・・う、うん・・・」 「さっき言ったじゃない?お礼よ、お礼」 「ありがと・・・」 「じゃ、私そろそろ戻るわね。ジュース御馳走様」 「お酒飲んだのに、顔は赤くならないんだね」 「ふふ。アンタは赤いわよ。じゃ〜あねえ〜」 半ば呆然とした感覚の中で、軽やかなステップで去っていくまりなを見つめ続けた 机の上に視線を落とすと、まりなの残して行った缶の中にまだ少しだけ中身が入っている もう一口だけ、今度は自分でお酒を口に含んだ (ははは・・・甘くて苦いってヤツかな?) ほんわりとした「酔い」に涼やかな笑みを浮かべる高畠 だが彼は、この後に訪れるであろう悲劇を予想できるほど全知でも全能でもない・・・ ◆ ◆ ◆ それから数時間後のビアガーデン 空になった幾つもの大ジョッキとお皿を目の前に並べられ唖然としている男に向かって愛を告げる女性の姿があった 『高畠すぁん、愛してる♪』 ・・・ あの後、勤務時間を終えて家路に着こうとする高畠を一人の女性が待ち伏せしていた 『高畠すぁん』 と何処かで聞いた口調で名前を呼ばれて腕を組まれた瞬間、 彼の脳裏には今まさにここで展開されている通りの光景がありありと浮かんでいたことだろう 同時にお札の数枚に羽が生えて彼方へと飛んで行くヴィジョンも見えていたに違いない ・・・ (できればもっと違うシチュエーションで言われたかったなぁ) 苦笑いを浮かべつつまりなの顔を見つめる これ以上ないという満面の笑みが頬の紅みのおかげでもっと眩しく見えた 「愛してるぅぅぅぅぅ〜〜」 「はいはい・・・」 「何よう?こんな美人に『愛してる』って言われて嬉しくないの〜〜?」 「嬉しいよ」 「だったらもっとこう、カンゲキを表情に現してもいいでしょおおお?」 「いやぁ、ボクは感動が表に出ない方でねえ」 「だけど昼間は真っ赤になって硬直してたじゃないの〜〜」 「いや、アレはいきなりで・・・」 「うきゃきゃきゃきゃきゃ!照れちゃってかわい〜い♪」 酔っ払いに腕を掴まれながら店へ店へとたらい回しにされた夜 見上げるとお月様が綺麗な三日月になっていた 「きれいなおつきさまぁ〜〜」 「そうだねぇ」 「よーし!おつきさまに乾杯でもう一軒行ってみよ〜〜う!!」 ぐいぐい引っ張られる腕に胸の感触が伝わる 汗をかいて少し冷たかったその感触がいかにも可愛くて、彼女らしくて、彼女らしくなくて・・・ 「あ〜〜。高畠のえっちぃぃ」 「ははは。やっぱりバレてた?」 「えっちな男は嫌われるわよぉ?」 「・・・そりゃどうも・・・」 「男はもっと渋くて、頼り甲斐があって、それでいてシャープで、だけどだけど実はナイーブで・・・」 「はいはい・・・」 まりなの「真の男像」の御高説が路地に響く 穏やかな笑みで聞き流す彼の頭上では三日月が相変わらずの淡い光を照らしていた |
| 四方山話(言い訳) |
|
どうも。毎度毎度の氷室バカtalkでございます。 ウメ様力説の「まりな×高畠」に影響されて作成いたしました。 一応夏ということで酒が出てきますが、 それでなくてもまりなを書くと酒が絡んできそうです とある業界の専門用語的読み方によると「A×B」の組み合わせの場合、 前者(=A)の方がイニシアチブを取ることになっておりますので、 ワタクシの場合もまりなにイニシアチブを取らせてみました(爆) っていうかそうじゃない彼女なんてちょっと想像つかないわ・・・ 勿論いつもの私の場合は間違いなく「氷室×小次郎」になるわけですね〜 複雑な方程式でしたが、知らない方がイイと思いますので皆様忘れて下さい。 読んでくださった皆様、 「コイツのまりなってこんな感じなのね」と思って下されば幸いです。 管理者より:「A×B」って「AバーサスB」のことかと思ってました。本気で。いや、勉強になりました。 |