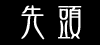| LOVEエプロン |
|
「ただいま。クライアントへの調査報告、済まして来たぞ」 事務所のドアを開けて声をかける。いつもなら「おかえりなさい」といったアイツの声が聞こえてくるはずだが・・・ 「・・・」 「氷室ー?いないのかー?」 「・・・・・・」 「全く。出ていくならカギくらい・・・っておおぅ!」 「・・・・・・・・・」 氷室はソファで本を読んでいた。かなり本に没頭しているらしく、オレが帰ってきたことも気付いていないようだ 「な、なんだ居たのか。居たら居たで返事くらい・・・」 「決めた!」 突然声を張り上げて立ち上がる氷室。いつにも増して真剣な表情のようだが・・・ 「!!?」 そしてこちらをキッと睨むような視線で見る。その眼光の鋭さには思わず後ずさりしそうになる程の迫力があった 「小次郎!」 「は、はい!」 「何が食べたい?」 「・・・へ?」 「今晩、何が食べたい?」 「そ、そうだな・・・昨日はコンビニ弁当だったから、今日は軽いモノが・・・」 「違うの!」 「違うって何が?」 「何を作って欲しいかってこと!」 「作る・・・?」 「そう!」 「夕飯を?氷室が?」 「そうよ!」 「でもオマエ、自分で料理が出来ないって・・・」 「何が食べたいの?」 鬼気迫る眼光の前に、オレの言葉はかき消された。しかしいきなり「何を食べたい?」って迫られてもなぁ・・・ 「何が食べたいの?」 顔をグっとオレに突き付ける様に近付けて、もう一度聞いてきた 「じゃ、じゃあカレーで・・・」 とりあえずカレーという言葉が口から出た。何故カレーか、と言われてもわからない。本当に頭にポンと浮かんだのがカレーだった、というわけだ 「カレーね?カレーなのね!?」 「あ、ああ・・・」 「わかったわ!じゃあ今から材料買ってくる」 「お、おう・・・」 颯爽と事務所を後にする氷室。後に残されたオレはただただボーっと立ち尽くすだけだった 「りょ、りょうり・・・出来ないって・・・」 既にそこには居ない氷室の背中に話しかけてはみたものの、返事が返ってくるはずもない 呆気に取られたオレは暫くの間、ドアを見つめていた 「ふー・・・」 溜息一つ吐いてソファに座りこむ 「アイツが・・・料理ねえ」 普段やらない料理をするのに気合を入れるのは分かるが、それにしてもあの鬼気迫る眼光はなんだってんだ? 「・・・」 つい数分前の、アイツの表情を思い浮かべる 「フフ・・・ハハハハハ」 あの表情。そしてアイツの苦手な料理・・・きっと数時間後には事務所のキッチンで悪戦苦闘する氷室の姿が拝める事だろう 「カワイイ所もあるじゃないか・・・ハハハ、ハハハハハ」 誰も居ない事務所に笑い声が響く。今夜は久々に楽しい夕食が過ごせそうだ ------------ 「ただいま!」 事務所のドアが開くと、そこには相変わらずの表情の氷室が居た 「おう、おかえり」 氷室はドサっと買い物袋をテーブルの上に置くと、中からエプロンを取り出した 「そっか・・・そんなモノこの事務所には無かったな」 「ええ」と軽く返事をして氷室はエプロンを身につける。料理をしない、という割にはなかなか似合ってるじゃないか (それとも普段見慣れていないからかな?) と不謹慎な感想が頭に浮かぶ。もっとも口にしたところで今のコイツの耳には届かないだろうが・・・ 「何か手伝おうか?」 「ううん・・・貴方は座ってて」 (アナタ・・・ね) いつもならオレの事を「小次郎」と呼ぶコイツが、ことさら使ってみせた「貴方」という言葉 言われた方も、そしておそらく言った方も幾ばくかの緊張を感じたに違いない (それほどのもんかね)と思うと、またしても笑いが込み上げてくる 「まずは材料を切って・・・と、次に・・・」 キッチンでブツブツ言うアイツの後姿を見ると、思わず後ろから抱き締めたくなる衝動に駆られる だが・・・ (折角、だもんな) 愛の手料理というヤツを食す、滅多に無い機会だ。今抱きつくのはお預けだな そのぶん、ベットで・・・エプロンのままというのもなかなか・・・ などとオレがあらぬ想像をしている時だった 「・・・言っとくけど」 包丁の動きを止めて、氷室はいきなりこちらを振り返った。頬はほんのりと赤みを帯びている 「い、今はダメだからね」 「・・・」 ・・・読まれたか・・・しかも「今は」と来たもんだ。よっぽど今のオレからはヤらしい光線が発せられているんだろうな まあ「今は」と完全に否定しない所が、可愛らしい所でもあるわけだが・・・ はいはい、と返事をした後オレはテレビのスイッチを点けた ・・・ トントントン、と言う音が聞こえる お世辞にもリズミカルとは言えないが、こんな音をこの事務所で聞いたのは何年振りだろう (あの時以来、か・・・) 最後に作ってもらったのが一国の女王サマとはねぇ・・・つくづく妙な巡り合わせだな・・・ 「・・・炒めた後は、煮込んで・・・」 しかし・・・ 元諜報機関のエージェントで、探偵稼業に必要なスキルも殆ど備えてるコイツにも苦手なものがあるんだな しかも、それが料理とは・・・ 「やだ!焦げちゃったじゃない!」 ・・・ 「んもう・・・どこがいけないのかしら・・・」 ・・・ 「あ〜ん、もうどうしてこんな味になるのよー」 ・・・わざと、じゃないよな・・・ 「これを入れて・・・やだ!美味しくなったじゃない!」 ・・・ 「私って才能あるのかも♪」 ・・・カワイイ・・・ 「スグに美味しいのが出来るから待っててね、ア・ナ・タ♪・・・なんちゃって・・・」 ・・・ 「?小次郎?どうしたの?」 「え!?あ、いや・・・何でもない」 「そう。もう少しだから待っててね」 可愛くて見惚れてた・・・とは言えないよな・・・ 「これでよし!っと。後は暫く煮込んだらオッケーね」 ・・・今夜は覚悟しとけよ・・・ ------------ 「お・待・た・せ〜」 料理が出来たようだ。大き目のナベを持つ手には、おそらくこれも今日買ったであろうミトンが着けられている 「あんまり自信ないんだけど・・・」と言いながらも氷室の表情は明るい 「どれどれ・・・」 「ちょっと!」 「んあ?」 「いただきます、くらい言ってくれないわけ?」 「え、ああ、わりぃわりぃ・・・いただきます」 クスっと笑いながらどうぞ、と返してくる。そっちから要求しておいて笑顔で返すとは・・・どうもこういう時の女というやつは理解に苦しむ 「・・・」 「・・・どう?」 「美味い・・・」 「ホントに?」 「美味いぞ、このカレー」 「やだ、嬉しい・・・」 「おまえ、苦手とか言いながら料理得意なんじゃないのか?」 「苦手よ。今でも自信ないわ。でもカレーくらいは私でもできるってことよね」 「ホント美味いぜ、オマエも食べないのか?」 「ううん。貴方を見てるだけで十分♪」 「ハハハ・・・バカかオマエ?」 「あ、言ったわねー・・・あら?」 「ん?どうした?」 「ご飯粒・・・」 「ば・・・いいよ」 「いーじゃない。照れなくても」 「こ、これくらい自分で取れる」 「あん、動かないで。一度やってみたかったんだから・・・」 そういうと氷室は手ではなく、顔を近づけてきた 唇の端についたご飯粒をペロっと舐めて取り除く ガマンできなくなったオレはそれに合わせて唇を重ねた。一瞬戸惑った表情を見せたが、すぐに氷室も目を閉じる 「ん・・・」 「・・・」 「ふふふ、私の作ったカレー、美味しいじゃない」 くすくすと笑う氷室。たまらなくなったオレはそのままソファに押し倒した 「やだ・・・もう、エプロン外してないんだから・・・」 「そういうのもなかなか・・・」 「ばか、ちょっと・・・もう・・・ホントに怒るわよ」 「一度やってみたかったんだな、コレが」 「もう・・・」 と言いつつも向こうから腕を絡めてくる 「ね」 「ん?」 「残ったヤツもちゃんと食べるって約束する?」 「おお、美味いモノは最後まできっちり食べるぞ」 「ふふ・・・ありがと」 ------------ 料理が苦手、と言った氷室は確かに苦手だった。だが、少なくともカレーに関しては自信がついたみたいで・・・ この後も色々と失敗作を食わされる目にも遭うわけだが、そういう後には決まってカレーが食卓に上るようになった その度に味もよくなっていくのだが、どうもこれ以外は相変わらず苦手なまま、のようだ 「まあ、カレーには不自由しなくなったな」 「はぁ・・・料理ってやっぱり苦手・・・」 「そんなことないさ」 のやりとりがこの後何回も続くようなる。その度に暖かいものでオレの胸が満たされていく 「料理は味の良し悪しで決まるもんじゃないんだぜ?」 氷室が一度ハンバーグと称して、真っ黒なケシズミを食卓に乗せた時のことだった がっくりと肩を落した氷室の横に並んで座って、髪を撫でながら言ったことがある 「・・・うん」 「料理ってものは・・・」 「・・・」 「・・・」 「・・・料理ってものは・・・なに?」 (味よりもオマエの気持ちが嬉しい、だなんて言えねえよな・・・) 「その・・・なんだ、アレが大事なんじゃないかな」 「フフフ、何よそれ」 笑ったところを見ると、オレの心が読まれた、ということだろう 「だから、な、そう落ちこむなって」 氷室は「ありがと」と言ってオレの肩に寄り添う様にもたれかかってきた 肩を抱いて少しだけこちらに引き寄せる 「さ、片付けようぜ。今日はオレも手伝うよ」 「うん・・・」 と言いながらも氷室は身体をこちらに寄せて来た 「もうちょっとだけ、ね?」 「おう」 肩を抱いていた腕をもう一度髪に伸ばし、長い髪をゆっくりと撫でる 目の前には焦げついたフライパンに、材料の切れ端が散乱した流し・・・傍らにはオレに寄り添う氷室の長い髪 事務所中に漂う焼き焦げた肉の臭いと、愛しさすら感じさせる淡い髪の香り 元エージェントで仕事はそつなくこなせるのに、料理ができないコイツ・・・ 「ハハハ、このアンバランスさが醍醐味ってヤツだな」 ?という顔でオレを見つめる氷室 その顔に軽くキスをした後、どちらともなくクスクス笑い出した 「片付け・・・しましょうか」 「ああ、やろう」 氷室はすっと立ちあがり、エプロンの帯をもう一度きゅっと締めなおした 「片付けも料理の一部よね?」 意気揚々と流しに向かう氷室。几帳面なコイツは片付けという作業には苦痛を感じないようだ 料理で失敗した分、自分の好きな片付けくらいはきっちりやろうと思っているのかもしれない 「洗った食器、拭いてくれる?」 「おう」 食器と食器が重なるカチャカチャと言う音、レモンに似た洗剤の香り、嬉しそうに歌う氷室の鼻歌・・・ コレもまた料理の醍醐味だな、と思いつつ、オレは目の前の食器を拭いていった |
| 四方山話(言い訳) |
|
毎度どうも、氷室バカのtalkで御座います。 Zac.様の氷室エプロンに触発され「氷室バカとしては私もやらねば!」と思い立ち、 今回作成するに至りました・・・が、作ってびっくり恥ずかしいのなんの! 私の中の氷室イメージって「可愛さ」も勿論あるんですけど、 やはり「健気」とか「切なさ」が先行してる感じがします。 でも今回は折角ですから「可愛い氷室」をということで作ってみました。 後エプロンが・・・やっぱ男の夢とロマンですよね。 読んでくださった皆様、 「ああこのバカの頭の中ってこうなってるのね」と思ってくだされば幸いで御座います。 |