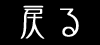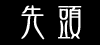| ささやかな幸せ |
|
「はあ、私ってやっぱり才能ないのかしら・・・」 荒れに荒れ果てた台所を眺め、溜息を一つ。 どう見ても皮の方に食べる所が多く付いていると思われるジャガイモ。 御世辞でも微塵切りにしたとは言えないほど大きく切られた玉葱。 皿の上ではなく地面にベタっと置かれた(というか落とした)挽肉。 周辺一帯は小麦粉とパン粉にまみれ、その中にポツンと座り込むポニーテールの女性が一人。 彼女の手もまた小麦粉とパン粉にまみれ、何処にも触れられないような有様である。 「いつもジャンクフードじゃ申し訳ないから、ちょっと頑張ってみようと思ったんだけど・・・」 小次郎の事務所に来てからどのくらいの月日が経ったのだろうか。 天城探偵事務所唯一の社員として、小次郎の恋人として、彼女なりに今まで尽くしてきたし、 仕事でもプライベートでもまだまだ彼の為に尽くしたい事は沢山ある。 小次郎への気持ちが社員のそれではなく真実の愛であることは、自分でも薄々気が付いていた。 しかし、彼の事を考える度、常に頭の中に過る桂木弥生の存在。 全てにおいて彼のNo.1になろうとは思っていなかったが、 桂木弥生と比べてた場合、どうしても自分と比べてしまう事が多かった。 その度に、「彼女は彼女、私は私」と言い聞かせたが、 どうしても一つだけ何とかしたい事があった。 それが、料理なのである。 「あ〜あ、あの人は苦もなく見事に作ってしまうんでしょうね。 ・・・やっぱり、悔しいな・・・。」 小次郎から弥生の料理腕前は何度も聞いたことがあった。 得意料理はシチューだという事、どんなに忙しくても料理は作ってくれた事、 栄養が偏らない様に考えて作ってくれた事、などなど。 それを聞く度に、彼女の胸は強く締め付けられた。 自分に出来ない事を小次郎にしてあげられる人がいる・・・。 憎らしいというより、出来ない自分に腹が立った。 「小次郎が帰ってきたとき、一度くらい料理を目の前に笑顔で迎えたいわ・・・。」 今日は小次郎が調査に出る前にそれとなく食べたい物を聞いておいた。 小次郎はいつもの様にほか弁のオカズを聞いているのだろうと思って答えたに違いないが、 そのとき彼の口から告げられた食べたい物は「コロッケ」であった。 はっきり言って、料理に慣れた人でもそう簡単に作れる代物ではない。 何よりも、作るのにはそれなりの道具が必要だ。 調理器具が満足に揃っているとは言えない天城探偵事務所の厨房ではとても難しい。 しかし、氷室はどうしても作りたかった。 小次郎が一日の調査を終え、疲れて帰ってきた時、 温かい料理と温かい笑顔で迎えてあげたかったのだ。 そして、小次郎の優しい笑顔と共に「ただいま」が聞きたかった。 それが、彼女のささやかな夢、ささやかな幸せ。 この夢が叶えば、桂木弥生の話を聞いても胸が締め付けられなくなるような気がした。 が、現状ではその夢も叶いそうにない。 厨房は荒れ果て、材料も殆ど使い物にならなくなってしまった。 そして、彼女の指には痛々しいほど沢山の包丁傷。 時計の針も既に午後6時を指そうとしている。 今日の小次郎は昼間の調査がメインなので、 戻ってくるのは余程の事がない限り6時〜6時半の間なのだ。 「しょうがない、今日もほか弁を買ってこよう・・・。 この有様は・・・小次郎を台所に入れなければ済む話よね。」 とりあえず、手に付いた小麦粉とパン粉を洗い流し、 食材と一緒に買ってきた特価980円のエプロンを外そうとした。 (これも・・・2度と使うことはないかもしれないわね・・・) エプロンの後ろは、紐を結ぶ形ではなくボタンで留める形になっていた。 意外に自分の背中側にあるボタンは外しにくいもので、 慣れない物を身に着けていた所為もあるだろうが、やはり上手く外せない。 「んしょ、は、外れないわね、なかなか・・・」 悪戦苦闘をするが、頑張れば頑張るほど下手に絡まって複雑になってしまう。 「も、もう、意外に大変なんだから・・・・・・あっ!」 エプロンがパサリと音を立てて床に落ちる。 その一瞬の出来事はまるで手品のようだった。 そして、その手品の種は自分の後方に立つ今一番顔を合わせたくない、最愛の人。 「あ、こ、小次郎・・・」 「氷室・・・これ、どうしたんだ?」 厨房の酷い有様を見て、小次郎は当然の如く問い掛ける。 「・・・」 「黙ってちゃ解らないだろう・・・」 「・・・うっ・・・うっ・・・」 彼女は堪らず涙を流し始めた。 一番顔を合わせたくない人に見られてしまった。 自分の無能さを小次郎の前に曝け出してしまった。 そして、何より悔しかったのだ。自分自身に。 一通り落ち着くまで沈黙の時間が続いた。 そして、自分自身への悔しさを振り払い、彼女は口を開いた。 「・・・いつもジャンクフードばかりだから・・・ 何か小次郎の為に作ってあげたかったのよ・・・。 そして、小次郎が帰って来た時、温かい料理を前に『おかえり』と言いたかったの・・・」 「・・・」 「私ね、意外に思われるかもしれないけど、弥生さんが羨ましかったのよ。 弥生さんは小次郎に対して、私にとって夢みたいな事が簡単にできるわ。 些細な、ほんとに些細な事なんだけど・・・私の夢なのよ・・・。 そして、料理もできない自分が本当に腹が立つ・・・んっ!」 彼女が全てを言い終わらないうちに、彼女の小さな口は塞がれた。 何がなんだか解らなかった。 一瞬の出来事に驚く彼女に、小次郎は言葉をかける。 「こういうのは、結果じゃないんだよ。 その過程でどれだけの想いが込められているかが大切なんだ。 氷室は俺の為に頑張ってくれた。 それだけで、それだけで俺は嬉しい。 弥生と比べる必要はない、氷室、お前はお前なんだ。 料理が出来ない氷室もひっくるめて、俺は・・・」 今度は小次郎が全てを言い終わらないうちに、彼女の小さな口が小次郎の口を塞ぐ。 それは、長いほんとうに長いキスだった。 |
| 四方山話(言い訳) |
|
どうも、久しぶりに書いてみました。 今回は珍しく氷室がメインです。 短い・・・というか短すぎ。 はっきり言って物語にもなっていません。 物語と言うよりは物語の一シーンを抜き出しただけのような内容です。 ただ、別に「愛がないから書けないぜ!」って訳じゃありませんよ。 本当は料理を作る過程を失敗続きのコミカルな内容で書こうかと考えていたのですが、 なんか氷室じゃなくても変わらないなあと思って止めました。 それならば、内に秘める感情を表現した方がいいかなあ、と。 行きついた先がこんな内容になりました。 私の氷室像って、あまり自信過剰にならず、 他人と比較して自分の悪い所ばかり先行して考えてしまうイメージなんですよ。 そんな人が自分の求めるささやかな幸せの為に、 悪い所を見つめ直し、頑張ろうとする心境を表現してみたかったんです。 そして、その頑張りはちゃんと伝わってるんだよ、ということも。 見えない所で努力するタイプだと思います、氷室って。 正直言うと、私と同じタイプなんですよね。 なんか最後の「頑張りはちゃんと伝わってるんだよ」という部分は、 自分自身に言い聞かせるかのような気持ちで書きました。 まあ、私の場合は口で言うほど頑張ってはいませんけど・・・。 「料理が出来ない」って結構いいネタなんですけどね。 ちょっと、物語としては薄かったかなあという感じです。 素材を活かし(生かし)きれなかった結果になってしまったかなあ・・・。 |