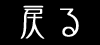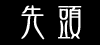| それは舞い散る桜のように |
|
もう泣かない・・・ そう決めたのは最後に抱かれたあの夜だった。 だからどんなに辛いことがあっても頑張って来た。 −−−−−−−−−−−−−−−−−− 『話があるから一緒に食事しないか』 春の麗らかな日、私は小次郎から食事に誘われた。 突然の誘いに戸惑ってしまった結果、半ば強引に連れ出された形ではあるが。 (・・・) 小次郎との付き合いは長いが、 向こうから食事に誘ってくることなど滅多に無いことであり、 しかも彼から話を持ちかけることなど浮気のフォロー以外には考えられないことだった。 だから、こういった突然の誘いに対処できる術には長けていない。 (話か・・・) 待ち合わせ場所であるセントラルアベニューに着いてから20分が経った。 こういった待ち合わせの場合は約束の時間より10分前には来るよう常に心掛けており、 今日も例に違わず10分前に到着していたので厳密に言えば10分待たされたことになる。 待ち合わせの時間になっても姿を見せないのは小次郎にとって当たり前の光景であった。 普段であればイライラして煙草の本数も次第に増えていくのだが、 今日はまだ心の準備が出来ていないのでむしろ有り難い。 私は手持ち無沙汰になり、行き交う人の流れを眺めながら周囲の雑踏に耳を傾けた。 携帯電話を片手に頭を何度も下げて謝りながら歩くサラリーマン、 昨日のトレンディードラマの結末に納得できない旨を大声で喚き散らしている高校生らしき集団、 昼食で食べたインドカレーの辛さがイマイチだったと語り合うグルメなol2人組み、 他愛もない会話で構成されているこの雑踏が逆に心の準備が出来ていない私には丁度良かった。 そんな雑踏の中でひときわ目立つ声を放つカップルがいた。 「雄二君、歩くの速い!」 「杏子が遅いんだよ。慣れないハイヒールなんて履いてくるのが悪いんだぞ。」 御互いに愛情の篭った悪態をつきつつ2人は私の目の前を通り過ぎていった。 (そう言えば、『小次郎』と呼ぶようになったのはいつからだろう) 最初は『小次郎君』だった。 彼は「小次郎でいい」と言ってくれたが、直ぐに相手を呼び捨てに出来るような度胸は無かった。 だが、小次郎を『男性』として見るようになった頃から『小次郎君』は逆に言い辛い呼び方になっていた。 それが恋人と呼べる存在になった時だったのか、初めて抱かれた時からだったのか、 曖昧な記憶を辿るがその原点は結局想い出せない。 あまりにも小次郎と共有した時間が長く、そしてその存在が大きすぎた故の安心感。 それがこんな大事なことすら忘れてしまうことになろうとは。 そもそも今の自分は『小次郎』と呼び捨てにできる身分なのだろうか。 単なる友達として呼ぶ訳ではない、親しみと尊敬と愛情の意を込めて愛しい人を呼ぶために。 ・・・私はその資格があるのだろうか。 「すまん、弥生。待たせた。」 息を切らせながら小次郎が到着した。 彼は額にほんのり浮かんだ汗を袖で拭いながら申し訳無さそうに私を見る。 「い、いや、私も少し遅れてきたところだ。」 ウソだ。 いつもなら文句の1つや2つは言うところであるが、何故か本当の事を言えなかった。 それどころか、彼をまともに見ることすら出来ず視線を逸らしてしまった。 「・・・そうか・・・なら良かった」 そんな私の挙動を疑うことも無く、彼は私の足元を見てからそう呟いた。 普段なら私の足元に落ちている煙草の吸殻を確認すれば分かるものだが、 今日の私は吸っていなかったので彼の目には本当に遅れて来たように見えているのだろう。 「なんか、怒ってないか?」 「そ、そんなことないぞ」 やはり視線を逸らしたことに何かを感じ取ったらしい。 こういうとき洞察力の鋭い人間、とりわけ『探偵』という職業の人間を相手にするのは分が悪い。 「・・・・」 「そ、そんなことないと、いってるだろう」 「・・・ま、いいか じゃあ、行こうか」 彼はそう言うと私に背を向けて歩き出した。 少しばかり間合いをおいて、私もその背中を追った。 −−−−−−−−−−−−−−−−−− 「お待たせいたしました。本日の主菜『仔牛ロース肉のポアレトリュフワインソース』でございます。」 「あ・・・すみません・・・」 彼が連れてきたのはセントラルアベニューでも指折りの高級フランス料理店だった。 彼にこんな場所へ招待されたことなど一度もない。 ただ私と食事をしたいだけなのか、それとも私に用事があるのか、私に告げることがあるのか、 テーブルに座ってから今までお互いあまり言葉を交わさないまま時間を過ごしたこともあり、 いつもと違う彼の行動から真意が読めず、私の心は落ち着かなかった。 それでいて自分の目の前に彼が座っている光景が懐かしくもあり嬉しかったりもする。 だから、何か胸の部分が宙に浮いているような、そんな得体の知れない感覚に苛まれていた。 「弥生、あまりこういうの慣れてないんだな」 「えっ?」 「もっと堂々と振舞っているものだと思ってた。」 彼に心の内を見透かされているようだった。 勿論、フランス料理は何度も食べたことがある。 普段なら「小次郎が連れてきてくれないからだ」と文句の一つも言えたものだが、それすら口にすることが出来なかった。 もっとも、私が『彼に食事へ招待される』資格を持っているかどうかすら分からないのだから。 「・・・久しぶり・・・だったからかな。」 (小次郎と会うのが。) その一言は口に出来なかった。 「ちょっと意外なんだが・・・ まあ、フランス料理なんて滅多に食べるものじゃないしな。」 彼は私の『久しぶり』がフランス料理のことだと思ってくれた。 「まあ、そんなところだ。」 彼の思ったままの反応に相槌を打つ。 ここで『小次郎に会うのが』と返したらどうなるかと一瞬思ったが、 その後の反応を見るのが怖くてその考えは簡単に掻き消された。 「ま、俺は慣れていないどころじゃないんだけどな。 もう窮屈で窮屈で今すぐにでも暴れ回りたい心境だ。」 「ふふ、小次郎には似合わないもんな」 「はは、その通りだ」 今日初めて自然に笑うことができた。 彼もそんな私を見て目を細める。 優しく私を包み込むような視線が嬉しい。 笑うことで少し落ち着きを取り戻したからか、目の前に出された料理も心なしか美味しく感じられるようになり、 目の前の料理が既に主菜になってしまっていたことを少し後悔した。 「ところで小次郎、私がお前を呼び捨てで呼ぶようになったのいつ頃だったか覚えているか?」 心が落ち着いてきた勢いに任せて先程疑問に思ったことを聞いてみた。 「ん・・・確か初めて弥生を抱い・・いや気持ちを確かめ合った時かな。」 予想もしない質問を投げられて困惑するかと思いきや、彼はあっさりと答えた。 「何か気になることでもあるのか?」 「いや、さっき小次郎を待っていたときに目の前を通ったカップルの男の方が 女の名前を呼び捨てしている声が耳に入ってきたものでな。」 「そうか」 他愛ない質問に対して自然に返答しただけのことであるが、 彼の答えは、まだ彼の心の中に私が存在している、そんな気がして私は嬉しかった。 むしろ先程思い出せなかった私の心の中に彼が存在していなかったのではないか、と不安になる。 その気持ちに呼応するかのように、胸の部分が宙に浮いているような得体の知れない感覚が再度蘇った。 「その、あんまり美味くなかったか?」 不安になったことで私の表情に陰りが見えたのか、 彼は申し訳無さそうな心配そうな顔をして尋ねてきた。 「い、いや、美味しかった。」 「それなら良かった。」 私の返答に満足したのか、また優しく包み込むような視線を私に向ける。 嬉しい。 凄く嬉しい。 私を見てくれていることが。 (でも、小次郎の眼はまだ私を見ているのだろうか) 彼の視線の先にあるものが私でないとしたら・・・。 「そうだ、私に話があるんじゃなかったのか?」 これ以上考えてしまうと聞けなくなってしまいそうなので本題を振ってみた。 極めて明るい声を出したのだが、その言葉を聞いた途端に彼の表情が強張った。 「あ、いや・・・」 返事も何処か強張った感じで浮かない。 よくよく考えれば『話がある』と言ったのは彼なのだから私が負い目を感じることはないのに、 彼の表情を見ると、聞いてはいけないことを聞いてしまった、そんな罪悪感に囚われる。 その後、お互い特に会話も成り立たないまま食後の珈琲を嗜んで彼と店を後にした。 結局、話というのは聞くことが出来なかった。 −−−−−−−−−−−−−−−−−− 中央公園の桜は見事としか表現できないほど綺麗に咲き乱れている。 こんな日の夜は花見客で賑わいそうだ。 かえって昼間の方が静かなのではないか。 桜のアーチが見事に形成された公園の道を2人で歩く。 レストランを出てから相変わらず2人の間に会話は無い。 話し掛けたいのだが、お互いに気の利いた言葉が見つからないような感覚。 彼はいつになく真剣な顔をして、何処か遠くを見るような目をして、ただ黙って歩いていた。 『話があるんじゃなかったのか?』と尋ねてからずっとその調子だ。 別に『話がある』と言って誘ったのは彼であり、当然私にはその件に関して尋ねる権利がある。 しかし、今の私は弱かった。 先程私に向けてくれた包み込むような優しい笑顔は 追求すればするほど別の人に向けられてしまうのではないか、そんな不安に駆られる。 いや、もう既に彼の眼は私を見ていないかのようで怖かった。 もし彼の眼が私を見てくれなくなってしまったのなら、自分がどうなるか分からない。 そして、何よりも彼にとっての『私の魅力』というのが分からない。 彼の為に磨くべき『私』が何なのか分からない。 自分を見てくれなくなってしまうのではないか、という不安と 結果自分がどうなってしまうのか分からない、という不安、 そして彼にとって自分が魅力的な人物かどうか分からない、という不安が入り混じり、 私の弱さを形成してしまっているのだ。 私は実感した。 やっぱり自分は小次郎の事を愛している。誰よりも、誰よりも。 彼に呼び出されてから今まで、心の中にあるこの得体の知れないもの。 期待・希望・不安・絶望・困惑・混乱・・・・ その中の『何であるか』は特定できない。 全てをひっくるめ、これは私が彼を愛しているという証なのだ。 手放したくない、いや、手放されたくない。 もう、私には『彼』しかいない。 でも・・・彼にとって『私』という存在は・・・? そんな私を嘲笑うかのように、楽しそうに会話をするカップルがすれ違う。 彼ら・彼女らは自然に言葉を紡ぎ、自然に笑い合っている。 それが過去の自分達を見せつけられているかのようで切ない。 私は思わず振り返り、目でカップルを追ってしまった。 私の視線が変わったことに気付いたのか、突然彼が口を開いた。 「・・・桜、綺麗だな」 「えっ?」 唐突だったので少々間の抜けた返事をしてしまう。 「今日の夜は花見客で賑わうんだろうなあ」 「そ、そうだな」 「弥生とも随分酒を飲んでないな・・・今度久しぶりに飲みに行くか?」 「え?・・あ、ああ・・」 それからまた無言の時間が再開する。 (頼むから私に優しい言葉を掛けるな・・・嬉しくなってしまうから) 周りから見たら『仲睦まじく桜を鑑賞しながらの散歩』になるのだろうか。 だが、私の心は誰かに鷲掴みにして留めておいて貰いたいほど落ち着きが無く、 この場にいるだけでどうにかなってしまいそうな感じだった。 ・ ・ ・ そして、丁度園内を一周したところで彼の歩みが止まった。 「弥生・・・」 「な、なんだ」 突然名前を呼ばれて声が上ずった。 しかし、彼は気にすることもなく私と正反対の方向を見つめながら言葉を続けた。 「前、自分が『何になりたいか』じゃなくて『何になれるか』を考えろって言われたよな。」 「ああ。」 「・・・俺がなれること、考えたよ。」 次の瞬間、突然彼が振り向き、私は彼の腕に包み込まれた。 そして、私の左手薬指に冷たくて温もりのある何かがはめられた。 「えっ・・・」 「夢を叶えた弥生に微笑んで欲しい・・・それが俺の夢だ。 一番の魅力である弥生の笑顔を、俺だけの為に見せて欲しい。 ・・・もう、俺にその資格はないかもしれないけど。」 左手薬指にはめられた何かを確かめる。 それは銀色に光る指輪だった。 涙が止まらなかった、いや、止められなかった。 もう泣かないと決めたあの日の決意は脆くも崩れ去った。 (いいだろう、今日くらいは) 強い風が吹く。 桜の木が一斉にざわめき、桜の花弁が舞い散った。 同時に私の目に浮かんだ涙も風に流された。 そして、舞い散る桜の花弁と同化する。 その光景は、まるで私の涙を拭ってくれたかのようだった。 そして私は舞い散る花弁に後押しされ、精一杯の笑顔で精一杯の勇気を振り絞った。 「小次郎・・・愛してる・・・」 再び強い風が吹く。 桜の木が一斉にざわめき、桜の花弁が舞い散った。 春の麗らかな弥生の日に舞った桜の花弁は、 まるで私を祝福しているかのようだった。 −−−−−−−−−−−−−−−−−− もう泣かない・・・ 次にそう決めたのは桜舞い散る日、彼の腕の中で涙を流した後だった。 どんなに辛いことがあっても2人で頑張っていこうと思う。 私の涙はもう、桜の花弁と一緒に舞い散ってしまったのだから。 |
| 四方山話(言い訳) |
|
どうも、本当に久しぶりに書いてみました。 実はかなり前から書き始めてはいたんですけど、どうも何回か失敗しまして。 今回の話は、小次郎が弥生にプロポーズする時の話。 断わられ「気持ちが離れてしまう」のが怖くてなかなか言い出せない小次郎、 そしてそんな小次郎の態度を見て何とも言えない不安に駆られる弥生。 プロポーズは極端ですが、異性を好きになったことがある人ならこの気持ち分かっていただけるかと。 ただ、読んでみて弥生の不安に駆られる心境がちょっとクド過ぎたかなあとも思います。 最初は小次郎視点と弥生視点と両方用意してたのですが、 今よりももっと表現がクドくなってしまいましたので止めました。 まあ、運良く弥生視点で小次郎の様子を描写する方がしっくりきましたので。 タイトルは某18禁ゲームから拝借したものですが、 最初から「弥生」=「3月」=「桜」=「桜吹雪」=「涙」という繋がりを意識しておりました。 まあ、弥生を「泣かせたかった」ということで。 ですから意外ですがタイトルは後付だったりします。 「ああ、ピッタリな題名のゲームが発売されたぞ。拝借させてもらおう。」と。 この話、実は「ちっぽけな夢」とリンクしております。 「ちっぽけな夢」の後にこの「それは舞い散る桜のように」へと繋がるのです。 また、以前配布した壁紙(背景に2つの指輪があるやつ)がこの話のイメージ画像になります。 残念ながらここには載せられないんですけど、持っている人は見ながら呼んでみてください。 でもホント、しばらく書いてないと言葉が出てこないですね。 精進しないとなあ。 |