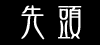| 霞草 |
|
「・・・ふぅ」 「何よ、溜息なんか吐いて」 「いやあ、さあ・・・弥生がな・・・」 「・・・」 「寂しそうなんだよね」 「・・・そう」 「・・・お前、それだけか?」 「・・・」 「なんかさあ、その、怒るとか・・・ないの?」 「え?ええ、そう・・・よね」 「『あの女と会ってるの?』とか言わないのか?」 「別に・・・気にしてないわよ」 「で、そこでなんで目を逸らすんだ?」 「そらしてなんかいないじゃない!」 「いや、逸らした。・・・顔色も悪いぜ。」 「顔色が?」 「俺の気のせいか?・・・ならいいんだけどな」 氷室は両手を小次郎の頬に当てて、ぐっと顔を近づけて呟いた 「今、小次郎の頬に触れているのは誰?」 「氷室だろ。」 「今、貴方の瞳に映っているのは誰?」 「・・・・・・そんなことも分からないのか?」 「言って」 「そんな必要があるのか?」 「言って!」 「氷室じゃないか。他に誰がいる。」 「本当にそう?本当に私が映ってる?」 「・・・ああ」 「あの女性が・・・」 「ああ、弥生のことか。それがどうかしたか?」 「あの女性が映ってる・・・貴方の瞳にはあの女性が映ってる」 「弥生は・・・別に映ってない。」 「だったらどうして会ったことも無い人が寂しいってわかるの?」 「なんとなくな。・・・分からないか?」 「分からない・・・分かりたくない!」 「・・・そうか。じゃあ・・・」 「や・・・ちょっ、放して!」 「体で分からせてやる!!」 そう言って、小次郎は氷室を事務所の外へ連れ出した。 「な、何よ!」 「いいから来い!」 小次郎は無理矢理氷室を車に乗せ、アクセルを吹かした。 「どこに連れて行く気?」 「・・・」 小次郎は無言で車を走らせる。 15分くらい走っただろうか、見知らぬ墓場の駐車場で降ろされた。 「ここは・・・?」 「前にも話したと思うけどな、今日は探偵としての技術を俺に叩きこんだ人間の命日なんだ。」 そして、小次郎はお世辞でも立派とは言えない墓の前まで連れてきた。 「桂木、源三郎・・・。桂木ってあの?」 「ああ。そして、その人間が好きだったのが・・・かすみ草だった。」 決して立派ではない墓には、その墓を覆い尽くすかのような数のかすみ草が置かれていた。 腰を屈め墓前に手を合わせる小次郎。 この人でもこんな事をするのかしら、といった面持ちでそれを眺める氷室。 「私も手を合わせていいかしら?」 「・・・ダメだ。俺の話を最後まで聞くまでは」 「聞かせてくれるの?」 「・・・氷室の中で、弥生を『女』ではなく今だけは『人間』として見ることが出来るなら。」 「今だけ・・・?」 「ああ」 小次郎の眼差しはいつになく真剣だった。 勿論、彼の目は髪に隠れていたが、それは雰囲気で分かる。 「氷室には悪いんだが、この日だけは弥生と会っていた事を認める。 ただ、今年に限ってあいつは約束の時間に現れなかった。 待ち草臥れてこの墓の前に来たら・・・・既に花が置いてあったんだ。 もう、何度来たかは俺も忘れたけどな。 ・・・あいつがこんなに花を持ってきたという記憶は無い。 俺の分を考えていたとしても・・・だ。」 「そう・・・」 「あいつは・・・女としては弱いが、人間としての弱さというものを見せたことはなかった。 花という物が人の心情を表す、ということは聞いた事は無いが、 俺にとってこの光景は、あいつの本当の弱さを見ているようで、 そして、あいつの寂しさを表現しているように思える。」 「綺麗な花ね」 小次郎は、頷きもしないで続けた。 「さすがに、あの男に対しての気持ちは弥生も俺も一緒だ。 これに関してはおまえがいくら文句を言っても覆らない事実なんだ。 ・・・寂しいんだよ、あいつ。勿論、一人の人間としてな。 それが俺には・・・な。」 (寂しい?) 「この墓に眠る男に対して共通の想いがある限り、俺はあいつの寂しさが分かる。 ・・・そして、その寂しさを俺の目の前で見せようとはしなかったんだ・・・。 別にな、いつもなら普段の強がりだと思うさ。 だが、共通の想いに対してだけは・・・強がらないと思っていた。 でも強がりを見せた、いや、強がりすら見せなかったのかもしれない。 それが、この花に表れている・・・のだと思う。 あいつの精一杯の表現なんだろうな・・・寂しさに対する あいつは俺に見せなかったんだ・・・その寂しさを。 それが俺には悔しくて。 あの男に対しての寂しさを共有できるのは・・・世の中に俺しかいないからな。」 ・・・初めて見る彼の表情 自分の前では決して見せないだろうと思うと痛みを伴う鼓動を感じる いつもなら痛みを和らげてくれるこの人から痛みを感じるなんて・・・ 不安とも嫉妬とも言えない薄暗い感情が胸に込み上げてくる その得体の知れない感情を振り切るきっかけが欲しかっただけなのかもしれない 何気なく彼の背中に触れようと手を伸ばした、その時だった 「・・・スマン、氷室。」 「え・・・?」 「事務所で弥生の話を出したのは、いつものように怒って欲しかったんだ。 このままあいつの寂しさを俺の心の中で引きずっていたら ・・・お前を悲しませることになったかもしれない。」 「小次郎・・・」 名前を呟いてそっと背に抱きつく 背中に心地よい重みを感じながら、空を見上げる小次郎 もう一度視線を落すと、かすみ草の白さが目に付いた 「・・・氷室をここに連れてきたのは、 お前に対する俺の想いが白さを失いそうになったから。 そう、いつまでもこのかすみ草のような白さを持ち続けていたいから・・・かもな。」 「・・・綺麗な花ね」 「お前に対する俺の想いは・・・この花のような色をしてると思うか?」 「ふふふ、どうかしら」 「・・・ズルいぞ、それは」 「ねえ、もう手を合わせても構わない?」 「ん?ダメなんて言ったっけ?」 「意地悪」 すっと立ち上がって静かに手を合わせる氷室 少しだけ寒さを含んだ風が彼女の髪とかすみ草を靡かせた 小次郎が感じた淡い香りは、かすみ草の香りだったのか、それとも・・・ 「・・・そろそろ戻るか」 「ええ」 そして、振りかえりざま思い出したように小次郎が呟く 「あ、言い忘れてた。」 「ん?」 「俺の瞳に映っているのは、間違いなくお前だけだぜ」 その時、その言葉を掻き消すような風が流れる。 「えっ?今、何て言ったの?」 「・・・いい天気だって言っただけだ。」 「そう・・・。でも貴方の想いも、間違いなくかすみ草の色だわ」 「ん?何?」 「いい風、って言っただけよ。」 強めの風が吹いた。乱れた髪をかき上げながら小次郎を見つめる いつもは無造作に伸ばした髪で見えない彼の目が、今だけははっきりと分かった 小次郎の顔を覗き込んで、くすくす笑いながら呟く氷室 「私が映ってる」 「いつだって映ってたさ」 もう一度吹いた風と同時に二人の唇と髪が重なる。風が止んでも重なり続ける唇と髪 微かに香るかすみ草の香り 互いの目には風に靡くかすみ草と、絡み合う二人の髪と・・・ そしてお互いの瞳が映っていた END |
| 四方山話(言い訳) |
|
★ 西の氷室バカより ★ ついにやってしまいました。東の弥生バカ&西の氷室バカの合同小説ですね。 酒の勢いで作ってしまった+あまり考えずにその場のノリで作ってしまったので、 シチュエーションやセリフのやり取りに不自然な所なども多数あると思いますが、 とにかく作ってる最中は終始爆笑してたのが印象的です。 「よくもまあこんな恥ずかしいセリフが書けるもんだ」とか「アンタはやっぱりイヤらしい」とか・・・ それはもう罵詈雑言の連続。けど正直楽しかったですね。 今回は一応(私に気を遣ってくれて?)「小次郎-氷室」のスタンスで作成してみました。 このセリフや文章はどっちが書いたものだ?とか考えてみると面白いかもしれませんよ。 まあ大抵は一発でわかるかと思いますが。がっはっは。 ★ 東の弥生バカより ★ ストーリー性云々はこの際抜きにして、こういう物を作った事に非常に意義があるなあと。 (栄光の記録か恥の記録かと問われれば、勿論後者になる可能性のほうが大なのですが) まあ兎に角、楽しかったですねえ。 交互に台詞を書いていくという方式を取ったのですが、お互いの思惑の読み合いになりました。 「ああ、こういう方向へ話を持って行きたいんだろうなあ・・・でもそうはさせるか。」とか。 次の機会があるとしたら、是非弥生で御願いしたいです。 最後に一言、 貴方やっぱヤらしいわ・・・おじさんビックリだ。 |