
黒岳展望台より4月の富嶽

黒岳展望台より4月の富嶽
愛鷹登山口
| 大沢を割石峠 割石峠から 越前岳 |
愛鷹神社 − 北面沢出会 − 割石峠 − 呼子岳 − 高場所分岐 − 9:30 10:21 11:32 12:41 12:51 |
 |
越前岳 13:34 出発が遅く、昼過ぎの山頂にたつ。無風、水蒸気を多く含む春の大気は、山頂よりの眺望を輪郭を乏しくさせている。この時間帯になっても登山者が訪れる。我々を含めて3パーティーになる。 |
 |
ヒオドシチョウ♀ 13:50 天気がよい。3ヶ月ぶり、二日酔いと条件がそろう。0.47リットルのテルモス、1リットルの水筒、リンゴ1個、みかん3個。補給した以上の水分が老廃物とともに吹き出し、肌に触れているものをぬらす。男性の汗には、やはり雌を引きつけるらしい。 |
 |
残雪 14:05 越前岳より東尾根にはいる。この冬は太平洋沿岸の多雪の年。ここ越前岳北面にも例年では見られない残雪が見られる。 |
 |
富士見台 14:13 山頂より緩やかな下降が続く。かって、このコースは樹木に覆われまったく展望の期待できないルートと記憶していたが、現在、北側を切り開き展望台としている。遮るもののない展望は圧倒的な迫力がある。しかし、人工的な感じも否めない。 |
 |
位牌岳 14:14 富士見台展望台より南面を望む。前岳を左に従え位牌岳が大きい。縦走路中の峰は春霞の中である。 |
 |
大崩壊 14:25 黒岳に向け下降中、突然大きく崩壊した壁面に出会う。今までのルートは、谷底である。愛鷹火山の噴火活動によりたい積が繰り返された記録を読みとることが出来る。今回は割石峠まで、登路である大沢の中、上流部でも頻繁に左右の壁が崩落した現場を見てきた。死火山が末期を迎えていることが実感される。 |
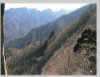 |
鋸岳 14:41 木々が葉を落としたこの時期は眺望が得やすい。歯の特徴は袴越岳付近から見た鋸に一歩譲る。 |
 |
黒岳 15:26 ここ黒岳は越前岳東尾根の末端に位置する「コブ」の一つに過ぎなず、山頂として意識されることは少ない。愛鷹神社への分岐より緩やかに登る返す。山道の左右は広く切り払われており、開放感に満ち本日のフィナーレとしてふさわしい場所である。時間が遅くなり、今回もカットするつもりであったが、連れの意向もあり足を延ばすこととなった。下のサファリパークからの遊歩道がここまで延びており、山屋の親しんでいるそれとは雰囲気の異なる道標が要所要所に配置されている。 |
 |
スギ 15:46 黒岳の名の由来が話題になる。この愛鷹連峰には、位牌岳南面に密度の極めて高いスギの純林がある。下和田天然スギ学術参考林として保護されている。連峰内にはいたるところに天然スギが散在する。遠くからは、落葉樹の中にとひときわ黒く見られる。ここ黒岳も天然スギの多いところで巨木も20数本を数える。山頂は切り開かれており、芝で敷き詰められ弁当を広げるにはうってつけである。ここもまた、北面の落葉灌木林が伐採されて、座って富岳と対面できる。山頂には標識が2つある。一方には1086m、もう片方には1087mとある。四捨五入か、切り捨てかの違いで決まるらしい。 |
 |
分岐 16:06 |
 |
あしたか山荘 16:09 かって、尾根上の分岐のあたりにあったと記憶している。当時廃屋になって久しく朽ち果た姿を見せていた。連峰上のコースの調査を思い立ち、10数年ぶりにトレースして存在を確かめた。現在、予約制、電話で連絡すると、管理人がマイカーで乗り付け、部屋の清掃をして受け入れの準備をしてくれるとのことである。ただし、管理人は下山してしまうので、素泊まりである。収容は6人とアットホームな雰囲気を味わうことが出来る。水場、トイレ、テント場がこじんまりと配置されている。 |
 |
愛鷹神社 16:37 林道に面している鳥居とバランスのとれない小さな祠が立つ。横に「登山道」と刻まれた丸石が置かれている。神社前には10台ほど駐車が出来る。今回林道の舗装工事でここに駐車できず、さらに10分ほど歩かなければならなかった。いずれ、土を踏まずに神社前まで達することになる。 |
| 今回の行程 | 所要時間 7:07 休憩時間 1:21 実働時間 5:46 |