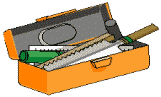 |
D I Y コーナー |
 |
| お遊び新聞 |
THE OASOBI SINBUN |
D I Y |
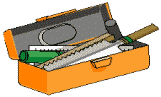 |
D I Y コーナー |
 |
日常生活の中でその気になればかなりのことが自分の手で出来るのではないでしょうか。
もちろん、専門の知識が必要であったり、高価な道具を必要とするような事には手を出せませんが、既製品では寸法や使い勝手などがいま一つだったり、業者に頼むとかなりの費用となるものなどでも、ホームセンターなどで材料を買ってきて
DIYで出来るものは数多く有ると思います。
我が家でもペンキ塗りや棚などの作製取り付け・包丁研ぎ、大物では中古でもらったカーポートの設置などなど多くのことを
DIYで行っています。
中には既製品を購入した方が安上がりの物もありますし、また自分自身の日当の高い人には向かないかもしれませんが・・・。
(^o^)
我が家の DIYの紹介の中で今回は車と自転車を記事にしてみました。
なお、人使いの荒い女房殿は私のことを「一家に一人必要な便利屋さん」と称しています。
( 俺が死んだら困るぞー。)
車 (ユーザー車検)
車齢19年の1BOXのバン、調子も使い勝手も良いのだがエアコンは付けてないし、冷却系統のホース類は何時はぜてもおかしくない状態で長距離運用は不安で出来るようなものではない。その上、ボディーは錆でボロボロ、雨漏れもする状態では・・・、ついに引退さ
せることにした。
今度の車も室内容積が大きく、山行時のベースキャンプなどに用途の広いバンにして、バンの最大の欠点でもある毎年の車検は、この買い換えを機会にユーザー車検でカバーしていくことにした。
一年経過しいよいよ車検の時が来た。
インターネットなどで情報を集め、予約方法・持ち込む時間帯など不明な点は陸運事務所に電話で問い合わせした後ユーザー車検を実行した。
初めてのこと少々不安はあったが、検査に持ち込んでみると案ずるよりも生むが安しで車検は呆気なく終了した。
自分の車の状態もよく分かるし、車検費用は印紙とマークシート代のみ、DIY派ユーザーにはお薦めである。
( 中部運輸局発行のパンフレットにも <車の保守管理はユーザー自身の責任です。>と記されています。)
ユーザー車検の実施方法などについては多くのHPも在りますし、まずは陸運事務所へ問い合わせてみるのが良いかと思いますので、この紙面での取り扱いは差し控えました。
3回のユーザー車検
ユーザー車検も3回経験し、車検場の検査ラインを通す事にもやっと慣れたかな?といった感じである。
HP更新にあたり、3回の車検の様子を簡単に報告します。
初めてのユーザー車検 (1999.6)
雑誌・インターネットで情報収集し、事前に予約を入れ車を点検。
自賠責保険・自動車税納税証明書・分解整備記録簿など必要書類を揃え、かなり早い時間に車検場へ持ち込む。
車検場で揃える検査票などは、同じユーザー車検仲間がいて「ここにある・・・」と教えて
くれた。
書類審査も終わり、いざ検査ラインへ、検査官に初めてのユーザー車検であることを告げると親切にもラインの終わりまで立ち会ってくれ、気になっていた自動検査ラインも無事通過し、あっさりと車検合格となった。
なお、このとき念のため車検場の横にある予備検査場(Oモータース運営)で予備検査を受けようとしたが、入り口には「ユーザー・代行車検お断り」の看板が出ていた。
もし本番で何か不具合があっても、デーラーの修理工場を利用すれば・・・と、車検場へ向かった。
2度目の車検 (2000.6)
昨年同様に、車・書類を準備して車検場へ、2度目となると車検場での印紙の購入や書類揃えも慣れたもの、しかしこの慣れがいけなかったのか、予約番号を控えたメモを落として探しまくったり、書類審査の窓口では、なぜか検査票に「丸代」の印を押されたり。
この「丸代」の印については気にもせず検査ラインへ向かったのだが・・・。
今回は検査官もなぜか事務的、昨年のラインの通り方について手取り足取りの親切さとは打って変わった態度。
まあ、いいかでラインへ入ったものの、今回は電光表示板とスピーカーから流れる音声だけを頼りの検査、ギアをパーキングに入れたままサイドブレーキの検査をしてしまい、気づいたときには「サイドブレーキ引きずり」で検査不合格で次の検査へ向かう指示が出てしまった。
再度ラインを通り、サイドブレーキについても無事合格、総合判定印をもらう窓口に書類を提出した。
このとき窓口の検査官から「お宅はユーザー本人ですよねぇー」の問い、「本人ですよ、免許証を見せますか?」に「いや、結構です」と答えが返り、検査官は「丸代」の印の上に赤線2本を引き、「ユーザー車検」の印を押した。
「丸代」印は、車検代行の印とこのとき判明した。
3度目の車検 (2001.6)
今回は検査票にきちんと「ユーザー車検」の印、これなら・・・と検査ラインへ、ところが
外観検査終了時に検査官から「初めてじゃないなら分かりますね・・・」とあっさり言われ
てしまった。(一年経つと結構忘れるんですけど・・・)
昨年の失敗を踏まえ、表示盤と音声に注意し自動検査ラインを全て合格で無事通過、やっと要領がつかめた感じである。
その後
2002年の車検もユーザー車検(4回目)で済ますことが出来た。
ワゴン車との税金の差額や、ユーザー車検と業者車検の費用の差額で新しいパソコンを買ったことになる。
3年後にも車検で浮かしたお金でパソコンを・・・なんて思ってしまうのである。 (^^
その後も業者の設備を必要とするような整備箇所は出ていないので、毎年ユーザー車検を実行している。
![]() も愛車をユーザー車検 (2002.8.19)
も愛車をユーザー車検 (2002.8.19)
女房殿の車も今年は車検、新車購入後の初車検でも有るし、特別不具合も無いこと、女房殿も仕事が休みでもあることなどから、ユーザー車検を体験してもらうことにした。
(車の名義が女房殿であることから、私が車検に持ち込むと代行車検となります。)
盆休み明けなら車検場も空いているだろうし、もしもの場合ディーラーへ持ち込む事も出来ることから、予約を19日(月曜日)に、点検や書類作成は車検前日の18日午後に行った。
(ユーザー車検なので点検実施者は車の使用者である女房殿で、私は手伝いとなります。) (^^
夕方前には車の点検も整備記録簿などの書類準備も全て終わる。
19日、女房殿と私と車検を見学したいという次女の三人で車検場へ。
道も空いていて早めに車検場へ到着、予想通り車検場も空いていた。
マークシート・印紙類を購入、検査票などに必要事項記入し書類を揃え受け付けを済ませ、いざ!検査ラインへ。
| 窓口へ書類提出(心配でのぞき込む) | 車をライン入り口に移動、これから車検開始です。 |
4年前に私が初めてユーザー車検で持ち込んだ時には、親切に検査官がライン終了まで付いてきてくれたので、今回もそれをあてにしていたのだが・・・、車検ライン入り口での外観検査が終わると後の検査要領の説明もなしに検査官は消えてしまった。
検査官にもいろいろな人間がいるだろうが、今回の検査官は指示の声も小さく不親切、はっきり言ってハズレ!、女房一人であったなら、かなり困った事と思われた。
(検査項目の幾つかは未チェックで合格印、やる気が有るのか疑問に思われた。)
しかたなく、検査ラインの横に付いている見学者通路から私が指示を出して行った。
ライン最初の排気ガス検査では、記録器にうまく検査票を入れる事が出来なかったので、その後は全て私が記録器への検査票挿入を行った。
サイドスリップの検査では、進入速度が早く・・・、AT車だからアクセルから足を離しただけで進んでしまうのだが、そんなことでの不合格は避けたい。「早い!、早い!」と叫びまくってしまった。
スピードメーター検査ではパッシング操作が理解できていず(S/Wをすぐ放さないのでセンサーが感知しなかった)数回のやり直し。
最後の下回り検査では検査終了後は車を斜めに進め、ピットに脱輪するのではといった始末であった。
なんとか無事車検を終了することができたが、ここに使用する予定の各検査ごとの写真は撮ることが出来なかった。
(写真どころでは・・・)
関連記事:Home News 6
![]() の二度目のユーザー車検 (2004.8.2)
の二度目のユーザー車検 (2004.8.2)
女房殿の愛車も二度目の車検時期となった。
私が事前に点検し異常無いので今回もユーザー車検で通すことにした。
前日に点検・書類作成、車検は二回目だから前回より少しは慣れて・・・と、思っていたら順調に行ったのはサイドスリップの前進まで、ブレーキ・スピードテストのローラーなどには、行き過ぎたり、戻り過ぎたり。
ブレーキ・テストに移る時にはローラーの中に後ろタイヤが入らない。(電光掲示板の指示はサイドを戻せと出ていたのに引いたまま)
横から見ていたが、車が小さく軽いから?それも奇怪しいとサイドブレーキを確認させたら引いてあった。
それでも、今回はスピードメーターテストでのパッシング合図はすんなり、僅かながらでも前回の経験が生かされていたようだ。
今回も検査ライン横の見学用通路から指示を出すのに忙しい車検であった。
写真撮影も考えたが、指示優先となるから無理だろうと最初から諦めていて正解であった。
それでも無事車検終了、午前9時半過ぎには帰宅、ステッカーの貼り替えを済ませることができた。
![]()
自 転 車
月に一度の不燃物収集時に少し壊れていただけのマウンテンバイク(
MTB )が出されていた。
当時の我が家には友人が処分するというのをもらったボロボロのママチャリが一台あっただけ、駄目もとで、拾って来て修理を試みた。
壊れている部品を自転車屋に注文すると、これが思ったより安い値段で手に入るし簡単に修理できた。
これに気をよくして、僅かな期間しか使わない子供用の自転車からママチャリまで不燃物で出されている物を拾って来ては、部品を寄せ集め一台に仕上げることにした。
自転車の部品はかなり共通化されているし、新品部品でも値段は安い。
必要な特殊工具は購入し、また分解方法が分からなかった箇所は自転車屋で教えてもらったり(単に左ネジであっただけであったが・・・)で我が家のママチャリは全て6段or18段の変速付
きである。
今では製品自体がかなり安い物が販売されているし、家族分も揃っていることから自転車作りは行っていないが、パンク・その他修理などは全て自分の手で行っている。
なお、拾って来たMTBの具合よさから、MTBの虜になり女房用に新車購入してしまった。
十年程前の話である。
今までは外して出すことが義務付けられていたタイヤ・サドルが、平成14年度からはそのままでよくなり、そのまま使用可能な物も不燃物として出されている。
![]()
 |
たいしたものではありません。 HDDのカバーを外し、中のディスクが見えるようにしただけのものです。 パソコンにHDDが付いているのは当たり前の時代、しかしその中を見た人は少ないのではないでしょうか。 我が家でもこれを家族に見せると「ふーん、ハードの中はこうなってるの」と感心されました。 |
作るきっかけは、クラッシュしたHDDを私が中を見たくてカバーを外したことからであった。
そのHDDはH.Tさんに譲り、彼の机上に飾られるようになったのだが・・・。
ある日、彼の家へ遊びに行った時に「来た連中が触るので・・・」とボソリと一言、ディスクを見ると見事に曇っていてカバー取り外し当時の鏡面の輝きは無い。
幸い私の手元に同機種の動作不良HDDが1台有ることから、もう少し置物らしく作ってみることにした。
HDDのアルミ製カバーと同形状の透明材質の物が簡単に手に入れば交換するだけだが・・・、ホームセンターなどで容易に手に入るアクリル板等の透明材料では凹凸や折り返しの加工は簡単には出来ない。
今回は、我が家に有った材料で手間もお金もかけずに作ることが出来たので、ここに紹介することにした。
| ハードディスクのカバー形状 | |
 |
カバーの形状で二種類に分けられる。 左画像上はカバーが平面状に作られていて加工が楽な種類。 左から 取り外したWestern Digtal Caviar 21600のカバー 同 Caviar 2850 Quantum 6400A 下はカバーに凹みを設けてあるもの。 左から 富士通 MPA3026AT Quantum 1280AT Western Digtal Caviar 2540 取り外した CONNER CFS420Aのカバー |
 |
| カバー形状が平面状のHDDの場合 使用HDD = Western Digtal Caviar 21600 制作手順 1.ハードディスクボディーとカバーの間に巻かれているテープを剥がす。 2.カバーを取り付けている7本のビスをヘキサゴンレンチを使用して取り外し、カバーを外す。 (1本はディスク回転軸センターに有るので、貼られたシールを捲るか剥がしてビスを外す) 3.取り外したカバーと同寸法にアクリル板を切断し同じ位置に孔を開ける。 4.「3.」で作成したアクリル板を取り付ける。 5.ハードディスク本体とアクリル板の隙間をテープなどで塞ぎ、本体横のネジを利用して任意の脚を付ければ完成である。 備考 「2.」で使用したヘキサゴンレンチは、HDDに使用しているビスが一般的な寸法の物ではなかったため、2ミリのレンチの6面をヤスリで削って専用レンチを作成した。 「3.」で使用したアクリル板は、取り付けビスの本数が多いので、1ミリのものを使用した。 この厚みだと鋏で切れるので加工が楽である。 「5.」のサイドの隙間塞ぎ用には、家に有ったデスクマットとして使用した透明シートの切れ端を10ミリ幅くらいに切断し周囲に巻き付けた。 これはホームセンターなどでテーブルマットとして寸法で切り売りされている透明シート(厚さ1ミリ)である。 |
 |
完成写真 脚は丁度良い適当なものが有ったので先端に圧着端子を取り付けHDDのサイドの取り付けビスを利用して付け完成である。 H.T氏への譲渡用で初心者の目にも触れることから電源とIDEケーブル、ジャンパーピンも付けておいた。 |
使用した材料と工具
[材料]
動作不良HDDx1 (Western Digtal Caviar 21600)
アクリル板(厚み1ミリ) 100x145 x1
透明テーブルマット(厚み1ミリ) 約10x約490 x1 (下側で重ねて止めたため)
[工具]
ヘキサゴン・レンチ(カバー脱着用=サイズは不明、2ミリのものを改造)
3.5ミリのドリル(アクリル板への孔開用)
鋏(アクリル板切断用、刃渡り100ミリくらいの普通の裁ち鋏)
+ドライバ
セロテープ(透明シート取り付け用)
両面テープ (透明シート取り付け用)
| カバー形状が凹みの有るHDDの場合 使用HDD = CONNER CFS420A 制作手順 1.ハードディスクボディーとカバーの間のシールを剥がす。 2.カバーを取り付けている4本のビスをヘキサゴンレンチを使用して取り外し、カバーを外す。 3.取り外したカバーと同寸法にアクリル板を切断し同じ位置に孔を開ける。 4.カバーの厚みと同寸法のスペーサーを作る(or適当な物があれば用意する)。 (今回スペーサーに使用したものは外径6ミリx肉厚1ミリのアルミパイプである) 5.本体裏の基板を取り外し、カバー取り付けネジを4ミリにタップで切り直す。 6.「3.」で作成したアクリル板を本体との間にスペーサーを入れ取り付ける。 7.ハードディスク本体とアクリル板の隙間をテープなどで塞ぎ、本体横のネジを利用して任意の脚を付ければ完成である。 備考 「3.」で使用したアクリル板は、取り付けビスの本数が4本(四隅)のため、ある程度の強度も必要と思い2ミリのものを使用した。 (この厚みでは鋏での切断には無理が有るのでアクリル板カッターを使用した) 「5.」のタップでのネジ切りは、スペーサーを入れることで、取り外したビスは使用出来ない。 HDDに使用されているビスのネジ山は一般的ではなく、長いビスの入手は困難と見て、入手の容易な4ミリのネジに切り直した。 「7.」のサイドの隙間塞ぎ用には、家に有ったデスクマットとして使用した透明シートの切れ端を10ミリ幅くらいに切断し周囲に巻き付けた。 これはホームセンターなどでテーブルマットとして寸法で切り売りされている透明シート(厚さ1ミリ)である。 |
 |
完成写真 スタンド脚には、古いRAM(30P)を使用した。 このRAMも不燃物としての廃棄PCからの拾得物である。 |
使用した材料と工具
[材料]
動作不良HDDx1 (CONNER CFS420A)
アクリル板(厚み2ミリ) 100x145 x1
4ミリx18ミリ ビス x4
6ミリアルミパイプ (1M長さの物をホームセンターで購入、価格は198円)
RAM(30P)x2(脚用、不燃物からの拾得物)
透明テーブルマット(厚み1ミリ) 約10x約490 x1 (下側で重ねて止めたため)
[工具]
ヘキサゴン・レンチ(カバー及び基板脱着用)
4.5ミリのドリル(アクリル板への孔開用)
アクリル板カッター
金鋸(アルミパイプ切断用)
ヤスリ(パイプ切断面仕上げ用)
+ドライバ
セロテープ(透明シート取り付け用)
両面テープ (透明シート取り付け用)
HDDの寿命は3年から5年といいます。
長く使用して寿命を迎えたものや、運悪くクラッシュしたものなど、このようにしてみてはいかがでしょうか?
![]()
こんなもの作りました! PART 2
外付けHDDの冷却ファン (2007.1.3)
PCショップの新年初売りセールでUSB接続の外付けHDDを購入した。
ネットの口コミなどを見ると、どのメーカーの物でも熱によるクラッシュが多いと評判は良くない。
確かにケースに密封されているせいで放熱は悪いだろうが商品として販売する以上テストもされているはず。
私はクラッシュは熱ばかりでなく中身のHDDの品質もあると思っている。
(人気のない安いHDDが使用されているようだ)
我が家の場合、邪魔にならない足元の奥の方に設置したことから風通しの悪い恐れもあり、中途半端に出来た暇な時間を利用してその辺に転がっている材料で冷却ファンを作ってみた。
揃えた資材は以下のものである。(主な物のみ)
・壊れた電源ユニット=>冷却ファンのみ取外し(12V 0.15A)
・ACアダプタ=>不燃物より回収しておいたもの(8.5V 1.1A)
・ファン取付けベース=>かなり昔に分解処分したカーステレオアンプの放熱器部分
 |
写真でも分かる通り、H形をしたベースに小さな鉄板を介してファンを取付けただけのもの。 |
 |
出来上がったファンはこのようにHDDの横に置いただけで使用している。 電源ユニットから取り外したファンは12V表示であるが無線機の安定化電源で電圧を6Vまで下げても動作することを確認した。(少し電圧を下げて使用する方が風量は落ちるが静かである) |
外付けHDDの用途は家にあるPC全てのドライブ・バックアップイメージの保管場所としていることから常時電源を入れている必要はない。手元に中間スイッチ設けてその先で2口に分岐させHDDと冷却ファンの電源を取っている。
本来なら裸のHDDを直接冷却した方が良いだろうがカバーを外すなど手を入れると保障に関係してくる。一年間はこの形で使用する予定である。
 |
|
|
 |
上の写真では分かりにくいが反対側は右の写真のようにやはり分解処分したカーステレオアンプの放熱器部分を抱き合わせておいた。(全くの気休めと思っているが・・・) |
紙面TOPへ
次の紙面へ
前の紙面へ 一面へ