みんなの実験室9
![]()
みんなの実験室9
蛍光ペンではない普通のサインペン、油性マーカー、ゴム印用スタンプインク、口紅に蛍光物質が含まれているものがあります。
これらをペーパークロマトグラフィーによって分離してみましょう。
<ペーパークロマトグラフィーによるサインペンの色素の分離>
サインペンなどのインクには何色かが混ざっています。これらをペーパークロマトグラフィーという方法によって紙の上で分けることができます。
その法方については 、「みんなの実験室6.」 (←クリックしてください)でも述べましたのでそこも見てください。今回の実験では、このクロマトグラム(色素が分離された紙)にブラックライトの紫外線をあててみました。すると蛍光を発するスポットが見られたものがありました。
| ●用意するもの 材 料-水性サインペン、油性マーカー、ゴム印用スタンプインク、口紅 用 具-天ぷら敷き紙(両面ともざらざらなもの。片面がつるつるのものは水の吸い 上げが非常に悪いので使えない)、またはキッチンペーパー、コーヒーフィ ルターなど) コップ(または透明な空き瓶など)、わりばし、ブラックライト(右の写真) 展開剤-水、エタノール |
 ブラックライト ブラックライト |
●方法
<一次元展開法>
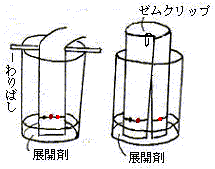 |
1)左の図のように紙の下端から2〜3cmのところに鉛筆で線をひきます。その線上にサインペンなどで、直径3mmほどになるよう、円形に塗ります。この図のように、間を空けていくつか並べてぬることもできます。 2)コップの底から1cmほどのところまで展開剤(水またはエタノール)を入れれます。 3)このコップに1.の紙を、図のようにしてつるすか又は筒状に丸めて立てます。紙の下端5〜10mmほどが展開剤につかるようにしてください。 4)このまま5〜10分(展開剤がエタノールの場合は15〜20分)おいて、展開剤を紙に上昇させ、試料の色素を展開させます。 |
<二次元展開法>
1)紙を、一辺が12〜13cmの正方形に切ります。
2)左の図のように、下端と左端から2〜3cmのところに、辺と平行な線を鉛筆で引きます。その交点に試料をひとつだけ塗ります。
3)これを上に述べたような方法によって展開します(第一次展開)。
4)このクロマトグラムを乾燥後、反時計方向に90°回転させ、第一次展開のときとは別の展開剤で再び展開します(第二次展開)。第1次展開の方向と直交する方向に展開して、スポットをさらに分かれさせるわけです。
| ●結果 昼間の光(白色光)の下で見ただけでも、試料の色がいくつかの色素のスポットに分離できたものがありました。さらに、ブラックライトで紫外線をあててみると、7つの試料すべてに蛍光物質が認められました。 |
||||
|
||||
| <二次元展開法によるクロマトグラム> | |
試料番号1の水性サインペンの黒は、水を展開剤とする一次元展開法では、赤い蛍光を発する物質があるようですが、ほかの色素におおわれていて、はっきりしません。そこで、二次元展開法で展開してみました。第一次は水で、第二次はエタノールで展開しました。 左の上と下の写真は同じクロマトグラムです。 上の写真は昼間の光(白色光)の下で撮影し、下の写真は暗所でブラックライトの光を照射して撮影しました。 すると、一次元展開法を行った場合より多くの種類の色素に分離され、蛍光物質もはっきり分かれました。 一次元展開法では、青、茶、ピンクの色素が分離されました(白色光で見た場合)が、二次元展開法では、ブラックライトの光の下で蛍光を発っするピンクの色素2つが分離できました。 以上展開した7つの試料について述べました。 蛍光物質が認められたこれらの試料は、黒または赤系統の色でした。 これらの実験を行う前の予備実験では、青、緑、黄色などほかの色についても調べています。その結果蛍光物質が認められたのが、黒または赤系統の色だったのです。蛍光物質を配合すると、より黒くまたはよりあざやかな赤になるのでしょうか。 ただ、同じ色でもメーカーがちがうと、異なった色が分離されてでてくることもあります。 <注意> ブラックライトから出る光は目に影響の少ない紫外線ですが、クロマトグラムを見るときは直接目に入らないよう、シェードをつけましょう。紫外線に照らされたクロマトグラムだけを見るようにしてください。 |
●追記
ブラックライトは普通、家庭にはありません。次のようにして代用品をつくることができます。
普通の蛍光灯からも、ごく少しの紫外線が出ています。蛍光灯に濃い青色のセロハンを二重か三重にしてかぶせ、目に見える光をできるだけさえぎると、ある程度は蛍光物質が発する蛍光を見ることができます。例えば、蛍光ペンで書いた絵や字を暗がりで、この代用ブラックライトで照らすと、蛍光がよく見えます。ただ、代用品ブラックライトから出る紫外線はわずかなので、ここに示したクロマトグラムの蛍光は、本物のブラックライトほどにはよく見えません。
なお、蛍光灯も少し熱を出すので、あまり長い時間セロハンをかぶせておくと熱がこもります。この実験は短時間できりあげましょう。
ペーパークロマトグラフィーで葉の色素をぶんりする実験は生物実験室11(←クリック)を見てください。
【参考文献】
「いろいろ蛍光あそび実験!!」『子供の科学』2001年11月号 P26〜29
| 次へ |
|
| 戻る |
|